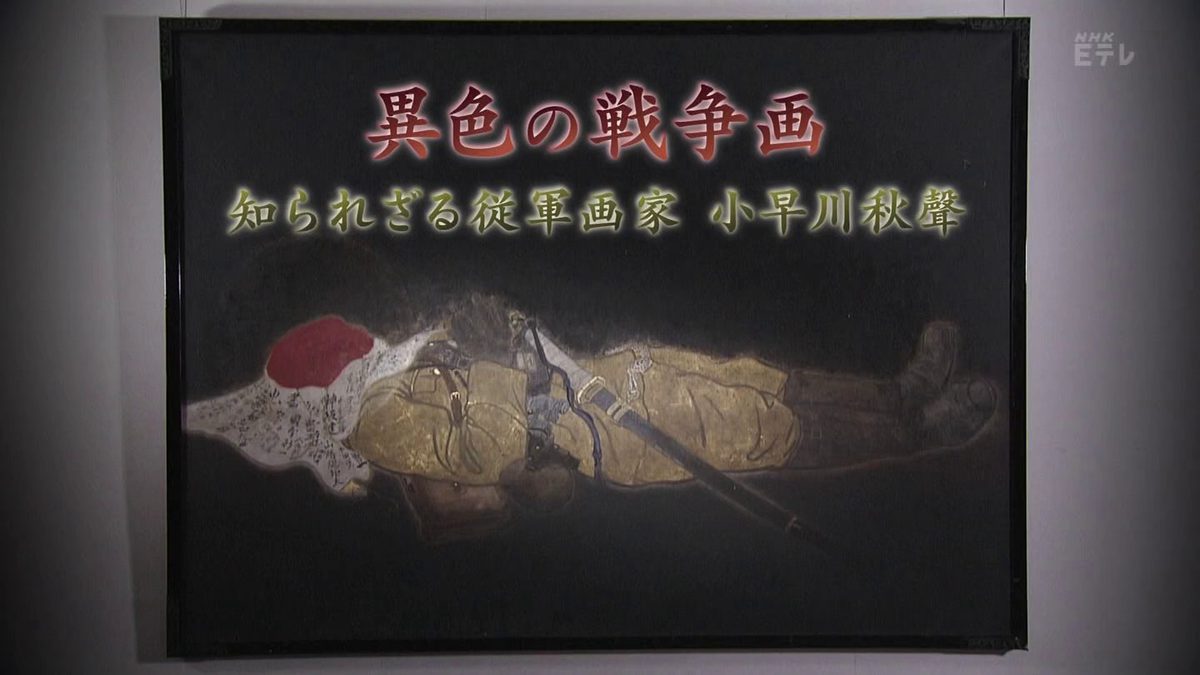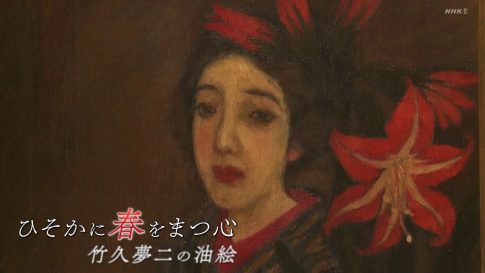大陸から伝来した瑠璃色のガラスの杯。幽玄の音色を奏でた幻の弦楽器。「第69回正倉院展」に出陳される 天平の美 の魅力と見どころをたっぷり紹介する。
天平時代の宝物を間近に見ることのできる「第69回正倉院展」が、奈良国立博物館で開かれている。8世紀、聖武天皇の遺愛の品を、光明皇后が東大寺の倉に納めたことが正倉院の始まりとされる。その後、大仏開眼の儀式で使われた品など、奈良時代を代表する宝物も加わった。番組では、現代の染色家による宝物の再現を通して、当時の最先端の技術を解明するとともに、国際色豊かできらびやかな正倉院宝物の魅力にせまる。
【ゲスト】作家…梓澤要,奈良国立博物館館長…松本伸之,【司会】高橋美鈴
放送日 2017年11月5日
日曜美術館「よみがえる天平の美~第69回 正倉院展~」
緑瑠璃十二曲長杯
こちらは楕円形の盃。横20cm、縦10cmほど。
よく見るとうずくまるうさぎの姿があります。
盃には植物の葉や茎の文様が大胆に刻まれています。
この盃のデザインは上から見ると波のような12の曲線が連なり、名前の由来となっています。
下から見ると全く違った造形美を楽しめます。
専門家の調査で、ササン朝ペルシャ。現在のイランで5世紀から同じような器・鍍金銀人物文八曲長杯があったことが分かっています。
この盃はペルシャなどの影響を受けた中国の唐で作られたとする説が有力です。
天平文化は大陸からの文化を積極的に取り入れていたのです。
犀角杯
インドに住む犀の角で作った盃。犀角杯。
インドから唐を経てニワンにやってきました。
犀の角は当時高級な装飾品であり、盃としても珍重されました。
また、細かく削って解熱剤としても用いられました。
槃龍背八角鏡
槃龍背八角鏡。聖武天皇が大切にしていた鏡です。
鏡の裏には見事な龍が刻まれています。
これは鋳型に銅を流し込んで作られたもので、中国製と考えられています。
描かれているのは中国で仙人が住むと考えられている山。
不老長寿である仙人にあやかりたいという願いが込められています。
こうした海外の宝物はどのようにして日本に渡ってきたのでしょうか。
大きな役割を果たしたと考えられるのが遣唐使です。彼らは当時等の都町案に派遣された使節。
宝物だけでなく先進的な技術や仏教の経典なども収集しました。
長安は世界各地からものや人が集まる国際都市だったのです。
玉尺八
制作された場所はよくわかりませんが中国が発祥とされるのが尺八です。
丈で作ったように見えますが、実は石を竹の形に切り出したもの。
大理石で作られた贅沢な品です。これも聖武天皇の愛用の品だと言われています。
再現・漆槽箜篌(うるしそうのくご)
宝物の中には不思議な形をした楽器もあります。
漆槽箜篌(うるしそうのくご) | 正倉院展(しょうそういんてん)キッズサイト
「漆槽箜篌の実物が残っているのはここだけです。今回が御覧いただける貴重な機会です。正倉院宝物の中には本来筆とだったものがいつのまにか別々に保管されるケースもあります。これはまさにどんなものでも大切に守り伝えてきたがゆえに発見された奇跡です」松本