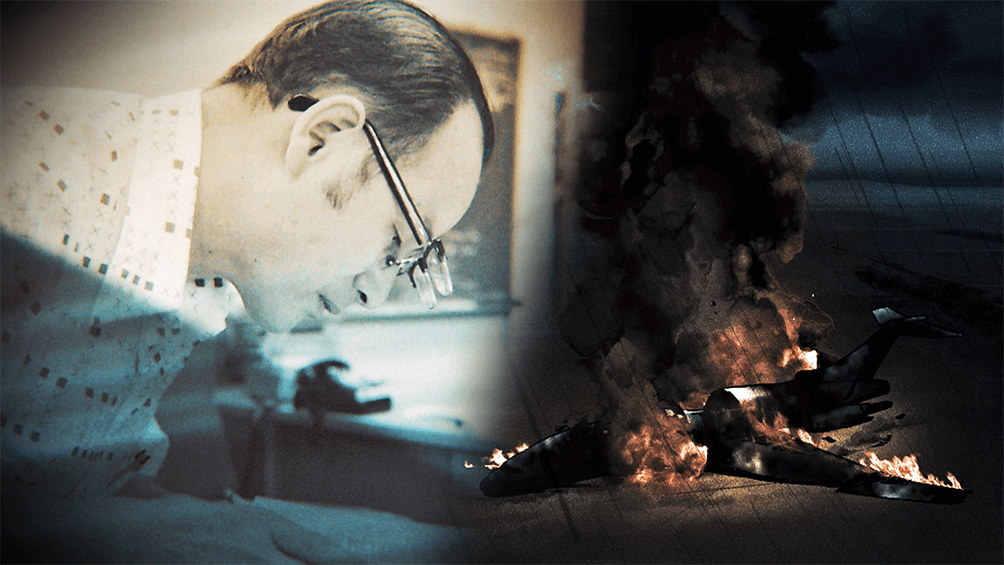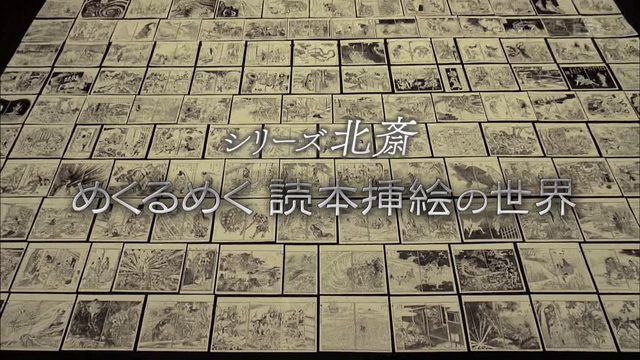ドイツ・ベルリンを拠点に国際的に活躍するアーティスト・塩田千春(52)。現在、生まれ故郷の大阪で開催中の大規模な展覧会を舞台に、その芸術の全貌に迫る。見る者を一瞬で惹きつける、糸を紡いだ大型のインスタレーション、若き日の苦悩を物語る絵画、大きな病を乗り越えて生まれたドローイング。そして、コロナ禍を経て、自分と他者、心と心の“つながり”をテーマに思索を重ねた大作に秘めた思いとは。大阪中之島美術館。
初回放送日:2024年10月13日
日曜美術館 「つながる私 塩田千春」

塩田千春(1972年生まれ)の出身地・大阪で、16年ぶりに開催する大規模な個展です。現在ベルリンを拠点として国際的に活躍する塩田は、「生と死」という人間の根源的な問題に向き合い、作品を通じて「生きることとは何か」、 「存在とは何か」を問い続けています。
10月4日大阪中之島美術館へ【塩田千春】展を観に行ってきたよ。
— °*♡Cherry♡*° (@cantata_140) October 5, 2024
赤い糸はご縁はこのように複雑にでも正確に繋がってるのだと教えてくれた。それと同時に血管のようにも見えて命の繋がりを感じてとても不思議な世界だったよ。 pic.twitter.com/xGx2SrMXKF
中之島美術館 塩田千春展
— SY🍶⚽️🐰YS ADV 4/12 (@sysysy50898801) September 27, 2024
「つながる私」
わたしたちは否応なしにつながっている pic.twitter.com/aaUnFOt5oM
糸を使ってここまでの現代アートの表現ができるっていうのがすごい魅力的で、なんかぞわっとするというか、すごい迫力があるというか、感覚が狂う感じ
自分の感覚がなんかすごい空間体験として面白そうやなぁと思って来たんですけど、思ったよりなんかその人間の繋がりとか、そういうふうに触れてはって暖かく思いました
美術家・塩田千春さん
大阪に生まれ、二十代の頃ドイツ・ベルリンに移住。以来、世界のアートシーンで異彩を放ってきたアーティストです。
sns の時代のビジュアルもすごく重要ではあるんですけれども、ただそのビジュアルの凄さみたいなことを超えて、何か本当に魂を掴み取るような、そういう力があると思いますね
愚直なまでに美術と向き合ってきました。作品を作るきっかけは自分自身の個人的な体験だと言います。しかし、それが完成すると強烈な吸引力で人々を惹きつける。塩田さんはこう言っています。
「私ってところから、それを超越して私たちになる瞬間、私たちになった時、芸術作品が成り立つ。」アーティスト塩田千春と今を生きる私たちがつながります。
「つながる私 塩田千春」
「電気がかかってるんですよね、これ。洋服ですかね。一枚のドレス、二枚のドレスから、あ、三枚。本当に、本当だ、裾がいっぱい広がって、布がつながってますよね。」「一枚の塔ですね。」「そうですね、この二体は二着が繋がっていて、なんか血管の中にいるみたいですね。」「私も流しちゃった、ここね。体内に入ってる感じが、みんな体の中にいるみたいです。」
塩田千春展つながる私②#塩田千春 #つながる私 #中之島美術館 #国際美術館#塩田千春展 pic.twitter.com/NmGQ1X7Sq6
— tetsuya jboy (@TetsuyaJboy) September 26, 2024
ずっと体感したいと思ってた塩田千春さんの作品まじで全部最高だった、、、 https://t.co/lAHjFguGa1 pic.twitter.com/8xrkPkfFxg
— あたりめ (@_ccucumber) October 2, 2024
『日曜美術館』です。今日は美術家の塩田千春さんの展覧会に来ています。案内していただくのは学芸員の国谷さんです。よろしくお願いします。
今回の展覧会タイトルが「つながる愛」。これを漢字で「私」と書いて「アイトリム」というタイトルですけれども、これどういう展覧会なんでしょうか?
「ちょうど一年前ぐらいですね、2023年の9月頃だったんですけれども、私がベルリンの塩田千春さんのスタジオを訪れました。その時、ちょっと今よりもまだコロナの名残が残っていて、塩田さんご自身も十個ぐらいの展覧会がキャンセルや延期になったりしていました。
なので、塩田さんにとっても私たちにとっても、いろんなものとのつながりがなくなった頃だったんです。それで、改めてこのコロナ後の展覧会ということで、つながりについてもう一度思いを馳せてみてはどうかな、ということで、まず『つながる』というキーワードが最初に出てきたんですね。」
「塩田さんご自身からは、『私』というふうに読んで、私自身の愛ですね。英語の ‘I’ と、あと目の『愛』、それから心、愛情の『愛』。この三つの『愛』をかけて、その三つの要素から『つながり』ということについて考えてみたらどうかな、というご提案をいただきまして、この『つながる愛』というテーマになりました。
塩田さんはドレスをよくインスタレーションに使われるんですけれども、塩田さんにとってドレスというのは『第二の皮膚』というふうによく表現されるんですね。
まず第一の皮膚というのは、ここに付いている普通の皮膚です。第二の皮膚はお洋服なんですけれども、その人が今、その服しかないので、その人本人は不在なんですよね。それでも、なんだかその人の記憶をその服が留めているというか、その人が不在であるにもかかわらず、その人の存在感を表すものが『第二の皮膚』というふうに表現されているんですね。」
「あぁ、 綺麗。また雨の中ですよこれは何のたびみたいな音がわぁーっとした中に」
「この作品のタイトルは『巡る記憶』というタイトルなんですけれども、水盤のところに水がポトポトと何箇所か落ちているんですね。これは、今ここにいない人の記憶を表しているんですね。その記憶がポトンポトンとお水の中に落ちていって、さらにそれがこの糸を介してつながっていって、今ここにいる私たちに届けられるという作品になっています。
この作品は大分県の別府市で発表されまして、別府を訪れられた塩田さんが、別府って温泉ありますよね。温泉からモクモクと上がる湯気を見て、ものすごい生命力を感じられたと。それに感動されまして、白でインスタレーションされたんです。そのものというよりは、それが記憶をつなぐ象徴として表現されています。
そうですね、記憶ってやっぱりその場にいない人のものは見ようがないんですけれども、糸って今私たちの目で見ることができるので、見えないものを見える糸でつなぐという感じですね。
次は絵画作品ですね。油絵ですか?
そうですね、1992年の作品で、ミサイルの作品です。ちょっと顔が半分も焼けて滲んでいるような太陽もありますね。
そのとおり、太陽もあります。塩田さんは1972年生まれなので、ちょうど20歳ぐらいの、大学に通われている頃の作品ですね。
もともとは画家だったんですね。
そうなんですか、こちらも1992年の作品ですね。同じ年に描かれた作品なんですけれども、印象がだいぶ違いますよね。先ほどの作品は、ちょっと抽象の要素が感じられましたが、こちらに来ると完全に抽象という感じなんですね。同じ年にこれだけ作風が変わるというのは、塩田さん自身がどういう絵画が自分のものなのか、自分が描きたい絵画はどういうものなのか、すごく迷って戦っていらっしゃったというのがよくわかると思います。」
塩田千春展「つながる私」よかった
— りのあ (@Tooroporgan) September 26, 2024
現代アートは思弁的なものも多いけど、まず感覚的に楽しいので塩田さんは好き pic.twitter.com/IJ8XmBnu87
大阪中之島美術館で「塩田千春 つながる私(アイ)」を見た
— エグザス (@Exasio) October 5, 2024
メッセージを用いたインスタレーションが特にいい
人とのつながりをここまで美しく見せてくれる展示は他にないな pic.twitter.com/WtF90ioMgt
大阪府岸和田市。久米田池の近くで、塩田千春さんは1972年に生まれました。両親は魚や果物を入れる木箱の製造会社を営んでいました。
「一日千個くらい作っている箱屋さんだったので、すごく毎日追われていました。一個いくらで売るような商売ではなく、自分を見つめるような、何かそういう世界に入っていきたいという気持ちがありました。当時、実際に絵を描くのがすごく好きで、絵を描いている時に自分の気持ちが落ち着くというか、絵を描いている時にだけ自分自身に会えるような気がしていました。画家になりたいって、十二歳ぐらいの時から強く思っていました。もう、それ以外に何者にもなりたくないって、かなり強い意思で思っていました。」
中学一年生の時に書いたポスターは、日本画家速水御舟の「炎舞」を参考にしています。大学では洋画を専攻しましたが、入学後、思うように絵が描けなくなります。自分の絵が誰かの模倣に見えてしまい、これが自分らしい絵なのかという悩みを抱えながら、交換留学でオーストラリアへ。しかし、環境が変わっても絵は描けませんでした。
そんな時、ある夢を見ます。
「夢の中で自分が絵になっているんです。自分が絵になっていて、その平面の中で、どう動けば良くなるかを考えていました。その経験がきっかけで、ほぼ次の日にベッドの資質を集めて、絵の具をかぶり、絵になることというパフォーマンスをしました。」
赤いエナメル塗料を使ったパフォーマンス「絵になること」。エナメル塗料によって、皮膚が焼けるような痛みを感じました。パフォーマンス後も、塗料がなかなか皮膚から落ちなかったと言います。しかし、この作品を通じて、塩田さんは自分らしさを少しだけ見出します。
その後、ドイツへ留学し、過激なパフォーマンスで知られるアーティスト、マリーナ・アブラモヴィッチのもとで学びます。そこでも、全身で美術と向き合います。
彼女の授業の中で「断食の授業」というものがありました。私のクラスは十五人ほどでしたが、その授業では一週間、食べず、話さず、水だけを飲むことが許されていました。毎日、一日中陰で自分の名前を書いたり、息が続く限り池の周りを歩き続けたりしました。翌日には目隠しをして一周回るといった、本当に修行僧のような授業でした。
最終日の朝、彼女が枕元にやってきて肩を叩き起こし、紙と鉛筆を渡されました。「何でもいいから一言書きなさい」と言われ、思わず書いた言葉が「ジャパン」でした。
極限状態で発した一言――「ジャパン」。そこから生まれたパフォーマンスが「トライ・アンド・ゴー・ホーム」です。
斜面にある洞窟へ、裸でよじ登り、転げ落ちてはまた登る。この洞窟は、遠く離れた祖国、日本を象徴していました。日本を思いながらも、洞窟に戻るたびに何か違和感を覚え、再び転げ落ちる。このパフォーマンスは、ドイツで暮らす塩田さん自身の葛藤を投影したものでした。
そして、このパフォーマンスは次なる作品へとつながります。
洗っても洗っても感触が残った、皮膚に染みついた泥。それは、世界中のアーティストが集まる芸術祭で展示されました。泥に染まった長さ十三メートルのドレス――それは「皮膚からの記憶」です。シャワーを浴びても、ドレスに染み込んだ泥は落ちません。それは、消すことのできないその人の記憶を象徴していました。
「塩田さんは衣服を第二の皮膚と呼びますたとえ着る人がいなくても、そこにこびりついた記憶がその存在を感じさせる。」
「こちらは大きな大きな地域ですね。奥に糸が張り巡らされていて、向こうが見えないぐらい見えないですよね。」
「いろんな形 の家がありますねこれもよく見ると、片 方に」
「本当だ、ちょっと倒れそうな。」
「編まれ方も様々ですよね。向こうが透けて見えるものもあれば、しっかりとした織りのものもあります。塩田さんは、もう日本よりもベルリンでの生活が長くなっていて、彼女にとっての故郷は『自分の心があるところ』なんだそうです。だから、ベルリンも故郷だし、大阪も故郷。どちらにも自分の家があるとおっしゃっています。
家というのは様々な形があり、家族とのつながりもこの糸で表現されています。家族とのつながりや、社会の中でそれぞれがどのようにつながっているか、家という単位でも様々なつながりがあることを表現したインスタレーションです。」
「なぜ塩田さんは糸を多用されるんですか。」
「塩田さんの最初の糸の作品は、今は赤のイメージが強いですが、実は最初は黒だったんですね。やはり絵画の出身なので、黒い絵の具を使ってキャンバスに線を引くことが多かったようです。でも、絵が描けなくなった時に、『キャンバスではなく空間に線を引こう』と思われたそうです。最初に、絵筆の代わりに糸で空間に線を引いたんですね。
このように、インスタレーションの発想も絵画から発展し、平面から空間全体へと広がっていって、今のような表現になったのだと思います。」
二十代の頃、ドイツに渡った塩田さん。ベルリンを活動拠点とし、精力的に作品を制作していきます。注目を浴びるようになったのは、本格的に糸を使うようになったこの頃から、糸の作品が一つのテーマとつながったのです。そのテーマが、不在の中の存在。
塩田さんが三十歳の時に制作し、その後何度も展示されたインスタレーション『静けさの中で』。それは九歳の頃の思い出でした。隣の家が火事になり、次の日、家の外に真っ黒に焼けたピアノが置かれていました。音の出ないそのピアノは、とても美しかったと言います。
塩田さんの言葉です。
「はっきりと得体の知れない魂として存在するもの。自分の心から音が消え、存在感が増してくる。」
同じく三十歳の時から発表している『眠っている間に』。空っぽのベッドに残された枕やシーツのシワ、その人はいないのに、その痕跡が存在感を伝えます。不在の中の存在。
塩田千春のインスタレーションは実際に観ると本当に凄まじい。
— 宇宙飛行士の日常 (@utyuiroiro) September 25, 2024
(※入口だけ動画OK) https://t.co/SHviTC2vlD pic.twitter.com/hFQ48ETY76
塩田千春さんの展示を見てきました
— 糸子 (@tooyi_kunui_21g) September 29, 2024
こんなに巨大でこの先の人生の中でまたお目にかかれることはないかもしれない、という予感のもと見つめました
目を凝らせば凝らすほど前後不覚になって目眩がしそうな、巨視と微視の綯い交ぜになる作品群 見られてよかった! pic.twitter.com/vVsANkzaVD
高知県黒潮町。塩田さんの両親の出身地です。ここに、塩田さんが忘れられない場所があると言います。いとこの本田ゆかりさんに案内してもらいました。
「ここが別れず、私が小さい時は、ここに 土が、おばあさんが下に土葬されたおばあさんがいて、土が盛り上がってて。」
塩田さんの母方の先祖が眠る 発火。塩田さんが幼い頃は土葬でした。墓の上で草むしりをした時、土の中から亡くなった祖母の呼吸が聞こえてくるような感覚に陥ったと言います。
「お盆の時にはここに帰ってきて、おばあちゃんが亡くなった時もここでお葬式をして、みんなで土葬してって言ってそういうことを小さい時から経験して、やっぱり人が生きていることとか
死んでいくことっていうの、なくなっていくことっていうのを身近に感じたっていう、多分私が一番 最初に感じた死だったと思うんですね。初めて死の恐怖っていうのをそこで初めて感じたんじゃないかな。多分今のテーマにして不在の中の存在っていうのは多分そこから来ているのではないかなとも思います。」
宇宙とつながる、球とつながる。これも一本の糸で縫ってあるんです。はい、糸が宇宙ですね。それと、ここに人みたいなものが描かれていますね。可愛らしい。繋がっているんですよね。
私も小さい頃からずっと思ってきたんですけど、人同士よりも宇宙とか大自然の方がつながっている感じがしてきたんですけど、それが表されているような、一人一人よりも安心する気がするんです。
「そうですか、守られているようなでもこっちは混乱 の中の人が二人になってるんです ねアロマンチックですね。」「人が二人に増えて、宇宙の中にいながら、また別の宇宙を持っている人と人がつながるっていう、なんか 心が温かくなる感じもうこれだけで絵本みたい。」
「一旦絵が描けなくなったっていう話がありましたけど、これ絵画作品ですね。」
「塩田さんは、二千五年にがんを罹患されていまして、それまでは油絵だけでなく、ドローイングを描くのも少し辛いとおっしゃっていたんです。しかし、がんを経験されたことで心情が少し変わり、ドローイングを再び描けるようになったとおっしゃっています。
『肩の力が抜けて、上手に描かなくてもいいんだ、自分が思うままに描けばいいんだ』という風に思えるようになったそうです。だからこそ、こういったドローイングが見られるのも、塩田さんががんの経験を経たからこそだと思います。」
「2005年のドローイングです。三十二歳の時、塩田さんは卵巣がんと診断され、二回の手術を受けました。その後、妊娠・出産を経て、制作に没頭できない期間が続きますが、その厳しい局面を乗り越えます。
使い込んだおびただしい数の紙と、それを受け止めるように置かれた小舟のインスタレーション『手のひらの鍵』。2015年、ベネチア・ビエンナーレの日本館代表として発表されたこの作品は、塩田千春の名を世界に知らしめました。」
そして2019年、25年にわたる活動を網羅する過去最大規模の展覧会が開催されました。ギュレーションを務めたのは片岡真実さん。
「その作品の空間に入って、なんだかわからないけどゾクッとするとか、なんだかわからないけれども、心を持っていかれるような、そういう強さはやっぱりありますよね。
でも、あのモリウェイス館で見せた黒い部屋は、森美術館だと六階に巡回しているんですよ。なので、私、七回同じ展覧会を作っているんですけど、いろんな場所で。でも、新しい展覧会場に行くたびに、黒い部屋では鳥肌が立つんですよね。毎回、『うーっ』って感じになりますね。」
片岡さんから展覧会のオファーを受けたのは開催の二年前当時を塩田さんはこう振り返ります。
「本当に嬉しくて、一番最初に思ったのは『生きてて良かった、生きてて良かった、今まで本当に作品を作り続けてきて良かった』ってことだったんです。でも、その次の日に健診があって、何かおかしいなと思ってたら、残していたもう一つの卵巣にガンが見つかって、手術をして、次に抗がん剤治療が始まる前に森美術館に行きました。片岡さんに『いや、実は次の日に検診があって、ガンが見つかったので、どうなるかわからないんです。私にはあまり時間がないかもしれません』って言ったんです。そしたら片岡さんが『じゃあ、決めていきましょう』ってなって、大体の部屋のインスタレーションは決めていきました。でも、新作の部屋だけは残していて、新作をどうするかというところで一年以上決まらなかったんです。
しばらくして、手術や治療の時に集めた点滴用のビニールバッグや針を彼女が集めていて、それを病院のベッドの上に、まるでクリスマスツリーに飾るようにライトと一緒に展示したいと言っていました。それが新作として出したいと。また、治療中に髪の毛が抜けるので、その様子を映像や写真に撮っていたんです。
だから、彼女は何事もそれを作品に結びつけるということしか考えられなくなっていたんですね。そういう庭園を出してきてくれたんですけれども、私は『今の瞬間のあなたの気持ちだけではなく、もっと包括的なものが評価されないと、作品にはならないよ』と言いました。『なので、これはまだ作品としては見せられないよ』って言ったんです。
『外在化する身体』という、ブロンズの体のパーツと牛革を使った作品が生まれたのは、展覧会のオープンの割と直前でした。自分の体のパーツがバラバラになって登場し、周りに吊られている牛革でできたものは、本当に内臓が外に飛び出してきたような、まさに外在化された身体なんです。私は『面白い展開をしたな』と思っていて、彼女は若い頃から性や死の問題に関心があったわけなんですけども、彼女自身がガンになって再発を経験したことで、その問題が一層重みを持つようになったんだと思います。そして、その後に実際に自分の体のパーツを改めて作り始めたということは、その体自体がこの世から消え、存在しなくなることを想像して、不在の中で存在としての体を改めて作ったのかなと私は思ったんです。
強い死への思いというのは、強く生きたいと思うことの裏返しでもあります。そして、彼女には生きることに向けた強い思いがあり、それが作品に表れているんです。本当に純粋なアートの力を見せてくれる人だと思います。
そして、この秋、故郷大阪での大規模な個展の準備を、三十人を超えるスタッフと共に進めています。展覧会の最後の空間を飾る作品は、この長い道のりを経て生まれた新作です。それをすごく大事にしなきゃと思っています。」
塩田さんは、つながりをテーマにメッセージを募集しました。集まったその数は千五百以上。すべてに目を通し、それぞれの思いが込められた一枚一枚を、円を描くように赤い糸でつなぎました。
「妻と結婚してもうすぐ三 十年になります目と目が合った瞬間に何かわかるということもありませんでもわかる気がすることはあります今まだ生きていること、ダメになりそうな時、支えてくれた人、消えてしまいそうな時、つなぎ止めてくれた人、溺れそうな時、息ができるようにしてくれた人私はパパ、ママ、弟とつながっています友達もつながっています。絵がかわいいですねこんにちは、 こんにちは、初めまして、よろしくお願いしますよろしくお願いしますできて嬉しいですこちらの作品はつながるわという作品ですねこれが生まれた経緯というのはどんなものだったんでしょうか。」
「やはりパンデミックの 間人とつながるなっていうことを言われていて、一五メートルの距離を空けることを強制されていて、つながること はできなかったつながることによって死ぬかもしれない私自身も展覧会が十個キャンセルになって延期になったりしていてでも実際パンデミックは開けてみて、これだけの人と自分はつながっていったんだなっていうのをすごい再確認するような気持ちになって豊田明の展覧会なので、つながりをテーマに作品を作ってみたいなと思って。」
「以前にもそのつながりというのをテーマにされたり、追求なさったことはありましたかいつ頃から始まったんでしょうか。」
「一途の作品ですね 糸 で こう作品を作っていったので、目に見える実際の井戸の線と目に見えないセントでひとつひとつなる心のほうですね心がつながっている意図が切れたり、絡んだり、結んだり、緩んだりっていうのはすごく心の動きと似ていて、それもすごく 私自身面白くて糸のお部屋というか、赤の空間と白の空間と中に入ってみるとすごく肉体的というか、人体の中を創造したり、そういったつながり、自分との肉体的なつながりを感じることが多かったんですけれども。」
「それは意識をされているんでしょうか。」
「入った瞬間、入って、入り口と一番最初に何が見えるかがすごい私にとっては大切で、一緒にして何かを歌いかける絵画とか 彫刻のように、ちょっとずつゆっくりと見に来た人が絵の前に立ってジワジワ伝えることもあると思うんですけど、私の場合も入った瞬間にも全て伝えて、自分の中で瞬間哲学 って思ってるんですけども、入った瞬間に生きてるってことはこういうことかもしれないっていうのは直感的にわかるっていうそうか、 それを受け取りました。」
「今日は本当にいろんなお話ありがとうございました。」
「私の作品は本当に 自分のちょっとした些細なプライベートのことから始まってるんですけど、多分どこかで今回手紙を集めて千五百枚のメッセージ以上のメッセージが集まった時に、私の些細なところから始まったコンセプトは何かもっと大きな共有できるものに変わると思うんですねその時に何か私だけの問題じゃなくなってくるそこで 共有が生まれて、やっと作品って言えるもの、アートになると思うんですだからそこまで行きたいなって。」