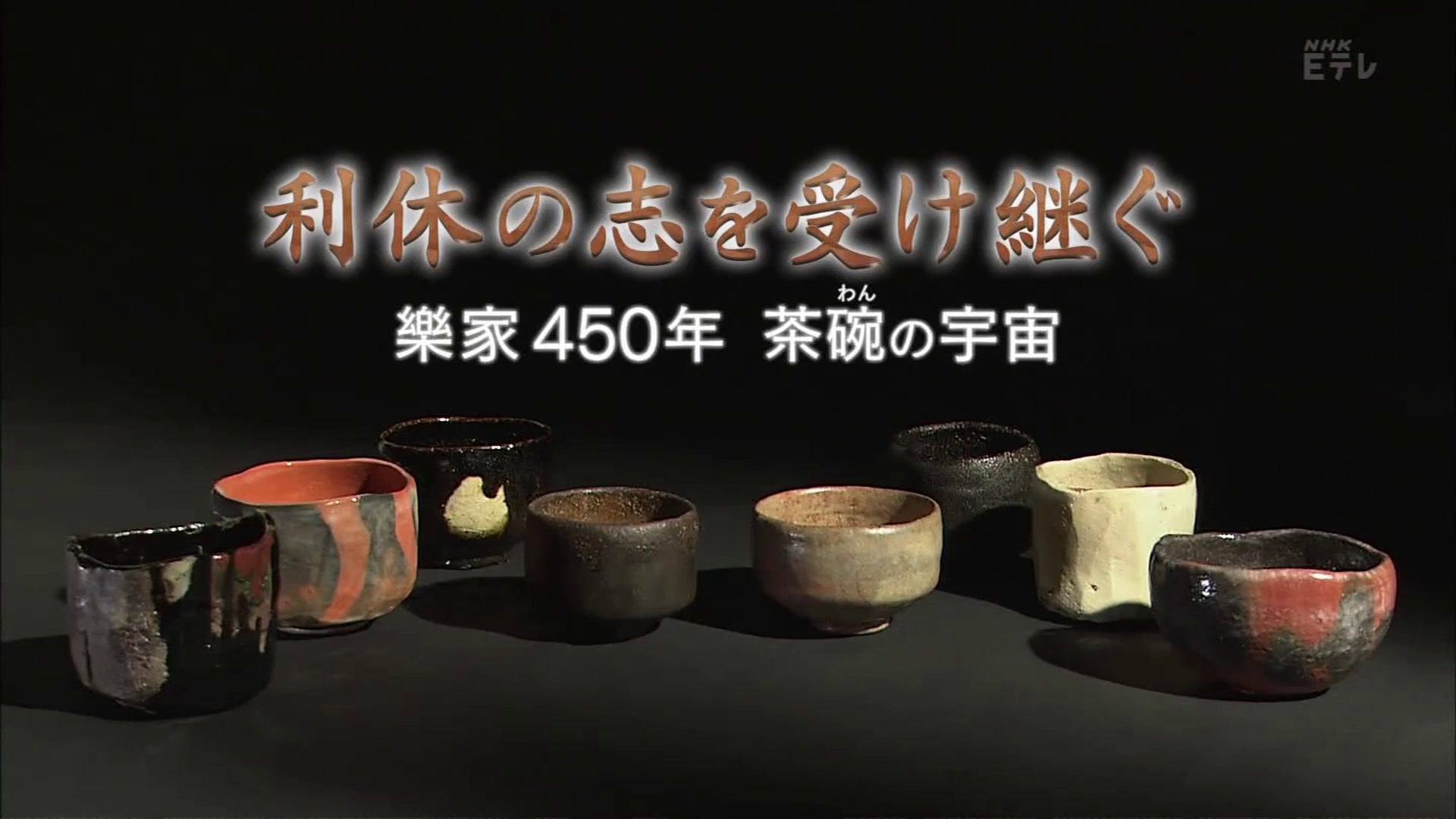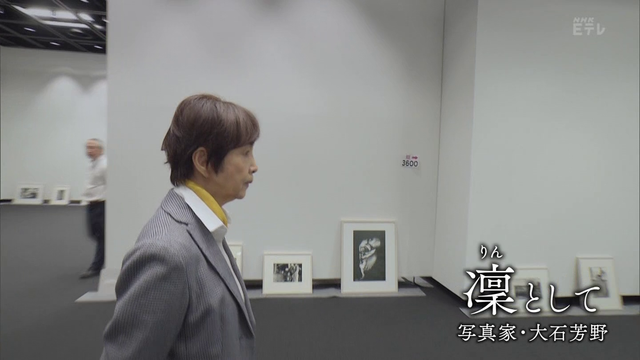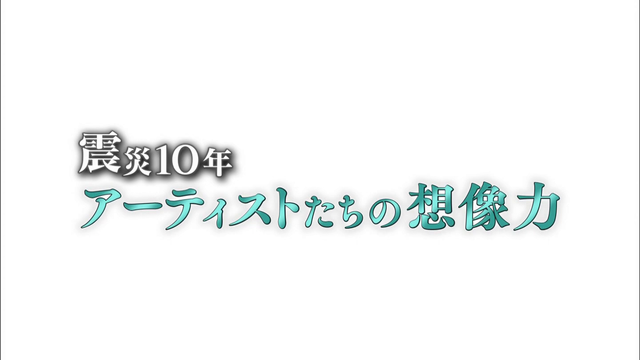350年にわたり陶芸界をけん引してきた萩焼の“三輪休雪”の名が十三代へ受け継がれた。新しいものへの挑戦を文字通り続けてきた歴代の当主たち。兄弟で人間国宝となった十代、十一代。ひつぎに横たわる黄金の骸骨「古代の人」など陶芸の枠を越えた独創性を貫いた十二代。そして十三代は土のインスタレーションや茶わん「エル・キャピタン」が名高い。これまでカメラがほとんど入らなかった三輪家を訪ね、その伝統のあり方を聞く。
放送:2020年5月10日
日曜美術館「萩焼 三輪休雪の世界」
50キロの土の塊と格闘する十三代、三輪休雪、68歳。
令和の世になったばかりの去年5月。
350年あまり続く三輪家の13代を襲名しました。
今花入れを作っています。
繰り返し叩き、押し続けた土の塊。
今度は日本刀でそいで行きます。
錆びた古い刀で断ち切った跡に、予期せぬ表情が生まれます。
「私の表現方法においては、刀で切る、削ぐ。切り跡、削ぎ後とかね、そういうものに限るない魅力を感じてるわけですよね。こういう風にして切ることによって、切ったあとが出てきたりとか、だからいろんな刀を使い分け、表情を作っていく」
10代から13代に至る三輪休雪。
常に革新的な作品を世に送り出してきました。
10代休雪は、それまでの萩焼には無かった柔らかな白。
休雪白を生み出しました。
11代休雪作「白萩手桶花入」
土の塊を日本刀で断つという斬新な手法を始めて用い、茶湯の世界に衝撃を与えました。
12代休雪作「蓮華母」。
高さ106センチ。幅118センチのハスに抱かれた龍神。
萩焼の枠に収まり切れないエネルギーを感じさせます。
そして現在の休雪13代作「雪嶺」。
日本刀の削ぎ跡で大自然の厳しさと神々しさを表現しています。
日本の陶芸界に斬新な息吹を吹き込む三輪休雪の世界に迫ります。
日曜美術館です。今日は山口県の萩市にやってきました。
萩は毛利輝元が400年前に開いた城下町です。小野さんはこれまで来たことは
「今日、初めて参りまして、素晴らしい天候に恵まれて、萩と言いますと近代日本の礎を築いた人たちを輩出したそういう土地柄。と同時に萩焼のイメージがとても強いですね」
今日は350年の歴史がある御用窯である三輪窯にお邪魔しました。13代の三輪休雪さんです。
「当事者としてましては、どういう風に評価されてるけどなかなかわからないんですけど、私が三輪窯で初代から12代までその時々においていろんなものを乗り越えてきてくれたわけですから、私もそのライン上に乗るということで、350年を超えるですね。時間軸の重みっていうのは確かに感じています」
13代が四年ほど前から取り組んでいるシリーズ「EL_capitan」の茶碗です。
狭い茶室の中で緊張感を持って人と人とが退治する茶の湯。
そのことを思った時、ふと心に浮かんだのが昔見た巨大な一枚岩でした。
昭和26年。1951年三輪家の三男として生まれた三輪和彦さん。24歳の時アメリカのポップアートに魅せられ留学現代美術専門の大学名門san_francisco artinstituteに入学します。
休みの日に出かけたカリフォルニアのヨセミテ国立公園。
自然が日本とは桁違いのスケールで迫ってきました。
そこで出会ったEL_capitan。
聳え立つ高さ1000メートルの一枚岩に圧倒され、畏敬の念すら覚えました。
その衝撃は深く心に刻み付けられ、後に茶碗作りの着想を得ました。
ろくろは使わず4キロの土の塊を薪で叩き、茶碗の高台や口作りは刀でそいで整形します。
土の側にも自分のなりたい形がある。
中途半端な気持ちで臨めば、土が刀を弾き返してくるといいます。
「ここを切ってくれって。そういうことなんです。僕が一方的に作用していくっていうことじゃなくって、彼もそれによって反応するわけね。お互いに作用とかとかその反応とかっていうのを繰り返す。ジャズでセッションであったりとかね、即興のインプロビゼーション。短い時間の中で繰り返していく。その時には俺は今度はこう行くぜっていうと、彼は答える」
三輪家から歩いて10分ほどのところにある松陰神社。
幕末。数多くの維新の志士たちを育てた吉田松陰が主催した松下村塾がありました。
身分や階級にかかわらず集まった高杉晋作や伊藤博文、久坂玄瑞らがここで松陰の薫陶を受け明治維新を牽引しました。
「萩は幕末の志士たちの活躍した場所。お家にもですね松下村塾で学んだ志士たちが訪れたりしたっていうようなこともあったんでしょうかね」
「そういうことは聞いています。三条実美候が八代休雪にあてた揮毫なんですが、不走時流ですね。時流に走らずやるべきことをしっかり足元を見てやりなさいという一つの戒めというそういう文言としてとらえてます」
「拝見すると岩肌のように屹立する肌」
「ヨセミテ国立公園の中にEL_capitanという名ずけられた花崗岩の一枚岩では世界最大のであると言われているもの」
「花崗岩の一枚岩の巨岩それを目にした時には相当大きな何かこうインパクトって言うか終えたっていうことですか」
「それを目の前にした時に畏敬の念を禁じえないっていますかね。今まで味わったことのない印象を感じおののきました。そういう経験体験がそのもう何十年か前なんですけど今ちょっと取り入れてそれを見ていただく方に共有したい」
「茶碗ですから手取りがいいとかお茶が飲みやすいということが求められるわけですけど私はそれを持つということではなくて、自然が持ってるそういう意気に達したいということ作られたんですけど。どうしてもねある重さとかも必要。ただ軽ければいいくということじゃなくてね」
ここで10代、11代の休雪さんの仕事を見てきます。
10代三輪休雪は明治28年に生まれ、15歳で三輪窯の職人になりました。
そして75歳の時、初めて重要無形文化財萩焼の保持者、いわゆる人間国宝に認定されました。
今にも飛びかからんとする獅子。
10代は細工物の名人と謳われた腕で数々の名品を制作しています。
豪快な尾の表現。
たくましい後ろ足。
迫力がみなぎっています。
さらに白い釉薬の開発にも取り組みます。
古い時代の銘品に使われた藁灰釉をさらに改良してこれまでにはなかった柔らかな白、休雪白を生み出しました。
稲藁を燃やしたワラ灰との調合の仕方を20年研究し、春の雪のような白を表現したのです。
11代休雪は先代10代の弟です。
長きにわたり兄を助け57歳で11代を襲名。
73歳の時、陶芸界で初めて兄弟で人間国宝に認定されました。
75歳から荒々しい茶碗。鬼萩作りに本格的に取り組みます。
水でこして取り除いた粗い砂を滑らかになった土に再び混ぜます。
地肌がざらついた程度だった従来の鬼萩とは一線を画した荒々しい土を作ります。
兄10代休雪と共に開発した三輪家の白釉、休雪白をたっぷりと分厚くかけたダイナミックな鬼萩茶碗。
釜の炎でほんのりとピンク色に染まった休雪白と化粧土をかけた土肌が現れた黒との美しいコントラスト。
直径16センチを超える堂々とした鬼萩を支えるがっしりとした高台。
鬼萩花冠高台茶碗銘「命の開花」。
造形作品として自立を目指した11代休雪。
伝統を守るのではなく伝統を作ることに心血を注ぎました。
「良くても悪くても自分のものを作る。借り物でない自分の物を作る。あるいは創造といってもいいわけだけど、自分の物であれば自ずと自分の魂が宿って相手方の心を揺さぶると」
11代の三男。それが13代です。
繰り返し乾かしてはくりぬいた茶碗の口作りを仕上げます。
若い頃はおいそれとは作ることができなかった茶碗。
10年ほど前からようやく本格的に手がけるようになりました。
鬼萩を極めた父11代休雪から「茶碗はお茶の道具ではあるが道具だけであってはならない」と教えられた13代。
今ようやく父の言葉が深く心に入ってくるようになりました。
雪嶺シリーズの花入れの薬がけです。
10代が開発した柔らかな休雪白。
13代はこの釉薬にこだわり、白だけで勝負しています。
通常よりもかなり粘り気が強い釉薬です。
中をくり抜き素焼きをした花入れはこの段階でも20キロ以上の重さです。
乾燥した土にたっぷりと釉薬を吸わせます。
釉薬が流れてほしい方向で止め、表面が乾くまで動かさずじっと待ちます。
釉薬のしたたったしずくの先一つ一つの動きまで、緊張感がみなぎっています。
13代三輪休雪作「雪嶺」
叩き、押し、日本刀でそぐ。釉薬の流れ。
険しい山肌に降り注いだ柔らかな雪。
13代が抱く山の峰への畏怖の念が込められています。
スタジオ
「岩肌からやなぎの木が自然に自生して入ってきて」
「命があるものを受け入れる器。小さいその花草でもいのちに変わるものには太刀打ちできない。最初花を生けるものとして当然意識して作ったんですけど、それを受け入れるためには命を預かるわけで、そのためにはただこれ使い勝手が綺麗だとかね、そういうことじゃなくて、大地の一片っていうか。それを作らなければ花に対して失礼だしそれを受け入れもなければならないというそういうつもりで作ったんです」
山口県立萩美術館浦上記念館。
近現代の三輪休雪作品が数多く収蔵されています。
休雪を譲った12代の作品も多数展示されています。
12代は13代の兄で現在龍氣生と号し、今も旺盛な創作意欲を見せています。
《蓮華母》
ハスの花に抱かれた龍神が今まさに天界へ解脱せんとしている姿です。
12代が最も重要なテーマの一つとしてきた死がモチーフです。
長さ3.6メートル幅1.6メートルの二つの棺に横たわる黄金の骸骨。
古代の人と名付けたこの作品は自分自身と妻を古代人に見立て、何千年か後に掘り起こされた亡骸として表現しました。
12代は日本人が忌むべきものとしてとらえがちな死を、人間だれしもが訪れる到達点として考えています。
パリで行った展覧会では12代の作品は現代アートの傑作として大いなる驚きをもって迎えられました。
「三輪家の伝統が云々とあるけど三輪窯の伝統なんてだった何もないですよ。もしあるとするならば、やっぱり何かをやろうとする情熱でしょう。私は伝統の中で何が一番大事かつったら、あれをこうしてああするとかね、こうやってつくんだとか。そんなことをね自分が一生懸命やってんね、自分でそれはいくらでも研究してやってきた。昔の人がそれを研究して自分たちで行ってきたんだからね、我々だってそれやればやれないことなない。秘伝という特殊なものがあってね、それを受け継ぐ受け継がない。そんなものは何もないです。あるとすればなんか自分というもの、自分自身を突き動かしてくるもの。そういうものがあるかないかの問題です」
窯焚きです。
朝7時の火入れから一昼夜を超える炎との真剣勝負です。
初代に始まり13代に至るまで、350年炎と向き合い続けてきました。
一番手前の作品を入れていない大きな窯・大口にどんどん薪を入れていきます
温度が上がり窯が荒く呼吸を始めます。
火入れから19時間たった午前2時頃。
作品の入った窯へ移ります。
慎重に薪を投げ入れます。
釜の中の状態は炎の色や形でも確認しています。
長年の経験と勘が頼りです。
焚き始めて16時間。
「よし」
テストピースを引き出し、釉薬の溶け具合を確認します。
薪を入れ続けるか止めるか最終判断です。
「よし。やめ」
火を止めて五日間さまします。
「EL_capitan」
目前に屹立する巨大な岩の壁。
その壁に挑む人間の雄々しき魂。
13代三輪休雪。
伝統をそのまま受け継ぐのではなく、常に新しいものを生み出し、それを伝統に積み重ねていく。三輪休雪の生き様を繋いでいます。
スタジオ
「お茶どうぞいただきますと言われましたが、どこから飲めばいいんですか」
「飲むっていう行為が、自然なこととして特に意識せず歩いたりすることと同じで、器で飲むと呑むという行為もまた自然なことではないんだっていうことを意識させられます」
「お茶をいただかれて、何かに力をがみなぎってくるとか、何かが覚醒されるっていうものであっても良いのではないかと思います。例えば昔武士が戦に赴く時に刀を置いてお茶を立て、その人の何か特別な大事なその時に使って頂ければいい」
「今思ってるのは、最初から茶碗を作ろうと思ったらやっぱりできないですね。茶碗というものが頭に最初にあると厳しいものはできないと分かりました。土と私がいかに接するか、そういうことをして、そして最終的にそれをくり抜いていて器にする必要最小限の要素を取り入れることからそうして残ったものが茶碗というものということがわかってきた。最近やっとそういうことが分かってきて、最初もうこれは茶碗でなくてもいい。最終的に残ったもので茶が飲めればいいじゃないかっていうこと」
今日はどうもありがとうございました。