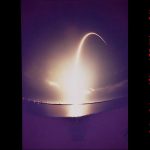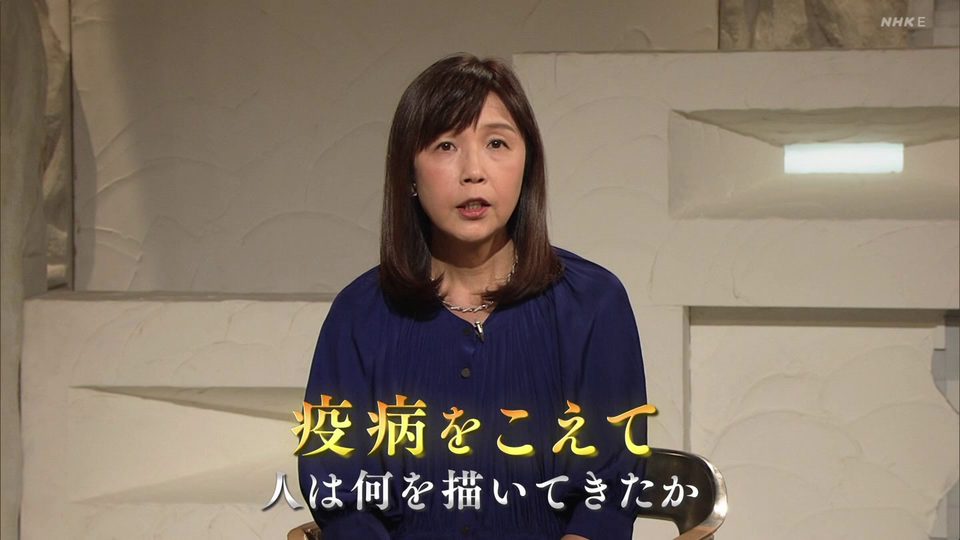造形作家・岡崎乾二郎の芸術活動は多岐にわたる。「抽象の力」で平成30年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞するなど、美術批評にも携わってきた。絵画とも彫刻とも判別できない約40年前のデビュー作「あかさかみつけ」や、鮮やかな色彩が物語を感じさせる絵画で、岡崎は何を表現しているのか?開催中の展覧会場を訪れた司会の二人は、作品を前に岡崎と語り合い、感じることと思索することが折り重なる岡崎のアートを体感する。
【出演】造形作家…岡崎乾二郎,美術史家…林道郎,詩人…阿部日奈子,詩人…ぱくきょんみ,【司会】小野正嗣,柴田祐規子
放送:2019年12月29日
日曜美術館 「芸術を視る力 造る力 造形作家 岡崎乾二郎」
造形作家岡崎乾二郎。軽やかで美しい色彩を纏いながら、何を表しているのかと考えさせるその作品。絵画や彫刻を始め、見るものは常識に揺さぶりをかけられます。40年にわたる作家活動も美術の枠には収まりません。建築の設計もすれば絵画のようなタイルも制作。舞台美術やメディアアートなどあらゆる表現の分野を横断しています。
様々な批評や絵本も手掛け、文章家の一面も。全てに共通しているのが、見て感じたことを考え抜いて表現すること。そこから生まれる作品はどれも独創的です。「僕としてはどんなことでも自分で考えて自分で答えを出さないと、人のやり方を真似するとすぐ忘れちゃうから逆に。自分で考えたことであれば、なんとも繰り返して、なんでも自分でわかるまで子供と言うから気が済まないと気持ちがあって」

1981年。25歳の岡崎の記念碑的な作品。《あかさかみつけ》
距離や角度見る位置によってガラリと印象が変わります。大きさは30センチほど。一枚の板から切り出されたかのようなパーツで構成されています。素材はスチレンボードという美術作品にはほとんど使われていなかったものです。初期ルネサンス絵画に着想を得たという色彩。覗き込むと建物の中に入ったような、外とは別の空間が広がっていきます。
現代美術の研究所で学んだ後、岡崎は、これらの連作で初の個展を開きました。個展のタイトルは「建物の気持ち」それまでにない謎めいた表現に多様な解釈がなされ話題となります。個展は新聞でその年の展覧会ベスト5に選ばれます。美術雑誌でも特集の記事まで組まれました。翌年にはパリ・ビエンナーレに選出されます。一連の作品によって岡崎は一躍注目の作家となったのです。

岡崎の40年にわたる作家活動を展望する展覧会が開かれています。「視覚のカイソウ」展覧会のタイトルは一冊の本をめぐるように回想しながら作品を再会してもらいたいと名付けられました。
「この一角は岡崎さんの最初の個展に出されたシリーズっていうことなんですけれど、建物の気持ちという」「不思議な形をしたものが並んです」
一つ一つのレリーフが独立しながらも形や色が互いに響きあい連なっていく空間。軽妙な造形と複雑な空間表現が混在するその斬新さが驚きをもって評価されたのです。
「見れば見るほど、絵画の要素もあれば彫刻の要素も、建築の要素もある。あるいは都市デザイン的な要素も感じられます。あらゆる要素が集約されている作品で、絵画的な要素としては、色彩の選び方や塗りの技法が挙げられます。しかも、壁に掛けられているので、絵画の伝統にさおさす作品とも言えます。一方で彫刻でもあり、単純な話ですが、立体的な厚みを持っています。」
「同時に、あのように軽い素材で、内部に穴があり空間を持つ構造体は、20世紀の彫刻史を見ても、実験を重ねた作家たちの記憶を背負った作品でもあります。その意味では、いろんなジャンルが結節する点に位置していて、あんなに小さく軽やかなのに、人間が行ってきた造形の膨大な記憶を様々なスケールで呼び起こすような構造を持っているのだと思います。」
三角形の展開による立体的なフォルム。
頂点のみが地面に接し立っています。高さ3 メートル。重さ1.2トンの彫刻は一点のみで支え合い、バランスをとっているのです。重力に逆らうような軽やかさが非現実的な空間を生み出しています。岡崎はレリーフで試みた空間や時間への考察を様々な表現で試みていきました。
東京武蔵野の高台。2011年岡崎は自ら設計して自宅を建てました。自作のタイルをはじめ随所に岡崎の手触りが感じられる家はひとつの立体作品のようです。
岡崎乾二郎は1955年東京の建築家の家に生まれました。家庭には戦前のモダンな文化の気風が色濃く残っていたと言います。
「当時の児童教育で一番大事なのは、自分が感じていることを自分で再確認することを子どもたちに教えることでした。幸いなことに、振り返ってみると、私の父親は建築家で、もともと画家になりたかった人でした。また、母親の方は、祖父が牧師だったこともあり、教育的な環境に身を置いていました。祖父自身も教育に関わっていたのです。僕が一番興味を持ったのは、母親が洋裁が得意で、発明が好きだったことです。いくつか発明の賞も受賞していました。今思えば、本を読むというよりも、何でも作って自分たちで解決するというのが、家の伝統にあったように感じますね。」
岡崎のもう一つの顔とも言える批評活動。膨大な知識と、人が気づかない視点で本質を突く批評は広く知られています。去年出版した「抽象の力」は芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しました。日本の抽象画家たちが西洋絵画のあと守ではないこと。同時代的に表現の革新を理解していたと評価したのです。
「抽象の力」で取り上げられた画家の一人、坂田一男。岡崎の監修による坂田の展覧会が開かれています。
1889年岡山市に生まれた坂田一男。31歳の時にフランスへと渡り前衛的な作品を発表します。キュビスムを追求した抽象画家として論じられてきました。しかし岡崎は帰国後の作品に注目。同時代の欧米の作家と同じく、空間や時間を物質感あるものとしてカンバスに表現しようとしていたことを論証したのです。
同じような2枚の油彩。坂田のアトリエは2度も冠水の被害に見舞われました。この絵もカンバスの下の方の絵の具が剥落。これまで水害を受けた作品として扱われてきました。しかしそのダメージにこそ坂田が表現の可能性を見出していたのではないかと岡崎は推論しています。
「絵画の平面が、単なる空間ではなく中に詰まったものだと示す一番簡単な方法は、それをハサミで切ることです。カッターで切っても同じ効果が得られます。そうすると、よりボリュームがあるように見えてくる。実際にそういう作家がいます。坂田は以前からそうやってハサミで切ったり、いろいろと試みてきました。冠水に関しては、まさに文字通りで、はがされた部分がこんなにも実在感を持っていますが、これは少し嘘だと思います。つまり、こんなに茶色い地肌が出るわけがない。これは絵の具を加えているのではないかと思うんです。見事な土色が出ていますが、後に退色したり色が変化したキャンバスのものですよ。それなのに、これほど強い地肌が出ているというのは、疑わしい部分があると思います。ではこの形が偶然できた穴なのかというと、絵画の構図的には、前から輪郭線や形として、その領域がデッサンの中にあらかじめ含まれていたかのように取り込まれているわけです。
私がいつも言うのは、絵を見たときに『なぜこの絵を描いたのだろう』と考えることです。絵は作られたもので、それなりに時間をかけて描かれたものだから、無駄なことは一切しない。すべてが意図されたものとして捉えなければいけないのです。思いつきやその時の気分で描かれたわけではなく、何度も繰り返し描いているのです。だから、絵を感じたまま捉えることは正しい。なぜ感じたかを確認するために、何度も同じことが再起するように描き続けるわけです。だから、観ている側も他の絵で同じ効果を感じたことがあったら、それを確かめていくことで、感じるだけで思考が組み立てられるのだと思います。」
「何かをしつこく探し求めようとする姿勢がいつもあって、でもその何かは必ず繋がっているはずだと思い続ける。岡崎さんは、物事を見る際にそういった視点を持っているんですよね。それは、ある種の信頼や確信に基づいていると感じます。それが特定のアーティストへの信頼といった核心に似たものだったり、あるいはご自身がアーティストであるという自負に基づいていたりする。『この角には毛がある』という根拠を執拗に探し続ける姿勢には、その確信と信頼があるのだなと感じます。」
これまで岡崎は子供のための展覧会や絵本も手がけてきましたその中でこんなメッセージを送っています。
大人が世の中に自分を合わせることができること
大人だねと言いますけれど
多くの大人が芸術を鑑賞することが苦手なのは
芸術は1人で感じることから始まるからです
自分だけが感じていることは何なのか
それを突き止めようとすることが芸術の面白さです
答えはきっと見つかるはず
きっとという自信を芸術は教えてくれる
岡崎のパートナーである朴恵美さん。岡崎とは高校の同級生でした。
「彼が建築科を受けるって言うんですよ。でも、彼が劣等生だったことはよく知っていたので、どうやって受験勉強するんだろうって思っていました。勉強しているふりをするんだけど、ノートを見るといたずら書きだらけなんです。『この人と付き合うと、何か良くないことが起こりそうだな』って思いつつも、私はその頃から世界文学を全部読破するようなことを図書室でやっていました。図書館に行くと、本の裏には彼が書いた名前が並んでいて、『この人、何者なんだろう』って。彼も海外文学が好きで、私も受験勉強なんかしていない。お互いに劣等生で、大学なんか行けるわけがないんだけど、何か気持ちだけはとても弾んでいて。
その時、彼はいたずら書きだけじゃなく、消しゴムで彫刻を作り始めたんです。それを見てすごく感動しました。私はそのことについて考えて、彼に話しました。それが、私にとっては大きな出会いだったんです。
元々、私は在日の家庭で育っていたので、文化的なことに関わるなんて発想が全くなかったんです。でも彼は、その『できない』と思っていたところを突破してくれたと思います。芸術というのは、こんなにも身近で、消しゴムでさえ作れるものだってことを教えてくれたような気がしますね。」
白いキャンバスの上で、自らを祝福するかのように輝き、躍動する色彩たち。
岡崎は80年代初頭から絵画制作を始め、現在ではその作品が活動の中心を占めています。特徴の一つは、死を思わせる長いタイトル、そして色と形です。縦横無尽な筆致による色彩が、時にせめぎ合い、時に調和しながら多様な形を成しています。
こちらは、絵画制作のためのアトリエです。絵の具は全て自作のもので、硬さや乾いた時の発色などを計算しながら作っています。大枠の構造を元に、部分ごとの関係性を考えながら描き進めます。決まった完成像を目指すのではなく、制作過程で生じる偶然や問題をも取り込みながら、イメージに近づけていくのです。
「こうきてる感じ、これは裏から来た…コケコッコー期待だから。ありったけ折りたたんでN国に置いてるんだけど、置いてると裏も見たくなる。裏返したことを後悔したくなるっていう。まあ、そういうことを言葉で先に考えてやってるわけじゃないけど、自分のやってることを反省的に見ると、そういう意味では、粘土でこっちを作ったら、後ろも無効化せずに作んなくちゃいけないっていう。彫刻の場合は、裏表を同時に意識して、角のような部分にも手を入れなきゃいけないかもしれないね。」
色や形、全てにおいて寸分たりともおろそかにはできないという岡崎。どんなに些細なディテールも綿密に形作っていきます。一枚の絵を完成させるのに要する期間はおよそ二ヶ月。隣り合う形が似た姿になるように比べながら描いていきます。二枚で一組の絵画です。92年頃から岡崎は「水になった絵」を描くようになりました。
左側の小さな絵には、個性豊かな形がひしめき合っています。その中の一つは、水色をした顔のようにも見えます。右側の大きな絵にも、色違いで同じ形が描かれています。左右を比べてみると、同じ形で色の違うものが他にも存在していることがわかります。
「色や形その配置には一つ一つ意味があるのですが最後の雰囲気が変わりましたね。」「今ここにいますね。そして、もう二枚は一緒に構想されたのですか? 今、一緒に描いているのと同じストロークが同じ形として存在しています。ここでは、同じことが繰り返され、作家が自分で説明するのではなく、感じたときに仕組みがあるということなんです。色が起きました。次に、入ることで空間ができていると考えます。例えば、ピンクとこの色はだいたい彩度が同じです。空間が流れるように一つの空間ができるとします。
これと同じものがここにあるとして、これは別の色の関係を結んでいることになります。やっていくと音符のことと同じように、これはこの形が周りの人々との関係を結んでいるけれど、こっちでは別の人生を歩んでいるみたいです。すべて同時にそれぞれの場所で現れ、異なる空間を作り出しています。それを普通の絵画で考えると、一枚の絵の中には塗り分けの場所があって、全ての色や形が平面の中で最初から決められた領域に属することになります。自由にして別の平面を別の世界を同時に属すみたいにしたかった。」
「タイトルが作品のタイトルが物語みたいになって図書積み上げてもいいですか。」
「これ二人が同時に一人がこっち読んで1人がこっちを見て話が多分混じるよう
になって読んでみますねだから消えてしまった自分のコーヒーカップに目をやった。ポットに残っているコーヒーを一にぶちまけその上にカスを落とす。短い間に本当に次々色々なことが起こった。」
「昔は眠れない時、ウイスキーを飲んだものだが、今はどうしてもホットミルクになってしまった。ミルクを温めてスプーンで表面の膜を救い、カップに注ぐ。覚めるのが待てなくても、舌をやけどしたりして、せっかくの幸せをぶち壊しにするわけにもいかない。空は灰色に変わり、鳥が鳴き始めている。こうやって僕は待って、待って、待ち続けてきたものだ。
それで、この文章があると口の中で文章が繋がる。消防士と竜は同じように、ひとつのストーリーを描いている。これ、右で、左が寝かせていきますよ。いちにのさんはい。
すっかり冷えてしまった自分のコーヒーカップに目をやった。外に流れ出すコーヒーを眺めながら、同時に読み終わるかもしれないと思った。じゃあ、これで何を書こうとしたのかと考えると、この文章と文章の関係があり、この中にコーヒーや、特にミルクとコーヒーの関係がヒントとしてある。甘い夜、寝る前のひととき、時間が移行する行動がひとつのパターンから他のパターンに移る時、コーヒーを必ず飲む。その時に外気や気候が変化する情景があり、そういうシチュエーションを描きたい。
面白いのは、ひとつひとつの絵の物語が何か違って感じられることだ。感じたいですね。」
「でもね、一つ移動するのが服装ですが、ここだけを見ると関係しているようで違う関係もあります。今度行ってみるとまた違う関係性があって、無尽蔵にその関係性を探求していくというか、嬉しいです。そこまで理解してくれて。長野は、伝わらなかったけれど、これまで目にした膨大な芸術作品の記憶が、現実と同じようなリアリティを持って心の中に存在しています。そうした芸術作品の記憶の断片や、これまで経験したこと、日常の中で感じる様々な出来事が、あらゆるものが一つのイメージとなって結びついたとき、治ります。時間と空間を超えたイメージが色と形に置き換えられ、キャンバスの上に広がっていくのです。」
「ええ、便利ですね。こういうことも、そこではあり得た、ありえるだろうとかいうことを、自分が今見ているものだけじゃなくて、そこから思い出したものや、歴史的に記録されている他の人の経験などを含めて、場所の中で描くということが、まさに魔戒川や癒やしの匂いなどは自覚していなくても、急いで匂いを嗅ぐと何かを思い出すことがあります。臭いによって過去の記憶を呼び起こすことはよくあるわけですが、それは単なる思い出しではなく、その時間が再起してくれる強烈な匂いに最も近いものが色彩だと思います。
祝祭は、うまく使えれば、匂いと同じくらいリアルに時間を超えた生々しさを持っていると思います。まさにこの色は、過去の記憶を呼び覚ますような感覚を与えてくれるのではないでしょうか。」
もう一つ、岡崎ならではの色彩への感覚。それは他の表現分野でも新たな可能性を示しています。11月、池袋にオープンした劇場には、岡崎によるタイルの壁画が設置されました。高さおよそ3.5メートル、幅18メートルで、題名は『ミルチス・マジョル』。1985年からタイルの作品を作り始めた岡崎にとって、この作品は最も大きく、構想から4年の歳月を費やしました。鮮やかな赤を基調とし、それに対比するように青や緑の色彩が配置されています。
釉薬が塗られたタイルと塗られていないタイルが混在しており、全体でおよそ76枚。タイルの形状もさまざまで、なんと460種類以上に及びます。小さなものは3センチ、大きなものはその10倍のサイズです。微妙な高低差を持たせることで、壁面が平板にならず、豊かな変化が生まれています。これにより、壁面は見る位置や時間帯によってさまざまな表情を浮かべるのです。
『ミルチス・マジョル』のタイル制作に携わった技術者、芦沢正さんは「ひとつの色が決まるまで、10色以上の試作を重ねた」と語っています。
「やっていてやっぱり、これだけの形状や数、そして色の数も凄いですし、これだけのものを組み合わせて一つの面を構成するというのは、私も経験したことがないようなことで、それはすごく画期的だと思います。
普通の作り方は、大分市焼きのものに釉薬をかけて焼成しますが、岡崎さんの場合は、形状が400種類以上あるので、カットして使いたいと思うと、真ん中の部分のようにのっぺりとした状態になってしまいます。ただ、岡崎さんは釉薬の濃淡を一枚の中で表現したいという意図があると思いますので、それぞれ最終的な必要な寸法に合わせてカットした素焼きのものに釉薬をかけて焼いています。
こういった釉薬が貯まるところは、まさに揺らぎがある面が作られていて、光が当たるところや当たらないところが奥行きにつながっていると思います。表現されていることをタイルに置き換えて表現しているように感じていて、絵の具のイメージが釉薬に置き換わって使われているのかなという風に思っています。岡崎さんならではと言えると思います。」
詩人の阿部日菜子さん。かつてエッセイの中で岡崎のタイルの作品を食べ物に例えています。
「一つ一つのタイルに表情があります。たぶん岡崎さんは、この世にあるものは多様であればあるほど良いと考えている方だと思います。その“多様であるほど良い”という考えが、このタイルの表面の豊かさに表れていると思います。そこから、いろんな連想が湧いてくる気がします。私の場合だと、青と茶色と緑の配色から空と樹木という風景を感じました。それから、紫色の綺麗なタイルもあって、それはまるで熟した木の実、例えばラズベリーやブルーベリーのようで、美味しそうだと感じました。逆に、この建物の中に空や木々、緑があるんだなぁと思うと、ちょっと不思議な感覚を受けました。まるで家と外が反転したような、外にあるべきものが家の中にある、そんな驚きを感じて、なんだか嬉しくなりました。」

不思議な題名「ミルチス・マヂョル / Mirsys Majol /」
1940年に出版された漫画、火星探検から引用されたものです。
主人公の男の子が夢の中で尋ねる火星の人の長ミルチスマジョルなのです。
この原作は池袋を愛し、その界隈に居を構えた詩人の小熊秀雄。
火星での盛大な歓迎会の平和と幸福に満ち溢れています。
岡崎は火星と地球ふたつの街の未来への希望を重ね合わせ、壁画にこの名をつけました。
費用は光り輝くタイル。そこには子供の頃のキラキラとした思い出など、岡崎の様々な記憶の集積が存在しているのです。
芸術を見るそれを信じ、一貫して時間や空間をひとつの造形作品を形作ってきた岡崎乾二郎。その作品は芸術を見ることの豊かさを問いかけ別世界へと誘って国会いません。
「40年前の作品が出てきて、施設とも言えるけど、それはまぁ、40年前に自分が作ったもの。それなりに問題の解き方は合ってた感はあるんで、それなりに納得のいく答えを出してるって感じがする。40年経ってあまり変化していないな、進歩してないなって思う部分もあるし、変化していないことに対して、今やっても同じようになるだろうなっていう感じはありました。とりあえず一番最初に感じたことは、だいたいは僕が思っていた通りだろうなってことですね。」