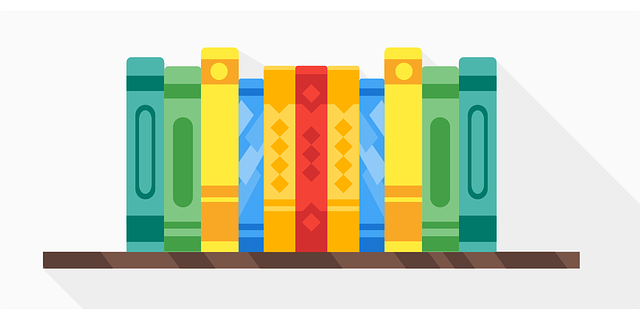戦争中、暗く静謐(ひつ)な風景画を描き続けた 松本竣介 。この程大川美術館の展覧会場にこしらえられたアトリエのモノを手掛かりに、松本の絵と人生を浮かび上がらせる。
戦争中、耳が聞こえないため徴兵を免れた松本竣介は、独特の雰囲気をもつ暗く静謐(ひつ)な風景画を黙々と描き続けた。それらは今昭和を代表する名作の一つとなっている。大川美術館では開催中の企画展で、松本竣介のアトリエを会場にこしらえた。戦争の時代を、この小さなアトリエを拠り所(よりどころ)に奮闘した松本竣介。番組では、アトリエに揃えられたさまざまなモノを手掛かりに、松本の絵と人生を浮かび上がらせていく。
【ゲスト】大川美術館館長…田中淳,【出演】建築家 松本竣介次男…松本莞,洋画家…小林俊介,島根県立美術館専門学芸員…柳原一徳,【司会】小野正嗣,高橋美鈴
放送 2018年9月16日
日曜美術館「静かな闘い~松本竣介のアトリエ~」
プロローグ
群馬県桐生市にある大川美術館。
この日展示室の一角にある洋画家のアトリエをこしらえる試みが行われていました。
アトリエの主だったのは松本竣介。
中学に入った頃病気で耳が聞こえなくなったため徴兵を免れ、太平洋戦争中も絵を書き続けました。
戦争の最中の国会議事堂。
暗く沈んだ風景の中、荷車を曳く人影がよぎります。
独特の詩情を湛える風景画を描いた俊介は線胡麻もない頃36歳の若さで亡くなりました。
松本竣介の息子莞さん。アトリエは幼い頃父と過ごした思い出深い場所です。
蔵書などかつてアトリエにあったものを並べていきます。
「知識を書籍から得るしかなかった。総合工房。絵を書くだけの場所じゃなかったことをいいたかった」
戦争という激動の時代。
松本竣介がアトリエを拠点として繰り広げた静かな戦いを追います。
静かな闘い
総合工房と名付けられたアトリエ。
美術だけでなく文化芸術の総合的な場にしたい。そんな願いが込められています。
盛岡で育った松本竣介は17歳の年画家を志して上京。
結婚して新居にアトリエを構えたのは23歳。昭和11年でした。
俊介は新進画家として活動し始めたところでした。アトリエができた年、俊介が最も熱心に取り組んだのは雑誌の刊行でした。
タイトルは雑記帳。エッセイを中心とした雑誌で作家の佐藤春夫、詩人の萩原朔太郎などそうそうたる著名人が文章を寄せています。
俊介は自らもエッセイを書き編集も行いました。
雑記帳発刊の翌年、昭和12年には日中戦争が始まり、日本は戦争の時代に突入しました。
国内も戦争に向けた総動員体制が敷かれようとする中、俊介の文章には切迫した危機感が伺えます。
「非合理的気風が権威の位置に付き、わけもなく暴力を振るっている今日。それに迎合しようとする気風が一般を覆う」
しかし雑記帳は資金難のため14号で廃刊になります。
最終号に俊介はこう書きました
「興奮し、わめきちらしている愛国者は、冷静にしている者が皆非国民に見えるらしい。今狂気と蒙昧の地に放り出されているに等しいと思うのです。じっとしていられない思いに駆られます」
雑記帳の発行とともに俊介は絵に打ち込んでいきました。
アトリエの本箱には俊介が影響を受けた西洋の画家たちの画集が数多くあります。
とりわけ俊介が気に入っていたのはモディリアニ。
酒浸りの若くして亡くなったモジリアニ。首の長い人物画を多く描きました。
こちらは俊介の女性像。
この絵を描いた頃俊介はこう書いてています。
「モジリアニの作品は長いこと私を翻弄した実際困ったほどだった。モジリアニは大画家ではなかったかもしれぬ。だが生きている歓喜と悲哀をあのように海岸に託したものはなかった」
画家たちの影響を受けながら自らの絵を模索し続けた心身画家の俊介。
雑記帳廃刊の翌年、初期の代表作と言われる大作を描き上げました。
画面全体を深い青緑が多い、幻想の風景のように街や人々が描き込まれています。
中央にはピンクのドレスを着た都会的な女性。
靴を磨く男がその傍にいます。
人物が互いに関連なく組み合わされています。
時計塔のある建物などが立ち並ぶ街並みも、正面から見た光景と上から見下ろした光景が入り混じります。
街のイメージがモンタージュの手法で浮かび上がっています。
この絵にも他の画家の影響が見られます。
蔵書にある野田英夫の画集です。日系移民の子としてアメリカで活躍した画家です。
都会で暮らす人々と街の様子が同じようにモンタージュの手法で描かれ俊介が大きな影響を受けたことがわかります。
近年、絵画だけではなく写真などの影響も指摘されています。
これらは俊介のスクラップブックです。
女性や男性を始め、建物、風景など様々な写真がジャンルごとに集められています。
スクラップブックを調査し俊介の絵との関連を調べてきた柳原一徳さんです。
「街の俯瞰風景を一つ一つ見ると一対一の対応はないと思いますが、俯瞰で撮られたものに関心を寄せていたのではないかと思います。
女性の姿。和装しても洋装にしてもいろんな人物を集めることであの典型的なイメージを抽出しているのではないかと思います。
こちらの帽子をかぶった女性は俊介が描いたスケッチなどにもちょうど同じようなものが使われてると思います。映画やグラフ雑誌から典型的なイメージを抽出してそれをタブローに描いていったのではないかなとふうに考えています」
俊介はモンタージュによる都会風景を連作していきます。
赤い色に覆われたこの絵ではモダンな女性が中央に大きく描かれています。
画面に無数にひかれた黒い線。俊介はこうした線に強いこだわりを持っていました。「この頃の僕の絵には針金のような黒い線がのさばりかえっている。考えてみると線は僕の気質なのだ。子供の時からのものだった。黒い線を1日引いているだけで、僕の空虚な精神は満足する」
一連の都会風景の集大成とも言われるこの絵でも独特の黒い線が目立ちます。この絵を書いた昭和15年。俊介は初めて個展を開き、その案内状にこう書きました。
「14歳の時に聴覚を失うこの道にふみ迷い15年を経た今日ようやく絵画を愛しそれに生死を託することの喜びを知り得た」
ゲストは日本の近代美術を長年研究してきた大川美術館館長の田中淳さん
紳助のアトリエをしつらえるという企画の狙いとは
田中館長「松本俊介は外へ行ってスケッチをしてきてもそれを持ち帰ってアトリエの中での作業がとても大事だったということが一つ。絵を書くだけではなく本を読んだり原稿を書いたりと過ごす時間というのが大事じゃないかと思いました」
総合工房と名付けたアトリエができて5年が過ぎた昭和16年。
俊介が雑誌に寄稿した文章が波紋を起こします。
きっかけは美術雑みづゑに掲載された陸軍の軍人たちの座談会でした。
俊介は赤線まで引いて丹念に読み込んでいます。
「亡国的な絵が非常に多い。絶望的な絵が非常に多いこの国家荒廃の時にああいう贅沢なことをして、呑気に構えておっては困る」鈴木庫三12
その頃俊介が描いた自画像です。暗い地面の上に黒い服を着て立つ俊介。
手を握りながら顔をやや斜めに向けています。
俊介の息子莞さん。
8歳の時に俊介がなくなるまでアトリエで父と一緒の時間を過ごしました。
「父の耳が聞こえなくて不便でしょうがないとか、意思の疎通がとってもうまくいかなくてイライラしたとかが泣き喚いたとかっていう記憶は全くないですね。空中に指で書いてコミュニケーションしてた。必要のためにカタカナは早く覚えたかもしれません。カタカナで何が欲しいとかどうして欲しいとかお腹が痛いとかお腹が痛いなんて言うを揉んだらすぐひまし油飲まされて我慢してトイレにそのまま連れてかれたり」
4、5歳の頃、莞さんはアトリエでお絵かきをしました。
それが今も残っています。
昆虫、電車、動物。俊介はこの莞さんの絵に刺激を受け、それをなぞるような絵をいくつも残しています。
青と白が混ざり合う画面にはっきりとした黒い線で蝉の形が描かれた俊介の絵。
それは莞さんの絵とそっくり同じです。
こちらは褐色の画面に自由な線の動きで象られた白い牛。
かつて黒い線を引いているだけで僕は満足すると言っていた俊介。
子どもが引く自由な線に魅せられたのです。
「5歳の少年の自由画を素材としたものである。このような素朴な感覚の中に絵画的に純粋な効果を発見することは画家としての喜びである」
莞さんが絵を描いていた頃日本はすでに負け戦でした。
学徒出陣。学童疎開。特攻隊。そして空襲。
昭和20年3月10日東京は死者およそ10万人に及ぶ壊滅的な被害を受けました。
東京大空襲の直後、俊介は莞さんたち家族を島根県に疎開させます。
しかし自らは東京に残りアトリエで絵を描き続けました。
莞さんたちに宛てた数多くのハガキや手紙が残っています。
「莞にこの絵がわかるだろうか。駅のあたりからお家の方を見たところ。今は B 29の暴爆でこんなになっちゃった」
「もうすごく厚くて腸をぎゅうぎゅう詰め込んだ後布団みたいなもの二枚合わせたね、原爆よけの僕好きだって言ってこれをかぶっていけって言ってそんなもん送ってきたありましたよ 」
どこからでも読めるようにレイアウトしたユニークな手紙。
「俺の絵は今非常に変わりつつある。1日に2時間元気で描ける時間があれば十分だ。明日の命も知れない今になって、仕事が明らかになってくるとは間一髪という危ない綱渡りだな」
そして敗戦。
俊介は莞さんにこう書き送りました。
「負けた負けた日本はアメリカに負けた男の子は皆目に涙をため、残念だ残念だと言っているよ。どうしたらいいだろうかしら。立派な人になること。莞ぼう。立派な人になれ。外地から裸で逃げ帰ってくる人々。戦いや空襲で肉親を亡くしてしまった人々に比べたら、我々は申し訳ないくらいに全てが残った。そして思想的にも無傷のまま前途のある俺がいるじゃないか」
終戦直後から俊介は自由な美術家たちの組合を模索したり、新たな雑誌の刊行を夢見たりしながら、アトリエで精力的に絵を書き続けました。
焼け跡の風景です。画面全体がまるでまだ燃えているように赤褐色に覆われています。
「生涯忘れることのできないものがある。奔流のように家々を舐め尽くして行く巨大な炎。猛火に一艘された後のカーッとした真っ赤な鉄くずと瓦礫の街。それらを美しいというのにはその下で失われたもろもろの美しい命、愛すべき命に祈ることなしには口にすべきではないだろう。だが東京や横浜の一切の夾雑物を焼き払ってしまった直後の町は極限的な美しさであった」
昭和23年。体調を崩していた俊介は周囲から休養を勧められたのにもかかわらず制作を続けました。
絶筆となった作品。
暗い背景に白い建物が浮かび上がっています。
異国風の聖堂のような建物。俊介が生来の気質だと言っていた線が太くあるいは細く。
建物の輪郭や模様を刻んでいます。
この絵を仕上げて間もなく松本竣介は36歳の若さで亡くなりました。
激動の時代、アトリエを拠点に静かな戦いを続けた俊介。そのアトリエで父の死を実感した瞬間を莞さんは鮮明に覚えています。
「突然、あれアトリエの匂いしないやって気がついたことがあったんです。本当にそう思ったことが不思議だっていうぐらいに何かアトリエって臭いがあったよなって、アトリエの匂いはやっぱり絵の具だとかパイプタバコに入った匂いでしょ。ひとつひとつ取り上げると香りというより悪臭みたいな印象だけどそういうのが全部混ざってた、頭の中に刷り込まれていたものがスパーンと、まっさらになっちゃったっていうのに気がついた。本当の瞬間ですよね」