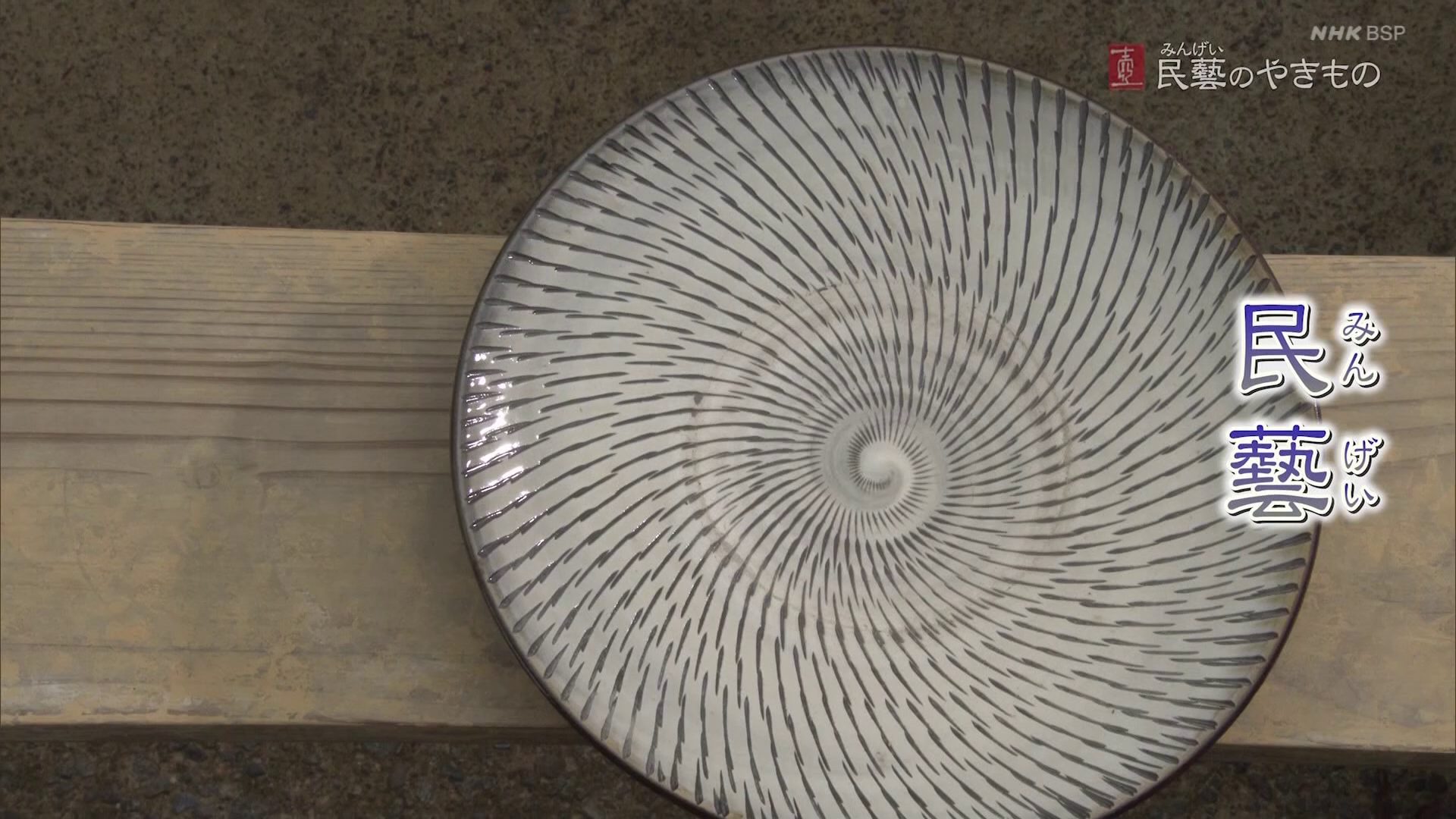ノスタルジック!和洋折衷のアンティーク▽西洋のコンパクトの装飾に金蒔(まき)絵の技が▽大正ロマンなファッションで踊るタンゴ倶楽部▽モボやモガも飲んだ!?大正生まれのカクテルにあのお漬物が!▽驚きのデザイン!女学生を魅了した銘仙▽モダンボーイが愛したステッキに宿る職人技▽今回は草刈正雄さん出演の土曜ドラマ「探偵ロマンス」とコラボ!草刈邸にあの名探偵がやってくる!<File573>
初回放送日:2023年2月3日
美の壺 「和と洋の出会い・大正ロマン」
大正時代――今からおよそ100年前にあった14年と5か月という短くも華やかな時代。そこで花開いた独自の大衆文化は「大正ロマン」とも呼ばれ、今再び注目を集めています。その魅力を象徴するキーワードは「和洋折衷」。大胆でポップな色柄の名刺入れや着物は、女学生たちのおしゃれ心が生み出したものです。また、モダンボーイに欠かせなかったアイテムの一つがステッキでした。
大正時代に生まれた日本のカクテルには、日本独特のお漬物が入っていたものもあり、驚きと魅力を提供していました。100年を経た今でも、大正ロマンは人々を魅了し続けています。そんな大正ロマンに秘められた美の世界へご案内いたしましょう。
東京浅草。店の間に挟まれた小さな路地の奥。そこに時間を巻き戻したかのような不思議な空間がありました。
「いらっしゃいませ、大正ロマンをコンセプトにしたアンティークショップです」
「レトロな雰囲気、綺麗なビーズバッグですね」
大正時代、女性たちの間で流行したクロッシェ帽子。当時の形を忠実に再現して作ったとか。
「これは大正から昭和初期にかけてのコンパクトですね。素敵な色合い。装飾は日本の金蒔絵の技法だそうです。大正時代の人たちはちゃんと咀嚼して自分で取り込んで、それで表現している。それがハイブリッドっていう形で、日本独自の日本人の体験に合ったものをやっているそこがかっこい」
稲本さんは日本人が生み出した和洋折衷の魅力に気づいてほしいと、このお店を作りました。
「こちらにあるんですけども、トンビマントですね。明治大正に流行したんですけれど、ここが袖ぐりが大きく開いているのが、着物でも洋装でもどっちでもいけるというので、これはこのボタンを取った時に和装の着物が入るところですね。ここにポケットがあったり、ビロードでパイピングしてあったり、手縫いの縫製の良さですね」
西洋のコートを袖が大きい着物にも合うようにアレンジ。日本人の感性が生ん和洋雪中の逸品です。稲本さんが主催するクラシックタンゴクラブがあります。集うのはお店の常連や大正ロマンに魅せられた人たち。当時を思わせる洋装や和装に身を包み、かつて和洋折衷を生み出した日本に思いを馳せる、月に一度の交流会です。
「西洋ばっかり刷り込まれているところをもう一回立ち戻って、日本人って何だったっけな、こういうんだったかなっていうのを絵空事にしないで何か表現していってほしいなって思いますね」
今日ひとつめの壺は「時を超えた和と洋の出会い」
大正時代をイメージしたカクテルを楽しめる場所が若者の街渋谷にあります。一歩足を踏み入れれば、大正時代に流行したカフェをイメージしたバー。オーナーは国内外のバーで研鑽を積み、カクテルの世界チャンピオンに輝いた鈴木淳さん。
「オリジナルのカクテル・モガティです。大正時代流行のおしゃれを楽しんだモダンガールをイメージして作りました。爽やかな甘さのお酒です少し華やかさもありながら、魅力的な色を添えるというイメージで作りました。」
なぜ今、大正時代のカフェなんですか
「その時代のカフェって、バーの一番全身、それまでホテルでカクテルを楽しんでたっていう文化が町場に降りてきて、その町場で日本人のバーテンダーの人たちが日本人のゲストに向けてカクテルを作るというところの文化にもすごい惹かれたというのもあって」
大正時代には鈴木さんにとって大切な日本人バーテンダーがいました。前田米吉さん、日本のバー文化礎を築いたと言われる人物です前田さんは大正時代末、一冊のカクテルブックを残しました。そこには本場ヨーロッパに先駆け、当時の最新のカクテルが掲載されていました。近年再評価されているバーテンダーです。前田さんのオリジナルと言われるラインコクテールを、当時のレシピを参考に作っていただきました。
フレーバーワイン、そして薬草系のリキュール、さらに苦味と香りのビターズを少しそれをよくシェイクし、グラスに注ぎます。そして最後になんとラッキョウが一粒入りまラインコクテールです。独特の香りとキリッとした口当たり、ラッキョウがいい味を添えています。
「当時洋酒が日本に入ってきて初めて見るお酒ほとんどだったと思うんですよね。こういうのを作ったらオリジナリティが出せるんじゃないのかなっていう好奇心一つで作ったカクテルだと僕は思うので、そういうカクテルを現代で飲むと味わいがまたちょっと特別な感情で飲めるのですごい好きです」
大正時代、大人たちはこのカクテルを前にどんな時を過ごしていたのでしょう。
大正末期、女学生をきっかけに日本中に広まったファッションアイテムがあったことをご存知でしょうか。その名は銘仙(めいせん)。もともとは売り物にならない絹糸で織り上げた値段の安い着物でした。それが化学染料の普及とともに、鮮やかな色柄を生み出していったのです。瞬く間に日本中の女性たちを虜にしました。それにしても、なんて大胆な柄、当時こんな着物があったんですね。学生時代からコレクションを始めた桐生雅子さん。現在、その数六百点以上、桐生さんが着ているのも銘仙です。銘仙はもともと地味な色柄でした。それが色鮮やかになるきっかけを作ったのは、ある有名な軍人でした。明治の末期に学習院の院長に陸軍大将の野木真之介が就任した時に、学習員に通う女学生の服装を目線以下のものにするようにというお達しを出しました。乃木希典野には、当時学習員の女学生たちが着ていた高価な振袖などは贅沢に映ったとか。そのため安くて質素な銘仙を着るように呼びかけたのです。でも、女学生たちは少しでもきれいな着物を着ていたい。そこで、銘仙の産地は輸入した化学染料を使い、それまでにない華やかなデザインを生み出していったのです。安くてデザインも豊富だったので、当時の女学生は本当にファッションアイテムとしておしゃれを楽しんだといいます。
「今でいうかわいいの原点は大正時代にあるのではないかと思っています。これは当時の婦人雑誌に掲載された銘仙のカタログ。最新のデザインはこうして広まっていきました」大正末期から昭和初期にかけて、十年間でおよそ一億短の銘仙が売られたとか。日本人独特の感性といいますか、懐の広さ、ポップでモダンで、とても百年前のものとは思えないデザイン性というのが、とても惹きつけられる魅力です。
二つ目のツボは、時代を移し、軽やかに 美しく
埼玉県秩父市。銘仙は関東が主な産地。中でも、秩父は最も歴史のある産地の一つです。新井則雄さんは秩父銘仙の技法を今も守り作り続けています。
「この織木も実は大正時代に作られたものだそうです。そしてそれから秩父銘仙の代表的な手法がほぐし折りという手法になります。これが見本なんですけど、こういった縦糸ですね。このほぐし折りっていうのはですね。縦糸だけに型染めをするっていうのが特徴になります」
織り上げる前に、縦糸だけに型染めするほぐし折り。一本一本の糸に染料が入るためにより繊細な表現ができるといいます。玉虫色の光沢を出せるのも秩父銘仙の特徴。縦糸と違う色を横糸に使うと、見る角度や光によって色が変化します。型染めの作業です。シート状に揃えられた縦糸を型で染めていきます。縦糸の数はなんと1600本。ほぐし織りの型染めは手作業ですわずかな柄のズレも出ないように、正確に型を置いていかなければなりません。しかも時間がかかれば染料が滲んでしまいます。熟練した技術があってこそ作られる銘仙です。これは今人気の秩父ウイスキーのメーカーと共同で作った作品。原料の大麦がモチーフです。「時代を移し、大胆に表現するのも銘仙ならでは。今自分が皆さんに来ていただきたいとか、自分が表現してみたいというものを表現するものが一番のこの名前の魅力、銘仙の特徴になっていくんじゃないかな。変わっていくっていうこともう一つの銘仙の魅力だと思います」
新井さんの代表的な作品です。秩父の山々をイメージしたもの。幼い頃から慣れ親しんだ故郷への想いを形にしました。伝統の技を守りながら、新たな感性で進化していく銘仙は今も生き続けています。
大正時代、人々は流行のファッションに身を包み、街を確保していました。おしゃれなモダンボーイたちは、ヤマタカ坊にスーツ。そして忘れてならないのがステッキでした。そのステッキという言葉を生み出した老舗があります。
「いらっしゃいませ」
明治15年創業のステッキ専門店です。
「これは銀製の持ち手に極端の棒をつけたもの。そしてこれ大国頭って言うんですって。昔からこの大黒頭と言われる手も多くありましたし、あとはこういったウェーブ状の握りやすい形のものですね。そういったものがやっぱり主流で前々回作られていたようですね」
シンプルな形だからこそ、細工や素材にこだわったステッキ。貴重なものを見せていただきました。南米原産の希少な樹木スネークウッドで作られた最高級品です。本当蛇の皮のような木目。ちなみに百万円を超えるものもあるそうです。これは竹のステッキ。日本の竹の根の部分を使い、熱をかけ手作業で曲げるというもの。今ではこうしたステッキを作れる職人はほとんどいなくなったそうです。創業者は高石さんの総祖父。元々は刀剣匠でした。明治になって、横浜で外国人紳士がステッキを持ち歩くのを見て、日本で最初のステッキ専門店を銀座に開きました。店の常連にはこんな方も。政治家・吉田茂。
「お似合いですね。いいものを作りしてお客様に喜んでいただくというのが一番大切なことでございまして、四十五年ほどステッキの方を取り扱っておりますので、私の人生の一部になっていると思いますね」
最後の壺は受け継ぎ、守ってきた想い
東京江戸川区。今では少なくなったステッキ職人の工房です。高橋秀雄さん。この道三十二年のベテランです。持ち手の型を移し、材料を切り抜きます。力を入れすぎれば材料が割れてしまう繊細な作業。次に持ち手の角を削り取ります。曲線で作られる表面の形はすべて高橋さんの手の感覚です。どこまで削るか、それは微妙な力加減。
「あの型通りに作って前は良かったんだけどそれがなんかなんかダサいなって思い始める時があるんですよなんかずっとやってるともうちょっとこっちの方がかっこいいかなみたいなそこで厚みを増したりしてそれでやっとかっこいい形が出来上がってくるみたいな」
長年の経験が受け継がれてきた形をより良いものに変えていく職人技です。
「ごめんなさい」
持ち手と棒をつなげます。ここまでわずか35分。つなぎ目を滑らかに整えていきます。
「使ってもらう人がいるから真面目に作んないとなっていう気持ちでは作ってますよね。ちゃんと自分の納得したものを届けたいっていう思いはある」
これは高橋さんオリジナルデザインのステッキ。二種類の材料を貼り合わせた持ち手が特徴です。実に滑らかな曲線眺め。集めた材料を見せてくれました。
「これがまあスネグところが、この材料を自分では使わないと言います。俺より次の人はもしかしたら技術もあるし発想もあるしっていう想像できちゃうんでだからそう考えると、良い材料は自分ですかっていうよりも、使い切るっていうよりも、残した置いてあげたいなっていうなのそっちかなぁ。こんなとしたら、いつか受け継いでくれる人がもっといいステッキを使ってくれるだからこそ貴重な材料は取っておきたい」
ステッキ作りに込めた高橋さんの思いです。