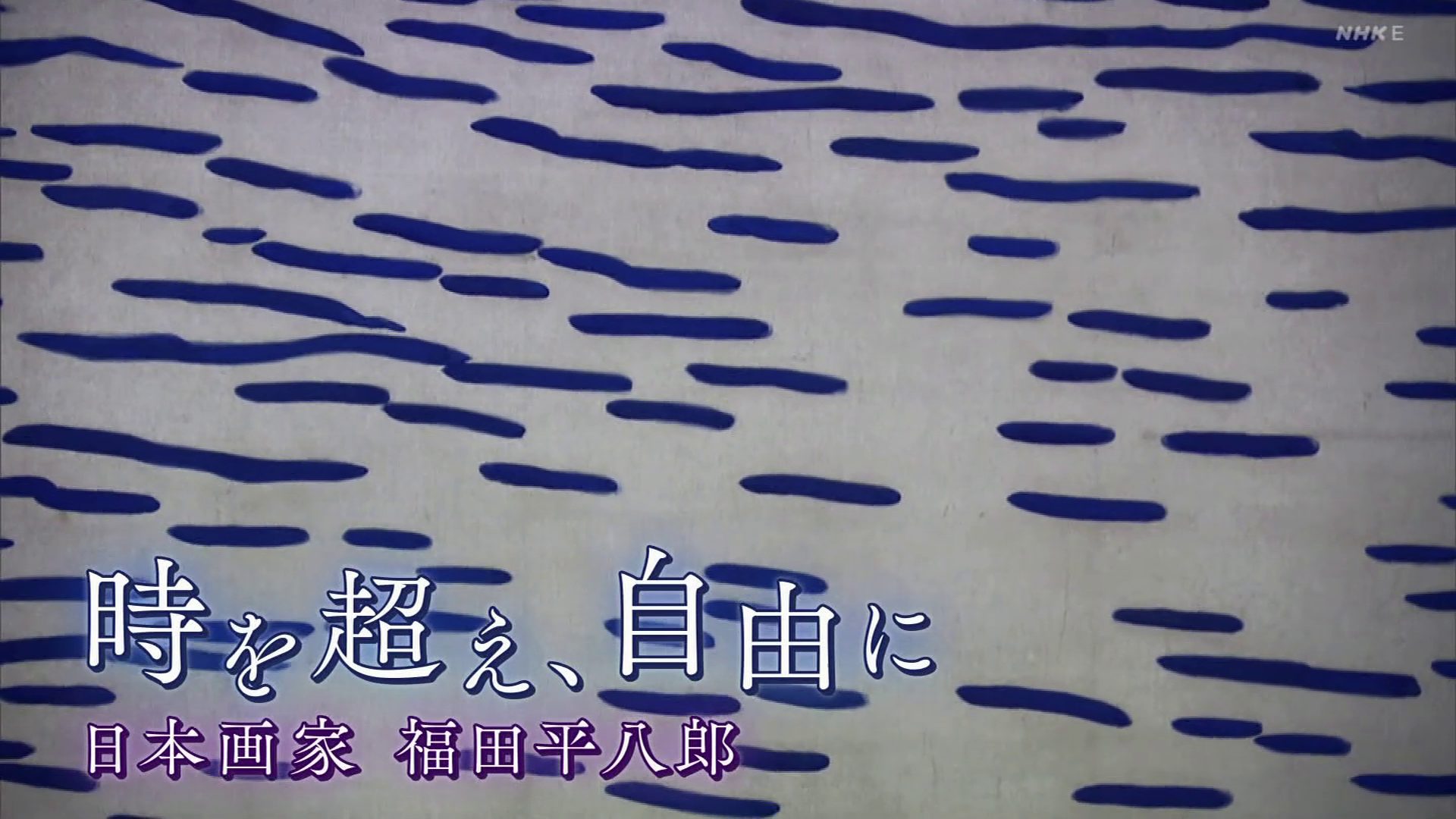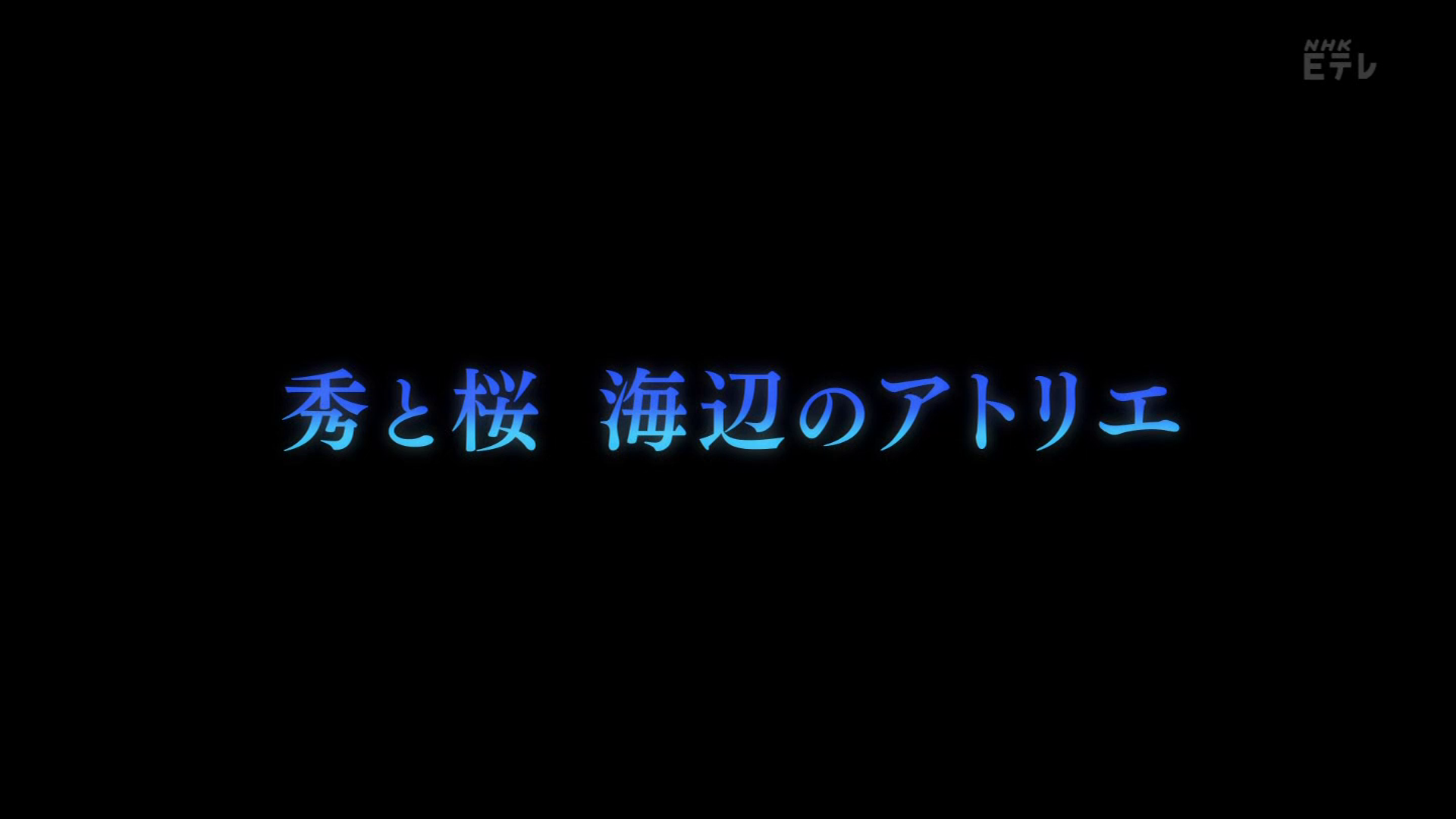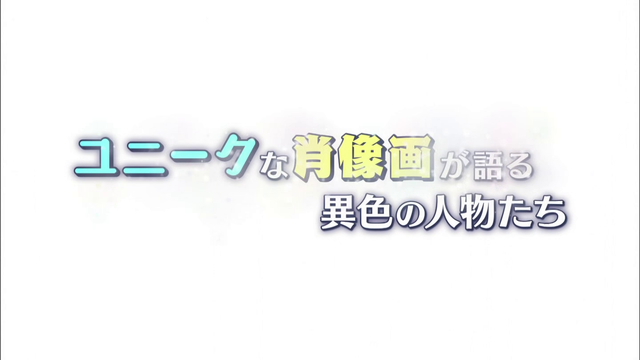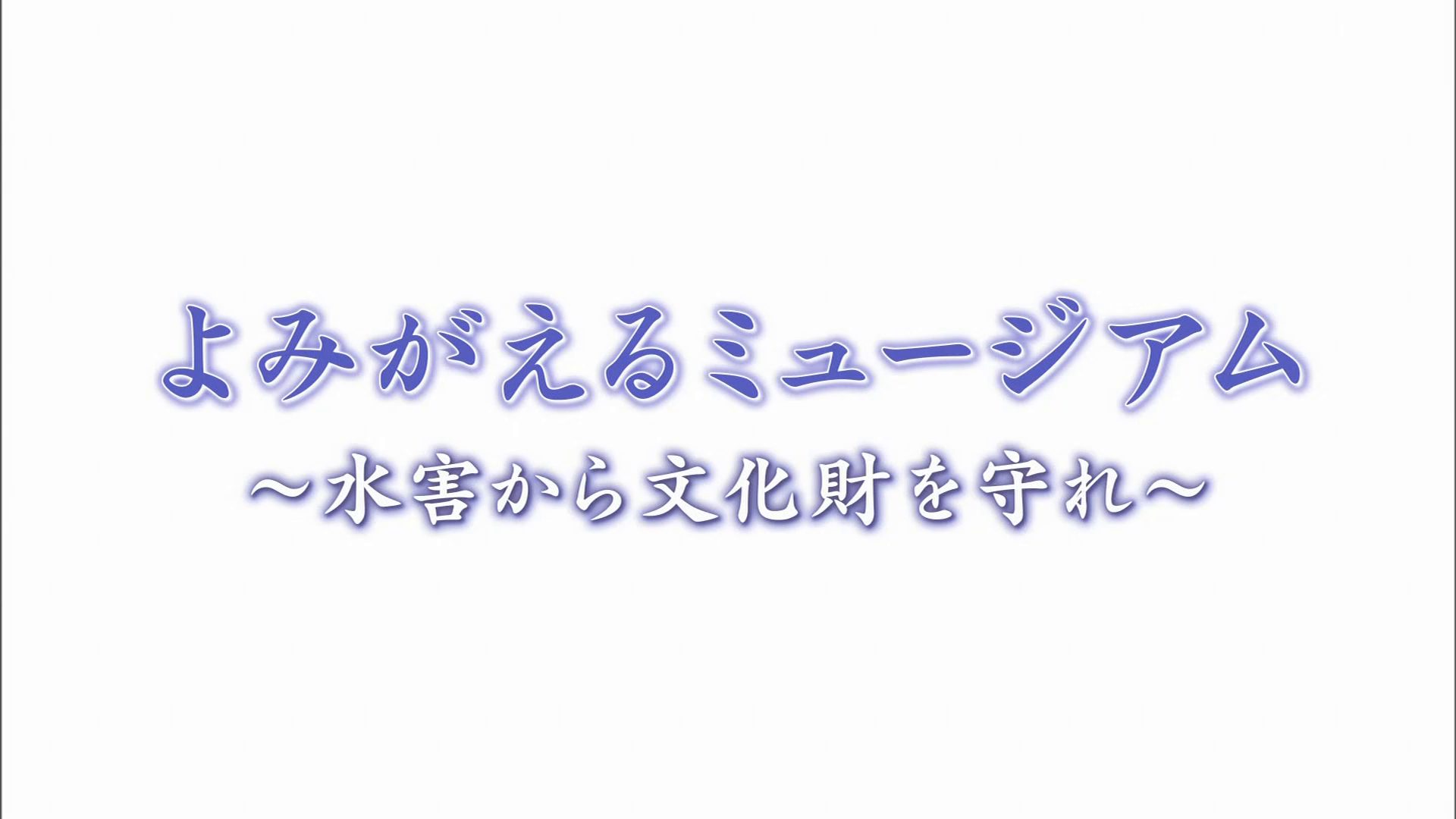写実なのか、抽象なのか。大正から昭和にかけて活躍した日本画家・福田平八郎(1892-1974)。時に賛否両論を巻き起こしながら、革新的な日本画を描き続けた。膨大な写生を重ねながら自然を徹底的に見つめ、まるで抽象画のような独特の日本画を追求した。若い頃から晩年まで傑作の数々を紹介。60年以上、倉庫に眠っていた幻の作品から、時代を超える美の秘密を探る。展覧会は、現在、大分県立美術館で開催中。
初回放送日:2024年4月14日
日曜美術館
画家は、その絵に何も言葉を残しませんでした。そして60年以上、家の倉庫の奥に封印されていたのです。青い空と雲だけ。しかし、そこには画家の挑戦の軌跡が秘められています。「これが発表された当時、賛否両論があり、問題作として位置づけられていたようです。」
描いたのは、大正から昭和にかけて日本画を牽引した福田平八郎。「大胆な色使い、自然を見つめる独特の眼差し。素晴らしいですね。全く古くなっていないどころか、まさか90年前に描かれたとは誰も思わないでしょう。」
その原点にあるのは、徹底した写実。しかし、見尽くそうとした果てに、彼は大きな壁にぶつかります。「息苦しい感じがします。すべてを変えてやろうという意気込みを感じますね。」
福田平八郎の芸術は、今なお私たちに響き続けています。
「時を超え、自由に 日本画家・福田平八郎」
日曜美術館です。今日は大阪の中之島美術館に来ています。ここでは、大正から昭和にかけて活躍した福田平八郎の展覧会が開催中です。本日のゲストをご紹介しましょう。日本画家の千住博さんです。よろしくお願いします。
ニューヨークを拠点に活躍する日本画家の千住博さん。代表作の『滝』をはじめ、自然をモチーフにした作品で世界的に評価されています。
「千住さん、福田平八郎というと、どんな印象の画家ですか?」
「そうですね、日本画の基礎を作った方です。とても重要な方だと思っています。現代日本画はここから始まったと言っても過言ではないですね。今日の展覧会、とても楽しみにしています。」
平八郎の最高傑作とも言われる「漣(さざなみ)」です。
「見たかったんです。何回見ても現代的だし目の前に立ってると体が勝手に揺れてしまう。現代でも、コンテンポラリアートとして十分通用するし、世界 の人がこれ初めて見たら、まさか九十年前にこれ書いたとは誰も思わないですよ。」

福田平八郎が生まれ育った大分市。地元の美術館には、多くの資料が残されています。吉田孝太郎さんは、長年にわたって平八郎の研究を続けている人物です。
「こちらが写生帳になります。福田平八郎の創作の原点となるものです。数百冊ありますね。」
これは若き日の写生帳です。美術学校の学生だった頃、講師から「君は自然を客観的に見つめるのがいい」とアドバイスを受け、その言葉を羅針盤として、彼は自らを「写生狂」と称するほど写生に没頭しました。
「徹底的に対象を観察して描く、これが彼のスタイルですね。細部まで観察することで、自然のすべてを掴み取りたいという思いを持っていたようです。」
子どもの頃から絵が好きだった平八郎。
十八歳の頃、数学の成績が原因で留年、地元の学校を中退し、京都の美術学校に入学します。
二十一歳の作「野原」。
制作年が確認できる最も若い頃の作品です。若い画家たちが新しい日本画を生み出そうと切磋琢磨する中、平八郎は成績優秀。古典を学ぶとどんな手法も苦もなく身につけていきました。
中でも得意にしていたのが写実。野原の上をよく見るとミツバチが飛んでいます。大きさはわずか一センチ。驚くほど細密です。
福田平八郎に強い関心を寄せている人がいます。画家の諏訪淳さんです。
一人の人間が降りる姿を見つめ尽くし描き切る、現代の写真絵画を代表する画家の一人です。まず目をとめたのは、ツルを描いた若い頃の素描。平八郎は写生をする時、動物でも植物でも自分の手で触れることを大切にしていたと言います。
「多分、間違いなく死んだ鳥だと思うんですが、おそらく死んだ鶴を手に入れて、それを地べたに置いて、地面なのかな、机なのかな、そこに置いて、それを写生しているように見えます。
この辺りにたくさんためらうような、探るような線が残ってますけれども、いろいろ試行錯誤してますよね。消したり、引いたり、彼は自分が知っている鳥の形っていうのは本当に思った通りだったんだろうかって、一つ一つ確認して認識し直してるんだと思います。きっと。
翼というものはこういうものなんだ、鶴っていうものの重みっていうのはこういうものなんだっていうのは、一つ一つこう確認をして、調べ直している。描いてるっていうのを調べているっていうような、そういうような印象がありますね。」
二十九歳、平八郎の名を世に知らしめたのがこの作品「鯉」。
鱗の数まで数え、光によって変わる色の違いまで捉えようとしました。
そして驚くべきは水の描写。鯉の影と濃淡によって描かずして水の確かな存在感を生み出しています。
この作品が帝展で特選を受賞。一躍人気画家となりました。
「すごいですね。一つ一つのその鯉も、鱗をこう一枚一枚の鱗もすべてこう描き尽くしてやるっていうような、そういうその描写の的確さ。嫌になっちゃいますね。
この鱗を全部描けって言われたら、描写するっていうことで言えば、まあ平八郎の影を俯瞰してみた時、ある頂点にはいると思うんですよ。これ以上描写力を上げて何の意味があるんだというところまで来ているような予感はしますけれども。」
しかし諏訪さんは同じ二十代の絵からあることを感じ取っていました。平八郎が長崎を旅した時に、羊の群れを見て書いた作品です。
「例えば動物が動いていて、現場でこれを描くことはできませんよね。だからいろんな場面を多分スケッチして、それを合成したような絵に見えていて、僕にはうまくいってるとはちょっと思えないっていうか、息苦しい感じがします。とても悩んでるっていうよりは、すべてを書いてやろうっていう感じがしますかね。」
画家として大成し、結婚。しかし、三十代半ば、大きな壁にぶつかります。写実の限界を感じ、自分の表現を確立できない焦りから、体調も崩すようになりました。
あまりに一本調子に過ぎる、あまりに細かすぎる、そんなふうにも言われたけれども、その時そうではない 道は私の前にはなかった。神経衰弱だ医師がそう言ったダメだ、到底人間の力では、自然のあらゆる部分など見極め得るものではありはしない。
転機が訪れたのは四十歳。恩師に勧められ、釣りを始めたのがきっかけでした。ある夏の日、なかなか釣れず、浮きを睨んでいた目を水面に移した時、突然心を動かされます。
平八郎の肉声が残っています。風がさー っと今度、逆波みが立たない、それから今度はね、いい頃合いの風が来て逆波が立ってきたまで、こんな竿を捨ててですね一生懸命写生しようと
平八郎は釣竿と写生帳を手に、十日かけて琵琶湖を一周。当初は実際の湖面に近い色を使い、魚も描こうとしていました。しかし、次第に波そのものを見つめるようになります。
「波の形は瞬間の動きでまことにつかみにくいものですいろいろな試みをして実体をつかむのに苦心しました。結局よく見ることが何よりの頼りとなるものです。」
完成直前のおおしたず発表した作品と変わらない大きさです。
「この下地の段階で、いろんな修正を加えているんですよね。こういう薄い線は修正した後になります。微妙に位置を調整しているんですよね。この下地の段階で完全に構図を完成させた上で、本画を描いているんですね。すべてが計算づくなんですね。この縦のすべてもです。一つ一つ、だから本画に起こしたときの書き漏れがないかチェックしているんです。あとですね、一本一本の線は本当にじっくり熟考された末に描かれたものなんです。やっぱり、何か新しいものを表現したい、自分の独自の表現をしたいという、そういう強い思いが結実した一点だと思いますけど。」
昭和七年、平八郎四十歳の作「漣(さざなみ)」。プラチナ博に群青だけで描いた波。この作品は発表当初、厳しい批判にさらされました。しかし、平八郎は言います。
「私一人だけには、あれで間違ってはいないつもりだ。」
「この辺は抽象ですから、例えば写真なんですか、僕は写実だと思いたいです。思いたいし、そう見えます。それはその現象への観察、その観察の果てに、こういう波というものはこういうものだと見て、波の実感を掴んだっていうような痕跡が見られるから。僕は、この辺は写真に見えます。」
発表された当時は浴衣の模様のようだっていうような批判もあったそうなんですね。
「でもこういう作風で発表するっていうことは、やっぱさっきも森本さんがおっしゃったけれども、その当時は 挑戦だったわけですか。その当時も今だって挑戦ですよ。」
「賛否両論はもう覚悟の上、それがやっぱりこの作品を生み出した、その緊張感なんじゃないでしょうかね。」
「どうしても描きたかったんだと思います。この絵から悩みを抜けたみたいなものって感じられたりしますか?」
「もちろんです、はい。もういらないもの全部描いてないじゃないですか。もっとここはもうなんかこう、図らずもおしどりが浮かんできたりとか、いろいろあるんです。切って葉っぱが浮いてたとか。それ全部いらないってことに最後気づいた。他というところが一つ突き抜けたところだったんじゃないですか。
描きたかったのは、その光のゆらめきとか、動いている実際に見ているよりも、きっと心に残ったキラキラした感じっていうのをずっと追い求めてね。ボーンと見つめてると自分の思い出の中みたいに見えてくるんですよ。それはね、そもそもすごくいいことをしちゃって、芸術作品っていうのは、見る人の記憶に触れるかどうかっていう、そこがとても大切なんですよね。
『私の代わりに描いてくれた』と多くの人が思う、感じる。それが結局、普遍性と言われるものの正体ですよね。みんなの思い出の海、私たちはこう感じませんか?どうですか?という問いかけなんですよ。」
「こちらが竹という作品です。すごくポップだし、竹に使われると思わないような色んな色彩が使われていてカラフルですね。」
「その柄も全部違うし、もちろん使っている色も、同じように茶色っぽくても全部違う色を使ってるし。この三本のこのたけのこも、よく見るともう全然違いますよね。もう見事としか言いようがないと思いますね。」
平八郎は独自の探求を続けます。
「このスケッチブックの表示にもですね、竹とあるんで すが京都近郊のですね竹林をくまなく訪ね回って、写生を繰り返していますね。」
竹とは思えないほど多彩な色。竹といえば緑青という伝統にとらわれず、見るたびに印象を変える竹を見つめ続けます。年を重ねてできたシミまで、三年見続けても、竹の色がとらえきれないと、ひたすら写生を重ねました。
「こういう風に色のメモが残っているんですよね。現場で色を入れるのではなくて、後で家に帰った後で色を入れるというようなことをしています。本人にしかわからないような略語が使われてたりするんで、写生の対象からまず何を一番強く感ずるかというと、形や線よりも先に色彩を強く感じる。そしてこの色彩を追求していると、自然に対象の形を捉えることができる。こんなに竹っていうのが色の幅があったものかっていうのが、ちょっと驚かされるんですけれども、実際、写生のスケッチから来てるんですよね。これはやっぱり必然から何かを読み取ろうっていう、そういう視線はもうそう感じます。」
この頃、平八郎はジャンルを超えて自由な絵画表現を研究する陸上会に参加します。マティスのもとで学んだ中川紀元ら洋画家たちとも交流し、西洋の新しい思想や理論に触れ、世界を広げていきます。平八郎が海外の画家たちから刺激を受けていたことを伝える絵が残されています。
西洋画の模写です。こちらはマーク・ロスコなど、戦後の展覧会で見たアメリカの抽象画家たちの作品です。西洋美術の展覧会に足しげく通い、気になる作品を書き写しました。ピカソが美術雑誌の表紙に描いた絵の模写や、色と形を簡略化した抽象の要素が強い作品に関心を寄せていました。
「非常に好奇心旺盛で、新しいものを吸収しようという意欲に溢れていた人だったんですね。何か新しいものを表現しようとしている、その方向性には共感するものがあるというようなことも語っていますね。」
平八郎はそれまでの日本画にはない斬新な表現に挑みます。
柿の葉の写生です。上が六月、下が七月。六月の若葉は深い緑、それが一ヶ月後、群青に水色のハイライトで日差しを照り返す様子を書き写しています。そして描いたのが青柿。まだ実が青い柿。艶のある葉に夏の光が降り注ぎます。平八郎は、この頃の葉が光を受けていろいろに変化するのがいっそう美しいと語っています。
大自然の呼吸とか脈拍とか、それこそは自然の面影であり、姿であるはずだ私はじっと見入った私の心を、その目が映した
不思議な写生が残されています冬庭で見つけたある光景それをもとに書いた 作品グレーと白 だけの静寂の世界これは一体
「これまた細胞みたいな。これが氷ですか本当に発想が自由ですよね。ひんやりした手を触った時、冷たいというのが何よりも描きたかったことなんじゃないかなと思います。
「氷っていう、まさに自然が作り上げたものを追求していった先に、この非常に単純化されたというか、八郎にとってはその本当の写実というか、そっくりに書くことだけでは到達できない思いっていうのがやっぱりあったんですね。」
「実とはそっくりに書くことではなかったかと、なかったんじゃないかと私は思うんですね。彼にとってのその要するに写実っていうのは、やっぱりそのものの真実の真実は何かを観察し尽くすことなんだと思うんですよね。その平八郎の場合っていうのは、自然の側に身を置いて一歩もそこから離れなかったということですよね。だからこれ、やっぱり愚笑画だと思って見ることが大切だと思いますね。そう思う方がより平八郎の心情に近づくんじゃないかと思うんですね。苦笑を見極めたら、結果的に極めて抽象的なものになっていったと。抽象的ですね、中小画ではなくてね、写真とか観察っていう彼の持っていた概念というのは、もっとものの究極の真実を見抜くというようなことだったと思う。」
謎の多い一枚が残されています。二千十四年、学芸員の吉田さんが調査のため遺族の家を訪れた時、倉庫の一番奥にある絵を発見しました。描かれていたのは空と雲だけ。七十四年前の日展に出品された後、一度も公開されたことのない幻の作品でした。発見された時、絵の表面には無数のシミやカビが発生し、修復が必要な状態でした。
「これ、発表された当時ですね、賛否両論あってですね、やっぱりちょっとあの問題作として位置づけられていたようです。平八郎自身どう思ってたかっていうのはですね、実は言葉が全く残ってないんですよ。結構平八郎は自分自身の作品について語っていることも多いんですけど、この作品に関してはですね、一切自らの言葉が残ってないんですよね。」
戦後、欧米の文化や価値観が一気に流れ込みます。当時の新聞記事です。「伝統に甘んじ、個性が失われてゆく日本画の危機」。西洋画に押され、その存在意義が厳しく問われていました。しかし平八郎は日本画にこだわります。雪が積もった日に写生をする姿。平八郎は冬の京都で日本庭園を巡り、写生を重ねました。
戦後間もない昭和二十三年に発表した「新設」。庭石に柔らかそうな雪が降り積もっています。雪は降り止んだ直後、結晶が輝いているところを表現しようとしたと言います。明るい紫を三十回も下塗りして、その上に白い五分を刷毛で何度も叩いて描いています。
「今や日本画と油絵の区別はただ使っている絵の具が違うだけというのですが、私は決してそれだけだとは思っていません。日本人が日本の伝統の基礎に立って自然の神髄を描くことにあると信じています。」
平八郎の目は意外なものにも向けられていきます。これは紙テープ。平八郎の孫の福田弘子さんです。「幼い頃、週末はいつも兵八郎の家で過ごしました。画室にておじいちゃんを見張って、その辺の絵の具で描いてとか、それが楽しみに家に遊びに行ってたって感じで、いつもずっとそこで二人でいた。」
「大和さんから見て、どんな人でしたか?」
「一言で言うと、ちょっと変わった花って感じ。なんか何でも気になったらすぐ撮影した。いただきものが多かったんですけど、果物とか。それをいただいたら、すぐとりあえず食べる前に撮影した。だから長々と出せば口に入らないんですよ。写生が終わるまでね。牡蠣と明太子、いただきものの富山のお菓子。テレビの天気予報で見た天気図まで、絵を描くために、どこそこ行ってそれを見るとか、そういうのは思えなかったような気がしますけど、ちょっと勉強へねとは言いたかったかな。私にそうやでって言うんじゃなくて、独り言やとは違います。」
そんな兵八郎がふと空を見上げた時、目に留まったのは青空と湧き上がる乳童雲。この作品は千九百五十年の日展に出品され、賛否両論を呼びます。平八郎は何も言葉を残さず、六十年以上封印されることになりました。しかし、修復の過程で意外なことがわかってきました。鮮やかな青を出すために、日本画では通常使われない化学合成顔料を使用した可能性が出てきました。平八郎の悪魔的探求心が秘められていたのです。
「もう明確になりましたね何かがいろんな紆余曲折を経て、いろんなものを削ぎ落として自由になったっていう。」
「全くその通りなんですよ。本当にね、圧倒的ですよね。平八郎が言いたかったことは、誰もが同じに空を見上げれば、こうやって見える雲と空を描くことによって、私たちは自由だと。どんな立場の人も、どんな国籍の人も、空を見上げれば、青空があって、大きく雲が広がっていることを見て感動しないわけがないだろうというね。本当の意味で日本画を新しい日本画の時代を迎えようとした、もうまさにその一作なんだと私は考えています。間違いなく世界が認めるアーティストであって、その根底は日本文化なんですよ。
どんな戦後、日本文化が否定されても、雪に埋もれたような形をとりながらも、日本文化というものを信じている。それもまた素晴らしいところじゃないですか。見ることを突き詰めていくと、一番見たいもの、一番伝えたいものっていうのは、やっぱり音楽にも通じるものがあるので、そういう意味でも、そういうことがしたいな、私もって思いましたし、本質を掴むということをね、やれるようになりたいですね。」