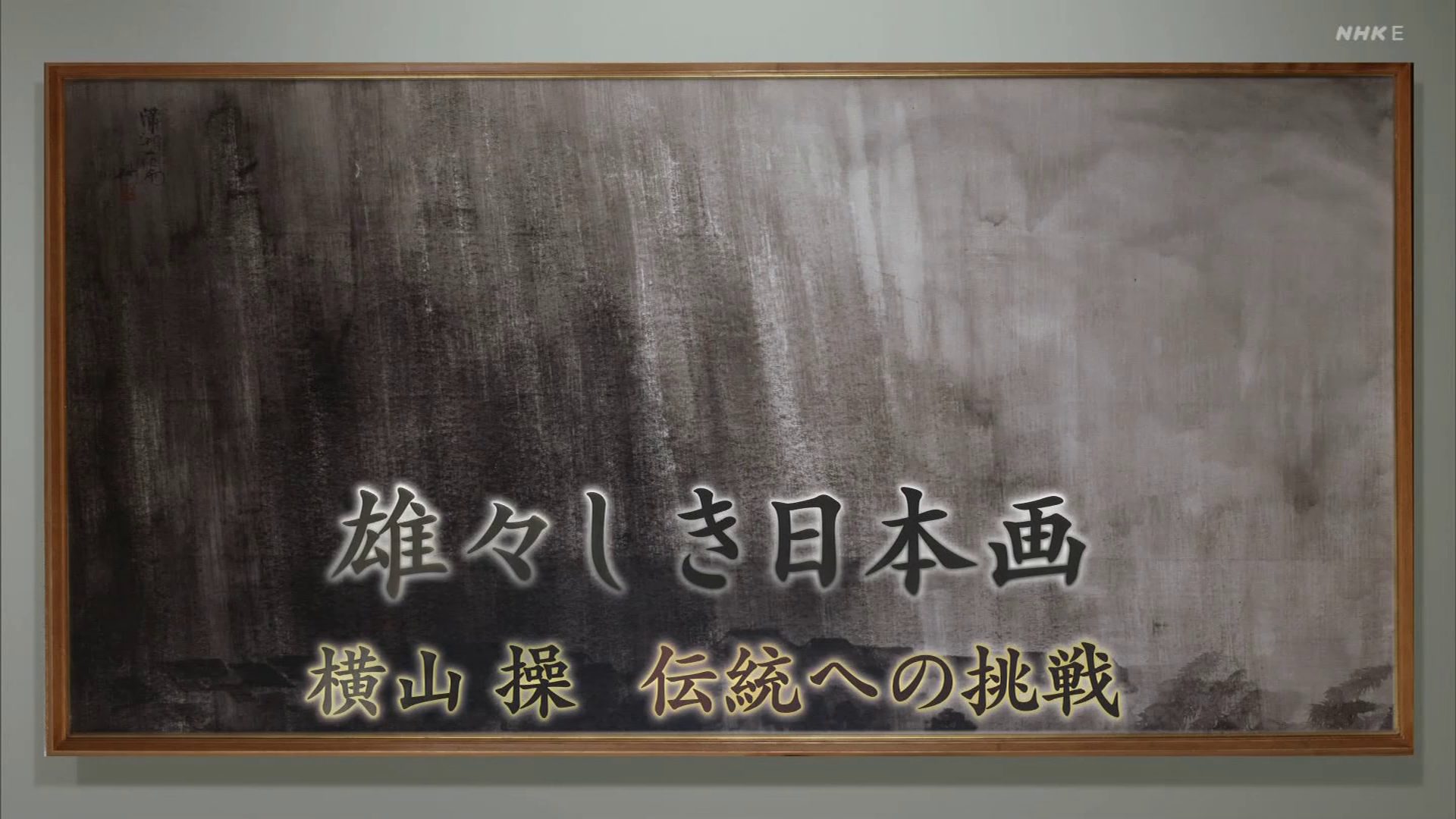1950年代、風雲児のように現れた画家、横山操(1920~1973)横山の絵が世間を驚かせたのは、およそ日本画らしからぬ画題だった。『溶鉱炉』は製鉄所の工場が描かれ、『塔』には、事で焼け落ちた谷中の五重塔の黒焦げた骨組みが描かれた。作品の根底には、20代の10年間を従軍とシベリア抑留で奪われた悲惨な体験が横たわる。番組では、生誕100年を機に日本画の伝統に挑戦し続けた画家、横山操の絵と人生を描く。
【出演】【日本画家】平松礼二,【日本画家】中野嘉之,【美術評論家】横山秀樹,【語り】柴田祐規子
放送:2021年1月24日
日曜美術館 「雄々しき日本画〜横山操、伝統への挑戦〜」

画面いっぱいに大噴火を起こす桜島。
これまでの日本画のイメージを打ち壊す絵です。
描いたのは日本画家の横山操です。
日本画とは生きている現実を表現することだと横山は考えました。
黒焦げになった骨組みを残す五重塔。
横山は五重塔炎上のニュースを聞いて現場に駆けつけました。
「灼け落ちて真っ暗なぬけがらをね、それを作品に仕上げるって事は見たことも聞いたこともなかったですから。静かなる世界を壊してくようなそういうものすごく革新的なものを感じましたね」
社会的な課題で旋風を巻き起こす一方で、横山は日本画の伝統にも挑戦しました。

一つは富士山です。
赤富士は人気を呼び、横山を流行作家に押し上げました。
もう一つの伝統への挑戦は水墨画でした。
白と黒とがせめぎ合い、まるで抽象画のような風景です。
「墨の色は深いんだ。何百色もあるんだということを、先生いつもおっしゃってるけども、悠久の空間っていうのかな。空間の捉え方が斬新だったと思いました。誰も考えなかった」
大画面に大胆な筆遣い。
雄々しき日本画とも言われる横山の絵。
日本画の伝統に挑戦し続けた横山操の作品に迫ります。
やれないのではない。やらないからだ。
自らを奮い立たせる言葉を画室に貼っていた横山操。
昭和30年この時35歳だった横山は、真正面から日本の現実を描くというかつてない日本画に挑んでいました。
敗戦から10年。
日本は戦後復興を終え、高度経済成長に差し掛かっていました。
それを牽引したのが鉄鋼業です。
横山はその工場を日本画で描いたのです。
横幅が11メートル近い巨大画面いっぱいに、製鉄所の内部が捉えられています。
太い鉄柱に上をワイヤーが渡り、クレーンが動いています。
もうもうたる水蒸気が室内に充満し、その間に溶け出した赤い鉄の流れが垣間見えます。
まるで工場の中にいるかのような臨場感です。
「僕は、僕の画面に今の日本をぶつけようと思っている。そこにはこんな構図にしようとか、こんな絵の具を使おうと考えることよりも、下手でも、まずくとも、自分ではそんな表現しかできないんだ。というところをとことんまで表そうと勤めている」
食料増産のために漁業の振興に躍起となっていた日本。
沿岸から沖合い。さらに遠洋へとを漁場を求めて行きました。
茶色い漁船の網がいくつも吊るされ、横幅9メートルの画面全体を覆っています。
黒いロープが斜めに走り、網越しに漁港の建物がシルエットで浮かんでいます。
人の姿は見当たりませんが、入り組んだ巨大な網を通して、漁師たちの働く姿が浮かんでくるようです。
桜島に写生旅行に出かけた横山は噴火を目撃しました。
その3ヶ月後に仕上げられた横幅4.5メートルの絵。
黒い山肌。
こぶのようにゴツゴツと突き出た岩山。
その中央から火山灰が激しく吹き上がっています。
噴火を目の当たりにした時の戦慄を、叩きつけているかのような荒々しい筆さばきです。
日本美術に影響を受けた画家・モネに触発され、新たな日本画を制作し続けている平松礼二さん。
高校生の時、横山操の絵を見て激しい衝撃を受けて以来、今日まで横山を生涯の師と仰いできました。
「この延々桜島には本当にね、自分もう言葉にならないくらいな衝撃を受けましたね。とにかく地底から沸き起こるようなエネルギーですとか高温ですとか、雷鳴ですとか、いろんなものが一度に画面からウワーっと僕らの方に降りかかってくるような感じがありましたね。そうだまさに革新ってこういう絵画のこと言うんだって、当時は思いでした。やっぱり戦後間もなくでしたから。本当に自分達も立ち上がってくんだって言う。若い者がいるそしてこういう革新的な仕事していきたいなっていうね、それこそ体の底からですね描かなきゃっていう使命感みたいなものが大きかったんじゃないでしょうかね」
バケツや鍋などが雑然と置かれた画室。
巨大な画面で日本の現実の姿を捉えるという破天荒な日本画はどのようにして生まれたのでしょうか。
その原点には横山の戦争体験がありました。
新潟県に生まれた横山は14歳の時、画家を目指して上京します。
それは昭和9年。
既に戦争の足音が近づいていました。
ポスター描きの手伝いなどをしながら画学校に通い、絵の勉強に打ち込みます。
しかし展覧会に絵が入選するようになった頃、召集令状が舞い込みます。
寄せ描きの書かれた日の丸と共に出征する横山。
この時、ちょうど二十歳でした。
兵士となった横山が赴いたのは中国戦線でした。
それ以後。敗戦まで5年間に渡り、中国大陸を転戦します。
従軍中の様子が伺える資料が残っています。
長年横山の研究を続けてきた横山秀樹さんです。
「中国に従軍していた時に故郷に送ったら軍事郵便の6通のハガキです。操が十分していた時も絵を描いていたということが分かる資料になります」
「今日はスケッチをしました。戦場の絶対の中にも、ふんわりと美しい優しいものがあります」
「操の支えだったんじゃないんでしょうかね。絵を描くっていうことが、やっぱりその戦争に行ってそこん中戦ってそれ生きていくっていう中でも、やはり一つの自分の生きてることの証というような、そういうものが操の中にあったんかもしれませんですね」
横山の戦争は敗戦になっても終わりませんでした。
シベリアに抑留されたのです。
連れて行かれたのは現在のカザフスタン共和国にある捕虜収容所。
そこで四年半もの間、石炭の採掘という重労働を強いられました。
昭和25年
日本に帰ってきた時、横山は三十歳になっていました。
戦争と抑留によって青春を翻弄された横山。
この頃、絵にかける熱い思いをこう記しました。
「虐げられし生活に満たされし喜びを求めて、すべては燃ゆる熱情と闘魂が芸術へ進ませ生活を斗わす。熱情と憤激。これが俺の人生だ」
熱情と憤激を持って横山が描いたのは日本の現実の姿でした。
かつて東京の谷中霊園には五重塔があり、東京名所の一つとなっていました。
昭和32年
この五重塔は放火によって全焼します。
横山はニュースを聞いて、まだ余燼が燻る現場に駆けつけて、その姿をスケッチしたと言います。
黒焦げになって無残な姿をさらす五重塔。
豪放な筆使いで描かれた黒々としてたくましい塔の骨組みは、圧倒的な存在感をもって迫ってきます。
「骨があるじゃないか。この骨が元なんだけって、色を制限して焼けた黒い炭のようなものだけでぐいぐいぐいぐいと骨格を描いていく。そこまで迫った作品はそれまで見たことなかったものですから。この作品が生まれる前にシベリアで抑留されて、過酷な経験をされているわけですよね。それで生きるか死ぬかって限界ギリギリですね。シベリアで死ぬというと骨と皮とかになってということですから、やっぱりどう着飾っていても、どう装っていても自分たちの一番やっぱり根っこのところは生きるか死ぬかなんだよっていうねなんか生死感みたいなところが現れて、骨と皮しか残らない事がでも本当はここにあるんだってところがね」
独創的な水墨画の作品で知られる日本画家の中野嘉之さん。
学生時代大学の教壇に立っていた横山操からじかに絵を教わりました。
中野さんが衝撃を受けた作品の一つが塔でした。
「臭いまで感じますね。後は熱気とね。焼け焦げた後の虚しい臭いというのかな。そういうものが特に僕はね、線の表現。墨の表現の中の後ろにあるブルーとか赤とか下地にちょっと残っているね、黒を塗る前の、こう計算された余韻を感じさせるための下塗り方。それがやっぱりその音と匂いを感じさせる要因でもあると。それがやっぱり横山操の腕の妙技だと思いますね。それはものを見た瞬間瞬間の、スケッチした時と同じような動きを心の中でしてる。普通に見て描こうっていうその行動がね、多分なかなかしないと思うんだよね。だから常に何かこう自分の欲求ってのがあって、そのチャンスってのを流さないですぐ行動するんですかね。いつもいつも頭の中には絵を描く。ものをつかむ。感じるって言うことをいつも心の中に宿ってたんだろうなと思いますね」
昭和37年
北海道の十勝岳が噴火しました。
たまたま絵の制作のため北海道に渡っていた横山は現地に駆けつけました。
目に焼き付けた噴火の様子を、横山は横幅6メートルを超える大画面に描きだしました。
「どす黒いキノコ雲が空一面突き上げられる。大自然の空間に怒りの山、十勝が彫り切り刻んだ見事な噴煙像だ。鳴動する大地。稲妻が不気味に光っている。何の怒りをぶちまけるか十勝」
「確か十勝は噴火しましたからね。現象面だけじゃなくて現象の上に自分は中の方から吹き上げる煙はね、自分のを取り巻くやっぱり人間社会に対する怒りであったり、反論であったり反骨であったりしたようにも見ましたね。やっぱり根源の中に自分が本当に苦しい体験をして帰ってきた中には、のうのうとその恵まれたところで絵をを描いてきた人いるじゃないか。あんちくしょうですよね。ついやっぱり絵が吉川先生の場合は叫びになってしまう。唸りになってしまう怒りになってしまう」
従来の日本画のイメージを打ち破り、画壇の風雲児のようになった横山。
40歳を超えると新たな課題に挑みます。
昭和36年
横山はアメリカに取材旅行に出かけました。
その様子を撮影した8ミリフィルムが残っています。
横山は東海岸から西海岸まで40日かけて旅しました。
とりわけ気に入ったのが荒涼とした岩肌が続くグランドキャニオンでした。
「人間が一度も荒らしたことのない地球のシワが。太古のままでここにある。創世記の原始を思わす巨大さであり、しかも自然の作りました、無限の構成美だ。自然の姿が自然のままに残された美しさ。僕はアメリカへ来て、見た」
大自然と対極にある現代文明が作り出した風景も横山は描きました。
ニューヨークの高層ビルです。
一見抽象画のように見えますが、両側に立つの高層ビルです。
ビルとビルとのわずかな隙間から真っ青な空が覗いています。
平松礼二さんは30年近く前、ニューヨークに行き、横山操と同じ場所に立ち、同じ風景を描きました。
「気負って僕だってやってみせるって言う気持ちで、追体験でニューヨーク行ったんですけど、出来上がってみた作品の洒落っ気が全然僕じゃない。横山先生はどこかキラッと効かせる洒落っ気。ようするにデザイン力あるわけですよ。ウォール街の頭の方にフット教会の赤い屋根がね、すっと赤い線を入れること。ふっと効かせるとこ。画面中で作ると言う。これはその時にこれだけ紺碧な青だったかどうかわかりませんが、ひょっとしたら心の中の色じゃないかなと思います。この画面で群青。群青と赤を対的に使いたいと。でも無機質な街はね、でもみんな生きてるよってことで暖かみを出せるような作為があったようにも思えますね」
四十歳を過ぎた横山は他にも新たな画題を手掛けます。
富士山です。
古来描かれてきた課題に挑む気持ちを横山はこう語っています。
「今まで誰も描いたことのないようなすごい富士を描こうと思う」
赤みを帯びた富士山。
その山容を切り裂くように稲妻の光が走ります。
あるいは太く。あるいは鋭く。
縦横無尽に走る金色の光。
雷鳴が激しく轟いています。
このあと横山は様々に変容する富士を描きつづけ、一躍流行作家に躍り出ます。
中でも横山が好み、世間の人気も高かったのが赤富士でした。
「私は富士が神秘のベールに包まれている時より、人間の現実的なドラマを思わせる一瞬が好きだ。私はふとこんな風景に亡くなったおふくろのあかぎれの手を思い出すのである。山腹から山頂へ赤く染めて輝く富嶽自身のドラマには、人間生活の営みに似た一瞬がある」
赤く染まった富士山から母親を思い出した横山。
ふるさと新潟の思い出は夕景と結びついています。
横山の生い立ちは暗い影を帯びています。
実は生後すぐに養子に出されたのです。
少年のとき横山が目に焼き付けた光景が故郷の弥彦山に沈む夕焼けでした。
戦争中の手紙の中でもその光景を懐かしく偲んでいます。
「小学校5年か6年頃だったろうか。私は何とも言えない寂しさから弥彦の山の端に太陽が赤く輝き、やがては小さな灯火がつくまで次々と思い出されて懐かしく」
後に、その印象を故郷というタイトルで絵にしています。
蛇行する川の白い流れ。
野原の向こうは真っ赤な夕焼けです。
「越後では秋から冬にかけてどんより鉛色の空が低く垂れ下がる日が続くので、時たま空一面朱色に彩られた夕焼けの印象は一段と鮮明に童心に刻み込まれた。子どもの目に映った夕焼けはいつも無条件に美しかった。年をとるにつれ、その後はだんだん複雑になった。ある時は雄渾に。ある時は悲壮に。またある時は哀愁をおびて、夕焼けはその時々で千変万化した」
「操が本当にふるさとっていうことで描くときには、寂寥感とか寂しさとかそういうの全体の画面に漂ってくるというのが出てくるですね。実の母もいない。お父さんもいないわけですよ。養子先だけがあるんだけど、そこので最初育ててくれたお母さんもいないです。心の中で支えになってるのは故郷だったと思いますね。故郷の風景。その中に自分の居場所っていうものを見出したって言うなところがあるかもしれない」
横山はふるさとの風景を白と黒の世界として数多く描いていきます。
横幅5メートル近い大画面。
目を凝らすと山間に雪が降りしきる様子だとわかってきます。
こちらは横幅6メートルの画面一杯に新潟平野独特の雪景色が広がります。
稲をかけるための歯さぎとして使われる木々が繊細な筆さばきで描き込まれています。
「寂寥感じゃないのかな。大自然の中にある風景ですけども、微塵もやっぱりその明るさが見えない。葉が落ちてしまえば裸になってくる、歯さぎが人間臭い感じに見えるんですよ。だから真っ白のとこに黒い木肌が、人間の骨が刺さってるようなそういうね寂しさがありますから」
横山は本格的に水墨画に打ち込みます。
フィルムに残る横山の姿。
この中で水墨画への思いをこう語ります。
「僕自身が生きてきた証みたいなものがあったりして僕だってことですよね。色だとか形だとか。線だとか光だとか影だとかってのはとらわれないでね。もっと俺自身のその心の本質をね、スパッとその白と黒の表現の中に置きたいという気がしますね」
横山はこれまで何世紀にもわたり描き続けられてきた水墨画の代表的画題、瀟湘八景に挑みます。
中国の洞庭湖付近の風景を八つの情景として描く瀟湘八景。
山や湖など、人間を取り巻く大自然の姿を詩情豊かに描き出しています。
水墨画ならではの静謐な絵です。
洞庭湖の上空に輝く満月。
湖面も空もひとつになって白々とした空間が広がっています。
様々な三角形の形をした網が並んでいます。
自然と共に生きる水辺の人々の暮らしが垣間見えます。
一方で霧や雨や風など、千変万化する自然の姿を荒々しいタッチで捉えた絵もあります。
激しい勢いで雨が降り注いでいます。
よく見ると下の方には家々が並び、かすかに水面も見えます。
荒涼とした風景が広がっています。
手前には引っ掻いたような荒々しいタッチで描かれた草が生い茂っています。
雲なのか霧なのか。
白と黒とがせめぎ合うように漂っています。
墨のにじみによって表現する「たらしこみ」という技法で幻想的な雰囲気が醸し出されています。
わずかにのぞく家並みがなければまるで抽象画のようです。
長年にわたり水墨の作品を数多く表してきた中野嘉之さんです。
瀟湘八景。三枝青嵐の中で横山が対応しているたらしこみの技法を見せてもらいました。
「そんなボトボト濡らすではなくて、少しかすかに。」
たらしこみをするところにまず水を塗ります。
紙にはあらかじめ礬水が引いてあるため水はすぐには染み込みません。
そして濡れている間に薄い墨を乗せ、滲ませます。
今度は濃い墨。
「上からたらして」
墨を伸ばしながら自然なにじみを活かしていきます。
横山はこうした「たらしこみ」を重ね、墨の奥深い微妙な色合いを出しているのです。
「筆の動かし方ひとつで水が動いて墨が動いてくれて、どういう空間を作るかってのは頭の中で計算した通りにこう行くわけではなくて、だけど頭の中では先生の完成像ってのがちゃんと作られていて、なおかつプラスアルファになるものを、どんどんどんのこの絵を描きながら見つけ出してるのってあるんですね。この空間はもう本当にどこにもないですよね。無限の空間だろうね。白い部分のこの空間が、この黒い墨とのコントラストをしてなおかつこの空間が凝縮されてすっと向こうに、永遠に向こうに行く空間をこの画面で作ってるわけですね」
この平砂落雁では、手前の草むらのところに横山独自の大胆な技法が使われています。
薄い墨と濃い墨で草むらの背景を描きます。
「ちょっと荒いので」
そこに洗い筆でタッチをつけます。
「これペインティングナイフを使っていまして、あまり日本画家こういうペインティングナイフを使ったりすることはないんだけども」
油絵で使うペインティングナイフです。
「こういうふうに先生は・・あんまりこうきつくやるんではなくて、強烈にやるとほじくってしまうので、上側だけを」
さらに墨を重ね、濃い線で草を描きます。
ペインティングナイフで引っ掻いた白い線と合わせ、草むらを表現しているのです。
「多分先生が葉っぱを、草原を描くときに、墨で描いただけではその奥行きが多分でないと思ったんですね。どうしてもこの紙の地肌で葉っぱの動きを出したかったんだと思うのです。不思議なふ距離感は出ますよね。だから厚みも出てきますよね。間に白が入ればこの空間の向こうにまたこういう空間があるって言うのが分かると思いますね。それを出したかったんだと思います。常に革新的でありたいって思われたと思いますね。そうね塔を描いたりとか、延々桜島描いた。あのぐらいの神経と全くよみがえるぐらいの神経でこの絵と対決をしたという風に思います。だからこの絵はすごく好きなんですけど、蘇らせる。物を描くときのその根底から動かすような力がこの中にみなぎっていると僕は思って」
中野さん自身も横山の作品に刺激を受け、30年以上前に瀟湘八景を描きました。
そして十数年前からは本格的に水墨画に取り組んでいます。
「だんだんだん僕は今墨のことに慣れてきて、墨の発色のこととか分かると悪戦苦闘だったんだなってのがわかりますね。墨を手がけてる人は先生が七転八倒してることがわかる。だけどそれをしないとこれが出ない。出なかったと思います。先生の生き様そのものでしょきっと」
**
昭和46年
50代に入った横山を病魔が襲います。
脳卒中で倒れ、右半身不随になったのです。
長く困難なリハビリを経た後、横山は絵筆を左手に持ち替えて、再び絵を描き始めました。
この年、横山はこんな文章を残しています。
「他人に対抗し、自分自身にも反抗し、あらゆる材料をひっさげた孤独な旅人。そんな心が絵を描かせる。私は今過去の作品を振り返る時、作品の一つ一つが絵の具代のなかった時代。酒を飲みすぎた時代。徹夜を繰り返した時代を想起させる。これらの不毛から脱出する帰り道はない。なぜなら現実は地獄に落ちているも同然だと悟ることから始めなければならぬから」
横山が左手で描いた絵です。
どんより曇った空。
ほっそりとした黒い木々が連なる林に残雪の白い道がくねりながら奥に消えています。
この絵を描いていた昭和48年。
横山は再び脳卒中に襲われ亡くなりました。
53歳でした。
死の床でこう語ったと伝えられています。
「悔しいは。地獄でも大作を描くぞ。日本画の将来はどうなる。あとは頼む」