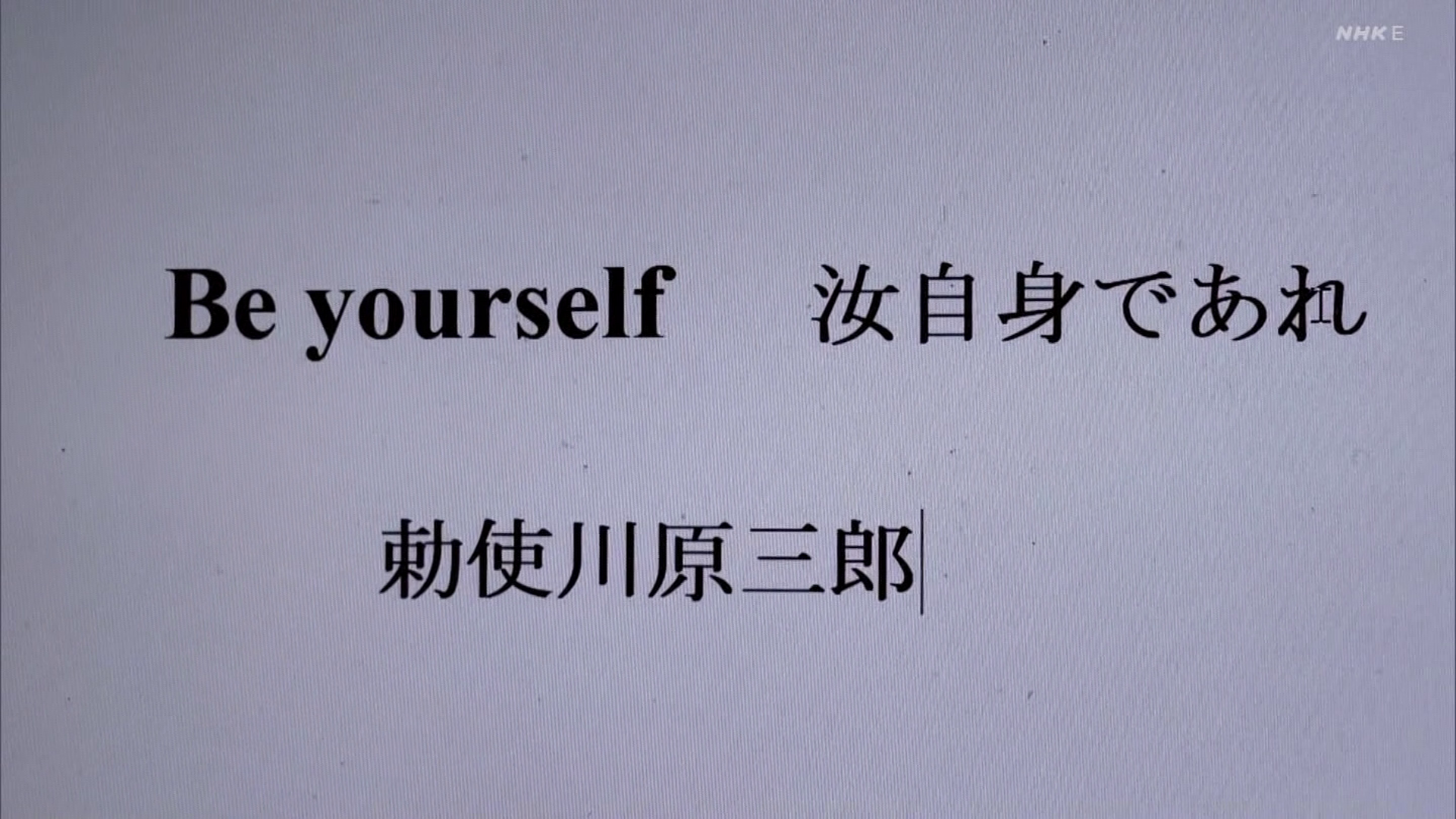「彼は自分の人生の残り時間を常に意識して、先を急ぐように生きていた」。家族や友人、近所の子供など、見知らぬ人々のさりげないポートレートで知られる写真家・ 牛腸茂雄 (ごちょう・しげお)。肉体的なハンディを抱えながら創作を続け、36歳でこの世を去った。死後40年、再評価の機運が高まる中、学生時代からの友人だった写真家・三浦和人は、この夏、牛腸のネガのプリントに挑んだ。浮かび上がる牛腸の「まなざし」とは。
放送:2022年10月30日
日曜美術館 「友よ 写真よ 写真家 牛腸茂雄との日々」

写っているのは見知らぬ人々。
なぜかちょっと懐かしい。
何気ないのに、心を掴まれる不思議な写真。

撮ったのは写真家牛腸茂雄。
幼い頃に患った病のために、肉体的な困難を抱え36年の人生を駆け抜けた。
三流程度の写真家で終わるようであったら僕は写真をやめたい
そうでなければ僕にとっては生きるという意味がなくなってしまうからです
牛腸は3冊の写真集を自費出版で残した。
「写ってるのはもちろん他人だし映してのも自分ではないんですけれども共感する、ここに自分がいるって言う様子がすごく強くある」
「そこにいつのまにか生み出されていたもう一つの宇宙が写真にすごくある」
牛腸と青春を共にし76歳を迎えた親友の写真家。
作品を40年間プリントしてきた。
「100年持つんじゃないかなっていう意識でやってる」
その写真は今も輝く。
「もちろん下の人たちなんですけど、友達とやってるような感覚になります」
「終わりを自分で感じながら生きられてたと思うんですけど、なんかそれを感じさせいあったかさが目の魅力だなぁと思ってて」
なぜ牛腸の写真は時を越えて人々を魅了するのか。

写真家 牛腸茂雄 との日々
写真家・三浦和人。
この夏大きな仕事を抱えている。
展覧会に向け、牛腸の作品を50点以上オリジナルのネガからプリントする。
「自分のだったかなんて、牛腸さんはいい加減なことを何一つしなかった」
焼いているのは牛腸の代表作。
公園で手を繋ぐ双子のポートレート。
「本人が厳しい顔をしているから代表作。これがニコニコしていたらダメだった」

今から45年前に牛腸が発表した「selfandothers」
謎を秘めた不思議な写真集。
1枚目を飾るのは元気に泣く新生児の姿。
あの双子もこの写真集の中に。
連なるのは何気ないポートレート。
思い思いにカメラを見つめる見知らぬ人々の眼差し。
ページをめくっていくと、中盤に出てくるのは牛腸のセルフポートレート。

「見る見られるという関係こそがもうあの写真集の骨格っていうか
本当に背骨になってる。写真集を見ている私たちが向こう側からみられている。写真を撮る。だからこそ牛腸さんの視線目線の追体験を私たちが否応なくさせられる。でそれは決してその攻撃的な力ではなくってじわっとゆっくり優しく心を鷲掴みにされてしまう作品と思いますね」

最後を締めくくるのはまた不思議な一枚。
「最後が霧の中にこうみんなしてフェードアウトしていくような子供達の群像だけですけども、まだ夢の中の光景を見てるみたいな感じなんですけども、目線がこっちに来ない。向こう側にもみんなも進んでいってしまって、霧の中に消えてしまうというある種の怖さ。彼我の彼方みたいな見え方もしてしまったりするわけですけどもそういうもので最後を締めくくるように見えますね」
牛腸の死後オリジナルのネガを大切に保管してきた三浦。
40年間、彼のために作品をプリントしてきた。
1960年代後半の渋谷駅。
急な雨で慌てふためく人人を牛腸が撮った。
渋谷は伍長との思い出の街。
牛腸さんは渋谷好きでしたか。
結構好きだったんじゃないかな、学校3年間いたし
ここはどういうとこに。
桑澤デザイン研究所。
牛腸との出会いはデザイン学校の入学式だった。
「授業が始まるクラス分けがされてる部屋に僕は結構早めに行って、前からさん番目ぐらいに座ってたんですよ
ここ座っていいですか声かけてきて、その時はずっと振り向いたら、牛腸さんがいるわけ。一緒にえっと思ったけどあどうぞ」
幼い頃に患った病気が原因で背骨が大きく湾曲していた。
身長は150センチ程度だった。
「牛腸さんが初めて僕と会ってるという感覚です」
「ここが住吉荘ですよね。それでここのホテルがあったとこが公園だった」
牛腸が下宿の前で遊ぶ子供たちを撮った一枚。
「学生の時はみんなで集まった場所だし、卒業してからは渋谷で終電帰れなくなって泊めてもらったり」
当時のフィルムが残されている。
夜突然訪ねてきた友人を迎える牛腸の姿。
「悪いなあと思いながらあげてくれるんです。牛腸さんお部屋は綺麗だった。ちょっと片付けてもうほんと聞いてもちゃんとしてたし。二十歳になった時ね、フィルムを10分かないつもお世話になってるからってくれたんです。その時に僕もすぐに二十歳になりますけどつって。二十歳まで医者にに生きられるかどうか分からないって言われてましたということをその時初めて。自分のことをあまり話さない牛腸が初めて
学校のカリキュラムは厳しかった。
「課題が重なってくると、本当牛腸さんと会うと徹夜したじゃないんですが。今日は何日目と二日目。十八歳からの牛腸さんとの一人で出てきてるから意識が僕らとはちょっと違う感覚だとつけてね」
牛腸は次第に写真に惹かれて入った。
「すごく迷ってた。まあ写真行けばちょっと大変だよね。大型カメラ持ったり撮影したり色々あるから、肉体は結構しんどいと思うよ。でも行くんだったらじゃあ俺が持ってあるから大丈夫だよ。目的が一つ同じだから。同じ釜の飯を食う一年間でした」
学校を卒業するとすぐに頭角を現した牛腸。
子供という作品を写真専門誌で発表した。
通りを行き交う人々の中にカメラを見て微笑む子供の姿が
このスナップには見えない子供がもう一人。
「ストレートに子供がパッと目に飛び込んでくる写真ではあるんですけれども、看板持った男の子とともに
お母さんのおなかの中にいるこれから生まれようとしている子供みたいなのが画面の中に捉えられてる。牛腸さんは人の命が生まれてそれでどんな風にそれがサイクルを作っていくのかみたいなことへの非常に興味を持ってると
そういう写真で彼は始まっているって凄い興味深いなと思ってます」
子供を発表した頃に牛腸が撮った三浦のポートレート。
三浦自身は好きになれなかったと言う。
その頃どんな感じだったんですか三浦さんご自身。
「会社やめてたのかな。それとも会社にいる時かな。その前後。多分牛腸さんにはいろいろ思ったけど、全然しっかりしてないからもっとしっかりしなさい感覚で撮ってんのかな」
誰とも遊び相手になってもらえず、ただ毎日食べたり寝たり。
気分の良い時には天井の節穴とにらめっこ。
こんな見れもひとつだけ私の友達でもあり、また私の愛したものがあった。
それは丸い20センチぐらいの鏡であった。
鏡は実に不思議な力を持っていた。
時には私の手となり足となり、どこでも写してくれたからだ。
裏の雨戸を開けてもらい裏で遊ぶ友達の姿を映し、
いつしか自分もその仲間に溶け込み一緒に遊んだ気になっていたこともあった。
生い立ち
1946年新潟県加茂市に生まれた牛腸茂雄。
幼い頃に胸椎カリエスにかかり、寝たきりの孤独味わった。
展覧会の準備のために三浦がやってきた。
牛腸の実家は金物店を営んでいる。
三浦は彼の死後ことある事に訪ねている。
だが残された資料や遺品には距離を取ってきた。
「僕は、この資料に関しては触らないようにしてるんですね。彼の個人的なことが多いじゃない。近すぎる」
三浦も知らない新潟時代の牛腸。
回送と銘打たれた文章に綴られていたのは小学校に入学した頃のこと。
その頃牛腸の体は既に病気で変わってしまっていた。
友達と遊んだり話したりすることもできる。
そんな夢と期待を持っていた私であったが、でももう前のように世間は甘くはなかった。
時にはせむし首無と声をかけられたり、見様見真似の仕草を示されたり
大人の人でさえも物珍しげにじろじろとそんな態度にはもうどうすることもできず。
やりきれない悲しみが頬を伝った。
そんな時いつも母のところへ逃げ帰るように駆け込んで、いつものように
「お母ちゃん学校行くの嫌だ。嫌だ死んでしまいたい」
と何度すがりついたことであろうか。
でも母はいつも優しく慰めてくれた。
「しげちゃんは男だろ、そんなことに泣いたりメソメソしたらみっともないよ」
と言って涙をふいてくれて、しげちゃんはまだ子供だから分からないだろうけど、まだまだこれから先、どんなにたくさん大きな山や川があるか分からないんだよ。
それなのにこんなことでメソメソするの母ちゃん嫌いだよ。
どんなことがあっても誰に負けない立派な人にならなくちゃだめだよと、
そんな事を言っている母でさえ涙ぐんできているのを見ると、
こんなことで母に心配かけちゃ悪い気がしたのか、
それからというものあまり母のところへ駆け込むというようなことはなかったようだ。
写真集「selfandothers」
そのちょうど真ん中のページには。
牛腸の母晴恵さんのポートレート。
「アップの写真です。一番大きい。ほとんど顔だけみたい。笑ってるでもなく悲しんでるでもなく、グレーな領域にあるにある顔ですよね」
母親を取った時のフィルムから牛腸が確認用に焼いたコンタクトシート。
そこには息子を優しく見つめる母の姿が。
しかし牛腸がプリントしたのはこのいち枚だった。
「幸せなご自分の子供を見つめて笑ってるっていう表情じゃないものを選ばれてるって言うのは、牛腸さんのやはりお母さんとの関係。単純ではない思いっていうのもそこにいはり組みたかったんだろうな」
仲良く手を繋ぐ男の子と女の子。
実は実家の裏手で撮影された。
「おそらくお隣のクリーニング屋さんの花壇の前で撮った。現在地的にはこちらのかなと思いますね。裏で遊んで手にかけてちょっとここ立ってみてと、手繋いでちょっとこっち向いてみたらと撮ったと思うんですけど。同級生
の床屋さんのお嬢さんで仲良くなかったんですけど、なんかこれ見ると本当に仲良いカップルみたいな感じでちょっとね。ほんと見慣れた裏の通りなんですけど、本当になんか異空間で表情なんかちょっと普段と違う顔でなんか今見ると不思議な感じがします」
おいの一幸さんの姿は写真集の一枚目にも。
そう、あの赤ちゃん。
「人と変わった雰囲気を持ってる大人の人。ちょっと歳の離れたお兄さんみたいな感じで、帰ってくるの楽しみで渋谷のおじさんって呼んでました」

こちらは牛腸の姉春子さん。子供の頃は弟のために毎日お使いに出かけた。
「体が悪いから栄養つけない駄目らしい。お刺身を持って、これより大きい皿のですが、それを持って毎日買いにいってた。その他にねカエル食べさせたことあるし、マムシも体がよくなるためにということでね、いろんな人のお話し聞いてそういうこともやりましたね。中学生自分からねデザイン関係の展で賞もらってましたね」
ポスターの公募展で受賞するなどデザインに興味を持っていた牛腸。
上京して専門的な勉強がしたいと願った。
「どうしてもそういう世界に行きたいって、意志が固かったから心配したけど、私はそのやりたいことをやるんだからいいんじゃねえのという感じで見守っておりましたけどね」
1965年。親は心配したが18歳の牛腸は上京する。
姉の春子さん宛に牛腸がつづった手紙が残されている。
その数40通以上。
「加茂祭りも近づき、姉さんのところもますます忙しい日々をお過ごしのことだろうと思います。僕はまあまあ元気で過ごしています。いよいよ仕事の準備に取り掛かろうと思っていますが、普通の人のように何キロ何十キロもある大型カメラを担いで自由に撮りまくるということは、体力的に全くと言っていいくらい難しいので、仕事の道もかなりきついです。でもここまで来た以上、小型カメラだけを使った仕事で押し通そうとかなり固い決心をしました」
「卒業するとほぼ同時にデビューして写真家として世に知られるようになっていた。今のクワザワ時代の友人の関口正夫さんと一緒に写真集として出すわけですね」

何気ない日常に潜む不思議な一瞬を捉えたスナップショット。

窓辺に佇む空を仰ぐ犬。
その姿はまるで哲学者。
「最初の写真集「日々」声かけられて、あれに一人20枚ですよね。持ってたんですね。彼はずっと見てて。少し足りませんね枚数がって言ってきっぱり。「日々」見るとやっぱすごいクオリティ高い。なんかねそのクオリティを維持するだけの、写真は揃ってませんっていうことだ友達だからとかそういうことはあまり関係ない」
渾身の一冊「日々」
しかし写真会の反応は冷たいものだったで。
「行為的な評価もあったのでしょうけども、かなり厳しい評価があった。牙のない若者たち。学生運動も盛んだったり、世の中が荒々しい、学園があちこちあのバリケード築かれたりというような過激な時代世相だったっていうこともあって、そういったところとあまりコミットしない、非常にこの平和な写真っていうのが「これどうなんだろう。世の中全てこれでいっていう風に安住しちゃってる写真なんじゃないか」っていうなんかないって厳しい印象もあったですね」
批判がありましたが。
「何とんちんかんなこと言ってんのかなという思いはありましたよ。だけどそれはそう思うけど、でもこれが世間一般の目だよなと覚えました。(牛腸は批判に対する気持ちはありましたか)一度も聞いてない。彼は愚痴も言わないんだよね。ちゃんと受け止めてる。
姉の春子さんへの手紙には自分の写真に対するこだわりを隠すことなく綴っていた。
「僕の作品はじっくり何度も観ることで、じわじわ味わいが出てくる写真なのです。僕の写真は見過ごされてしまうかもしれないギリギリのところの写真なのです。一見、なんの変哲もないところで、僕はあえて賭けているのです」
そして牛腸は悩みながらまた一歩踏み出す。
「9月の末を迎えてようやくまだまだ混沌とはしているにはいるけれど、目指す方向がかなりはっきりしてきたようです。将来また何らかの形で写真集の2巻目を出版しようと考えているのです。自分の中の何かの可能性を信じて生きて行かないととてもじゃないけれど気が滅入ってしまう。他人から見るととりとめもない生き方をしているように思われるかもしれないけれど。ないはないなりにそれなりの何かが生まれるのではないかとある確信をもって感じるのです」
次、さらに勝負をかけるさらに踏み込んだ写真集を構想するって中で、人間の深層心理にのめり込んでいって、人間の内面の不思議な世界に分け入って行こうとする。なんとなくその自分の日常で合ってる人関係持ってる人、あるいはたまたま出会った人っていうものもあるようですけれども、そういう人たちとの微妙な距離感をたくさんとりためていきながら、自己と他者って何そういうことをテーマに写真集の実現に向かって進んでいたんじゃないかなという」
「これからは写真はもちろん、映画やとにかくいろんなことをやって行きたい。体力もわずかながら徐々についてきているようだし、小さい頃やれなかったことをこれからは取り戻さなくちゃ」
「間近の物を撮ることと、彼方みたいなものを撮ることがブレンドされてると言うか、誰もがそれぞれに持っているであろう関係の地図みたいなのもの。いろんな人との存在があるって言うことを牛腸は撮ることで一枚の写真だとなかなかそうはならないかもしれないけど、何十枚かの写真が集まった時にそこにいつのまにか生み出されていた宇宙。もう一つの柱はそういう感覚が牛腸さんの写真でしょうか」
子どもを写したフィルムに、なぜか牛腸の姿が・・・・
「子どもの目線で見たときに牛腸さんの体格ってのは、普通の人と違ってたでしょうから、子供の反応をさんざん経験してきたはずなんですよね。カメラはメカで、ここ押すととれるよなんて子どもに渡して撮ってみてといいながら、おそらくどうやったら打ち解けた環境を作ることができるかという工夫を相当ある時期意識してやったんじゃないかな」
「結構やり込められてますよ。牛腸さんやり込められてる。子供たちが結構楽しく牛腸さんをいじめてる。それを牛腸さんは楽しんでいる」
「明日は満30歳。よくもまあ生きてきたものだという考えもあるけれど、とにかく今までの自分の仕事に一つの決着をつけなければならない状況でもあり、一つの節でもある。大切な時期であると自覚しております。実は来春、写真集を出版することに決めました。写真集のタイトルは「self and others」です」
牛腸は5年以上撮りためた写真を再構成し、一冊の写真集を丹念に織り上げていった。
「自分の幸生きた証、写真家としての仕事を後世に伝えたいとかしたいっていうそういう意識が大きかったような。身体にハンディキャップを背負い、二十歳まで生きれるかどうかずっとさ言われていた自分のその命の残りの時間っていうものに対する意識がその人に合ったでしょうし、自分が何を作りそして残していけるだろうかっていうことを真剣に考えた中でやはり写真しかないな」
「牛腸さんと会っていなければ何してたんだろうわかんないね。もう今となっては。牛腸さんが東京出てきて
18年間であれだけの作品作って。僕はまだ50年以上過ぎてるのにまだそこまで行ってるかどうか。近づきたいと思います」
三浦は52歳の時に初めての写真集を発表。
かけがえのない子どもの時間。
三浦はこの一冊を牛腸へ捧げた。
展覧会に向けたプリントも大詰め。
「これはの最後。一番難関」
霧の中に消えていく子供たち。
selfandothersの最後を飾る。
舞台は神奈川の米軍キャンプで行われた花火大会。
花火が終わり、煙が立ち込めるグラウンド。
駆け出していく子どもたちの姿に牛腸はシャッターを切った。
「コントラストないんです。表現されてる。それをもっとはっきりさせてあげる」
そのままプリントすると立ちこめた煙がのっぺりとしてしまい奥行きが出ない。
陰影をどれだけ出すか。
三浦は40年間試行錯誤してきた。
現像の作業は重労働だ。
手作りの暗室にはクーラーがない。
「温度を20度から21、2度」
現像液を冷やすために使う氷は1日で8キロ。
もっとその花火の、その日の雰囲気が出ないか。こういうのって体力勝負じゃないですか。任せればね多分なんでもないと思うんですけどプリントすることは。今回が最後だから悔いが残らないにやろうかなと」
三浦は牛腸と最後に別れた日のことを時折思い返す。
33歳を過ぎたころから、牛腸の体調は急速に悪化していった。
「しんどくなってきたと電話かかってきて。階段上るのがシンドくなってきたからそろそろ家に帰ろうかなと思ってるって。まだ新幹線が大宮までの時代だったから、大宮まで見送りに行くと別れたのが最後」
生まれ故郷新潟加茂に帰った2月後、牛腸はこの世を去った。
最後の言葉が伝えられている。
「ネバーギブアップ」
写真家牛腸茂雄。
享年36。
展覧会がスタートした。
「self and others」最後の一枚に三浦が見つけたこと。
「この写真、霧の中に吸い込まれていく子供達っていう認識なんですね。こっちの世界とあっちの世界行くんですよね。みんなそれだと思った。ところがよーく見ると行く子ばかりじゃないんですよね。あっちの世界から戻ってきてくれる子もいるんです。これですね。この子はどう見てもこっちに来てるように見えるんです。
(それはプリントしているときに気づいた?)
向こうから戻ってる子がいるって子がいるってことは、こっちの希望のがあるのでは。希望の一枚。牛腸さん表現するために桑沢デザインでデザインとか写真の勉強して、自分の生き方をそこで探って、その新潟での18年間を出した。それはね、あの希望なんだよね。だから僕はこの写真を希望として見ていきたいなって思いはありますね」
情報
event&POPUP(写真展 はじめての、牛腸茂雄。) | 渋谷PARCO(パルコ)