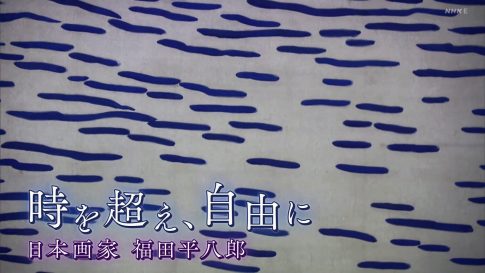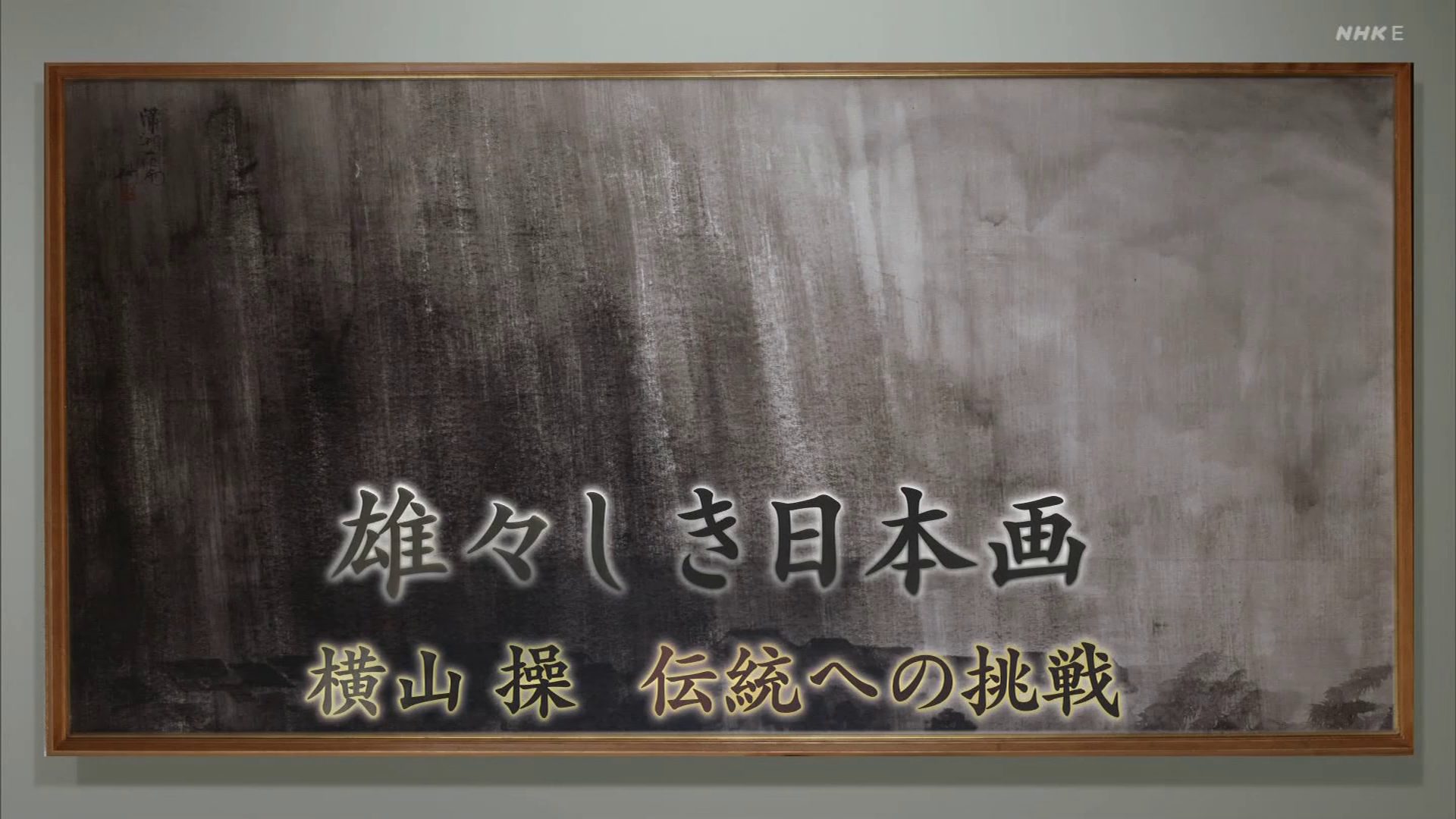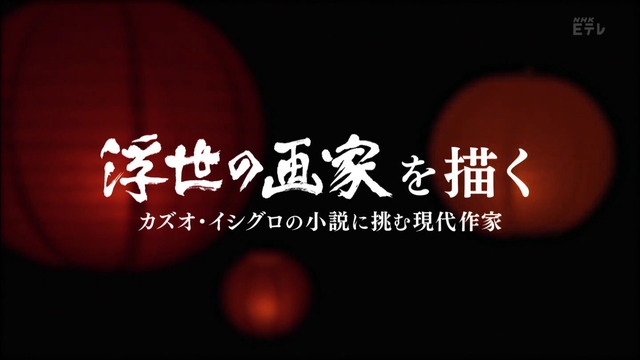流行にとらわれない独自の生地作りで注目のデザイナー・皆川明。服、絵画、さらに人生100年時代の幸せな生き方のデザインを目指す、異色デザイナーの頭の中に迫る!
ファストファッション全盛の今、流行にとらわれない独自の生地作りで注目されるデザイナー・皆川明。若い頃は長距離選手として活躍、魚市場でも働いた異色の経歴を持つ皆川は、服、絵画、さらには人生100年時代の幸せな生き方そのもののデザインを目指す。キャリア25周年を記念した大規模な展覧会から、異色のデザイナーの頭の中に迫る!
【出演】皆川明,谷川俊太郎,深井晃子,糸井重里,【司会】小野正嗣,柴田祐規子
放送 ; 2020年2月23日
日曜美術館「デザイナー 皆川明 100年つづく人生(デザイン)のために」
夜の美術館そのエントランスを舞台に一夜限りのファッションショーが開かれました。
どこか懐かしい花がら。
思わず触れてみたくなるような不思議な生地。
ファッションのトレンドにはとらわれないデザインが観客を魅了します。
手掛けたのはデザイナーの皆川明さん。
「ウキウキしたり嬉しくなったり、お洋服で気分が変わるんだ思います」「違う自分になります」
今年でデザイナー人生25年を迎えた皆川さんは自身も企画に関わった展覧会を開いています。
タイトルは「つづく」。流行に流されず、人生を共に歩み続けるものを作り出す。そんな信念を込めました。
さらに会場にはここ数年評価が高まる皆川さんの絵も。
服のイメージを裏切るもうひとつの世界。
「はじめてこの絵を見たときぎょっとしました。人間的なこういう裏があるんだという。怖かった」今日は、異色のデザイナー皆川明の頭の中に迫ります。
皆川明さんの展覧会
今日は東京都現代美術館で開かれている皆川明さんの展覧会にやってきました。
明日よろしくお願いします。
「デザイナーの皆川明です。本日はお越しくださってありがとうございます」
もうこの入り口会場入口からねワクワクするような色の洪水ですね。
「色々なテキスタイルをこの25年で作ってきました。立体的なものやプリント、刺繍などいろんな加工方法でつくっています」
こちらの部屋に入ると・・・服がたくさん。
まずやってきたのは洋服の森。この25年間に発表した服をあえて時代を混ぜて並べています。
昔の服の最新の服も同じように長く着続けてもらいたい。
ファストファッション全盛の今、自らの決意を示しました。
「 ここは森と名付けていますけど、まさに森のようにいろいろなテキスタイルや洋服が重なり合って一つの生態系みたいになっています。シンプルな形での気安さというものを大事にしながらそれでいて表面にある素材感とかそこに乗っている図柄ってものを楽しんでいただきたいなと思ってるんですけど」
これは普段着と考えていいんですか。
「そうですね。私たちは特別な日常の服ということをテーマにずっとやってきていて、日々の繰り返してるような毎日こそ特別なんじゃないかなっていうことを考えて、何かこうある日の服ではなくて、毎日自分の気持ちを高揚させるような洋服でありたいなーっていう考えだったんですけれど。何気ない毎日の中で洋服と一緒にいることで何か景色が変わって見えたり、その時の記憶が鮮明になったりっていうことが大事だなと思っていて」
何気ない日常の大切さを気づかせてくれる服。
そんな服を作るために皆さんは自分の手で生地を一からデザインします。
着る人にどんな驚きを届けよう。思いを込めた生地が服になり、着る人とともに歩み続けることを願っているのです。
芽
こっちの部屋が皆川さんの頭の中。服になる前を示した部屋です。
「これが原画の図案のもとになります」
皆川さんは生地のデザインから自分でおやりになるそうですね
「洋服はとってもシンプルなので、洋服のシルエットを何か特別な形というよりも、テキスタイルと形を合わせて、私たちらしいものを作りたいなんて思いがあって」
これを小野さんご覧になって何に見えます?
「ビー玉です」
「これはソーダウォーターと名付けたんですけれども炭酸水」
炭酸水の泡をイメージした生地「ソーダウォーター」の原画です。
実は隣り合う丸模様の生地の向き、綾目が互い違いになるよう矢印で方向が指示されています。
「よく見ていただくと、丸の中にある綾目がそれぞれ。一般的には一つの方向に全部変えてしまうということが多いんですけれどこれはそれぞれ角度を変えることで、陰影が生まれてくるので、重なった円同士もよーく見ると独立した縁が重なり合ってるというのが見えるようになっています」
「かすかですけど、そのかすかな表情をつくりたいなと思っています」
布、テキスタイルとして出来上がったときにどのようになるかってことまで想像して上でやってんですか?
「そうですね。それはこんな糸を選ぶとこんな重さになったり、こんな張感になったりということを頭に描きながら」
浮かび上がる泡を身に纏えば不思議と気分も上向きに。
デザインを完成させるのは着る人の想像力なのかも。
「今日は布を持ってきましたので。今うっすらと影のように丸い円が描れていますが、洋服をお店で見る時も最初はこの濃紺の洋服になります。
それをお客様が自らこのようにハサミを入れてもらいます。
お好きな洋服の場所で。そうすると蝶が出てきます。
いろいろなところにこの図柄で、いろいろなパターンで蝶々が隠れていて、
「これでやりたかったことは、機械が布を織ってそれを開けるのは持っている人。それを開ける場所とか開ける数で洋服がその人のものになっていくということしたいなと思って。または、初めはひとつだけ開けておいて、だんだん、また今年はここあけようと思ったり」
着る人が自由に模様を決める「かくれんぼ」
ハサミを入れた瞬間デザイナーの企みに気づいた人の微笑みが浮かんでくるようです。
皆川さんの強い意志が込められているウィンドフラワー。
「花というモチーフは、多くは可憐さとか優しい、可愛いという表情を持たされて
その象徴として用いられますけど、
これは見ていただくとお分かりのように向かい風に咲いてるんです。迎え風に飛ばされないように。風が吹いてきてそれになびいてしまうんではなくて向かっていってる。花を可憐さの象徴ではなくて、時には意志の強さとかを表現することにもデザインしてる」
「図案には全て背景にストーリーを持って、それから書き始めますから、はじめから私達のものづくりが始まった時からです。
ただ視覚的に美しいとか可愛いっていうことではなくて、なぜその図案を作りたいと思ったかっていうことを自分たちがしっかりと持ってそのストーリーを持ちながらものづくりに入っていくと思ってるんですね」
皆川さんのデザインを形にするのは日本全国の生地工場です。
中でも最も長い付き合いなのが神奈川県の山間にある小さな刺繍工場。
14人の従業員が皆川さんのデザインした刺繍のほとんどを請け負っています。
刺繍職人の佐藤敏博さん。
皆さんがその腕を最も信頼する仲間の一人です。
ブランドを立ち上げた25年前。
その腕を頼って皆川さんが仕事を頼みました。
「全部今度覚えてます」
最初の仕事はホシ*ハナ。
星のような花のようなあえて人の手の揺らぎを残したデザインは正確なほど良いとされる伝統的な刺繍と全く異なっていました。
「図案を見てですね、あのこれは行ける。内心私は思いました。あの小さな柄はあるんですけど、それなりに花びらの先の繊細さだったりとか、優しさがあるんですね」
佐藤さんの確信通り、ホシ*ハナはその後のブランドイメージを決定づける記念碑的な作品となりました。
2000年発表タンバリン。
整然と並ぶ円。
しかし、よく見ると一つ一つの刺繍の膨らみや間隔はバラバラです。
その方がより自然だとの考えです。
幾何学的なのにどこか優しい。
今も皆川さんの代表作として愛され続けています。
そして佐藤さんにとって忘れられない仕事がこちら。
刺繍を知り尽くした皆川さんからの挑戦状ともいえる発注に応えたレースです。
「37種類のモチーフ。鳥や花やそれは全員でこう行進しているような。
まさにその森の中を行進しているパレードのようなことを頭に描いて、それがあのみんながワイワイしながら重なってる。
洋服の上にあるということをイメージしながら描きました」
一針一針皆川さんの意図を読み解きながら、実際に刺繍をするように何万回も手を動かしコンピューターに記録します。
刺繍のデータを作るだけで数ヶ月がかかったといいます。
そしてようやく刺しゅう機へ。
完成に必要な1メートルをさすのに丸4日かかります。
「いろんな試行錯誤したものほど完成した時の喜びは大きいですし、まして作ったものを見ていただいた時にどんな反応が昨日
また一つの喜びでもありますよね
あの長いお付き合いをさせて頂いて彼の人柄だったりとかそういうものまで含めて布の上に表現したいっていうのがあるんですね」
「佐藤さんとても苦労されたと思うんですね。入力に一針一針全部入力するのに相当な時間かかふうに思いますし、やっぱり本当のやりがいっていうものを持ってもらえば、自然とやりたい事になるし、
やりたいことを人がやった時にはそれは良いものができると思ってるんです。なのでそういう気持ちを持ちながらものにしていく。形にしていくことをしたいなと思います」
デザイナーと職人。
それぞれが、喜びを持って仕事をする。
人生と共に歩む服作りには、そんな仕事のあり方も欠かせないと皆川さんは信じています。
生い立ち
1967年。皆川さんは東京蒲田、サラリーマンの家庭に生まれました。
中学高校時代は大学の駅伝選手を目指し、トレーニングを積む毎日でした。
「ちょっと先のための練習っていうか、自分の今日1日は少し先の何年か先のために役に立つんじゃないかっていう風に走ってたっていうのは運動の中で学んだことっていうのが今のものづくりにも影響してるなと思います」
しかし高校3年で足を怪我。
体育大学への進学の道が閉ざされてしまいます。
卒業後の進路も決まらない中あてもなく海外へ。
初めて訪れたパリで思いがけない出会いがありました。
現地でできた友人からファッションショーの手伝いに誘われたのです。
「よくわからないけど、みんながすごいエネルギーで一つに向かっていく感じ。こういう中に一生いたら面白いかもって」
帰国後。皆さんは服飾専門学校に入学。
しかし熱中したのは服作りの工場などで技術を学ぶことでした。
胸の内にあったのは半年ごとに新しい流行を生み出すファッション業界への違和感。
新しい何かを探していました。
「10年ぐらい。年齢でいうと30歳ぐらいまでずっといろんな下積みをして、そしてなんとなく自分で理解できてからまた自分の何か世界観を作れそうだったらやればいいし、あの特別なクリエイターになったりっていうことよりもずっとしばらくは物を作るってこと、ちょっとずつ覚えたいな。なんか毎日がリアルに、自分がちょっとずつ分かっていく感じを持って行きたいなと思ってやってました」
そして27歳。家賃が安かった八王子に借りた家で、たった一人でブランドを立ち上げました。
目指したのは、少なくとも100年は続くブランドです。
そのためには一体どんな服を作るのか。
ヒントは意外な所にありました。
当時皆川さんが生活費を補うために働いていた魚市場。
より良い素材を求めてプロがしのぎを削っていました。
「もしかすると、ほとんどその魚市場で今の自分の考え。洋服作りの考えは作られたような気がします。一番は材料を見る目がある人は、技術も高いなあって。例えばアラも料理にしたりとか、それは後に僕らが余った材料もしっかりとものにして行こうっていう考えに繋がっていて、材料が全部自分たちの可能性になってるっていう事を、優秀な職人からとても学んだ気がします」
3年目の1997年。ようやく運が向いてきます。
人気のファッション誌が皆川さんのブランドを表紙に抜擢。
その後も次々に特集が組まれたのです。
注目されたのは独創的な生地。
素材からこだわり、職人とともに作り上げたものでした。
服飾評論家の深井晃子さん。
皆川さんのデザインに意外な衣服との共通点を感じると言います。
「テキスタイルデザインがあってそして次のステップ。服の形に今なっていくという。そのことをはあのよく考えてみると、日本の着物が日本の衣文化にあったわけですけれども、その着物を作るステップと似ていたわけですね」
着物は形は極めてシンプル。
生地の染め方や刺繍のバリエーションで違いを楽しむファッションです。
深井さんは服の形は奇をてらわず、生地に徹底的にこだわり抜く皆川さんのデザインにも着物から受け継がれた日本らしさを感じています。
「テキスタイルのデザインを具現化っていうか、作り出してくださる職人さん達だとか工場だとか、そういうレベルが高くないことにはいいものができないわけですが、それはですね、やはり日本の着物文化が非常に高かったから、そういうものを自然に感覚の中で持ってらっしゃる方がまだいっぱいいるわけですよね。そういう意味においても日本の伝統的なものが引き継がれているなあという風に思いました」
皆川さんの服には長く着るための工夫が凝らされています。
17年愛用されたグレーのコート。
袖口が擦れた時、裏地から黄色が出てくるように初めからデザインされています。
長い人生と共に歩むことを前提にして作られているのです。
展覧会場にも人生の物語が刻まれた服が飾られています。
「長年着て頂いてるお客様からお洋服をお預かりして、その洋服と一緒に過ごした時の思い出を頂いてるというもので、こちらに着ていただいた年数ね、その中で起きた記憶を書いていただいている」
ある女性が四年前から着ているワンピース。
「この服を着て入院中の病院を訪ねた時、頑固で褒め言葉など素直に口にすることのなかった父が素敵な服だなとつぶやいた。そして着るにふさわしく常に自分を磨きなさいと。おしゃれへの興味が高まる十代の頃。内面こそを磨きなさいと言われ、反発心を抱いた記憶がふと蘇り、月日が流れ、同じ意味の言葉が深く心にしみるものへと変化していることを感じた」
ボーダーと水玉が友達のように仲良く並ぶワンピース。
「子供の小学校の入学式。このワンピースを着て参列しました。たくさんの友達に恵まれてほしいとの思い。それから6年後中学校の入学式。私はまたこのワンピースに袖を通しました。すっかり大きくなった子供の背中が眩しく見えました」
長く大事に着られた服が思い出の貯蔵庫になる。25年前に皆川さんが目指した服作りです。
「物っていうものから、それが後に、長く一緒にいることで記憶に変わるということをここでは展示していて、元々は僕らの想像力。想像から形になってその形がもう一度記憶になっていくっていう、感情と物の循環みたいなことをここで見ていただこうと思って、そしてそうするには長い付き合いが必要だということも」
皆川さんと10年来の親交がある糸井重里さん。
長年愛用したジーンズを皆川さんに直してもらったことがあります。
パッチワークで描かれたのは糸井さんと2年前に亡くなった愛犬ブイヨン。
子犬の頃ボール投げが大好きで、いつまでも続けていたブイヨン。
白く色落ちした線もボールの軌道に見立てられています。
「ジーパンとかも彼らの感覚で直してくれるって、じゃあお願いしますって言っていたら、たまたまそれがその皆川さんご本人に届いて、僕にやらしてくださいって言って、嬉しいですね。皆川さんの持ってる優しさっていうのは、何だろうなあ。倒れかかった時に受け止められる強さが。現実的に助けになるって言うところを考えてる気がするんですよね。人に対しても物に対しても。行き場がなくなっちゃった端切れはゴミ箱なのかなっていう風に感じたとしたら、それは悲しいことだよねって。そのままの人もいるけどそれを使ったらもっとまた人を欲しがるのできるじゃないっていう。そのパッチワークにしたり、ちょっとでもこう現実を作ろうとするんですよね。本当に優しいってそこまで見ることじゃないかなあと思うんで。すごい尊敬できる部分ですね」
皆川さんは現在52歳。
人生の残り時間を見すえ、ファッション以外の創作活動にも精力的に取り組み始めました。
この展示室。
根には新聞小説やコラムのために皆川さんが書き下ろした挿画が並びます。
絵には服のイメージとは異なる皆川さんの内面世界が現れています。
その世界観を最も伝えるのがこちらの絵本。
「はいくな生き物」
アクリル絵の具の荒いタッチで描かれた蝶、それとも象。
花粉を纏い、花になりかけた虫。
皆さんが想像した謎の生き物が次々現れます。
「いたぶべぼどここそこねおもいだす。なんかこういう絵を見てると自然に音が浮かんでくるのね。それで書いてますね」
絵を依頼したのは詩人の谷川俊太郎さん。
「初めてこの絵が来た時、本当にゾッとしましたよね。皆川さんがあんななんか綺麗なデザインの裏にこういうものがあるのかと思ったら。皆川さんの潜在意識の表現が。大げさに言えば人間的にはこういう裏があるんだっていう漢字で怖かったですよ。だからどういうテキストにするかっていうのだろうとちょっと苦労して、俳句の形五七五って定型にするっていうことでやっと解決できたんですよ。そうでないとどんな言葉を付けていいか分かんなくて。だすりんねそらどらしそれちりんりん。皆川さんの絵を拝見してると、絵と言葉で全然違うんですけどね、自分の詩の発想と共通なものを感じるんですよ。絵の出方が詩を書いている時の言葉の出方と似てるって言うのかな。割合つまりお店で綺麗な衣料品とかね雑貨類は皆川さんの意識から生まれている。構成されてるものが多い。でも絵本は彼の場合、意識よりもっと下の方の方のものから自然に生まれてくるような気がする。だから形なんかもう常識にとらわれないで変な形のが出てきても、それが自分だっていう風に言ってるんだろうなと思うんですけどね。言葉にはどうしても意味というものがあるから、どうしてもそれに縛られてそんなデタラメができないんだけど、僕の場合詩が出てくる言葉の源はやっぱり言葉のないところですね。彼の場合にも従来の造形とか、そういうものからじゃなくて自分のなんかも一番深いところから出てくる形とか色を描いてるなって感じしますね」
随分その服の生地のデザインとちょっと違う。これは何をイメージしているのですか。
「これは子供のための絵本。その時に子供の恐怖心とか、怖いっていう感覚ってどんな風に生まれたりするんだろうかって思って、もしかすると大人が思う怖いっことを子供達は面白いって思ったり、なんか好奇心が湧くものになったり、だんだんと恐怖に変わったりっていう体験を通してその捉え方が変わっていくんじゃないかなと思った時に、大人は知識で自分の中に取り組んでいきますけど、子供は思っていることとか想像していることが本物っていう風に頭の中に入っていくんじゃないかって。だから本当にいるかどうかじゃない自分の頭の中に入るものは何だろうっていうことだと思うので、浮かんでくることを連続で描いていって、自分の手からその瞬間しか出ないものを書いてみようと思ったんで」
それはもうご自身の中では服のデザインとは全く違うチャンネルですか。
「全く違う何かそういう衝動的な好奇心のままに描いた。僕にとっても一番尊敬する詩人でもあり、本当に若い頃から詩集を谷川さんの全集を持って読み続けている詩人の方なので、もちろん大きな敬意を持ちながらですけれど、その方が自分の絵にどんな言葉をワクワクする。そんな機会はそうないことだと思いました」
今から25年前に始まった皆川さんの創作活動。
服のデザインからスタートし、これまでに数多くの作品を手がけてきました。
しかし自分の人生だけでは決してやりたいことは完成しない。
初めから次の世代に受け継ぐことを考えていたといいます。
この展覧会はちょうどそのブランドとして25周年記念の展覧会。当初から長いスパンでお考えになってたものですか。
「僕はものを作るのはとても不器用なんですね。人よりも覚えるのが遅くて、時間かけて人よりも随分遅くなってそういうことかって気づくということは、それは子供の頃から陸上をやってる時も人よりも理解するのが遅いなーと。遅いなーっていう自覚があったので、あんまり人と同じペースで進めていこうとすると、きっと自分にはついていけない。違和感が残ってしまうなと思ったので、まあ自分の持ち時間。人生の時間よりも長いことを考えた方がやりやすいなと思ったのです。頭の中にはずっと先のことまで浮かんできますから。でも自分の人生にはそれを達成する時間が足りないだろうと思って。じゃあ次の人に考えを伝えたり、続けてもらったり、今回のテーマの「続く」っていうこともそうですけど、持ち時間は自分の持ち時間だけで考えない。やろうとしてることが必要な時間かけようというふうに思うのです」
大きな風景が凄い豊かに実現できるんだったら、自分はそこそれで幸せだってような哲学を感じて。
「確かにこの最初の今25年ですけど僕は受けもてる30年か何十年かというのはある種、土壌を作るというか、今日の色々な部屋の中で言うと土を作るっていうか、良い土を作っておけば良い種があれば育ちやすかったり、良い工場とお付き合いしたりとか、自分達のものづくりの考え方をきちんと育てていくって言うための土壌を作るっていう役割で十分自分にとっては喜びがあって、その中に絵を描いたりっていう個人的な喜びをたくさん含まれているので、それは本当にちょうど良いと言うか僕にとっては」
四年前、皆川さんがオープンした店があります。
60代以上の店員。
通称先輩方。
人生最後まで働き続ける場を作りたいと皆川さん自らが募集しました。
「お客様との対応で、ニコニコしてくださって喜んでお洋服を選んで下さってっていうとやっぱり嬉しいですね」
「続けられるかぎりに続けたいっていう気持ちはあります」
人生と言われる時代服も人も最後まで輝き続けてほしい。
皆さんの考える幸せな人生のためのデザインです。