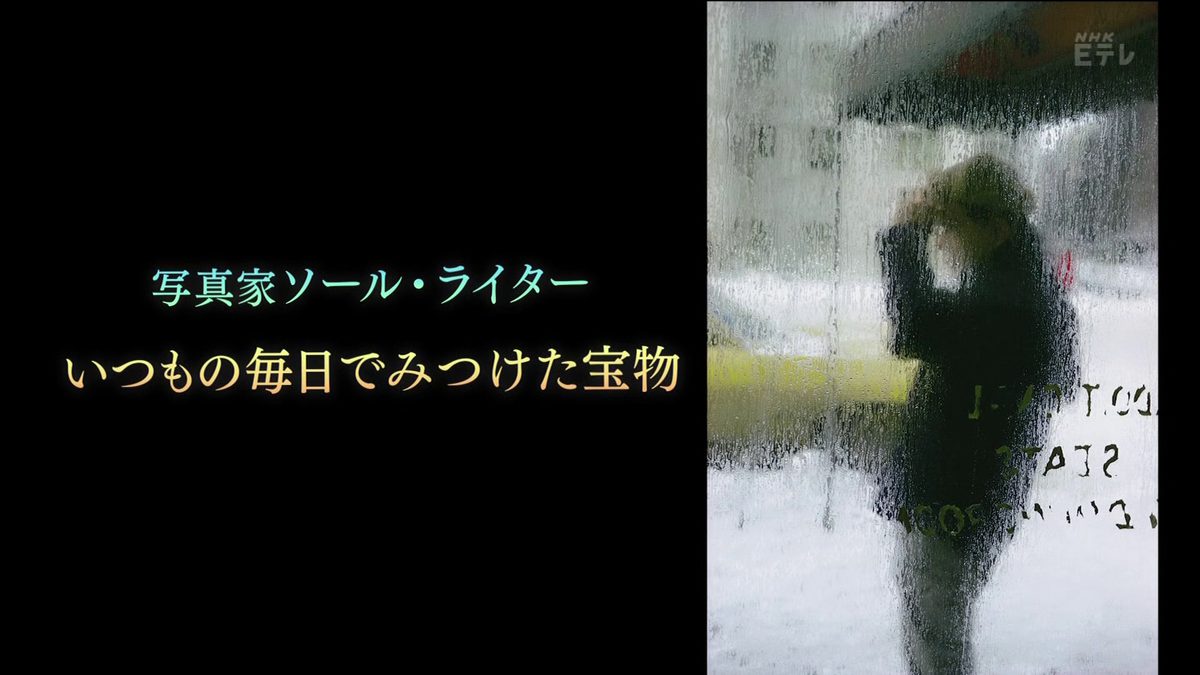人間が生み出した名画中の名画「蔵出し! 西洋絵画 傑作15選」。第2回は、ルネサンスのボスから19世紀のゴヤまでが登場。寓(ぐう)意に満ちた祭壇画は、今も謎だらけ!?人生をかけて描いた“光と闇の絵画革命”。一人一人が主人公。その一枚は今も市民の誇り!谷川俊太郎が言葉を失うあの名画。そしてスペイン宮廷画家が晩年に描いた「我が子を食らう」おぞましき一作。人間の光と闇が交錯する!
【司会】小野正嗣,柴田祐規子
放送:2022年7月12日
「蔵出し!西洋絵画傑作15選(2)」
日曜美術館です。シリーズでお送りしています蔵出し傑作選。
先々週からは西洋絵画を取り上げています。
先週一回目はラスコーの洞窟の壁画からモナリザまでを取り上げました。
今日2回目はボスから初めましてゴヤまでの5作品。
15世紀から19世紀にかけての作品となります。
では今日の一作目はボスのこの祭壇画から参りましょう。
その絵はモノクロームで描かれた天地創造の図の向こう側に広がっています。
ルネサンス時代に誕生した美術史上分類が困難な一枚。
傑作選6作目。
ヒエロニムス・ボスの《快楽の園》です。
左側のパネルはエデンの園か。神がアダムとイブを引き合わせます。
中央には一糸まとわぬおびただしい数の男女。
謎めいた動物や植物と戯れます。
右側は闇の世界。
人々が様々な形の拷問を受けています。
複雑な寓意に満ちた独特な世界。
ボス自身が謎に満ちた人物。
敬虔なキリスト教徒で相当な知識人だったことが伝わるばかりです。
17年前、漫画家の楳図かずおさんがこのボスの世界と出会っていました。
「すごいですね。何か楽しそうですね。アダムとイブが二人いて、それはこんなに増えちゃった。増えちゃったのが集まるっていうこと自体が何か意味があるかなって。集まることによって何かが起きるかなーって。その良いことも悪いことも堕落の始まりがあるかなと思ったり。音楽のオタマジャクシ見たい。一人一人が主張しているってんじゃないんですね」
貝の中から足だけが。
性愛を表しているのだとか。
甘い香りを放ついちごに群がる人々。
傷みやすい果実は快楽の象徴です。
巨大な耳にはナイフが。
神の言葉に耳を傾けのものの行く末を暗示するかのよう。
楽器に押しつぶされた人の尻にはなぜか楽譜。
日曜美術館では23年前その譜面を実際に演奏していました。
心を乱すような旋律。
音楽に潜む悪魔とも呼ばれ、中世の教会では使用が禁じられていたのだそう。
ハープやリュートなど、天上の音楽を奏でる楽器もここでは拷問の道具。
14世紀。ヨーロッパ中を恐怖の渦に陥れ、流行を繰り返したペスト。
神の怒りの表れだとされ、15世紀の末には世界の終末が信じられていました。
今に伝わる愚者の祭り。
現世に絶望した人々は魔物に扮し、教会や権威への批判をそこに忍ばせました。
誰もがみんな愚者である。
そんな人間観がボスの作品には漂います。
ボス自身の自画像だとも言われる男。
その瞳が見つめたのはどんな世界だったのか。
38年前。写真家の藤原新也さんが自分の体験と重ねて語っていました。
「最初にボスのように接したのは高校の1年のことです。ボスの絵に何故か惹かれたがかというと。僕の家が旅館をやってたけど、この旅館って非常に奇妙なこの建物ってかな。その中に居ると人の人生がどんどん過ぎ去っていくという。例えば大晦日の夜女中がお客と駆け落ちしたりとかね。それから自殺なんかがあって部屋が真っ赤に血で染まってたとか。警察が泥棒を働いたとか。僕の通っていた小学校の校長さんがやってきてらんちき騒ぎやるんですよ。昔の小学校といえのは由緒正しかったですからね。聖職者というイメージがあったんですけど、それが突然その僕の家の中で豹変する。その風景を欄間なんかに登って覗いていてね、それで人間模様の汚さとか愚かしさとか、そういうものが10何年か渦を巻いていた世界に住んでたもんだから、そういう体験とボスの絵を重ね合わせて見てたんじゃないかっていうか。ボスが描いた地獄の風景だとか悦楽の風景だとかそういうものは必ずしも想像の世界ではなくて、現実をデフォルメしたもんじゃないかということを思った。僕は写真家として地球上の国々を回ってますとね天国とか地獄とかそういう物ってのは今生きてる世界に常にあるんだという感じがするわけだから彼は空想したんじゃなくて写実したんだということですよね」
500年前、終末の世に産み落とされ今も謎に満ちた快楽の園です。
スタジオには同じように祭壇画を再現してみました。ずいぶん大きいですよね。
実に様々なものが書かれていますんで今日はこんなカードを用意致しました。
パネルの中にあるものを切り出したカードです。
この中から小野さんに探し物をしていただこうと思いまして、このカードの中から一枚選んでください。何がいいですか。
このカードにあるものをパネルの中でどの辺りにいるのか見つけてください。
実はフクロウは異教とか知恵の女神、あるいは悪といったもののモチーフということで色んな所に登場するんですね。だからそこだけではなくて、この辺りにもいたりして探しているといろいろな所に散りばめられている。
じゃあ、これ見つかりますか。
はい。それは何をしているのかと言いますと足元にご注目ください。
あのスケートしてますね。
そうなんですよ。地獄ってこう燃え滾るようなイメージがありますけど、氷の地獄。
本を読んでいる生き物を探してください。
ヒントは水辺というよりは水たまりです。アダムとイブの側にいます。下半身は魚のようなのに超半身はカモのようでもあり、しかしながら腕が出ていて本を読んでいる。
実に様々な謎めいたものが描かれていますが、これ全体を通して小野さんだったら何を読み解きますか。
人間のどす黒い欲望っていうかそういうものに対する神罰って言うかそういうものが描かれてるのかなっていう気がします。それにしたって絵として見て楽しい。細部は不思議なキャラクターたちが溢れていて、見て楽しいものではありますけどね。だけど全体としてこれが何を意味しているのかというと謎です。
醜さも愚かさも、人の全てが曝け出された真実の世界がそこには広がっているのかもしれません。
続いて2作続けてご紹介します。
闇を切り裂く劇的な光。
傑作選7作目は宗教画に革命を起こしたとされる一枚。
ミケランジェロ・メリージダ・カラヴァッジョの《聖マタイの召命》です。
カラバッチョが育ったのは北イタリアの小さな村。
6歳の時ベストの猛威から逃れるためこの村にやってきました。
しかし父親はペストで倒れ、母親も亡くなります。
死の影を間近に感じながら少年時代を送りました。
21歳の時。無一文のままローマへと向かいます。
絵の才能だけが頼りでした。
まもなくチャンスが訪れます。
由緒ある聖堂を飾る作品の制作を依頼されたのです。
人生をかけた大舞台。
カラヴァッジョはそれまでの常識を破る絵を描き上げます。
四年前漫画家のヤマザキマリさんと俳優の北村一輝さんがその場所を訪ねました。
聖マタイ三部作。
マタイがキリストの弟子となり殉教するまでの姿が描かれています。
中でも傑作とされるのが《聖マタイの召命》
マタイがキリストからの呼びかけを受ける奇跡の瞬間をカラヴァッジョは下書きもせず一気に描き上げたといいます。
「すごいなあ迫力が」
「だって魂が塗り込まれているから」
若き才能が画面に解き放ったのは闇を裂く劇的な光でした。
「あの光が差し込んでいるじゃないですか。あれってこの絵から急激に来たっていうかそれまでの絵っていうのはみんなに明るく対等に光が当たっている」
それまで宗教画は明るい光を隅々まで行き渡らせることで神の世界を表現していました。
しかしカラヴァッジョは違います。
私に従いなさいと指差すキリストは闇の中。
その先のマタイに強烈な光が降り注ぎます。
訪れた奇跡の瞬間。
それを際立たせたのが闇の表現でした。
「漫画とかでも同じで、漫画の一コマに黒ベタ塗るってすごい勇気がいるんだよ。真っ黒にしちゃったらものすごく意味が深くなっちゃう。ここに何を表してるのってみんなに聞かれそうとかね。でも聞かれそうに思わせることに効果があるわけだけれども。真っ黒にするっていうのね」
光と闇の効果を知り尽くすヴィットリオ・ストラーロさん。
地獄の黙示録漏らすとエンペラーなどを手がけた世界的な撮影監督です。
20代で聖マタイの召命と出会って以来、この作品に魅せられてきました。
「これが家にいないと。家にいなきゃいけない必須アイテム」
「カラヴァッジョが発見した照明方法とは全体ではなく、ある部分にだけ光を当てることです。もしある場面で全体をまんべんなく照らす光を使うとします。その時に表せる意味は調和ということです。しかし対立や対比を表したい時はカラバッチョのように一箇所を選んで光を当てるのです。彼は今から400年も前に光と闇がもたらす効果を発見していました。映画でそれを始めて表現したのは100年前に過ぎません。カラバッチョは最初の映画監督なのです」
さらに革新的だったのはこの絵が画庶民たちを主人公にしたことです。
描かれているのは卑しい身分とされた徴税人。
そこに神の光を当てることで苦悩を背負った罪深い人こそが救済されるべきだとしたのです。
しかしなぜこんな型破りな絵を描いたのか。
心にあったのは貧しかった少年時代に見た光景でした。
暗闇に差し込む光。
そこに集い、祈る人々。
「神の助けに一縷の望みを託してここにやってくる病んだ人や貧しい人々の姿。そうした人々が絶望と隣り合わせで祈りを捧げる光景はカラバッチョに強烈な印象を与えたはずです。そしてそれが画家の絵の土台になったと私は思います」
「絵画って、ただ単純に上手いとかどういう風に表現するのかじゃなくって、人間がどんなふうに生きたかっていうのがどんなふうに出るかによってクオリティとか持久力だったりとか。何世紀も残るかどうかとか。そういうことって、ここで決まるんだなーってすごい実感しました」
若き画家が人生を切り開こうと挑んだ聖マタイの召命。
400年の時を超え今も祈りの場に集う人々とともにあります。
次の傑作は17世紀。
時代の先頭を走っていたオランダから。
今年45年目を迎えた日曜美術館。
初代司会を務めた作家の太田治子さんがその作品を訪ねていました。
傑作選8つ目は誕生!我らの肖像画。
レンブラント・ファン・レインの夜景です。
「私はこの絵の前でこう大きく深呼吸したくなる。そういう不思議な伸びやかな心が解き放たれていく。そういう気持ちに今なっています。レンブラントが自分が描きたいように描いた。好きなようにのびのびと彼は描いたんだという、そういう気持ちを絵の前に立って私もこれ以上にのびのびとこの絵と対面できて嬉しいです」
海上貿易がもたらす富によって、当時オランダには市民が主役となる新たな社会が生まれていました。
そこで盛んに描かれるようになったのが集団肖像画です。
豊かになった市民がお金を出し合い、自分たちの姿を平等に描いてもらうようになったのです。
しかしこの絵は違っていました。
夜景。
地元の自警団からの発注で描かれました。
特徴はそれまでの集団肖像画にはない一人一人の生き生きとした描写です。
中央に描かれている隊長の手は、強い光を受け今にも動き出しそう。
レンブラントの光と影は、画面にドラマを生み出します。
太鼓を叩く者。
何かを指差し談笑する者。
大事そうに銃を抱える者。
今もレンブラントにちなんだ記念日やイースター祭に合わせ、市民達は夜景の人物になりきって街を練り歩きます。
「300年前のレンブラントが今だ慕われているのはすばらしい。《夜警》のパフォーマンスは楽しみの一つ」
晴れやかな衣装に身を包み、今日は名画の主人公。
「ひときわ高い拍手がいつまでも鳴り止みませんでした。《夜警》は今もオランダの人たちに愛されていることが胸に痛いほど伝わってきました」
オランダ市民を象徴する一枚です。
聖マタイの召命と夜警と2作品ご紹介しました。
この時代の光とか闇って今と全く違う状態だったのかなと思わせられる。
「もちろんその現在に比べたら夜の闇は深かったと思うんですね。同時にカラヴァッジョは自分が見た現実の光を絵の中に描くことをしてるんですから、人物たちが実際に彼の人の周りにいたような人たち、普通の市民ですよね。貧しい生活を実際に経験してきたことが絵の中に現れてるんだったから、理念としての光を絵の中に描き込むんじゃなく、自分の目で見た現実の光を聖書的な世界の中に入れていると。ある種確信じゃないかと思うんですよね。レンブラントだと市民の人たちが夜警に行くぞって言う差し出された手に光が当たっている。演出された画面。光と人物たちのポーズとか動きとか。劇的な瞬間って言うのが、どんな光を当てるかのようなことを考えている。人間の地上における活動なんだけど、聖性を帯びている。市民社会の姿を描いてるけど光の聖性を感じる」
では続いては傑作選9作目。
あの人の言葉から振り返ります。
「とにかく綺麗だなあ。本当に綺麗だなーって思ってるだけなんですね。言ってみれば呆然として立ってるだけで絵の前に。つまり他の絵見るときはいろんな感想が心の中に涌きますよね。言葉になったりなんかして。フェルメールの場合にはそういう感想ってな一切出てこないんですね。だから胸がいっぱいになってるのとかがあるんだけど、なんかシーンとして静かなのね」
傑作選9つ目。ヨハネス・フェルメールの《牛乳を注ぐ女》
40センチほどの小さなキャンバスに描かれた日常の風景です。
1632年。オランダのデルフトで生まれたフェルメールは、わずか1キロ四方の小さな町で生涯を送ったと言われます。
本業は宿屋。
大勢の子どもを育てる傍で絵を描いていました。
現存する作品は30数点しかありません。
フェルメール20代の時の作品。
静かにそそがれる牛乳。
ガラスの材質の違いまで描き分けられた窓。
固いパンの質感は光を反射する砂を混ぜた絵の具で再現されています。
あらゆる細部にまで観察を尽くすフェルメールの眼差し。
f:id:tanazashi:20200719172906p:plain
「これとっても有名な絵」
2年前篠原ともえさんが出会いました
「フェルメールは何かを誇張して描くというよりも、日常にある真実こそが美しいって思っていたと思うんですよね。なので素材感も嘘がなく、リアルに描いて、今ってこうインスタ映えとかね、結構誇張してシチュエーション作ってという世の中だけれども、でもそんなことなく、本当にふとした日常がどれほど美しさを持っているかっていうことをちょっと教えてもらったような気がします」
「僕はフェルメールという人は自分の内部の、自分の魂の内部の暗がりとか混沌とかっていうものよりも、自分の外に見えるものに興味を持ってたし、それを信じてた人だって思ってるんですね。現代美術件っのは外側に見るものも、もしかして幻かもしれないと、人間の心の中の現実を重視するって傾向があって、いろんなイズムが出てきてるでしょ。でもフェルメールってのは自分の肉眼が、実際目の前で見てるもの。そのものが非常に明晰に見えてるんだけれども、そこにあるどんなものも、それが存在していること自体がとても不思議であって、とても美しくて、謎に満ちているという風に見えてたんじゃないかと思うんですよ。だから光っていうのもね、彼にとっては例えば一神教の宗教の光って言うんで、例えばろうそくの光が一本だけあって周囲を照らすとか非常にドラマティックにスポットライトが当たるとかってありますよね。そういう光とちょっと間違うっていう気がするんですね。フェルメールの場合。そのキリストに当たろうがテーブルの上のコップに当たろうが、床の上のゴミに当たろうが同じなんだっていう、そういう見方ね。いろんな細かいものの間に違いはないっていう風にこの人は見てたように僕は勝手に思っているんですけどね。確かにね地味な絵なんだけども華やかなものがあるんですね。なんていうのか画面が生きてるわけね。そのなんか物が生きてる。描かれたものが生き生きしてるっていう事に圧倒されるんじゃないかと。とにかく美しいんですよ」
谷川さんに美しいんですよって言われると、本当にそうだと思いますよね。
「谷川さんがおっしゃってたように、自分の内面はいくらでも深く掘り下げることはできるんだけど、単純に世界が自分達の外側にあるっていう、存在してることに素直に驚いてみる。その驚きを的確にこれ以上ないっていう形で表現するっていう手法は科学的な態度かもしれませんよね。フェルメールは光学にも広い興味を持ってて、暗箱カメラと言うんでしたっけそういうようなものを見て作品を描いたんじゃないかとか言われてるじゃないですか。あるものを受け止めてそれをそのまま描くってね」
身の周りというか外側にあるものへの意識ということが研ぎ澄まされた感じがしてくる。
では、いよいよ最後の一作。ゴヤの一作です。
その目は何を見つめているのか。
我が子を食いちぎる姿。
スペインの巨匠。フランシスコ・デ・ゴヤ晩年の作品。《我が子を食らうサトゥルヌス》
ゴヤは当時最高の地位であったスペイン王家の首席宮廷画家でした。
国王やその家族の華やかな肖像を描いていました。
そんなゴヤが晩年になって描いたのがこの作品。
我が子に殺されるとの予言に恐れを抱き、生まれてきた子どもを次々と食い殺す神話の巨人サトゥルヌス。
いったい何がゴヤにこのおぞましい絵を描かせたのか。
1868年。ゴヤ62歳の時、スペイン独立戦争が始まります。
市民たちを巻き込んだ泥沼の争いでした。
理性を失った人々は怪物と化して行きました。
ゴヤは家に閉じこもり、自宅の壁に絵を描きます。
黒い絵と呼ばれる14点の連作です。
生前発表されず、ほとんど人目に触れることもありませんでした。
我が子を食らうサトゥルヌスが描かれていたのは食堂の最も奥の壁でした。
画家の絹谷幸二さんとスペイン美術史家の大高保二郎さんが語っています。
「人間というもの一皮剥いてしまえばこんなこともあるんだよ。こんなこともするんだよ。そういうところをですね。絵で見せた。指し示した。それはですねもう近代そのものなんですね。そして絵というものはただただ目に写ってくる美しいもの。麗しいものだけを描いたのではない。こんなにすごいことをするのも人間だよということを指し示したところに彼のそのヒューマニズムってんですかね、人間を見つめる眼。これは見たところ非常に残酷な絵なんですけれども、しかしこれは本当に心を洗ってくれる。人間とはここまでやるんだよっていうことを指し示してくれる美しい絵ですね」
「ゴヤは黒い14点で、我々に対して、スペインに対して、絵画による遺言のようなもの残そうとしたのではないかというふうに考えて」
戦後を代表する詩人の田村隆一さん。
自らの戦争体験を重ね、ゴヤについての言葉を残しています。
「人間だけですよ。同類を殺したり、虐殺したり、いじめたり、拷問にかけたり。だが人間はもっと生の根源。生は生きるです。生の根源に立ち戻って、人間も自然の一部。微少なる一部です。ただ写ってるだけじゃない。ゴヤの表現によって自分たちの心の中に眠っていたものが目覚めるところがリアル。人間の悲惨というもの。人間自身、スペイン人でもなくフランス人でもないんです。人間そのもの。人間存在そのものの悲惨さを具象化している・・・というふうに考えたらどうでしょうか」
人間が人間を知るための一枚です。
人間存在そのものを具象化してるという田村さんの言葉がね
「ゴヤっていう人が描いていた時代っていうのは、18世紀から19世紀じゃないですか。で、18世紀ってね啓蒙の世紀ですよ。だから啓蒙って何かって言うとリュミエールで光ですよ。光によってその闇が表現してるような無知蒙昧っていうか、迷信とか謝った差別的な意識とか闇。そういうものを光の合理的、人間の理性の光によって、それを照らし出すことによって、人類は、人間は良くなっていく。人間は進化していくんだと。社会はより良くなっていくってことが信じられたのが啓蒙の世紀じゃないですか。だけど、そういう風に思ってたら光が全然照らし出してない部分が人間の奥底にある。残虐性って言うか、暴力っていうか、そういう闇っていうのは、常に我々の中にあると。ゴヤは絵として具象化してる。それを田村さんのような方は見て、そこにあらゆる人種や国籍っていうか、そういう国を超えた人間存在そのものの持つ暗い部分、影、恐ろしい部分っていうことをこの世の中にあるって唱えてるんじゃないか。光と闇っていうものが重要な絵への主題になってると思うんですけど、素晴らしい絵を見ると、光と闇って何なんだろうっていう」
今私たちが暮らしてる世界の光や闇も含めてちょっと考えてみたくなる。そういう力が傑作と呼ばれるものにもあります。
「絵は外側にある世界の光を描いているようですがねそれは必ず私たちの内側にある光と闇に繋がっていくっていうことでもあるんですね」
次回はこの蔵出しシリーズ3回目。最終回です。