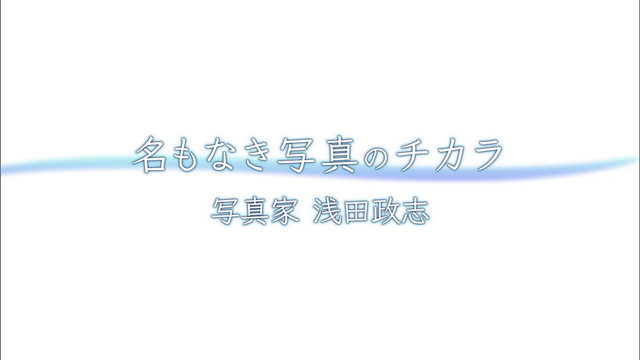消防団や極道など架空の設定を演じきるユニークな家族写真で知られる浅田政志。
しかし今、自分の色を出すのではない「名もなき写真」に心奪われている。
11年前、東日本大震災の被災地で、津波に流された写真が、人々に寄り添い支えとなる姿を見たことがきっかけだった。
多くの人ではなく、誰か一人の感情を揺さぶりたい。
新たな写真のチカラを信じて新作に挑む浅田の半年を追う。
初回放送日: 2022年3月13日
日曜美術館「 名もなき写真のチカラ 写真家 浅田政志」
「いつかの未来に向けて撮ってる気がしてて、その写真がある日その方の人生だったり、何か大切なものを振り返れるものになってればいいなと思うんですけど」
写真家浅田政志。撮影していたのは子どもたちの一番の思い出。
一緒に話し合って思い出に残したいことを決めました。
一年生はお気に入りの本を胸の前に掲げてパチリ。
「小学校の時に経験したこととかって、知らず知らずのうちに大きいものになると思って、みんなが好きな本を見つけたりとか、そういうことがみんなが大人になった時に思い出した時、今の自分と繋がってる何かを感じてもらえるんじゃないかなと思って」
校庭で拾った栗の実。
大好きなクラブ活動。
思い出のキャンプファイヤー。
みんなで踊ったソーラン節。
撮影した写真はプリントアウトしてプレゼント。
写真を手渡す。そのこだわりは11年前のあの出来事から始まりました。
東日本大震災震災。
震災から一か月後、津波で流された写真を持ち主のもとへ返すボランティアと出会いました。
写っていたのはそれぞれの日常。
写真を本当の力を目の当たりにした気がしました。
「手に持って見返すことによってでしか得られない写真の力があるなと思いましたね。ある人から見れば何でもない写真でも、あの人から見ればものすごく深い感情を揺さぶられるものであったりするんですよね」
写真の力を信じて探す。
新たな道の始まりです。
名もなき写真の力
浅田家には毎年恒例の行事があります。
降りてきたのは元気な子どもたちに父母。
さらに兄の家族で総勢九名。
実家のある三重県からやってきました。
毎年必ず家族全員で集合写真を撮ることにしているのです。
なりたい自分の姿を写真で叶える。
そのモデルとして家族を巻き込んで作り上げてきました。
町を火事から守る、みんなのヒーロー消防士。
映画のワンシーンをイメージした極道一家。
何だか笑えて力が抜けるような写真は写真界の芥川賞とも言われる木村伊兵衛写真賞も受賞。
そして家族写真は撮り始めて21年。
今も恒例行事として続いています。
今回撮影の地に選んだのは兵庫県。
「一年生なんですようちの子が。お兄ちゃんが四年生と六年生になったんですけど、全員小学生は今年しかないなと思って、色々調べてたら兵庫県がランドセルの有名なところだと知って撮りたいとおもって」
役を演じきるために欠かせない衣装。
入学祝いのランドセルに甲子園。
優雅なファッション。
撮影はセルフタイマーを使って行います。
しかしそこは十一月末の寒空の下。
「相当やばいです。風が思ったように凄い」
なかなかOKを出しません。
「要領がとても悪い。準備もですけど」
「予備知識が全くもらえないので、衣装とかも分かんないし」
「言わないですよ」
「自分の頭の中では相当こう広がってあるやろうと思うんだけど、政志はどっちかと言うと上手にみんなにプレゼンができてないから」
撮影開始から二時間。
思わぬ幸運が。
「虹が出ている」
「はいおしまい」
ドタバタの末撮れたのがこちら。
「虹だけはちょっと嬉しかったですね。結構レアなものが撮れました。今まで超寒かったかもしれないですね。寒いけどそういうもういつかはいい思いになったらいいなっていう気持ちを込めて」
撮影の翌日、三重県津市にある実家を訪ねました。
おはようございます
風邪ひかんだ
寒かったなあ
やばかったなあ
「僕の記念写真はこうな何でもない日に、特にこの日は記念日じゃないんですけど、家族でああだこうだ言ってやると。その日自体は記念深い思い出になってくるんですよね。新しく記念日が生まれていくような感覚があって、なんかこう記念日を作る記念写真なのかなっていう風に思っていって、そこはなんかこう伝えていきたいっていうかな。やりがいっていうかそういうとこありますね」
家族写真を撮り続けるきっかけとなった一枚を見せてくれました。
「これが一番最初に撮った家族写真。これまで取ってきた写真の中で一番どれが好きですかとか聞かれるたびにこれって言ってるんですよ。これから始まったんで、これから二十何年続く今でも続いて、これからも続けたいなと思って家族写真に出会えた写真なので」
当時通っていた大阪の写真専門学校の授業で課題が出されました。
写真一枚で自分を表現しなさい。
「ずっと一枚でどうしようかなどうしたらいいかなって考えたらふとこう一生に一枚しか写真が撮れなかったら自分はどんな写真が撮りたいのかなとか、なんかそういう疑問に変わっていって、その時に何か一緒に一枚しか写真が撮れないなら家族が撮りたいなと思ったんですよね」
小学校時代のある日の思い出。
その日父と兄と自分が同時にケガをしました。
そして母が看護師をしていた病院に駆け込んだのです。
「家族の姿と家族のこう記憶みたいなことが同時に写ったら自分の中でふさわしいいいかなと思って。家族の写真って誰でも撮れるし、決してカッコいいものでもないし、全然撮りたいとは思わなかったんですよね。実際に撮ってみたら楽しかったですよね。
みんな楽しそう
今浅田は新たな家族写真に取り組んでいます。
「一番新しい作品の、私の家族という作品の部屋になります」
新作私の家族。
でも写っているのは一人の男性。
どこが家族写真だというのでしょう。
「一人でも家族の物語を感じられる写真が撮れないかなと思って、そこを意識して作ったのは私の家族って作品なんですけど、やっぱりある他人なので、他人の人生の家族の人生を感じることができればいいなと思って挑戦してみているところですね。新作なので、僕もまだまだこれから続けていきたいなと思ってますけど」
新作私の家族
その原点は11年前。
当時浅田は青森県八戸市で得意のコミカルな作品を地元の人たちと一緒に撮影したばかりでした。
自分にもできることはないか
八戸を訪ねた浅田に地元の人たちは言いました。
もっと大変なところに行ってやってくれ。
たどり着いたのが岩手県の海沿いの町、野田村。
震災発生から一か月。
町はまだ混乱の中にありました。
大量に送られてくる支援物資の仕分けを手伝った帰り道、役場の前で一人の若者に出会います。
織田洋輔さん。
千葉で学生生活をしていましたがふるさとが心配で戻っていました。
織田さんは津波に流された写真を持ち主に返そうと洗っていました。
「写真を洗ってる時に浅田さんがいらっしゃって、お声掛け頂いて写真を洗ったりする中で実は写真撮ってている仕事をしてるんだよっていうことを聞いてまそこからですかね色んな活動にこう協力してくださって」
写真洗浄のボランティアを手伝うことにしました。
思い出の卒業アルバム。
何げない家族のスナップ。
汚れの落とされた写真を多くの人が食い入るように見つめていました。
「僕が思ってる以上に皆さんが写真のことをやっぱりこうに関心があって、写真のことをだいぶ大切に思われてて、何て言うかな、実際に僕も写真一枚一枚洗う中である種こう自分の得意な撮り方だったりとか、今まで自分が作ってきた写真の世界観だけじゃなくって、何もなき写真が本当に数え切れないほどあって、そういった写真って日頃は目を向けられるものでもないかもしれませんけど、持ってる力っていうのかなそういうのを凄く感じたんですよね」
今も続く活動に参加している浅田。
その中で新たに撮りたい写真のイメージが湧き上がってきました。
「いかに僕の色を出すかっていうことじゃなくて、その人が本当にこの写真が宝らものだっていうか、大切だなって思える核っていうかな、それを写したいと思うし、たとえ写真では素朴なたたずまいだったとしても、何かその人のここを映したいっていうところが見定められて撮れてるんだったら自信持って作品として出していけるような自分なりにも変化は出てきましたね」
そして始めたのが私の家族プロジェクト。
ある一人の人にとって特別な一枚を撮影してて渡す企画です。
この日訪ねたのは応募の中から選ばれたこちらのお宅。
地元に根付く写真館の二代目・細井佑基さん。
細井家には佑基さんのお父さんが撮影したという家族の写真がたくさん残されていました。
目に止まったのは仲良く映る兄弟の姿。
「両親がよく言った、たった一人の血の繋がった兄弟なんだからって言うのが僕の中ですごい印象に残ってて」
三歳下の弟さんにも話を聞くことに。
何をどう撮れば特別な一枚になるのか。
「うん兄弟がもう見たことないぐらいやっぱり豪華なアルバム持ってるんですよね。それが凄く僕の中で印象的で、この素敵なアルバムなんか持ってる人幸せだなと思って」
今度はお母さんの初美さん。
写真を撮られるのが苦手だという初美さん
家族写真の時には体を半分隠して写っていたりするんです。
「家族写真で撮る時はやっぱり体半分どっかに隠すとか、撮るなとか、逃げたりするんですけど」
「お母さんどこが一番似合う所」
「うちの台所っていう感じです」
半分隠れてるお母さん。
父さんの貴さん。
この写真館を始めた初代館長です。
今も佑基さんと二人でお店を続けています。
実は佑基さん。写真館をつぐ気はありませんでした。
大学卒業後、東京の不動産会社に就職。
その後幾つかの仕事を経験しましたがやりたいことは見つかりませんでした。
写真館をつごう。
東京で八年間写真を学び、三十五歳で帰ってきました。
「水戸に帰ってきて、朝の九時半から夜十八時まで同じお店の中で二人でいるとやっぱりお互いの主張とかがぶつかるというか、撮影内容について話し合った時に
まあ父はこうした方がいいんじゃないかっていうのを言うんですけど、僕としてはちょっと前時代的だなっていう風に思ってしまって素直に聞き入れられない部分がやっぱりあるんですけど」
スタジオの中で照明などの職人技を極めようとするお父さん。
しかし佑基さんのやりたいことは違うのだとか。
「お店を僕父ほぼ任せて外周りというか営業とか、カウンターでお客さんとか友達とあって喋ってるって言うか喋ってることの方が最近多くて」
スタジオには膨大なネガフィルムが置かれていました。
お父さんが撮り続けてきた地元の家族。
「お父さんが今まで撮られてきた足跡を表現したいなと思って」
このネガフィルムとお父さんの姿を一緒に撮ることにしました。
いよいよ佑基さんの特別な一枚を撮影します。
撮影場所にはお父さんがこだわり続けたスタジオを選びました。
「今この場所で生まれて、本当は写真次ぐ気なかったけど、やっぱりおやじの仕事次いでみたいなって思うようになって、小さい頃からおやじに撮られてた思いとかをこう感じながら撮ってる感じがなんか出たらいいなと思って」
最後にもう一枚。
佑基さんが幼い頃お父さんと一緒にランニングをした思い出の場所。
父の後を走る佑基さん。
「浅田さんに写真を撮られてる父を見て、撮り溜めてきた歴史とか、今までのやっぱり父の写真っていうのを見て、逆に僕が見返したことで父に対する尊敬っていうのが出たのかなっていう風には思いました。まだ追い付けないし追い越すことはできるのかなってすごい思うところであって、でもいつかは追い抜きたいそうではあります」
撮られることで気付くこともある。
佑基さんにとって特別な一枚になったでしょうか。
私の家族。
こんな応募もありました。
自称築百年の古民家に、四世代で酪農を営んで暮らしています。
私の曽祖父は町長や酪農組合長を務めた人でした。
夫の祖父は町会議員として、私の曽祖父と共に働いた人でした。
私たちはそんなことは知らず結婚するとなって、相手を紹介するとみんな素性を知っていて、共通の知人も多く私の家族と夫の家族はまるで最初から一つの家族のようでした。
息子たちにもいつかこの大きな繋がりを感じてほしいと思って応募しました。
外之内加奈さん。
築百年という家で待っていたのはご先祖様たちです。
ご先祖様と一緒に撮影することに。
「ご先祖様の存在というか大きいなと思って、写真でこう飾って。これをこう感じながらこう普通に普段に生活する写真を撮った」
加奈さんがひいおじいさんが残したアルバムを見せてくれました。
地域を豊かにしようと酪農を始めたひいおじいさん。
家族のアルバムにはこの土地での一家の歴史が刻まれていました。
加奈さんは酪農家として四代目にあたります。
結婚したのは同級生の智則さん。
応募の手紙にあったように、挨拶の時、両家がもともと知り合いだったと分かりました。
結婚を機に仕事を辞め、加奈さんと一緒に酪農をしています。
「妻がやりたいことがある」
「牛乳を売りたいとかもあるし、そのあとこの町でやってきたみたいなことでなんかこうもっと生産だけじゃなくって人に知ってもらうような立場の牧場になっていけばいいと」
実は加奈さんの父昌雄さんも結婚してから酪農を始めていました。
「ここで二人並んで撮ってみたい」
何かを思い付いたよう。
ちょっと恥ずかしげなふたり。
「集合写真は撮ることはあっても、あの二人で写真撮ることは本当にないだろうなと思って。まだまだ遠慮があるんでお互い。そこはもう少し自分が繋いでいけたらいいのかなっていう風にまその写真を見て戒めにできるといいな」
子どもたちの散歩についていくことになりました。
ここで散歩の様子を一枚。
子供たちは近所のお宅の庭先にいました。
ここで一枚撮ることに。
「本当に毎日あのおばちゃんとあって、よく本当に可愛がってくれて、おじいちゃんおばあちゃんで。でも親戚な訳でもないし、だから一緒に写真を撮る機会もないけど、毎日繋がりがあって、かわいがってくれた近所のおばあちゃんがいるってことをきっと彼らを忘れちゃうかもしれないけど、かわいがってもらったんだよってことをなんかこう残せるかなと思って」
加奈さんにとっての特別な一枚とは何なのか。
「なんかそういう大きい街の何ていうかなこの地域も含めた家族観みたいなことを撮れればいいなと思ってるんですけど」
家と牧場を繋ぐ一歩道。
この地で酪農んを始めて以来八十年以上。
一家が幾度となく行き来してきた道。
ここで撮影をすることにしました。
「遠い会ったこともないご先祖のことをイメージしながら」
ご先祖様に見守られ一本路に立つ加奈さん。
その時心に浮かんだのは。
何百年も前から繋がり続けて今ここに私がいる。
そして私もまた次に渡すバトンを手にしている。
私はどんなバトンを渡せるだろう。
「今ゴールじゃなくって、これからも続いていくその家族の物語の中のある一つの時代っていうかな、大きな家族の中でどんどんこうまた渡していくようなことが写真からこう伝わったら嬉しいなと思って」
四か月後。
外之内家に小包が届きました。
お母さんだ
きれいに撮れてる
写真は早速神棚へ。
「おじいちゃんとご先祖様に報告して、手を合わせるときになんかよくみんなで見れるよ」
「これが大事だなって思った今の気持ちをもう本当そのまま残してくれたって感じなので、息子が大きくなったりとかした時に見返しても、今の気持ちそのままをなんかまた見れるのかなっていう風に思います」
写真は細井さんの家にも。
「息子のアルバムは最高でした」
「あんまり仕事風景を見ないので新鮮な感じです」
「うんやっぱりお店を継ぐっていう決意をした場所でもあるお店にかざろと思います」
新たな形の家族写真。
その力が見えてくるのはきっともっと先のこと。
「一緒に作品を作ってからがある意味こうスタートなんですよね。本当にその写真の意味みたいなことが、写真にとってよかったといつかの未来に思ってもらえるように最後は形にして渡してます。それが家の中で飾られてその写真とそれぞれの方の物語がまた始まったら嬉しいなと思ってますね」