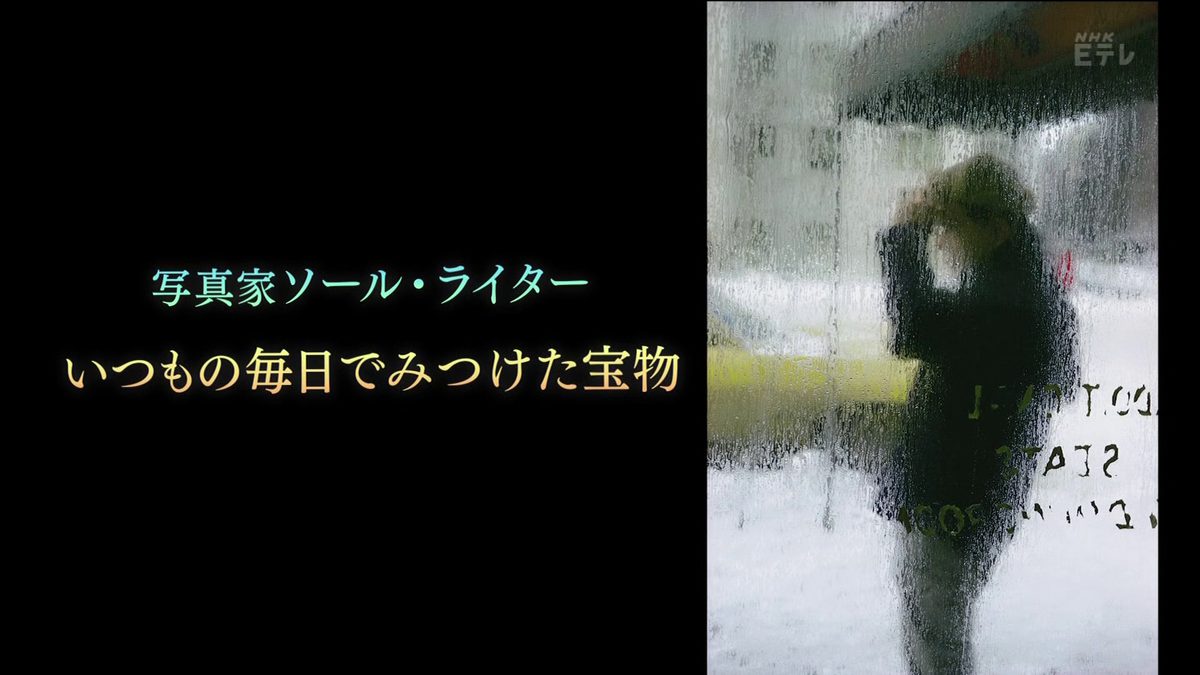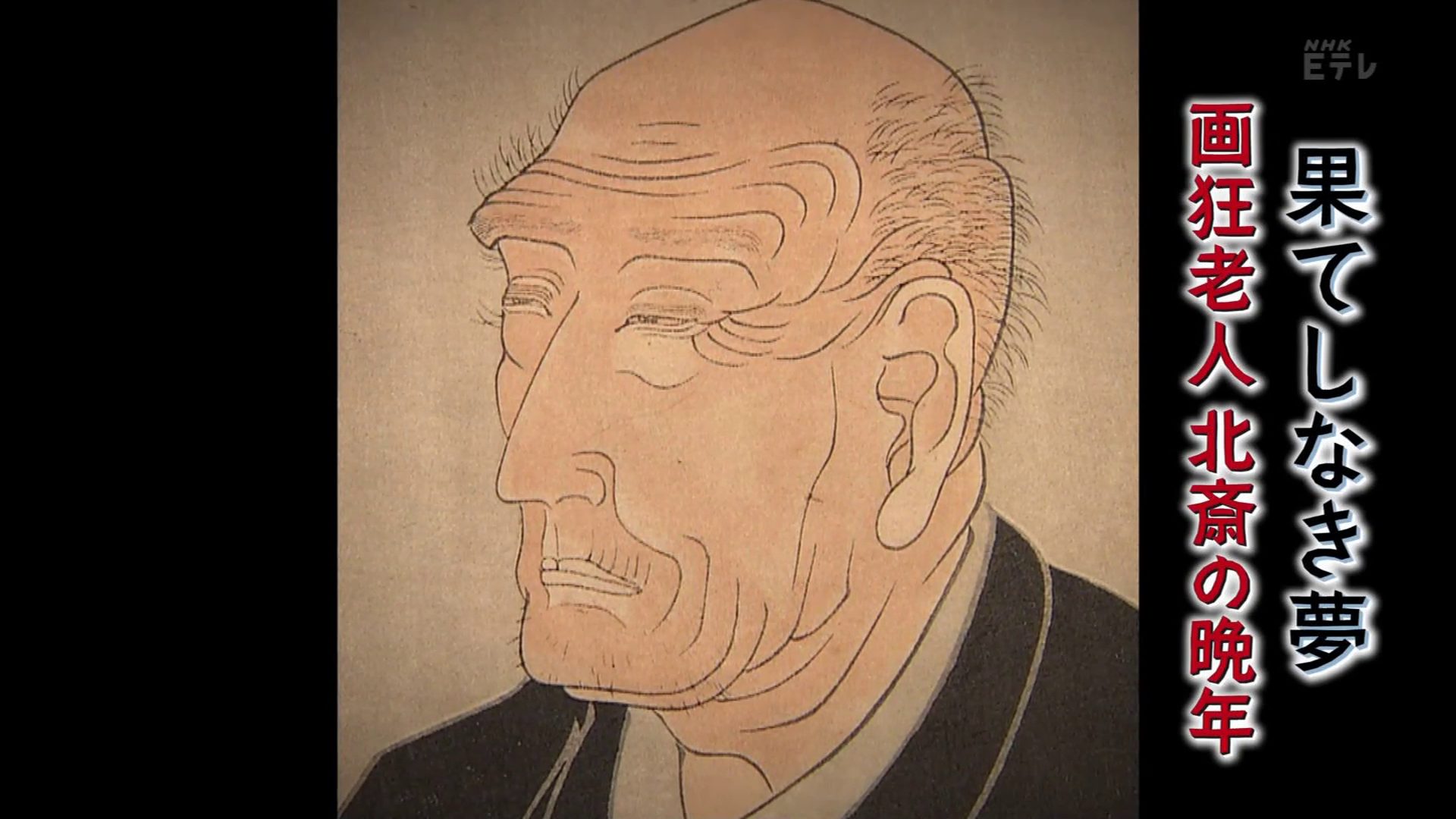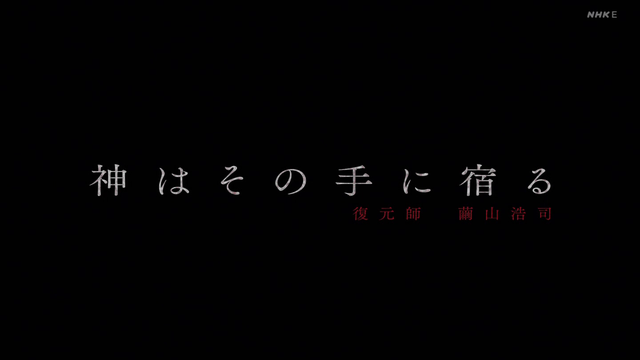「私は無視されることに人生を費やした。それでいつも幸せだった」。元々ソール・ライターは、1950年代からファッション写真の最前線で活躍した写真家。しかし80年代、突如スタジオを閉鎖、表舞台から姿を消す。再び名が知られたのは、四半世紀が過ぎた80代。人知れず撮りためてきた路上スナップが出版され世界中で人気となった。残された言葉、関係者の証言を手掛かりに、なぜその写真が時代を超えて心を打つのか探る。
放送:2020年2月9日
日曜美術館「写真家ソール・ライター いつもの毎日でみつけた宝物」
今、SNS などネットで見かけるソールライター風と名付けられたスナップ。
上から覗き込んだ構図。
画面の端に鮮やかな赤い傘。
どれも独特な視点で切り取られたものばかり。
ソール・ライターは2000年代、80歳を過ぎてから世界に発見された写真家でした。
その代名詞はストリート・スナップ。
雪が降る通りにできた無数の足跡。
そこに鮮やかな赤い傘。
日常に潜む一瞬の光景を見たことのない構図と鮮やかな色で切り取る。
それをどこかに発表することもなく50年以上続けていました。
「彼は生活を変えませんでした。
朝起きてからスケッチブックに絵を描くとかコーヒーを飲むとか近所を散歩するとか、毎日どこに行くにもカメラを持ってそれは亡くなるまで変わりませんでした」
金や名誉を求めず、日常に目を向け続けたソール・ライター。
「雨粒に包まれた窓の方が私にとっては有名人の写真より面白い」
その生き方は今日本で多くの共感を集めています。
三年前に開かれた回顧展には8万人以上が来場。
写真集は4万部。
Saul Leiter: All About Saul Leiter
ほぼ無名の海外の写真家としては異例の人気です。
なぜ今を生きる日本人に響くのでしょうか。
「雨の日でも雪の日でも写真にしてますよね人生をすごく楽しんでた人じゃないかなと思います」
「すごいことは写ってないんだけど写っている写真は何かすごいことが映っている」
不思議な魅力にあふれたソールライターの世界今なぜ私たちはその写真に惹かれるのでしょうか。
ソールライターとは
2006年ドイツの出版社から出された写真集に世界的な注目が集まりました。
「アーリーカラー」ソール・ライターが83歳にして初めて出した作品集です。
Early Color
何も変わらない: ハンクとして芸術家の魂
All About Saul Leiter
それは撮られたまま日の目を見なかった八万点から発掘された作品達でした。
写っていたのは1950年代のニューヨーク。
カラーフィルムがまだ一般的ではなかった時代に撮られた色鮮やかな街の風景。
撮り方も独特です。
画面のほとんどが黒と赤。
よく見れば真ん中には白い車と人影。
板の隙間から見える通りの光景を捉えた1枚です。
こちらも大胆な構図。
画面の大半をカーテンのようなものが覆っています。
半世紀以上も前にカラースナップを人知れず探求していた写真家がいたことに世界は驚きました。
ソール・ライターの写真を愛する一人、写真家のかくた みほさん。
北欧・フィンランドを撮り続けながら、ヒット曲のCDジャケットなども手がける人気の写真家です。
角田さんは3年前雑誌の仕事でソール・ライターの暮らしたニューヨークのアパートを訪ねました。
60年間を過ごした部屋。画家が好む北向きの大きな窓。
ライターは1946年。23歳の時に画家を目指してニューヨークに出てきました。
しかし次第に趣味であった写真にのめり込んでいきます。
ちょうどカラーフィルムが実用化されたばかりの頃でした。
ライターが暮らしたのはマンハッタンの南にあるイーストビレッジ。
「こういうぐらいとかですかね」
ライターがスナップしていたのは歩くと20分ほどの狭い範囲でした。
「なんか本当に普通にどこにでもあるような町と言うかお肉屋さんとか割とちょっと近所の人が使うようなお店とかが多くて」
イーストビレッジは家賃が安かったことからアーティストが多く暮らした町でした。
外に安売りのワゴンをいつも出しているお気に入りの書店。
散歩の途中一休みしたベンチ。
ライターが撮っていたのはニューヨークのローカル。
ごくごく普通の街並みだったのです。
そんな風景をガラリと変えるのがソールライター独特のまなざしだと角田さんは言います。
「私は単純なものの美を信じている。もっともつまらないと思われているものの中に興味深い者が潜んでいると信じているのだ」
ソール・ライターはガラスを利用して日常を神秘的に撮ることを愛しました。
角田さんがカメラを向けたのはショーウインドウ。
どんな写真を撮ったのかと言うと。
「ガラスに映ったポスターの方に赤い色が利用できないかなと思ってガラスとか鏡とかに写っている映り込みを利用して奥行きがある写真にしていくっていうのがポイントかなと思ってます」
角田さん今度は地面にはめ込まれたガラスにカメラを向けます。
歩く人の足下にその上半身が映り込むまか不思議な光景。
二つ目の特徴はポイントカラー。
「誰もがモノクロのみが重要であると信じていることが不思議でたまらない。美術の歴史は色彩の歴史だ」
シンプルな色味の背景に明るい一色を入れ印象深い画面に。
街中に息づくビビットな色を拾い上げ、まるで絵のように画面の中に納めます。
「赤い椅子があるのもなんかあるかも。赤い椅子。白い人と白い閉じてる傘とかなんかちょっと連動性があるやつとかもモチーフに結構選んでたりするので。黄色い可愛い子が来た」
道路のグレーに女の子の黄色がポイントカラー。
通りかかった自転車の車輪もアクセント。
「自転車が来てよかった」
ソール・ライター三つ目の特徴が1/3構図です。
「私の好きな写真は何も起きていないように見えて、片隅でナゾが起きている写真だ」
1/3構図は画面を縦か横に3分割しその一箇所に被写体をまとめて配置する方法。
ライターは画面の隅に視線を集め、そこで起きている物語に私達を引き込みます。
角田さん郵便ポストを撮っているのかと思いきや。
「赤を入れつつ人の足元がちょっと1/3みたいな感じで、普通だともっと足によって撮影したりとかしたとこですけど、割となんか本当に画面の中のすごい小さいところを、ソールライター見せようとしているので、これぐらいも余白が多いような構図とかでも、写り込む感じと構図が1/3とかにできるとちょっとソールライターっぽく撮れるかなっていうところがあります」
ソールライターにはことさらに愛したいくつかのモチーフがあります。
その一つが傘。
時には傘の端だけのことも。
ある時アシスタントが言いました。
もう傘はたくさん。
彼の答えは。
「私は傘が大好きなんだ」
雨粒や水滴も彼が愛したモチーフ。
普通だったら見過ごしてしまうような一瞬の出来事。
「雨粒に包まれた窓の方が、私にとっては有名人の写真より面白い」
雪のシーンも多く登場します。
ソール・ライターのまなざしを通して見つめると、
いつもの毎日が少し違ったように見えてくる。
「自分の美しいなって思うものを探していたしてる視点っていう感じで毎日同じ景色の中で人とか車とか動くものだけが少しずつ変わっていく被写体が入って写り込んで来てっていう感じで、本当に何か儚さとか刹那とかそういう一緒の美みたいなものを見出してたのかなって思いました」
スタジオ
ファッション写真家
実はソール・ライターが最初に注目されたのはファッション写真家として。
手掛けていたのはハーパスバザー。エル。ヴォーグといった一流ファッション誌。
その手法は少し変わっていました。
「スタジオでも撮影を好む編集者たちとも働いた。スタジオだと昼食会ができるから彼らにとっては快適だったのだ。外で働いていたら昼食会ができないからね。では私は仕事で働くのが好きだった」
板を持った作業員が通りがかり画面を遮ったユーモラスな一枚。
彼はファッションでも街中で起きる偶然をうまく取り込んだ写真を撮りました。
収入はトップクラス。
ニューヨークのメインストリート5番街に広いスタジオを構えるほど。
しかし華やかな世界は彼の求めたものではありませんでした。
「かつて、ファッション誌での一年より、好きな画家の一枚のデッサンの方が私にとってはより意味があると編集者に行ったことがある。彼女の表情は凍り付き、完全に軽蔑の眼差しで私を見つめていた」
そして81年。事件が起きます。
ライターの晩年。
アシスタントを18年間務めたマーギッド・アーブさん。
「モデルの撮影をしているとき、スタジオの後ろにビジネスマンが大勢並んでああだこうだと指示を出すんですね。彼は耐えられなくなってカメラを置いてその場から出て行ってしまったのです」
スポンサーの意向が強くなり次第に自由な表現ができなくなったファッション写真からソール・ライターは身を引きます。
毎日カメラを持って近所に出かけ、まるで都会の仙人のように暮らすようになりました。
「友人たちからの援助でなんとか暮らしていたのです。電気代さえ助けがなければ支払えなかったのです」
仕事のオファーがあってもなかなか受けなかったと言われるライター。
親しい友人はこんな冗談を言いました。
「ソール。君はチャンスを避ける才能に恵まれているね」
しかしライターには成功や名声よりももっと大事にしていたものがあったのです。
それはライターの秘められた過去に関わっています。
1923年。アメリカピッツバーグで生まれたソール・ライター。
家は代々ユダヤ教の宗教指導者を務めていました。
高名な学者だった父親のウルフ。
将来を嘱望されていたソール・ライターは子供の頃から厳しい戒律を守り聖職者になるための勉強に励みました。
しかし、23歳の時に神学校を中退。
ニューヨークへと旅立ちます。家族の失望は大きかったといいます。
「ソールの話では、父親に学校を退学してアーティストになりたいと告げたとき、父親が言ったのは シャガールになってもいい、チェーホフになってもいい。物書き、画家はいいが写真家は職業の中でも最も低いものなのだ と」
偶像崇拝を禁止するユダヤ教では、他人を写真に撮ることはタブーだったのです。
家族で唯一写真家になることを応援してくれたのは二歳違いの妹のデボラでした。
繊細で感受性豊か。
デボラはソール・ライターにとって初めてのモデルでした。
十代から二十代にかけて撮ったポートレートが100点ほど残されています。
「ソールライターとデボラは親友のような関係でした。厳しい戒律の中で生活していたので、おそらく少年時代の彼の唯一の友人が妹のデボラだったのだと思います」
しかし、幸せな時間は永遠ではありませんでした。
デボラは20代で精神を病み入院。
生涯戻ることはなかったのです。
ソール・ライターがその後の人生を共に歩んだのがソームズ・バントリー。
二人はファッション写真家とモデルの関係で出会いました。
ソール・ライターのアパートにかかっているのは二人が書いた油絵。
共通の関心事である絵を通して親しくなり、そして恋人になりました。
愛するソームズのポートレート。
自分の信じる道を進むソールを支えた存在でした。
「成功のために全てを犠牲にする人もいるけれど、私はそうしなかった。私を愛してくれる人。私が愛する人がいるかということの方が私にとっては大切だった」