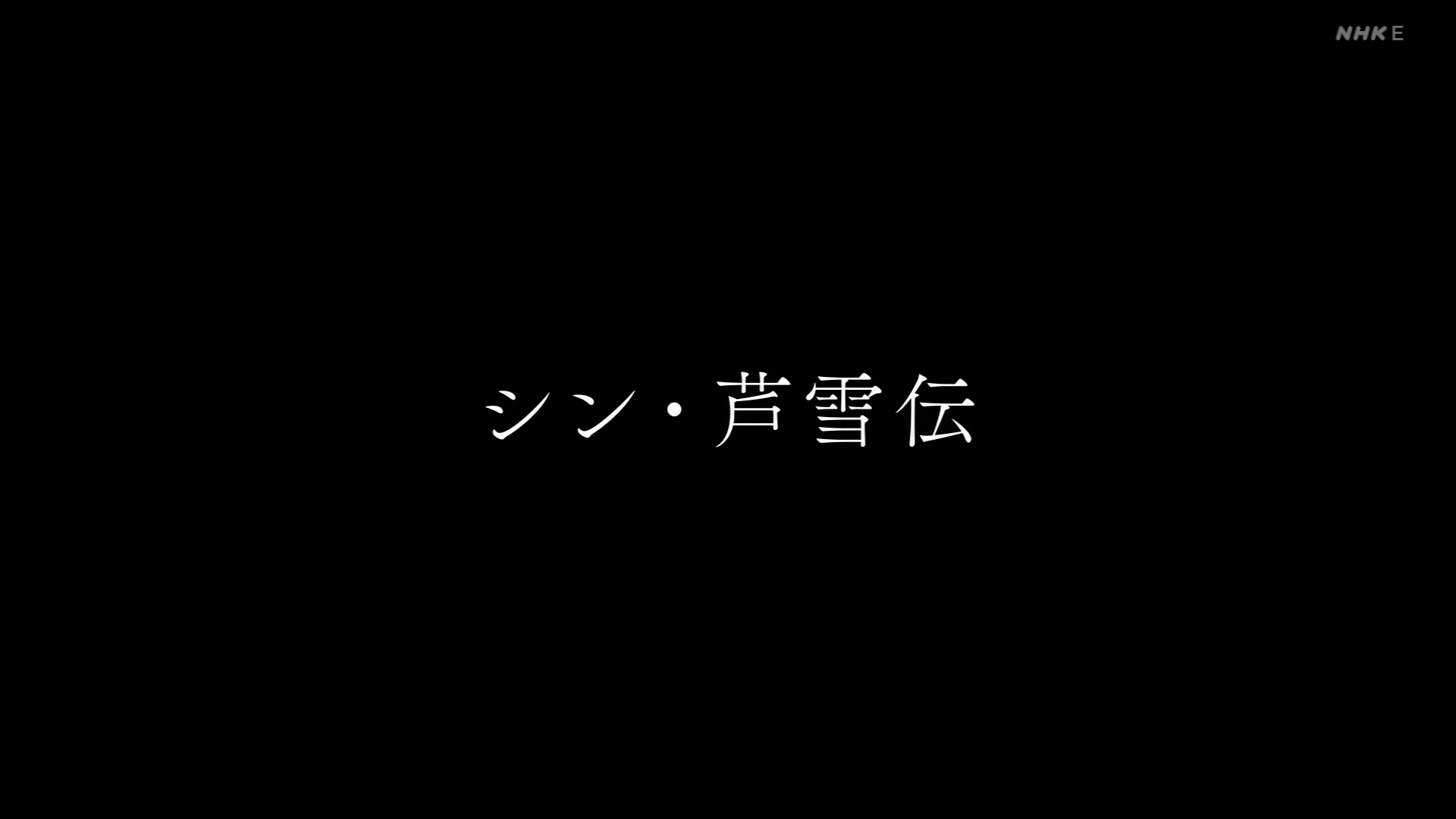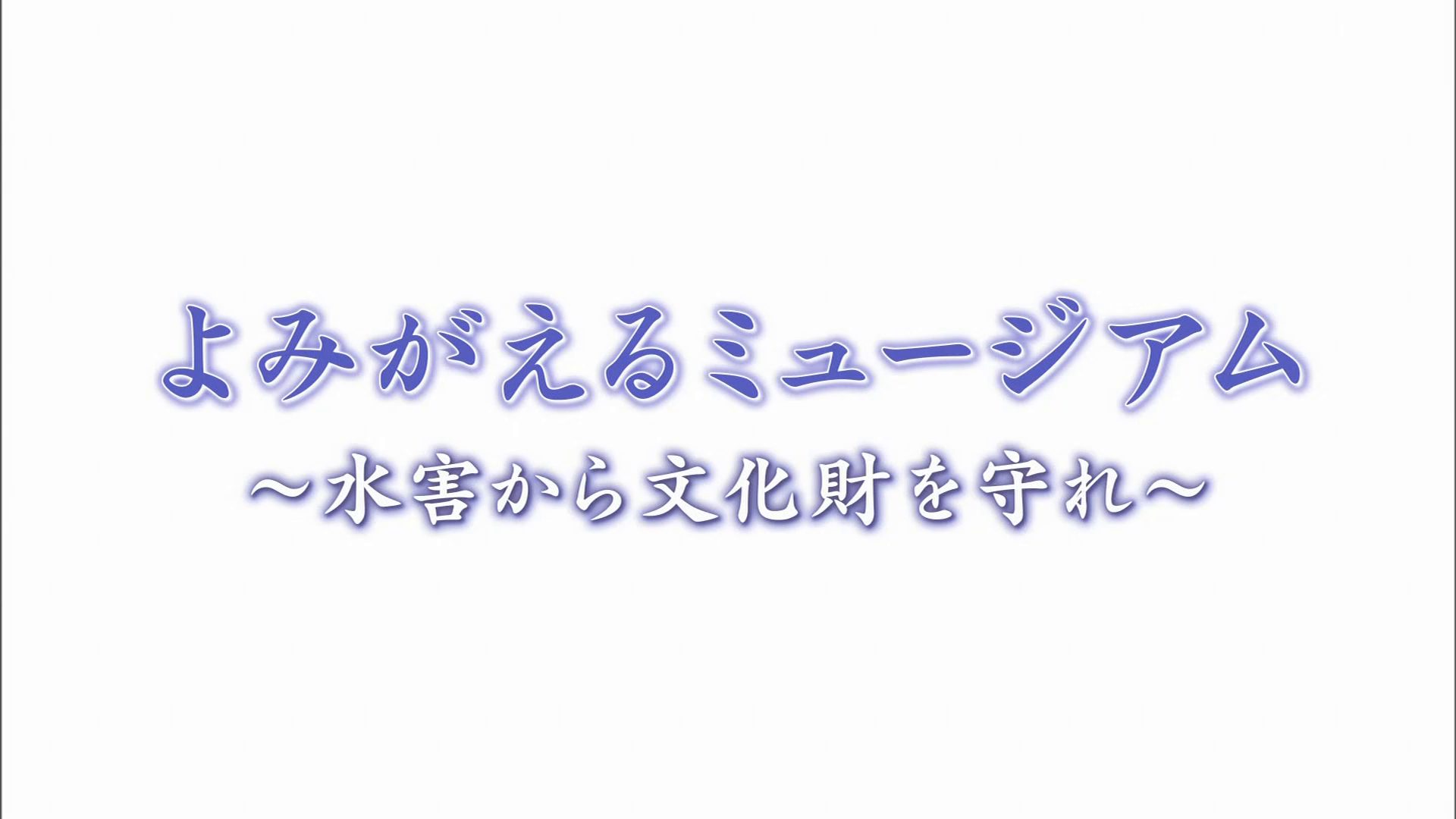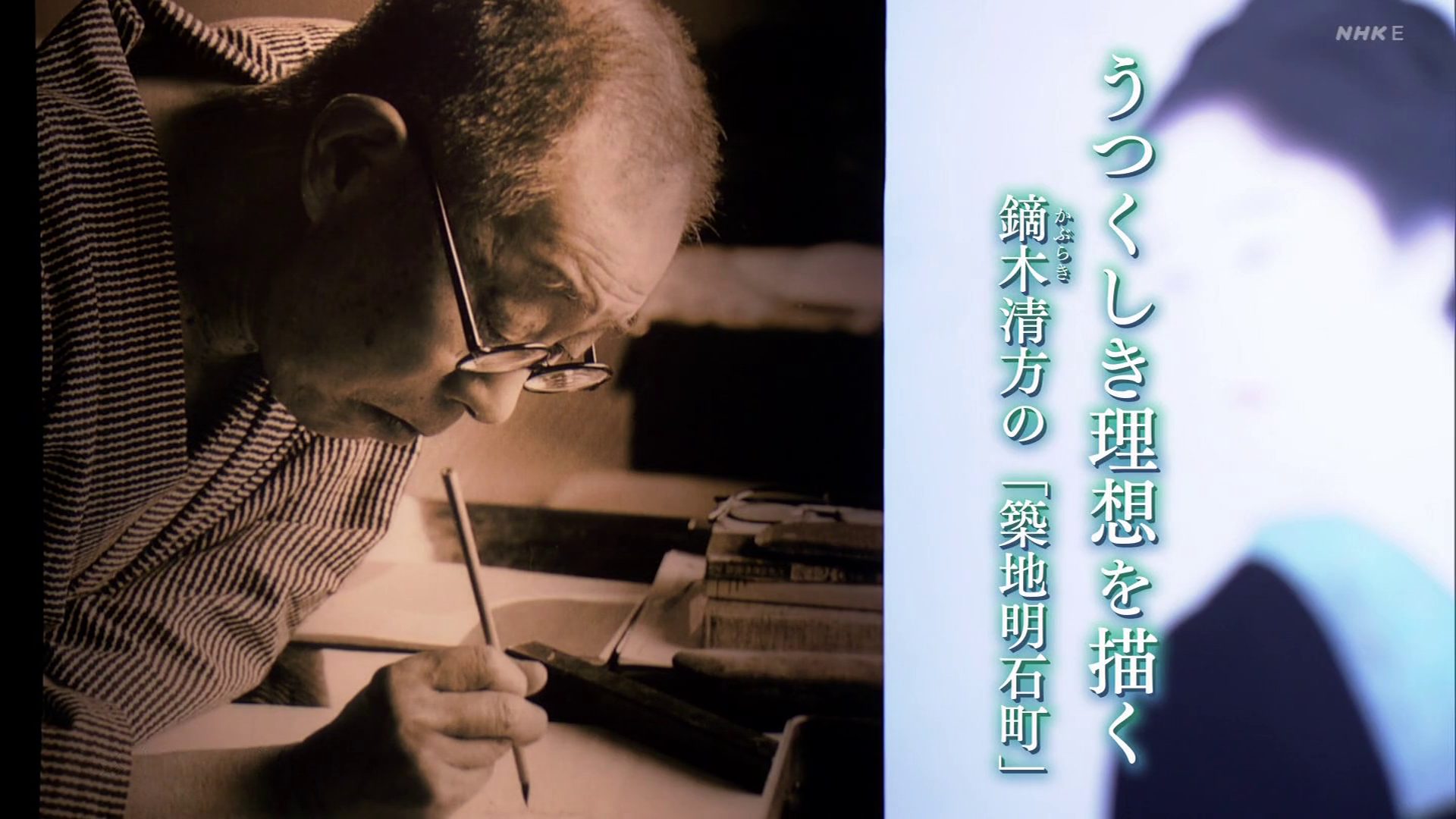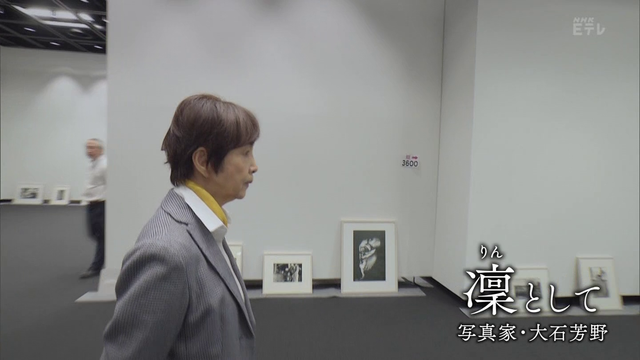江戸時代中期に京都で活躍した長沢芦雪。若冲や蕭白と共に、奇想の絵師の一人として人気が高まっている。奇抜で大胆な画風から、自分勝手で反抗的、恨みを買って毒殺されたなど、悪いうわさが伝えられてきた。しかし近年の研究から、師の教えを守り、高度な技と独自の発想で人を驚かせる絵を描き続けた、新しい人物像が見えてきた。今、大規模な展覧会が開かれている大阪中之島美術館を舞台に、傑作の数々が物語る真の芦雪像に迫る
初回放送日:2023年11月26日
日曜美術館
それは謎の始まりでした。
220年ほど前、大阪で一人の男がこの世を去ります。長沢芦雪、46年の生涯でした。
大胆不敵な筆さばき、常識破りの奇抜な構図、そしてこの世ならざる怪しさ。芦雪が描く命の姿はまさに奇想天外です。
芦雪はその人柄もまた破格だったと伝えられています。大酒の上、短気、いつもわがままな振る舞いばかり。そのため最後は恨みを買い、暗殺されたのだと言います。
しかし伝承は真実の芦雪を伝えているのか。残された芦雪直筆の手紙、そして半世紀ぶりに姿を現した幻の作品。研究者たちは今、自らの目で作品と向き合い、芦雪の新たな人物像を読み解こうとしています。
今生きている2023年、生きている自分たちの上で改めて作品を見ることで、基礎とは違ったイメージを受けたり、正しい芦雪像みたいなものにも迫っていけるんじゃないかなと思いますね。謎に包まれた絵師長沢芦雪。奇想の憶測に潜むその素顔を見つめます。
「シン・芦雪伝」
長沢芦雪が最後の時を迎えた大阪。生誕270年を迎えた今年、記念の展覧会が開かれています。
「存在感が遠くから見てても圧倒されるような力強さがあって、吸い寄せられるように近づいてみると、細部はたやすく描いているように見えるんだけど、本当にあらゆるところに意識が傾けられていると思うんですよね。風が流れている、風が流れて、これ、龍から何かが走っているのか、雲の中で何か光が稲荷神のようなものが走っているのか、よくわからないんですけど、本当に雲の中を龍が自在に動いているという、これ行くと今度虎で、それもやっぱり躍動感があって、動いている感じがします。」
「竜頭と並ぶ」芦雪、三十三歳の傑作。
「毛ですよね。粉のような毛が動いているというか、明らかに運動しているんですよね。毛がこちら側に親しみやすい可愛らしい顔をしていて、そういう虎が動いている。戦死したこの絵が躍動感を持って、しかもこちらに飛び出してきそうな存在感を放つという、どうしてこういうことができるのかっていうのはね、だって描かれているのは炭だけですよね。炭の濃淡と線だけで、こういう不思議な現実を作り出しているというか、それに圧倒されました。」
半世紀ぶりに公開された貴重な作品。和歌山那智の滝を描いたこの一服はい、流れ落ちる滝色を塗らず、絹地本来の白と筆のかすれだけで水の勢いを表す露雪の技。掛け軸の真ん中に、小さな絵縦横わずか三センチの中に書かれているの は五百人の羅漢たちです。極端なまでに微細な描写、しかしすべてが形をなし躍動する様はまさに奇想の景色です。中国の禅の逸話を描いた江川律描部。芦雪の巧みな技と驚くべきイマジネーションが見る人を楽しませます。
「簡潔な線と墨の塗り方で、後ろにある重量感と、そこに乗っている軽やかさが同時に描かれています。この隣の絵では、下が海だったら浮かんでいることになりますよね。空に陸のようにも見える黒い塊は、実はクジラの背中だとか。これまで全部空想で描かれたものなのですが、クジラ越しに見た量の世界、発想がすごくないですか? これは本当に思いつかないです。この辺り、何なのかっていうと、少しぼやけた濃い炭が焚き火みたいになっていて、お鳥様が炎に包まれているような感じです。今の段階で露雪がどんな人かと言われたら、絵を描くのが楽しくて、非常に技術も高い、いろんな基本を使いこなせる人で、それを示すことなく、いろんな組み合わせで驚かせることができる人だと思います。」
奇想の絵師として高い人気を集める長沢芦雪は、実はその生涯を語る資料がほとんど残されていない謎の絵師でもあります。
大正時代、その実像に迫ろうとした人物がいました。美術史家のあいみこうです。あいみこうは、芦雪の子孫やゆかりの人物に聞き取り調査を行い、『芦雪物語』を発表します。そこには、芦雪の人柄をうかがい知る驚きの逸話が数々記されていました。
多趣味多芸だったという芦雪。中でも、駒回しの芸は名人の域に達するほどでした。ある日、殿様に呼ばれ、その芸を披露した際、高く放り投げたコマを受け損なうと、それが目に命中し、血しぶきがあたりに飛び散るほどの大怪我を負ってしまいます。しかし芦雪は「ご心配には及ばない」と周囲の静止を振り切り、そのまま芸を続けました。このことが原因で芦雪は片方の視力を失ってしまったというのです。
また、芦雪の気位の高さを物語る逸話もあります。丹波亀岡藩の殿様から絵の制作を依頼された芦雪は、一メートル五十センチを超える対策を駆け上げました。ところが、出来上がった絵を屋敷に持参すると、取り継いだ家来からあまりに高額だと値引きを持ちかけられます。これに腹を立てた芦雪は、それでは引き取りに及ばぬと作品を持ち帰り、別の人物に売ってしまいました。このことを知った殿様は怒りが収まらず、その責任を負った家来は切腹したと言います。
逸話は天才肌で高慢な人物像を伝えています。
しかし、それは
真実をどこまで伝えているのか。去年、芦雪像の再建築を迫る一枚の絵が見つかりました。「こちらが外国展示になります。これ五十二年ぶりに発見されています。」
縦164センチ、横99センチの大画面に、はみ出さんばかりに描かれた大黒天。実は、半世紀以上にわたり、行方がわからない幻の作品として知られてきました。
研究者たちにとって、行方不明になる以前に撮影された古い画像だけが、この作品を知る唯一の手段でした。
小槌を抱える手元の部分は奥行きがなく、平面的に見えます。その特徴から、伝承通り、露雪は石丸だったと考えられてきました。
半世紀ぶりに姿を現した大黒天像。露雪研究の第一人者である岡田秀幸さんは、実物を初めて見た際、立体感あふれる巧みな描写に目を奪われました。そして、伝承にある「赤眼露雪」の信憑性に疑いを持ったと言います。
「両手で打ち出の小槌を持っているんですけれども、写真で見ると確かにこの辺りが平面的に見えて、空間がよくわからなかったんです。でも、実物を見るとやっぱり、ぐっと小槌を持って胸の前に非常に大きな空間があり、後ろには大きな袋を背負っています。そこにもふっくらとした奥行きと空気感が感じられます。
片方の目が不自由だという説がありますが、その伝説とは少し違うかなという印象ですね。決して視覚に制約がある中で描いたというよりは、こうした描き方を意図的に選んだ表現の一つではないかと思います。
これまで『奇想の絵師』として引き継がれてきましたが、今生きている私たちが改めて作品を目にすると、奇想とはまた違ったイメージを受けるかもしれません。そうすることで、より正確な露雪像に迫れるのではないでしょうか。」
長澤芦雪は1754年、現在の兵庫県に生まれたと伝えられています。しかし、どこでどのように育ったのか、詳細は何も分かっていません。確かなのは、20代の頃、京都で随一の人気と実力を誇る絵師、丸山応挙の下で絵を学び始めたということです。
応挙が描いた孔雀や大象を細かく観察し、写し取る写実的な表現は「真に迫る」と評されました。応挙の下で、芦雪はその画風と技術を余すところなく吸収していき、千人を超える応挙の弟子の中でも、一、二を争う実力を身につけていきました。
しかし、『芦雪物語』によると、奔放な性格の芦雪は、次第に師の教えを窮屈に感じ始め、度々応挙と対立。そのため、3回も破門されたと伝えられています。
芦雪が33歳の時、人生の転機が訪れます。応挙の命により、和歌山南部に向かった芦雪は、忙しい師匠の代役として、再建されたばかりの寺を飾る襖絵を制作します。応挙の束縛から解放され、自由になった芦雪は、自らの画風を手に入れたとこれまで考えられてきました。
「師匠である応挙との関係は複雑で、和歌山の寺のために描いた作品では、応挙との距離があったため、芦雪はより自由に描けたというエピソードがあります。しかし、実際にはどうだったのでしょうか。」
「和歌山の各寺に関しては、若き頃に丸山応挙が住まいの制作を依頼された際、忙しすぎて弟子を派遣したという話は伝わっています。ただし、なぜ芦雪が派遣されたのかについては詳しい説明がありません。そのため、たくさんいる弟子の中でなぜ芦雪が選ばれたのかについてはあまり考えられていないようです。」
皇居はなぜ芦雪を選んだのか。師を敬い、その教えを信奉する芦雪の姿があったからだと岡田さんは読み解きます。古代中国の伝説の美女を描いた二服の掛け軸右が応挙、左はまだ和歌山に向かう以前に露雪が書いた作品です。
「応挙は本当に中国の絵を勉強し、そこから理想的な美しさを描いています。桜の花びらや水の流れ、岩の描写も非常にリアルで、現実に存在しているかのような描き方です。しかし、露雪は応挙とは異なり、着物の中に体を描くようなこともあります。応挙の技が隅々にまでみなぎっていますが、露雪は二十九歳の時に描いた作品においても、応挙と同じ写実的な美人図を描きつつ、独自の表現を見せています。
露雪は、細部において彼らしさを表現します。例えば、着物のシワをかすれさせたり、非常に鋭い綺麗な線を引くのが特徴です。髪の毛の表現やまつ毛も細かく描かれています。松の描写も独特で、色をつけずに隅だけで描いたり、枝の出所が曖昧なこともあります。
露雪の作品は、西洋的な美しさに焦点を当て、全体のバランスよりも女性の美しさに注力しているように見えます。彼の作品は、女性をいかに美しく描くかに重きを置いています。
露雪は応挙の技術を自らのものとしつつ、一方で独自の表現を模索していました。和歌山に行く直前に描いた掛け軸には、皇居とは異なるリアリティが見られます。真ん中にホテルさんがいて、周りの家の方が人形を見ているという設定です。下の犬の視線を追っていくと、湖底で遊ぶ人形が見えるようになっています。ホテルさんが遊んでいる場面や、スズメたちが飛んできて、尻尾を上げた雀を多いと読んでいる様子も描かれています。これは、まるで動画の一部をストップしたような、リアルな動きや時間の流れを感じさせるものです。」
「実は応挙自身もまた、師の教えを学びつつ自らの独創性を追い求めた絵師でした。応挙は若き頃、江戸時代の最大流派である狩野派にその技を学びます。狩野派では、絵師自身の個性ではなく、先祖伝来の画風や筆遣いを忠実に学ぶことが求められました。しかし応挙は試行錯誤を繰り返し、写生を重視した独自の画風を確立します。
応挙が語った「絵はどのような姿勢で学ぶべきか」についての言葉が残されています。「師の手本を映さず、自分勝手に何でも描くことは正さなければならない。ただし、手本を映すだけの教え方はよろしくない。絵を学ぶ者は法を捨てるべきではない。ただ同時に、その法にとらわれすぎてはいけない。」つまり、応挙のスタイルや技術を学んだ上で、自分の個性を出すべきだという教えです。
このような考えを持つ応挙のもと、芦雪は自らの独自の画風を育むことができました。そのため、芦雪が和歌山のお寺に派遣されたのも納得がいくのです。ちょうどその応挙が自分の狩野派の肩を破って新しいスタイルを書き始めた時期が三十代の初めで、露雪が和歌山に行ったのは三十三歳ですので、ちょうど同じぐらいの時期なんですねですので、今日も露雪を見ていて、何かここでバンと雷が落ちるようなインパクトがあれば変わるんじゃないかみたいな それで中山に行ってこいって言ったんじゃないかなと、ちょっと想像したくなるそう、いい先生ですね丸山は今日、私が自分の、なんかね、あの自分の絵を確立するために、その今はその時期だということを見極めて、それをすごい背中押してあげたっていう、そういう物語ができるわけですよ。」
独自の画風を模索する芦雪に、若き日の自分の姿を重ねた応挙。師の期待に応え、芦雪は和歌山の地でその才能を見事に開花させます。描いたのは我が子を厳しく育てる獅子の子落としの物語。毛を逆立て、吠えるのは親獅子。傍らには親のもとに駆け寄る子供の獅子。芦雪が応挙から学んだもの。、れは絵師としての生き様。確かな資料がほとんどない中、芦雪の人柄を知る貴重な作品があります。水辺に立ち、空を見上げる庭の鶴。
「島根・松江藩主の弟で、俳人として知られる節斎から依頼され、芦雪が描いた絵ですが、鶴が一羽しか描かれていないということで送り返されたのだと思います。芦雪が最初に描いたのは、一羽の鶴だけでした。しかし、依頼主の節斎はこれにどうしても満足できませんでした。
オスの鶴が画面の外を向き、外にいるメスの鶴を呼んでいるという、非常におめでたい構図でした。絵の外まで物語が広がるような、そういう意図があったんですね。しかし、節斎から『もう一羽描きなさい』という注文がありました。
そこで、芦雪はメスの鶴を描き加えましたが、横に水が描かれているため、二羽の鶴がいると、メスが二羽いることになってしまいます。そこで、芦雪は液体を蒸発させるようにして、少し茶色い小型の鶴を描きました。
実は、鶴の子供は茶色いので、子供の鶴を描き加えることで、お母さんを呼んでいる絵に仕立て上げたのです。これは非常に機知に富んだ対応だったんですね。接戦に宛てた芦雪の手紙が残されています。
「呼び鶴というのは、絵には一羽しか描かれていませんが、メスを呼ぶ図なので、見えなくても二羽いるという絵なのです。しかし、ご依頼ということなので、書き加えました。毎回お世話になっております。お祈り、お送りいただき、加えて御礼申し上げます。」
非常に丁寧に書かれていますので、常識的な人だったのではないかと思います。非常に柔軟というか、「はいはい、わかりました」という感じですね。彼が本当はどう思っていたかはわかりませんが、手紙からは、きちんと対応している様子が伺えます。極めて一般的な対応であり、残されている手紙からは、現在言われているような変人のイメージは読み取れません。
和歌山で独自の画風を見出し、自信を得た芦雪は、ますます活躍の場を広げていきます。ほぼ等身大の「山姥」など、数々の障壁画を手がけた芦雪は、この頃から大迫力の人物画を描くようになります。
文豪・夏目漱石の小説『草枕』には、こんな一節があります。
「画家として、世に頭の中に存在する婆さんの顔は、高さ五尺余の芦雪の描いた山姥のみである。芦雪の図を見たとき、理想の婆さんは、ものすごいものだと感じた。」
岩山に遊ぶ猿の群れ。筆と墨だけで、多彩な表情を描き出す芦雪の技がさえ渡ります。独創性に磨きをかける芦雪。しかし、その頃、同じ京都には圧倒的な技巧で人気を博す二人の巨匠がいました。
一人は伊藤若冲。超絶技巧から生み出される色彩と描写で、現実を超えた命の姿を描き出す天才絵師。そしてもう一人の天才、曽我蕭白。絵の隅々にまで貫かれた強烈な個性。その画風は賛否両論を呼びながらも、斬新なものを好む人々を虜にしました。
芦雪が絵師を志した頃、二人はすでにその独自の世界観で画壇を席巻していました。そうした中で、芦雪は先人たちとは異なる「奇想」を目指したのです。それは一体どのようなものだったのでしょうか。
「これは虎ですよね。虎です。『うずくまる虎』という作品になります。」
「これは一見すると、こういうことを言うと怒られるかもしれませんけど、上手なのか下手なのか、ちょっとよくわからないですね。」
「芦雪はですね、同時代の画家たちの中でもユニークで、ユーモアがあります。この作品はまさにそれを表している一つの作品だと思います。『赤髪』といって、宴会などの場で即興で描く絵のことです。しかし芦雪の赤髪には変わった趣向がありました。輪郭線がないんですよね。最初に顔を描くと、次に体を描く時、毛並みをシャシャシャッと一筆で勢いよく描いていきます。」
「筆の勢いに任せて描くその線は、頭の中で構図を考えた上で、顔を描いて、それが徐々に大きな虎に見えてくるんです。この虎がうずくまるポーズをとっているのも、どこか猫っぽくて可愛らしいんですよね。これも一種のエンターテイナー的な描き方だと思います。」
「江戸時代のエンターテイナーを代表する一人ですね。芦雪の生きた時代の人たちは、見慣れた絵とは違う、新鮮な空気を感じ取らせるような斬新な構図や描き方に驚かされたでしょう。漫画的な要素も感じられますが、即興で披露されたものだと考えられます。」
「こちらの作品、何が描かれているでしょうか?」
「**植物ですね。**茎が描かれていますが、露雪の作品はどこか驚きを含んでいます。近づいて見てみると、黒い点々があるのが見えますか? 蟻の行列です。」
「一見しただけではわからないですよね。近づいてようやく気づく蟻の存在は、まさに見る人を驚かせる意図が感じられます。」
「掛け軸は床の間に飾り、遠くから鑑賞するものですが、近づいて初めて得られる発見と驚きが、芦雪の新しい鑑賞体験を作り出していたんです。やっていないことをやろう、という意識があったんですね。」
「彼は、前の世代の画家たちがやっていたことに対して、自分が生きている今の時代に新しさを持ち込みました。それが芦雪の得意技であり、他の画家と違うところだったのかもしれませんね。」
「破天荒な人だからこそ、破天荒な作品を描けたという印象でしたが、話を聞いていると、彼は非常にインテリジェントで、周囲の動向にも敏感に反応しながら、新しいことに挑戦し、人々を楽しませたいという意欲が強かったんだなと感じました。」
四十六歳で突如この世を去った長沢澤芦雪。恨みを買って毒殺された。またその傲慢さゆえに絵の仕事がなくなり、困窮の末、自ら命を絶ったとも言われています。