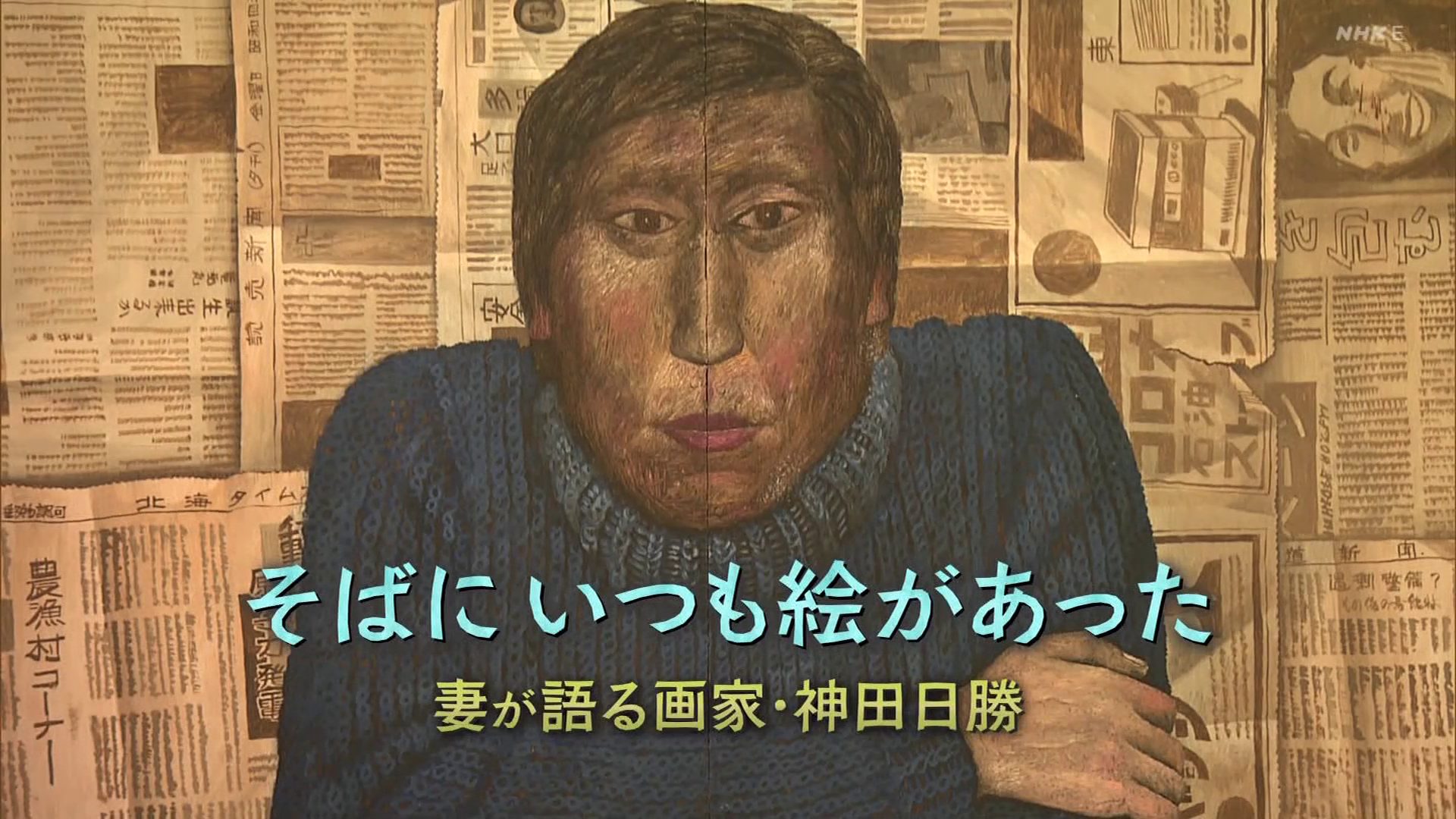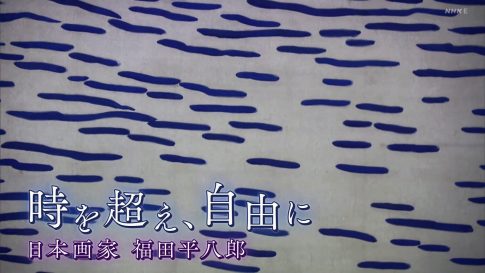17世紀スペインの宮廷画家として活躍した ベラスケス 。神話や宗教を描いた絵に価値がおかれた時代に主に肖像画を描き、革新をもたらした。その技法とは何なのかを探る。
ベラスケスは、後世の名だたる画家に影響を与えた。印象派の父と呼ばれるマネは、「画家の中の画家」と称え、前衛芸術の巨匠ピカソは、ベラスケスの名画「ラス・メニーナス」を基に58枚もの連作を描いた。何が後世の画家を魅了したのか?それこそがベラスケスの絵画が持つ革新性だった。東京の上野で開かれているプラド美術館展を司会が訪ねながら探る。ゲストは「ベラスケスが大好き」という漫画家の荒木飛呂彦さんほか。
【ゲスト】漫画家…荒木飛呂彦,早稲田大学名誉教授…大高保二郎,【司会】小野正嗣,高橋美鈴
放送 2018年4月15日
日曜美術館「静かな絵画革命~宮廷画家 ベラスケス の実験~」
「大好きで、真似したりしているのバレちゃったんですかね」
「今日は呼んでいただいて、またベラスケスにお会いできて誠に光栄でございます」
ー荒木さんの漫画の人物たちの肉体美。ある種筋肉の躍動する肉体を思い浮かべます。
「漫画って印刷されてどのくらいというものなんですが、雑誌の表紙ってのは肖像画。主人公をバンっと見せる。読者に訴えるってのがあるんです。ベラスケスはまさにそんな感じで描いている」
「多分今の雑誌の表紙でもかっこいい。動いて見なければダメなんです。視点を移動させて見ないと。そういう目的で描かれていると僕は思う」
人々をひきつけてやまないベラスケスの絵画。
それは革新的な技法によって生み出されたものでした。
描かれているのは、当時王宮にいた障害がある背の低い少年です。
王族の子どもたちの遊び相手を勤めていました。
間近で見ると荒く大胆な筆の跡が伺えます。
プラド美術館の学芸員で、ベラスケス研究の第一人者、ハビエル・ポルトゥスさんです。
この新井筆使いがベラスケスの革新性の一つだといいます。
「近づいて手の部分を見てみると指が緻密には描かれていないことがわかります。」
「シミの集まりのようになっていますが、ちょっと離れたところから見てみると、そのシミが肉体のボリュームや質感を生み出しているのです」
荒い筆使いは立体感をどう出すかというベラスケスの実験だったのです。
さらにこの肖像画では背景の描き方で斬新な試みをしています。
人物の足元には影。
ところが床と壁の境目はなく、まるで抽象的な空間に立っているかのようです。
微妙な濃淡を持つ背景が、人物の強い存在感を生み出しています。
この絵に衝撃を受けたのは19世紀のフランスの画家で、印象派の父と呼ばれるマネです。
若き日のマネはフランスの画壇に限界を感じ、新たな表現を模索していました。
ヒントをもとめて訪れたスペインで出会ったのがこの絵でした。
私は彼の中に自分の理想の実現を見出した。
背景は消え去っている。
黒い服が全身を包む。
生き生きとしたこの男の肖像うを取り巻いているのは空気なのだ。
マネは絵を見た翌年、さっそくその手法を取り入れます。
マネの代表作。「笛を吹く少年」です。
ベラスケスはマネより200年も早く、肖像を際立たせる手法を試みていたのです。
「ベラスケスは人が物を見る時の視覚の習性について自問し、絵画の枠の外でその法則をいつも探求していました。だからこそベラスケスは先進的で近代的な画家になれたのです」
さらにベラスケスはかいがそのものの成り立ちを考えるような実験的な取り組みをしています。
ベラスケスの最高傑作と言われる「ラス・メニーナス」です。
描かれているのは王女マルガリータとその従者たち。
傍らには描き手であるベラスケス自身の姿。
そいて鏡の中に映るのは国王と王妃。
ふたりは画面の手前で王女たちを見つめるという構図です。
描き手と描かれる人、そしてそれを見る人。その三者を一枚の絵の中に描きこむことは絵画史上例のない試みでした。
そこに激しく触発されたのがスペインの前衛芸術家・ピカソです。
76歳になって、この絵をモチーフとした58枚の連作に挑みました。
描くとはなにか。画家とはなにか。
絵の本質に迫ることこそが晩年のピカソの大きな関心でした。
その時ヒントを求めたのがラス・メニーナスでした。
ピカソが描いたベラスケスの姿は、原作よりもかなり巨大にデフォルメされています。
西洋美術史の専門家、沼尻真理子さんはピカソがラス・メニーナスにこだわった理由をこう考えています。
「ベラスケスはいったいどういうつもりで描いていたのか。ベラスケスは画家をどういうものとして捉えており、描くとはどういうものかと考えていたのかを、この絵を研究することによって、少しでも知り得るかなと思ったのかもしれません。ベラスケスの絵は描くことにまつわる画家、描かれたもの、そして鑑賞者を全部書き込んでしまっている絵ですから、その中でも描いている画家を大きく描いたということは、ベラスケスと自分を一体化させ、画家というものを、描くという行為に対して非常に関心を持っていた。ということだと思います。」
スペイン南部の港町・セビリア。1599年。
ベラスケスは貿易で賑わうこの街に生まれます。
12歳で工房に入り、絵の修業をはじめました。
20歳で描いたこの作品は肖像画かベラスケスの原点を伺わせるものです。
イエスの誕生を東方の三博士が祝う新約聖書の一場面。
ベラスケスは身近な人々をモデルに肖像の群像として描きました。
横顔の老人はベラスケスの絵の師匠パチェーコ。
聖母マリアは師匠の娘であり、ベラスケスの妻ファナ。
イエスは生まれたばかりの娘フランシスカ。
跪き誕生を祝う三博士の一人には自分自身。
こうすることで描く人物の存在感や個性が増しています。
同じ頃のこの作品からはベラスケスの観察力の高さが伺えます。
よく冷えた水瓶にわずかに滴る水滴。
グラスに反射する光もリアルに描いています。
王国の都マドリード。
24歳の時ベラスケスは宮廷の画家になるため、自分の作品を王宮に売り込みます。
そこで運命的な出会いがありました。
国王フェリペ四世。
即位したばかりの王は政治の改革に意欲をたぎらせていました。
この王に認められ、ベラスケスは宮廷に召し抱えられます。
宮廷に仕えたばかりのベラスケスが描いたフェリペ四世の肖像です。
王が目指す質素倹約な政治を象徴するように、飾り気のない黒い衣装で描かれています。
左手のサーベルは国王が軍事の担い手であることを、右手に持つ勅令の紙は行政の責任者であることも示し改革を進める統治者であることを示しています。
この絵をX線で調査すると仕上がりとは異なる図案が現れました。
ベラスケスが王にふさわしい肖像を求めたことが見て取れます。
やや下膨れの顔は
スッキリとした細面に。
開いていた足は、控えめに閉じられ品位ある国王が演出されています。
それはフェリペ四世が目にしてきたほかの宮廷画家とは違った表現でした。
「ベラスケスが描いた簡素な構成と色彩を持つ肖像画。フェリペ四世はその中に自分が目指す新しく、質素な責任ある政治に通じる表現を見出したのです」
革新的な国王のもとでこそベラスケスは絵画で実験的な挑戦を続けることができたのです。
フェリペ四世はベラスケスの斬新な画風を気に入り、自分の肖像はベラスケスにしか描かせないとまで言ったといいます。
宮廷画家になって十数年。
ベラスケスはまた新たな挑戦をします。
国王が娯楽やまた、外交使節をもてなすために建設した壮大な離宮・ブェン・レティーロ宮。そこを飾るにふさわしい重要な絵画の制作を命じられたのです。
画面から飛び出すような躍動感。
次の時代を担う待望の王位継承者・カルロスの騎馬像です。
両足立ちの馬を斜め前から捉えた斬新な構図。
騎馬像は横から描くのが常識でしたが、あえて難しい構図に挑戦しました。
そしてこの絵にはあるメッセージが込められていました。
騎馬像の後方には実在するマドリード郊外の山々が描かれています。
新しい国王の時代になっても国が繁栄し、長く続いてほしい。
そんなフェリべ四世の願いを組んで描かれた作品だったのです。
宮廷画家として実験的な作品を作り続けたベラスケス。
その影にはあるライバルの存在がありました。
当時ヨーロッパ各国の王族たちの求めに応じ絵画を制作していたルーベンスです。
フェリべ四世にも招かれたルーベンスは一年間王宮に滞在し二十才下のベラスケスと交流を持ちます。
その間、ルーベンスは国王が集めた貴重な絵画を模写することがありました。
その時、ルーベンスの力量を見たベラスケスは対抗心を抱くようになります。
ルーベンスが得意としたのは神話を題材とした「神話画」です。
これは軍神・マルスが愛の女神ヴィーナスと逢瀬を重ねる場面。
黒光りする甲冑に身を包み男らしいマルス。
足元のキューピッドは愛の象徴として描かれます。