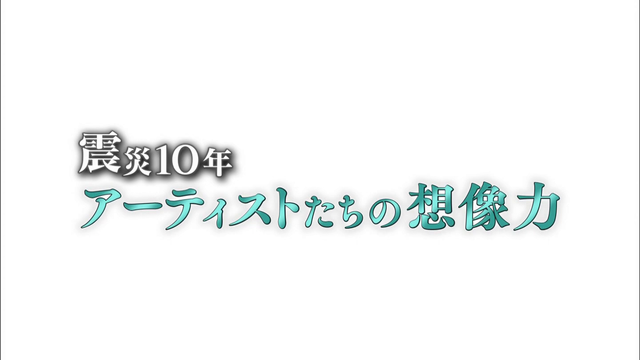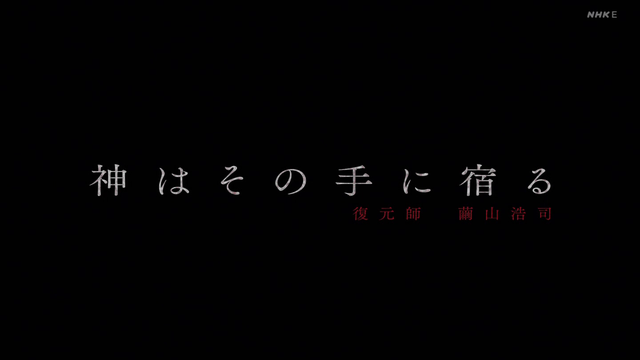水戸芸術館で開催中の「3.11とアーティスト:10年目の想像」展。東北でのボランティアをきっかけに創作を始めた、小森はるかさんと瀬尾夏美さんのユニット、福島の帰宅困難地域との「境界線」を描き続ける加茂 昂さん…展覧会は、 震災 が露わにした問題の1つが「想像力の欠如」だと考え、見る人の想像力を喚起しようとする。さらに作家たちの目はコロナ禍の「今」にも向かう。柳澤紀子さん、鴻池朋子さんのメッセージとは?
放送:2021年3月7日
日曜美術館 「震災10年 アーティストたちの想像力」
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年。
今アーティストたちは何を表現しようとしているのでしょうか。
被災地の美術館で開催されている展覧会。
震災直後から芸術の役割を問い直してきた若い作家たちが作品を通して答えようとしています。
そしてキャリアを積み上げてきた作家たちも新たな作品を発表し、表現を深めています。
アーティストたちが語りかけてくるものとは。
日曜美術館です。
今日は茨城県にある水戸芸術館に来ています。
水戸芸術館も10年前の東日本大震災で被災をし、それ以来毎年のように震災をテーマにした発信をしてきているんですね。
今開かれている展覧会「3.11とアーティスト、10年目の想像」という展覧会が今まさに行われているんです。
今日は主任学芸員の竹久侑さんにお越しいただいています。
今回の展覧会の10年を迎えたところでの展覧会はどういう意図で。
「今回の展覧会の前段に2012年に3.11とアーティスト進行形の記録っていう展覧会を行ったんですけど、それは震災の翌年の開催ですので、取り上げた活動というのが震災直後から1年間にわたって慣れてきたアーティストの活動だったんですね。ですので表現というものよりも記録する事とか、被災された方等に向けたワークショップとか、そういうものが非常に多かったんですけど、だんだん月日が経つにつれて、アーティストたちも作品を作る表現をするっていうことが始まってきていますので、今回は10年という節目にあたってアーティストの表現を紹介したいと思いました」
じゃあ早速中を見て行こうと思います。
この部屋は最初の展示室ということになります。
「小森はるかさんと瀬尾夏美さんというアーティストユニットです。小森さんは映像作家です。瀬尾さんは画家でもあり作家でもある方です。ここで展示をしているのは瀬尾さんが震災直後からずっとsnsで発信し続けてきた震災にまつわる言葉。具体的には陸前高田の変わりゆく風景ですとか、町の人々に聞いて彼女が書き残したこと、また彼女が感じた事っていうことが綴られて言ってるんですけども、目の前にあるのは瀬尾さんのスケッチです。
彼女その場にいて記録するような感じで街の風景をスケッチすることもあるので、そのスケッチ画の所々挿入されているのと同じように、小森さんの陸前高田の変わっていく様子を記録した映像も挿絵のように挿入されている」
被災地で10年の間なにを見て何を考えて来たかということについて話を買ってきました。
震災が発生した小森さんと瀬尾さんは大学生。
3月生ボランティアをするため東北の沿岸部に向かいました。
この時の滞在は3週間。
その後、何度も訪問を重ねました。
この映像は小森さんが印象に残る光景を切り取ったものです。
一方、瀬尾さんは現地での体験を言葉で記録しました。
こんなことが本当に起こるなんて誰も考えられない。想像もつかない。だから見に行ってください。地元の方にそんな風に言われることが何度もありました。
翌年二人は岩手県陸前高田市に移住します。
この街で起きていることに向き合いたい。
ふたりは町の人の声に耳を傾けました。
ある日小森さんと瀬尾さんは街に突然現れた光景に目を奪われます。
小森さんが撮影した花畑。
それは町の人たちが亡くなった全ての人。
そして失われた町そのものを弔うためのものでした。
自分の中に大きな影響を与えるようなこと体験っていうのはあったのですか。
「もちろん、未曾有の災害みたいな大きな物語は、それまでの生活に出会ったことのない想像力を超える出来事ではあったんですけど、ここの街全体を弔いたいって言って巨大な花畑は作ってしまうとか、何かそういう人たちの姿とか、そういう人たちがロジカルにやっている。全体を弔うのだから土を触るための作業が欲しいそして花を植えようとか、なんかすごく淡々とそれを組み立てて言ってる人達がいて、そういうふうに考えてたんだとか、そういう風に悲しみを共に生きてく形を考えてるんだとか思ったりすると、
自分だけの想像力みたいな事に頼らなくてもいいっていうか、もっともっと豊かなものがあるから聞いて、共有し合いながらやって行けばいいんだなって思った時になんかすごい自由になれるって言うか」
撮影した小森さんは花畑の向こうに亡くなった人たちの存在を感じようとしていました。
「私には見えないけど、その人たちにはある存在というか、亡くなった人たちの存在だったりとかにあるっていうものが見えて行った時に、それをなんとか記録できないものかっていうふうに思うようになっていったんだと思います」
2014年になると復興工事が進み始めます。
山を削りその土を街の上に十数メートルの高さまで積み上げることで新しい街を作るのです。
あの花畑も土の下に埋もれました。
町の人たちにとって新しい生活を獲得することは2度目の喪失を体験することでもありました。
花畑のエピソードに着想を得た瀬尾さんは震災後、一枚の絵を描きます。
《二重のまち》
復興後の陸前高田市の姿です。
新しい町の地下にかつての街があって、小さな階段で繋がっています。
瀬尾さんはこの発想をさらに広げます。
絵と文章による作品。
2031年。
未来の陸前高田市に住む父親と息子の物語です。
息子は20年前に震災があったことは知りません。
2031年春。
僕の暮らしている街の下にはお父さんとお母さんが育った町がある。
ある日お父さんが教えてくれた。
下の町の人はどうしているのと尋ねると、お父さんは僕を町の真ん中の広場まで連れて行った。
お父さんと一緒に階段を降りる。
広い広い一面の花畑がそこにある。
色とりどりの花。
様々な季節がここに1度にある。
お父さんにおいでと手を引かれて歩く。
広い広い花畑の中にいくつもの道筋がある。
ふとお父さんは立ち止まって、ここがお父さんの育った家だよと言った。
「私自身が最初に思ったのはかつての街あとを壊していって、新しい区土が盛られてこの上の生活が全然想像できないのに喪失だけがその時あったので未来にはつながっているんだっていうことを想像するための杖みたいな物語が欲しいなって、そう思ったのも街の人にとって町あとの喪失、記憶の拠り所の喪失ですよね。気を喪失するってみんなが見ていたものをなくしていくっていう感覚」
心の風景とか言うから自分にとって大切な懐かしい風景って心の中に助けられないに行こう着いたの思い出しですけども松さんはその風景の中に人の心があるんじゃないかってその風景の中にはそこに暮らしてきた今はいないかもしれないわ今を生きてこれから生きてくるであろう人達の心っていうのはその中に含まれている。風景そのものが消されてしまったらそれは彼にとってとてつもない大きな損失である。
現在の陸前高田市。
小森さんと瀬尾さんは今もこの街を見つめ続けています。
福島県双葉郡に通い作品制作を続けている方がいます。
加茂昂さん。
ここには東京電力福島第一原子力発電所があります。
「僕らができることはこのことから何を学ぶかって事考えないといけないと思って、意味のあったことにしないといけないって思いますね」
震災が起きたのは大学を卒業した翌年。
加茂さんは画家としての道を歩み始めたばかりでした。
震災前の作品です。
抽象的なモチーフを複数重ね合わせたインスタレーション。
自分は何者かと問いを発しながら作品を作っていたと言います。
「自分の世界と自分との関係がバグったなって思った。ファミコンとかの世代なんですけど、ファミコンをけ飛ばすとバグるって事もよく言ったんですけど、なんか自分と世界との関係が一瞬そこでバグってしまって、意思疎通が止まってしまった瞬間。それを回復するのに多分すごい時間かかったんじゃないかなと。想像力を超えた出来事だったですよね」
震災以降、加茂さんは何も描けなくなってしまいます。
今できることは何なのか。
加茂さんはボランティアとして宮城県石巻市へ向かいます。
そこで頼まれたのが商店街のシャッターに町の人たちと一緒に絵を描くことでした。
この体験が加茂さんの心を修復します。
「通りがかったおばあちゃんがちょっと絵を見てくれって、描いているところを。石巻が津波で色がなくなってしまったんだけど、このシャッターに色が戻ってきて、すごい嬉しいって言ってくれたんですね。それがすごい嬉しくて、それまでは何もできないんじゃないか、絵を描いていていいのかと思っていた。でも何かできるかもしれない。もしかしたらできるかもしれないって思った」
震災の5年後。
加茂さんがテーマにしたのは立ち入りが制限された区域との境界線でした。
「金網で覆われてる景色が印象的だなと思っていて。ここもあと何年かしたら中間貯蔵施設ってことになる。なくなるわけじゃなくてより目に見えなくなる。これがあるうちに景色を描いとこうかなと思って」
加茂さんの正面に立つ一枚の立て看板。
加茂さんの作品です。
山の向こうに沈みゆく夕日。
その光は山裾や野原。
そして雨上がりの道路を照らします。
昆虫などの生き物は草木の間を自由に行き来し、風も吹き抜けます。
しかし人間だけはこの看板一枚に遮られています。
「本当に田舎の細い道を走ってると、あぜ道のところにコーンと看板だけで、ここから先に入っちゃいけないよっていうサインがあるとこがあって、本当に人間だけ入っちゃいけないと思う。風景としてものすごくきれいだなと思うんですよね。で、これだけ綺麗な景色があって、元々は田んぼだったんですけど、人の営みがあって、けどそこに入っちゃいけなくてね、その矛盾みたいなものを表したくて」
*
宮城県仙台市の沿岸部。
荒浜地区を描き続けている作家がいます。
佐竹真紀子さんです。
2017年に完成した作品。
一面に塗られた鮮やかな青が印象的です。
絵の中心にはあの日の津波が描かれています。
この作品で佐竹さんは荒浜という地域を古い歴史とともに表現しています。
画面左に描かれているのは、震災が起こる以前の活気あふれる街の姿です。
場面はさらに遠い過去へと遡ります。
江戸時代、住民たちが総出で地引き網を引っ張っています。
古い街の記憶を描くこと。
その発想は住民たちとの交流から生まれました。
2015年。
佐竹さんは被災地の実情を知りたいと荒浜に通っていました。
この時、生活に欠かせない路線バスが当分の間開通しないことを知ります。
佐竹さんはもともとバス停があった場所に偽バス停という作品を作って設置しました。
住民たちはこの作品を歓迎しました。
偽バス停を基点にありし日の荒浜が蘇ったからです。
佐竹さんと住民の交流が始まります。
古い映像を通して村の歴史を知るという地域のイベントに参加したときのことでした。
「その土地がもともといつから始まったんだよってことを伝える時に写真より前の、時間を残している絵っていうものと立ち会って、その絵を土地の人たちがハーっと驚きながら、何から書き込んでいる瞬間にあった時に、これはすごいことだなって思ったんですよね。なんかすごい時間の長さを超えて誰かに伝えるとか、誰かの想像の手がかりになるっていう事が起きるなってすごく強く思わされた瞬間がありました」
荒浜という土地を過去から辿る佐竹さん。
最後は現在の風景で締めくくりました。
震災が起きた3月11日。
毎年この日には海岸から一斉に風船を飛ばすイベントが行われています。
風船は様々な色で塗り重ねた絵の具の層を削って表現しています。
風船には豊かだった過去の楽しい記憶が詰まっています。
今私たちは瀬尾さんの境の前にいます。
作品を拝見していると、その場所に行ってとどまって暮らしてる人たちと、その言葉に耳を傾けるってこと。すごく人間的な行為だと思うんです。作品とアートの芸術の作品になっていくってことには時間がかかるのかなって思います。
「そうですね当初は記録とか記述していくっていうところから始まっていくのが多くの作家で見られた出発点だったりしたんですけども、月日を追ってどのように街自体が変わって復興しようとして行こうとしているのかっていう。復興って言うとポジティブに聞こえますけどそれだけではないような気持ちっていうのを多分彼女たちは気付いていたと言うか、そこに耳を傾けていると思うんですよね。その記録だけじゃなくって自分たちはアーティストなので、どのように表現していくかっていう時に、事実を基にした物語を作っていくっていう時に想像の余地を見る人に与えてくれる活動に転換して言ったんだと思うんですよね」
震災の災厄を経験した場所に行って、若いアーティストたちも自らの想像力の変容を経験している。だから彼女ら彼らの想像力の変容していく。成長していく記録でもあるのかな。
「忘れられないのが、震災と原発に事故があった後に、想定外という言葉が繰り返し使われてましたよね。それがすごく私の中で残っていて、それが自分の身に起こる。自分に手繰り寄せて想像するということがすごく難しかったのだと思う。あれは私たち誰もが加茂さんも想像を超える出来事だって言ってましたけど、本当にそうだったと思うんですよね。でもふと、もともと芸術って、想像することと想像させることというのが、得意の仕事だったんじゃないかと。芸術にとって重要なひとつの仕事っていうのは、想像力をいかに喚起することだったんじゃないかと、そこを問い直すことが一つのポイントになっています」
震災はキャリアを積んだ作家たちの作風にも大きな影響を与えました。
60年にわたって版画などを発表し続けてきた柳澤紀子さん。
柳澤さんも10年前の震災で大きな衝撃を受けた一人です。
震災の日。
東京都内にいた柳沢さんは深夜になってようやく車で自宅へ向かいました。
「12時頃。夜中の12時頃。出まして車で自宅まで戻るとき、都内なんですけど、戻る途中にもうほんと光は全くなくて、しかもたくさんの人がもう黙々と歩いてる姿見て、その時に私が5歳だった時に第二次大戦がちょうど終わったその時の風景。焼夷弾を浴びて逃げた時にあの見たものすごい火の真っ赤にもどこもかしこも燃えたそういうその風景とオーバーラップして、何だろうこれはって思いましたね」
そして福島で発生した原発事故。
「被爆国でありながら、なんでねなんでこんなふうになっちゃったのかっていう失望って言うかね」
福島を何度も訪ねた後、柳沢さんはチェルノブイリへと向かいます。
ここで原発事故があったのは1986年。
福島の30年後を感じ取ろうとしたのです。
今も居住を禁止された町。
そこで心を打つものに出会いました。
植物や動物が旺盛な生命力で生きていたのです。
「もう住んでる人間なんて問題にならないぐらい動物達がもう生き生きと元気にまるまる太って、豚だでもみんな。それは圧倒されましたね。じゃあ放射線は全部なくなったのっていったらあるわけね。そういう不条理的なものも感じましたね」
その体験は作品にも変化をもたらしました。
初期を代表する作品の一つ。
円や直線で表された幾何学模様は生命の根源を探求する柳沢さんの抽象表現でした。
震災後の作品には動物の姿が多く現れるようになりました。
自らの過ちで住めなくなった土地。
それでもそこに生きる動物たち。
その揺るぎない生命力は人間の愚かさと対照的に見えます。
震災と原発事故から10年。
今世界では新型ウイルスが猛威を振るっています。
災厄が続く時代、柳沢さんは表現を模索しています。
「原発、被爆国でとても言葉で言えないぐらいな人災ですよね。今度のコロナもね、こんなに地球が丸くて、こんなに人がいるんだっていうのもみんな初めて知ったと思うぐらい、世界中マスクかけてるってのも非常にストレンジな感じもするけどだけど、それ事実であって、環境はもう待ってられないって言われてるぐらいひどくなってきてる。それをみんな気づいたっていうことはね望みかなっていう気もするし。自分も今後は制作出来る範囲でやってる時にその辺をねなんかこう色と形でどういう風に表現できるか」
柳沢さんの新作です。
素材は羊皮紙。
かつて記録の媒体として人間の文明を支えました。
生贄となった動物。
自らの命を失うことで他者に命を与えます。
そこには共生の希望が感じられます。
今年1月突如出現した不思議な物体。
コロナの時代に妖怪アマビエを描くというプロジェクトから生まれました。
縦10メートル、横24メートルの巨大な妖怪を作者は《武蔵野皮トンビ》と名付けました。
素材として使われているのは牛の皮です。
何枚も縫い合わせて作られています。
「僕が知っているアマビエの姿とは違いますが、アマビエの持っている超自然的な理解を超えたパワーを秘めてものに見えますよね」
作者はなぜこのような作品を作ったのか。
そこには震災の経験があるといいます。
これまで斬新な作品で人々を驚かせてきた鴻池朋子さん。
「この素材なんですよ」
作品をみると、パッチワークじゃないけど、形がみんなバラバラだ違うんだなと思ってたんですね。
鴻池さんは震災後、作品制作の素材を変えなめした皮を使うようになったのです。
鴻池さんの震災前の作品です。
人間の足を持つ狼。
生と死を連想させるどくろ。
日本画で人間存在の根源に迫ろうとしていました。
ところが震災後、鴻池さんは絵が描けなくなってしまいます。
自然の圧倒的な力の前に世界への疑問が生まれたのだと言います。
「個展会場の自分の作品を見たときに、なんか情熱がないと言うか、冷めていると言うか、なんか白々しいと言うか、こんなところにいる場合じゃないなという。でも具体的に何ができるわけでもない状況にあって」
それから4年。
試行錯誤を重ねた鴻池さんは震災後初めての展覧会を開きます。
巨大な作品は美術界に大きな衝撃を与えました。
この時、素材としていたのが何枚もの皮だったのです。
古くから人間が生きるために利用してきた皮。
「皮に描く感覚っていうのは、きれいに描くってよりも相手に傷つけるような快感がありますよね。しかも切って繋げたり、穴開けてどうこうしたりっていう作業を縫って向こう行ってまた戻ってくる。やっていると夢中になってやってて生きてる感じがする」
鴻池さんは描くという行為を根源から見つめ直しました。
人間が生きるために利用してきた動物たちを素材にすることで、人間が生きるとは何かを取り直したのです。
「大きなシステムが変わるっていうことは、動物の一匹の動物としては人間がいるんだったら、他の人たちとか他の種類もいるって事も考えざるを得ないと言うか、そこまでどうやってそのイメージってどこまでちゃんと考えていけるだろうかってのがひとつと。でもえーっと人間を食べて生きていくっていうことが同時にあるって言うことで、その両方をちゃんと考えざるを得なくなる時代に入ったかなと」
震災から10年。
そして新型ウイルスの感染に見舞われた今、災厄に立ち向かう鴻池さんのアマビエです。
微生物。蜂。狼。トンビ。
あらゆる生き物と共に飛び立とうとしています。
鴻池さんのあの作品は本当に大きくて近くで見るとすごい迫力なんですよ。だけど皮でできてるでしょ。風が吹いたりとかすると揺れたりしてそのまま遠くに飛んでいきそうな、強風の日には。そんな事も想像させるって言うかね
空に向かって飛んでいくような。
「人間の存在を見直すような大きな転換点が震災によってもたらされたんだなとすごく感じました」
作家の方達が言ってることと、柳澤さん、鴻池さんがいっていることと通底するものがあるじゃないかと思ってました。皆さんが口を揃えて言ってるのは人間の想像力の小ささですよね。矮小さ、無力さそれに災厄自然災害ということに出会って気が付く。
「目に見えないもの。それは心の情景だったりすることもあれば、残っている汚染されているけれども見えない物質であることもあると思うんですけど、その存在があることを知ったアーティスト達がそれをいかにイメージに移し変えようとしているかっていうことが作品に表れているんだなって風に思うんですよね。あるものをきっかけにそこにないものをアーティストたちがどのように言って思いをはせて、作品に作って行って見るわたしたちがそれをどう思っていくかっていうこと。創造の連鎖みたいなものがなんか生まれていくんじゃないかなって気がしています」
震災ってものが見えない。見えないものといえば、今僕たちコロナの中で生きて、コロナウイルスっていうものと共生してるか。そのことをどういう風に考えていくかっていうことですね。この震災以後の世界を生きていく上でどうやって私たち生きていくのかってこと考える上でやっぱりアーティストって素晴らしい仕事をしてるんだなって思いました。
改めてこの10年ってどんなことが起こったのかって見直してみると。
「上が地震で下がそれ以外の自然災害ことをまとめていて、実感としても思ったんですけど、すごく水害がこの10年で多かった」
この10年だけでもこれだけ多くの災害に私たちはあってきたんだ。それでも生きているって思ったりもしますよね。
「災害が明らかにしたのが私たちの想像力が貧弱だったということだと思うんですけど、でも瀬尾さんが言っていたように自分ひとりの力では太刀打ちできないんですけど、彼女が高田の方たちの花を作る様子を見てすごく喚起されたように、集合体として私たち人間がどのように記憶を紡いで行けるかっていうところなのかなという風に思いますね」
想像力って人間に固有の能力だという風に思いがちですけど、高田の人達が花を植える。土を掘って花を植えると鴻池さんが手を動かして。必ず身体を通して、一人だけじゃなくて複数の身体から体があってその中で活性化されて根付いて広がっていくもんなんじゃないかってことを感じました。
「いかにそんな作品を身体的に経験する追体験する。そういうことができればいい。見るって言うだけよりも歩く。一緒に歩いて行く。そういう感覚で自分の体に落とし込んでいくような、自分ごととして繋ぎ直すようなことになると」
震災とかがあると芸術の役割は何だとか芸術家の役割は何だって言うなことあるじゃんすか。でも問われてるのは僕たちの役割じゃないかと思うんですよ。芸術家たちは自分たちの持ってる限りの手段と想像力を使って応答しようとしている。それを僕達が複数の周りにいる人間がどう受け止めて自分ごとにするかって僕たちが問われている感じがします。
今日はどうもありがとうございましたございました。