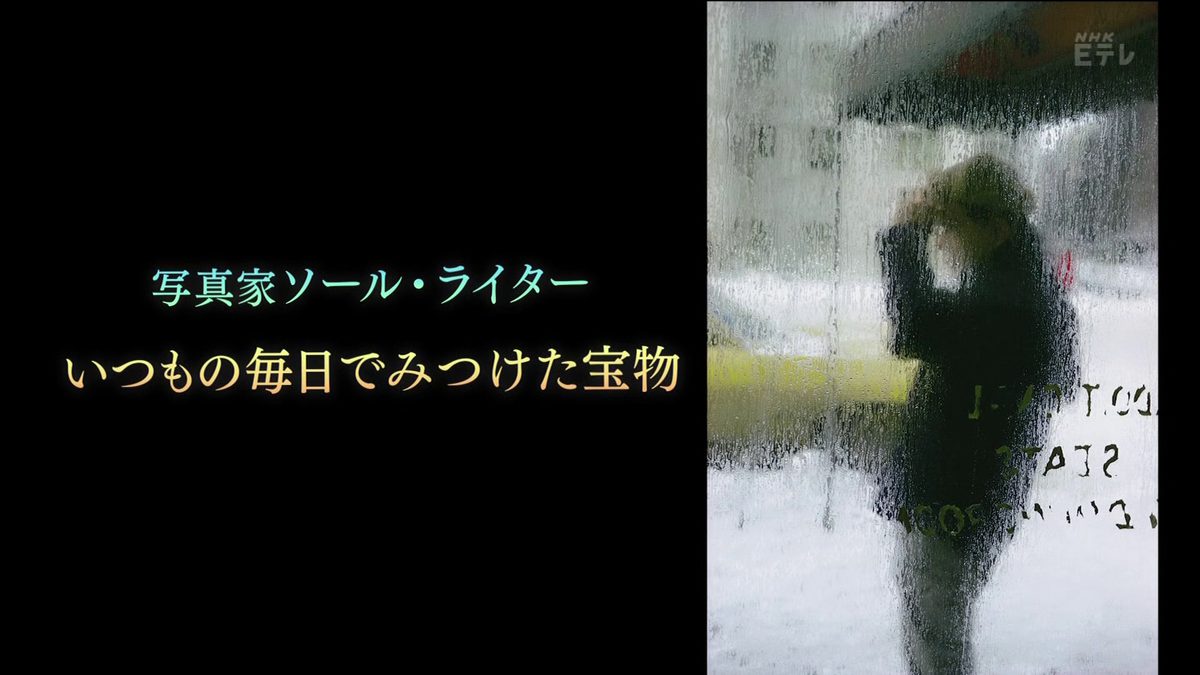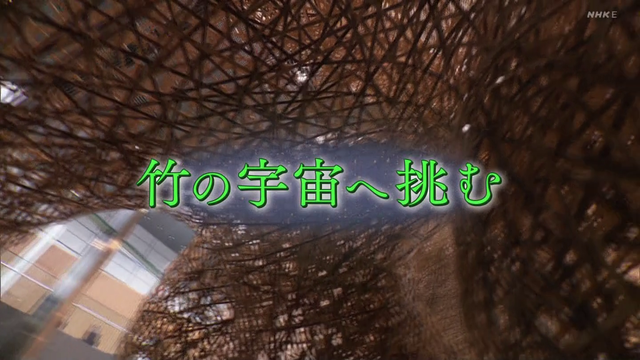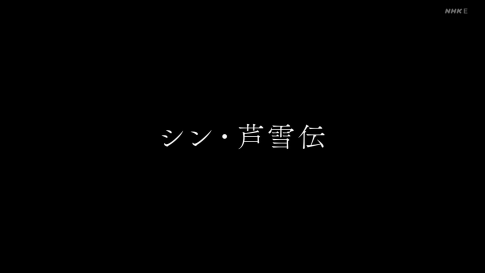東京国立博物館で異例の現代美術展が開かれている。日本を代表する美術家・内藤礼の個展。東博所蔵の縄文時代の土製品と作家との出会いから生まれた展覧会は、展示室全体をひとつの作品として体感するもの。空間に身を置き、そこここに配されたささやかなオブジェたちに気づくことで、感覚がときほぐされてゆく。窓からの自然光を受けて刻々印象を変える会場を、様々な時間に出演者たちが訪問。映像と言葉で内藤礼の世界へと誘う。
初回放送日:2024年8月25日
日曜美術館
東京国立博物館で、日本を代表する美術家、内藤礼の展覧会が開かれています。タイトルは「生まれておいで、生きておいで」です。ここ東京国立博物館で、現存作家の古典は極めて異例のことで、準備も前例のないものでした。展示室の窓を戦後おそらく初めて開けました。
内藤礼の作品は、個別の絵や彫刻ではなく、一つの空間として作り上げられます。観る者は空間に身を置き、まずその全体を感じます。やがて、そこここに置かれた小さく繊細なオブジェに気がつき、観る者の感覚が研ぎ澄まされていきます。
制作への思いを内藤は語ります。「なぜ作るのか」という問いに対して、それは「それこそ幸福。この世が幸福である場所だということも信じたいから」だと。そういう小さな瞬間が、ないのではなく、あるということを信じたいし、知りたいからです。そして、存在することそれ自体が祝福であれと願う内藤礼の世界です。
展覧会は東博の三つの会場をたどる構成になっています。内藤の作品から、どういう感情が生まれるのか、今日は何人かの方に展覧会を見ていただきます。
美術家・内藤礼 地上に生きる祝福
「こんにちは、よろしくお願いいたします 今日は内藤さんについてお付き合いがとっても 長い小池さんにいろんなことを伺いたいなと思うんです。」
「四十年ぐらいになるのかしらそんな長い時間とちょっと思えないんですけども、これまでの記事、記事をずっとご覧になってこられたので、いろいろ教えてくださいわかることはとても深い広い世界の内藤さんですから、できる限りお手伝いいたします。」
「では、最新の展示を見ていきたいと思います。展覧会は、内藤礼と東博の所蔵品の出会いから始まりました。その所蔵品が会場の最初に置かれています。安産や豊穣を願う縄文時代の出土品。女性の体を思わせるくびれのある形を、内藤は「母体」と呼びます。傍らに置かれた枝と石は、出土した貝塚の近くで内藤が見つけたものです。
「これを目にした内藤は、自らのある作品を思いました。それが「使者のための枕」です。息を引き取った人が安らげるようにという思いを込め、この二十七年間作り続けている作品です。母がもたらす新たな生命、死者たちからの呼びかけ—「生まれておいで、生きておいで」という展覧会のテーマが生まれました。」
展示室は、生きることも死にゆくことも含め、人生を祝うような空間です。暗さに目が慣れると、球体の鮮やかな色が見えてきます。生きる喜びを表しているようです。
「静かにたゆたう風船は、生まれたての魂と死にゆく魂でしょうか。見る人によって、どんな世界を見ているかは違うと思うんですけど、そのことも理解して、あまり造形として見せるのではなく、こちらから何かを引き出されるような、そういうことができるアーティストだと思います。そして、理解しようと思わなくてもいいんだなぁって。」
「ああ、綺麗っていう、それだけでも許してもらえるような気がしたんです。」
「そうですよね、現代美術って難解だなんてよく言われますけど、もっと見る人が自由になっていたら、いろんな見え方ができるんじゃないかしら。」
東博と現代美術、意外な組み合わせしかし内藤作品と博物館には響き合うものがあると言います。
「内藤さんの作品っていうのは、その根底にずっと通底するお考えとして、生きることと死が不可分である、分けられないものであるということのもとに作品を作ってらっしゃると思うんですけれども。」
「その辺りというのは博物館と通ずるところがある。つまり、歴史というのは私たちとすごく離れたことではなくて、いろんな人がある種亡くなって、生まれて亡くなって、その繰り返しが歴史だっていうふうに思うんですけれど、この博物館というところは、そういった亡くなった人たちが作った、その時代に生きた人の証しが詰まったところであって、その辺が内藤さんの作品と非常に通ずるところがあって、一つ一つのものが今生きている自分にもつながるものであるということがあると思うんですね。」
二番目の会場は東博を象徴するとも言える展示室です。天井の高い光に満ちた部屋で、普段は全く違う暗く静かな展示室です。内藤は何十年も閉ざされてきた窓を開けることを提案しました。絨毯や仮設の壁をはがすと、タイルの床と大理石の壁が出現し、建築当初の空間がよみがえりました。
無数のガラスビーズが母系と名付けられています。この空間全体が内藤の作品世界で、両側の壁には絵画が並びます。一見何も描かれていないような画面で、描いた日付の順に二十八枚が展示されています。
どう向き合えばいいのか、内藤の絵画を高く評価するキュレーターのミジャエル・ヘディングさんに言葉を寄せてもらいました。
「内藤礼の絵画と初めて出会った人はきっと驚くでしょう。絵画を見るとき、人は何かを認識しようとするものです。ここにあるのは純粋な色彩の広がりだけです。何のモチーフも、どんな単純な形も描かれていないのです。この絵を見つめるのは、自分自身を見つめるのと同じようなことです。作品との対話が生まれ、見る人の中に絵が現れてきます。」
内藤自身はこう語ります。
一度も書いたことなかった 花や木や風景はでも、風景描きたいという気持ちを抑えられないんだなだって探し出すんだもんちょっとした形や色の組み合わせから描こうとしなくてもだからなんか自分に許したんですよ、ある時そこからはもう特定の風景ではなくて、地上の生の好奇を書くということが始まって、人間の意図の通りにできたことを喜ぶよりも、自分の中の無意識に気づいていく方が、私としては生の実感が強い
「武蔵野美大で、内藤さんが卒業制作をした時に、内藤さんの先生が私に電話をくださって、「ちょっと面白いものが生まれているから、見たらどうですか」と言われました。「あなたも好きだと思う」ともおっしゃってくださったので、飛んで行ったんです。卒業制作を見たら、本当に誰も作ったことのない、透明な世界がそこにあったので、それ以来のお付き合いなんですよね。」
1991年、小池さん企画の展覧会で発表した事情に、一つの場所を設けました。鑑賞者はテントの中に一人で入り、十分間身を置きます。女性の体を思わせる繊細なオブジェ、緻密に配された光。一人の鑑賞が終わるごとに、内藤自身が中に入り、作品を整えました。
「テントの中に入るということは、母の体内に入るというようなことでもあるのね。それはとてもラジカルなことですよね。千九百八十年代、九十年代の頃って、そういうことで言ったら、女性の体内を見るみたいなことで言ったらとっても過激なんだけど、でもそういうふうに見る人もいるし、とにかく作品に対峙して、きちんとその空間でアーティストのメッセージを受けるっていうようなこと。それはもう一人十五分以内ぐらいで、でも一時間に四人しか入れないような展覧会で、願い津さんもその一人が入った後、その度に綺麗にまた整えて、そんなようなことをしてたんですよね。」
瀬戸内海の直島。内藤の転換点となった作品があります。住み手のいなくなった家の内部を作品に、足元のスリットから光が差し込みます。訪れる人は一人ずつ十五分間、空間に身を置きます。自然の光や外からの音など、コントロールできない環境を受け入れた初めての作品。常設の展示も初めてのことでした。
「今まで展覧会が終わると、片付けて聞いていくということを十何年かずっと続けてきましたが、ここは初めて半永久的に、自分がこの直島にいてもいなくても、この空間の中に自分がいてもいなくても、こういうふうに毎日を迎えて、一日の光の変化をそのまま受けて、ここにあって形を持っている場所が存在しているというのは初めてです。」
「ご自分の中で確かさのようなものが持てているというのはありますね。それは不思議な感じがします。今までは見て、そこに自分がいて見ている時にしかなかったのです。不要な床などを全部外して、外から来る光と建物の空間の裏のようなものを見せてくれた時に、すでにある空間や物、建物をここまで可視化するその力を感じましたね。だから、それは彼女にとっても重要なポイントだったかもしれません。」
大きく空いた天井から雨や雪が降ることも、虫や動物が入ってくることもあります。午後一時、光が強くなりました。
「いや、見えない。こっち側に来ないと見えない。長く身を置くことで、いろいろなものが見えてきます。こうすると溶け込むのか、ああ不思議。鉢むきに立たないと、はっきり見えない。」
手島美術館を共に作り上げた建築家に話を聞きました。
「手島の方が見に来て、「なんちゃないっていう、何もないじゃないか」と言いました。それで内藤さんはすごい、確かに禁止してた。全然何もないことはないですからね。でも確かに、入ると何もない。あの驚きっていうか、何もないんだけど、もうなんとないいろいろなものがあるわけですね。」
「あの透明感っていうのはすごいな。アーティストが立派な彫刻を作っておいて、それも素晴らしいんだろうとは思うんですけど、そうするとやっぱり完全に分立する建築とアートなんで、経験と美術が。でも内藤さんの場合はそうじゃなくて、完全に一体なんですよね。だから手島が「それ、なんじゃない?」っていうのもよくわかるなっていうか、そういう種類の透明感は内藤さんの作品というか、建築というか、アートにはあるんですよね。」
夕方の光が差し込むと新たな景色が生まれました。東博の会場にも、ささやかなオブジェが。
「それによって、本当に違う景色を見せてもらって、多くのものがあるわけじゃないのに、こんなに別世界になるんだなぁと。光と影と青空と、外に見える緑と風と音、自然の要素だけで、こんなにフルオーケストラのように違う曲になるというか、とても贅沢な時間でしたね。こんなに毎日、私たちは祝福されて生きているんだなぁと思います。ふんだんに太陽の光を送ってくれて、風を通してくれて、虫は泣いていて、こんなに私たちは日々もらっているのに気づかないんだなぁと思いました。そこここに置かれています。亡くなった我が子を忍んで取った足型だとされる土葬品。内藤が選んだ縄文時代の出土品です。当時の人々が食べたイドシシの骨。同じ場所から出土した鹿の骨。内藤は動物の骨にもかつて生きていた者たちの姿を見出しました。つぶらな瞳のイノシシ儀礼のために作られたと考えられて、いま す、これまでほとんど展示の機会がなかったものです。」
「縄文時代の造形というと、火炎型土器や遮光器土偶が有名ですが、実はそれらは時代を代表する造形であり、縄文時代の地域や特色を特徴づけるものです。しかし、実際には縄文時代の一人一人の個性を象徴するようなものではないんですね。」
内藤さんが今回の展覧会の準備をする中で少しお話をさせていただいた際、「作為のない」という言葉が伝わってきました。ものによっては非常に簡素な造形のものもあるのですが、内藤さん的には、それが縄文造形の本質、もしくは自分の作品とつながる部分として捉えられたのかなと感じています。
「生まれておいで、生きておいでという声が、足型に込められています。二歳から三歳で亡くなった子供や、イノシシの骨、鹿の骨。彼らも私より先に生まれて生きて、生を終えた存在です。これらは私にとって生の先輩であり、その小さな子供や動物たち、あるいはその土産品としてそれを作った人たち、見ていた人たち、すべてが私より先に生まれて生き、そして生を終えた人たちです。そのすべての生きた彼らから、声が聞こえるんだなというふうに思うようになったんですね。」
窓を開け、光を受ける会場は時間によって見え方が変わります。午後二時に訪れた西澤竜恵さん。内藤と手島美術館を作り上げた建築家です。
「結構、内藤さんの展覧会が来ると、いつも内藤さんの美術作品を見るというよりは、内藤さんの建築を見ている気になってしまいます。すごい空間的な感覚を持つ方だなと感じます。」
「空間に達する感覚の鋭さや正確さが非常に際立っていますね。なんかかつて建築の技術というのは一体だったんだろうなと思う瞬間があります。内藤さんのような存在を見ると、そういうことを感じます。」
「かつて建築家という技術者は一つの存在だったし、建築と美術は一体だったんだなということを、内藤さんのような存在が証明しているような気がします。」
午後四時、西から光が差し込み空間を包みます。三本松智代さんは過去に二度内藤の展覧会を手掛けています今回は博物館の通常の展示と大きく異なる点があるといいます。太陽の光で影を作る足型三本松さんはここに内藤の思いを読み取りました。
「子どもの足型を特別個室で、初めて特別な腰ではなく、自然光で見ました。普通、博物館では自然環境で自然光をあまり使わないのですが、試みとして、縄文の人と同じ環境、同じ光の下でそれを見たいという作家の意向がありました。その陰影がすごくリアルでした。」
「大人のお墓から出てくるということは、自分の子どもか何かの型を取って、穴が空いていて紐をつけて、きっと大事に飾っていたか携えていたものを、その人が亡くなって一緒にお墓に入れてもらっていたというストーリーが、非常に実感として伝わってきました。二十三歳ぐらいのお子さんの足ぐらいの大きさだと思うのですが、足がここに踏みつけられたという跡が、その光景を浮かび上がらせ、その人間とその子どもの様子も想像させる足型でした。」
「ものすごく精を感じたのですが、それはきっと自然光で見たからこそ、より一層感じられたのかもしれません。」
「内藤作品の魅力はどんなことでしょうか。多分「好き」とか「わび」とか、そういうものも何でもないように見えますが、実はものすごい粋を込めて見出した美だったり、造形化したものだったりすると思います。文化はやっぱり簡単には出てこないもので、誰かそういうアーティストが心身を削って考えを深め、形にしたものだと思います。そういう意味では、彼女は本当に我々の代わりに世界の中から美しいものを取り出して見せてくれているアーティストであり、その作品の魅力がそこにあるのではないかと思います。」
午後六時、会場にやってきたのは写真家の畠山直也さん。三十年以上、内藤の作品を撮影してきました畠山さんに内藤作品との向き合い方を尋ねました。
「彼女の作品にはいつもきっかけみたいなものがあります。つまり、何もないのではなくて、何かがある。それが見えないとしたら、まあ見えない人には見えないかもしれないけど、きっかけみたいなものが必ずどこのどのパートにもある。種みたいなもので、そこから何かを芽吹くわけですよ。芽吹いて成長するためには時間が必要ですよね。だから、きっかけで、つまりなるほどって思って会場で出るだけでは何もならないって言いますかね。
いつもその目のようなもの、種のようなものが無数にあるわけですから、それが伸びるのを見ないといけないでしょ。それが時間がかかるということですね。成長するのは何が成長するかというと、あなたの中で作品が大きくなるということですから、そのためには時間がいるってことです。」
日付が変わり、午前十時、朝の光の中、次の訪問者がやってきました。若松英介さん。じっと座って見つめていました。
「同じ光は二度ない。だから、私たちが生きているこの時も二度ないんだってことが、まあ、とっても自然に我々は時々教えられたことはなかなか入ってこないんですけど、もっと私たちの深いところに自然に入ってくる。だから私たちはもっと今生きている時間を大事にしていいし、大事にもできる。
そして、かけがえのなさってことがなんとなくわかりづらい現代なんですけど、私たちがここに存在してるってことそのものが、もうかけがえのないことだっていうのが自然に感じられてとても印象深い一時でしたね。
だから光そのものが何であるかっていうことよりも、光があるということがすごいことなんだって、何か感じていただけるような気がしたんですけど。」
作品空間に身を置き、自分自身と向き合うそうすることで自分の中から見つかるものがあったといいます。
「我々はもう少し祝福されていることを思い出さなくちゃいけない。だから、ないものを思い出すことはできないんですけど、我々の中にしっかりあるんだから、我々はまず思い出すことから始めようって、なんかそんな促しがあるように思いましたけどね。」
最後に第三の会場へ。窓から差し込む光が空間を満たします。その中央に置かれた作品、タイトルは「母系」。水の入った瓶を重ねています。空の瓶はかつて生きてきた者たち、その上の水で満たされた瓶は今生きているものたちを象徴しています。丸く水をたたえた水面が窓からの光を映します。
「私たちみんな同じ空気を吸って、同じ光を受けているんだけれども、そういうことを改めて気づかせてくれるっていうことですかね。だから太陽を浴びたり光を浴びたり、そういうことすべて、あ、そのこと自体が恵まれている、彼女の言葉で言うと祝福されているっていうことなんだけど、そういうことを改めて思わせてくれる。それがもう作品に一貫した思想だと思うんですよね。そういうことがやっぱり内藤さんならではの世界を作り出すし、そこから私たちが感じること、その魅力っていうんでしょうか。「生まれておいで、生きておいで」という呼びかけ、その声が聞こえている、受け取っていると願うという、そういう気持ちです。」