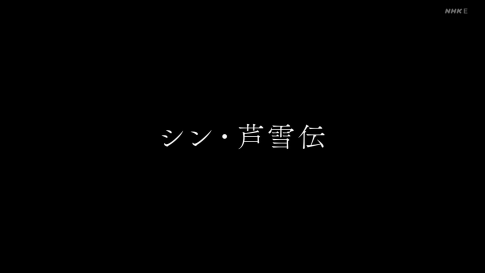圧倒的な人気を誇る、18世紀京都の絵師・伊藤若冲には、幻の傑作がある。昭和8年にある図録に白黒写真が掲載されて以来行方不明となった「釈迦十六羅漢図」だ。12万もの升目により画面を構成する若冲ならではの描法による大作。昨年専門家チームが結成され、このほどデジタル復元が完成した。写真1枚から極彩色世界をどうよみがえらせたのか。そもそも若冲はなぜ困難な技法に挑み、作品にどんな思いを込めたのか、謎を探る。
初回放送日:2024年7月14日
日曜美術館
墨線が生み出す無数の枡。そのひと枡ひと枡に彩色した風変わりな絵があります。升目描き。十八世紀、京都の天才絵師伊藤若冲が編み出した唯一無二の描法です。現存する升目描きの作品は三点。しかし、実はもう一つ幻の作品がありました。昭和八年の展覧会図録に掲載された一枚の白黒画像それは紛れもなく、若冲の升目描きによる描画でした。その後、行方不明となった作品を、この写真から当初の姿にデジタル技術で復元する挑戦が始まりました。
「一つの白黒写真から完成形に目指してでどれだけのことを考えられるんだろうか。それにはどういう手がかりを見つけられるんだろうか。「尋常じゃないっていうことを皆さんわかってるんでしょうか っていう感じでした。」画像から割り出したマスの数、およそ十二万。若冲はそこにどんな彩色を施したのか。
延べ一万時間を超える作業を経て、幻の傑作が蘇りました。「プライス本よりもむしろ静岡本に近い短い紙型ですね。さて、いろんな問題が出てきますね。ここからでそもそも若冲はなぜこの絵を描いたのでしょうか。浮かび上がるもう一つの升目描き屏風との知られざるつながり。升目描きに秘められた若冲の祈りが、今、明らかに。
「若冲 よみがえる幻の傑作〜12万の升目に込めた祈り〜」
「日曜美術館です。今日は伊藤若冲です。」
「若冲といえば、今や最も人気のある江戸の絵師といっても過言ではないと思うんですが、その若冲が描いた幻の傑作があったということなんですね。」
「そうなんです。若冲というと、生き生きとした鳥が描かれていたり、ふわふわっと可愛いワンちゃんだったり、親しみがありますよね。」
「その幻の傑作なんですが、『十六羅漢図屏風』なんですけれども、これをデジタル技術でよみがえらせようというプロジェクトなんです。そのもととなったのがこの図録です。かなり貴重なものになります。今からおよそ九十年前の昭和八年に大阪で展覧会が開かれた際に作られた図録です。資料としてはこの一枚の写真しかないという。ここからどのように復元していったんでしょうか、見ていきましょう。」
2023年一月、幻の屏風を復元するための初めての会合が開かれました。大阪大空襲があったその時、デジタル復元のエキスパートを中心に、若冲に詳しい美術史家、東京芸術大学の保存修復日本画研究室のメンバー、そしてレタッチャーと呼ばれる画像加工の専門家が集まりました。復元を目指すのは『釈迦十六羅漢図屏風』です。大阪大空襲で消失したと考えられています。
屏風には、十六人の羅漢が坂の下に集まった場面が描かれていました。十六羅漢とは、釈迦の最高位の弟子たちで、仏滅後もこの世に残り、仏の教えを守って衆生を救う役割を担っています。両端には仏教の世界で神聖な生き物とされる唐獅子と白象の姿があり、地面には蓮の花が咲き誇っている様子が確認できます。多くの専門家が、もし現存していれば傑作だと評価しています。
プロジェクトを率いるのは木下雄さん。彼は大手印刷会社で文化財のデジタル復元を手がけてきました。2017年には関東大震災で焼失した北斎の絵馬を、一枚のモノクロ写真から蘇らせることに成功しています。木下さんは数年前にこの写真を見たとき、他の作品以上にデジタル技術が力を発揮できると感じたといいます。
「12万マスもあるので、あまりにも作業量が膨大ですよね。デジタルという技術を使うことで、実際には実現が難しそうな課題に対して、現実的な方法を提案できるのかなと思いました。」
しかし、復元は序盤から壁に突き当たりました。
「うーん、片方しか描いてないというのは普通じゃないんだけどね。ちょっと謎だな。どうしても画像がぼやけているので、ディテールを明確にするのが難しいんですよ。」黒く潰れた釈迦の衣の部分。九十年前の画像を拡大しても不鮮明な箇所が至るところにあります。そこで若冲の他の作品に手がかりを求めました。
「これがすごい参考になる。これ、結構な発見じゃないですか。」と目をつけたのは、ボストン美術館に所蔵されている『釈迦菩薩図』と『文殊菩薩図』です。これにそっくりな絵が京都の東福寺にもありました。中国の元時代に描かれたもので、釈迦菩薩図は全体の構図や持ち物、何より衣のひだを忠実に描き写していました。そして、東福寺の釈迦菩薩と文殊菩薩は三尊像を構成するもので、その中には釈迦の姿も残されていました。若冲はこの模写を参考にしたと考えられます。屏風に描かれた釈迦と比べると、全体の姿や衣に入れた手の形、衣紋のひだの流れ方など、いくつもの共通点が確認されました。
こうした検証を繰り返しながら、見えない線をあぶり出していきます。さらに、細かな部分には何が描かれているのかが分からないところも多くあります。
「左から四人目の羅漢は、手に何かを持っているようにも見えるんですが、ここにリングのような形が見えたんで、『これ、尺杖かな?』って思ったんです。でも、ずっと長いものしか頭にイメージがなかったので、一旦排除してしまったんですよね。それで、別のことをいろいろ調べていくうちに、短い尺杖があるらしいっていうことを見つけて、『あ、じゃあそうなのかもな』って発見した時は、やったって感じでした。」
こうして、徐々に線が引かれていきました。しかし、形以上に困難なのは、何の情報もない「色」。色については、他のマス目描きの作品を参考にすることにしました。
マス目描きには二つの屏風があります。一つは静岡本と呼ばれる『樹花鳥獣図屏風』。右隻には大輪の花とともに23種の動物、白土を中心に虎や唐獅子、ウサギなどがいます。左隻には鳳凰を中心に31種の鳥、鶏や孔雀、おしどりなど、水辺に集う生き物たちの国際式の楽園です。もう一つは旧プライス本と呼ばれる『鳥獣花卉図屏風』。水を背景に象と鳳凰を中心とした生き物を表す構図は、ほぼ同じです。
マス目描き屏風をいち早く世に紹介したのが小林正さんです。マス目描きとは、どのような描法なのでしょうか。
「だいたい、間隔1センチメートル内外の四角いマスを作って、そこに絵の具を一色、あるいは二色、それ以上の絵の具を埋めていって、全体的な図柄が、そういう色の四角い点で表現されていくという、空前絶後の特殊な描法なんですね。この静岡本は、ちょっとやんちゃな自由度の高いマス目の作り方なんですけど、出光美術館にある『鳥獣花卉図屏風』というのは、そのマス目の色の面が、カチッとしてるんですね。」
二つの屏風には、細部に大きな違いがありました。鳳凰の頭部をよく見ると、『鳥獣花卉図屏風』は正方形のマスがきれいに並んでいます。一方、『樹花鳥獣図屏風』は、大きさや形にばらつきがありました。どちらの屏風を参考にするべきか、慎重に検討を重ねます。
「これすごい雑なんだよね。外でプライスさんが比べると、そこまで丁寧じゃない、中間的な感じがするね、なんかね。」
『釈迦十六羅漢図屏風』の白黒画像を細かく見ていくと、それぞれのマスの中に正方形が描かれてあって、さらにアクセントとして描かれているんですけれども、それが全部左下に描かれているんですね。『鳥獣花卉図屏風』では、むしろ正方形の中の中心に描かれています。
もう一つ、方眼線の幅についてです。『鳥獣花卉図屏風』だと正確に12ミリメートルの幅で方眼線が描かれていますが、『樹花鳥獣図屏風』だと平均すると9ミリメートルぐらいで、幅に広い狭いがあります。『釈迦十六羅漢図屏風』の画像を見ていくと、この方眼の幅がやはりまちまちなんですね。この点からも『樹花鳥獣図屏風』との類似が指摘できると思います。」
九つのパターンに基づいて、東京芸術大学のチームが彩色サンプルを制作していきます。化学調査で特定した顔料を使って、微妙に色味を変えた数百のマスのサンプルが作られました。
ここでさらなる難題がありました。この「わじみ」の部分を出すのが難しくて、輪っか状に、というか、外側が濃くなる現象ですね。複数の顔料を混ぜ合わせた色を塗ると、それぞれの比重の違いから外側に濃い色がたまることがあります。静岡本に見られるこの現象も再現しようとしていました。サンプルを何枚も何枚も作って、ようやくその表情が出せました。ですが、その表情を作っておかないと、実際に復元のデータを作る際に、外がじんわり濃いというニュアンスをうまく再現できないと、全く見た目の印象が変わってしまうんです。
完成したサンプルが検討会に持ち込まれました。「結構違う、こんな感じですね」「よくできています。」
このサンプルをもとにレタッチャーがデータに落とし込み、デジタル上で彩色するガイドにしました。画像加工を行うレタッチャーは八人、場面ごとに担当を受け持ち、彩色を進めました。サンプルをもとに複雑なニュアンスを加え、デジタルで色を復元していきます。作業には一年半、延べ一万時間以上が費やされました。
デジタルの画面に現実感をもたらしたのは、あの「わじみ」でした。実際の絵の具だと、紙に染み込んだり、様々な現象が発生した上で発色しますが、データの場合は非常にフラットで何の変化もないものになってしまうため、その現象を追いかけることで、絵の肉質感に迫れるということです。「本当に、それがあるだけで全然違います。」
こうして、十二万のマスが埋められていきました。
今年三月、最終データが完成し、印刷の日を迎えました。マスごとに特殊なインクを何層も重ね、微妙な凹凸まで再現します。「復元ってどうしても完璧ってことはありえないですよね。答えが分からない中でやっているので。ただ、こういう取り組みがなかったとすると、若冲にまだこういう作品があったんだということを知ってもらう機会もなかったと思うので、その一つの方法として復元というのはあるかなと思っています。」
プロジェクトチームには、完成した屏風を真っ先に見せたい人がいました。若冲研究の第一人者、辻信雄さんです。「ああ、これはまたなんじゃ…。」「復元プロジェクトが完成しました。」「いや、このみすぼらしい写真がこうなっちゃったっていうんだから。表具を施した完成作の高さは百八十三センチ、幅は六百一センチの大作です。このね、これをモノクロで見ても、この力強さっていうのが、恐ろしい。ちょっと度が過ぎているね。」「そうなんです。龍がこうやってこうなるわけです。」「力強いですよね。全体に何かエネルギーがみなぎっている感じがしますし、若冲独特の豊かな表現がここに発揮されています。」
蘇った釈迦十六羅漢図屏風は、マス目描き作品の中でも特別なものだったと辻さんは言います。「この屏風の他の三点と比べても、人物、ラカン(羅漢)が描かれているのが特別です。人物が主題になっているというのは他にはありません。しかも、若冲はおそらく自分自身をラカンの一人として描き、自己を表現しているのかもしれません。だからこそ、彼はこうした滑稽な像を描いたのではないかと思うんです。」
辻さんは続けます。「十六羅漢を正面に出す人なんて他にはいませんからね。しかも、このようにマス目描きで描くというのは、若冲の思想が深く反映されています。これをきっかけにして、さらに多くの議論が活発化されることを期待しています。」
スタジオトーク
今日はスタジオに復元プロジェクトの完成直前の試作品をお借りしました。八点あるうちの一つですが、完成品と同じ大きさです。こんなに大きく、そして色鮮やかになったんですね。本当にあの小さな写真からこれだけのものになったというのは驚きです。
スタジオには、復元プロジェクトの監修をされました美術史家の山下裕二さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
「いや、びっくりしました。あの白黒の写真からこれが生まれてきたというのは、本当に驚きです。かなり困難なプロジェクトでしたね。最初にこの話が来たときは、たった一枚のこんな小さな脆い写真からどれだけ復元できるのか、僕自身も半信半疑でしたね。でも、約二年の時間をかけて、最新の技術を駆使してこれだけのものが出来上がったのは、非常に感慨深いです。」
「他の作品と比較してヒントを得て、少しずつ完成に近づける作業だったんですね。そして一つ一つのマスに色を埋めていくわけですが、その色の特定作業もVTRで見て非常に興味深かったです。」
「そうですね。もちろん若冲の他の作品も参考にしながら、モノクロのフィルムで撮るとこれぐらいの明度になる、という具合に試行錯誤して推定し、色を復元していきました。だから様々な角度からこの復元プロジェクトが進められたんですね。最新のデジタル技術を使いつつも、VTRに出てきた芸大のチームが実際の絵の具でサンプルを作り、それをデジタルに反映させるという、デジタルとアナログの融合だったんです。」
「このプロジェクトのデジタルである良さは他にもありますか?」
「途中、試作品のようなものを何度も作っていきました。それを我々が見て、ここはもう少しこうした方が良いのではないか、とアドバイスすると、次の会議の時にはその修正が施されたものが出てくるわけです。約二年間、何度も会合を重ね、徐々にブラッシュアップしていった結果、これが完成したんですね。本当に大変でした。」
「ありがとうございます。僕自身はそうでもないと思いますが、レタッチャーの方々や実際に絵の具で描いてくださる方々には、本当に並外れた労力がかかっています。どうしてそれを思いついたのかと感心しています。」
「要するに、誰もやっていないことをやろうと思ったんですね。そのマス目を書く作業だけでもかなりの忍耐力が必要です。実際、若冲がどの程度自分で書いたのかについては議論がありますが、これだけの量ですから、おそらく弟子たちも動員したのではないかと思います。全体の構想はもちろん若冲が立てたのでしょう。」「辻信雄さんも、このプロジェクトをもとに今後の議論が活性化することを期待しているとおっしゃっていました。」「けれども、やっぱり気になるのが、そもそもなぜこれが描かれたのかというところですよね。そのあたり見ていきましょう。」
京都伏見の弱虫は晩年、地元の寺院である赤宝寺の門前に庵を結びました。赤宝寺は、中国から伝わった禅宗の一派である大爆襲の寺院です。弱虫は禅の教えに深く帰依していました。山門をくぐると、裏山に弱虫が精魂を傾けて作った石仏群があります。その中には、シャカ十六ラカンズ病部にも通じるユニークな表情のラカン像が見られます。約五百体のラカンが身を寄せ合うように集まっています。彼は絵を一枚売るごとに、石仏を一体作るというスタイルで、自ら描いた絵を元に石仏を彫らせていたのです。
近世の京都画壇を研究する岡田英幸さんによれば、「五百という数字には、多くの仏を含むという意図があったと考えられます。仏の世界を立体的に表現しようとしたのだと思います。」赤宝寺図は、京都の国立博物館に所蔵されており、おそらくこの図が設計図となっていたと考えられています。
赤宝寺図は、弱虫が描いた仏の理想世界を示しており、特徴的な山門を中心に広がる水辺の情景が描かれています。そこには多くのラカンが集まっています。
山門の先には、この絵の最も重要な場面があります。それは、釈迦のもとに集う羅官たちの光景です。この光景は、赤宝寺の石像にも現れています。
また、この絵にはもう一つ注目すべき点があります。画面右に描かれた水を渡る白象と唐獅子の姿は、シャカ十六ラカンズ病部と通じるものがあります。
岡田英幸さんは、シャカ十六ラカンズ病部が晩年の弱虫によって赤宝寺で描かれた可能性があると考えています。さらに注目すべきは、受火鳥獣頭病部との比較です。蘇ったシャカ十六ラカンズ病部と改めて比較すると、画面構成が非常によく似ていることがわかります。画面下部には大輪の花びら、中央部分には水、そして上部には木々、さらに白銅と唐獅子の姿が描かれています。これらの要素は、両方の絵に共通しています。
岡田さんは、これらの病部が同じ世界を表現している可能性があると述べています。「同じマスメガキという手法で、時の社家の世界と動物との世界を表現する構想があったかもしれません。制作時期が一致する可能性が高いですし、それが同時に作られた、または何らかの関連の中で作られた可能性があると思います。」
復元プロジェクトを監修した新井さんも二つの病部のつながりを感じています。今回復元をするにあたって、また改めて細かく観察してみると、描き方が似ていることからすると、両者が別々のものではなく、一連の関係性を持っていたというふうに考えておくべきだと思いますね。もし元本が両方存在していたら、これらの関係について何か言及されていたはずですよね。こう立てたかもしれませんね。動物と鳥をこっち側で、これはこっち側で、というような配置だったかもしれません。」
小林さんは、シャカ十六ラカンズ病部が受火鳥獣頭病部に囲まれるように配置されていた可能性を指摘します。「そうすると、シャカ十六ラカンズ病部が、受火鳥獣頭病部と似たような構造になるかもしれません。弱虫が生きとし生ける者の命の輝きを精密に描写した同色彩のもので、釈迦三尊像を本尊として、その左右に十五尊ずつ並べられたとされます。」
晩年の弱虫が全勢力を傾けて仏を称号した同色彩の園。その後で釈迦十六ラカンズ図病部と受火鳥獣頭病部が描かれました。「この二つの別々の作品が、三つの両側に配置されることで宗教的な空間を作り、仏の慈悲の空間が生まれるのではないかと考えられます。これを想像すると、両側に並べられる素晴らしい空間が形成されるというのは、非常に豪華な構想ですね。」
釈迦十六羅漢図屏風と受火鳥獣頭図。それは晩年の伊藤若冲が升目描という得意な手法を用いて到達したもう一つの命の輝き、仏の理想世界だったのかもしれません。
「浄化本」と呼ばれる生まれる樹花鳥獣頭図と、そして釈迦十六羅漢図には、書き方だけではなく世界観にも類似が見られます。この二つには深い繋がりがあるのではないかというお話でした。
「まず重要なのはサイズが大きいということですね。これ、言ってみればご本尊に当たるわけですから、それはサイズを大きくしている。静岡本はそれより少し小さいですが、先ほど小林先生が指摘されていたように、これをこういう風に立てることを想定していた可能性は十分あると思いますね。十六羅漢図屏風の大きさが分かったからこそ、そうしたつながりがあるということも信憑性が高まっているということですね。」
「空間を作りたかったんですか?」
「そうですね、どこかの寺院の空間を総合するために、若冲が構想した可能性は十分ありますね。世界観というのは、この動物たちが釈迦やその周りに集まってくるという、そういうことじゃないですか。仏教的なワンダーランドですよね。それを晩年の若冲はその赤宝寺で立体でもやろうとしたし、こういう絵でもやろうとした。ラカンという存在に対して、ずいぶんシンパシーを持って、自分も羅漢になりたい、要するに仏に近づきたいみたいな、非常に強い信仰心を持っていたわけですよね。」
「幸せそうな図ですね。」
「そうですね、囲まれることを思うとそうです。それにしても、この升目を十二万も埋めていくというのは、とてつもない作業量ですよね。ですから、若冲がこの升目を一つずつ埋めていくというのは、これ僕の考えなんですけれども、その写経に近いんじゃないかと思うんですね。要するに、お経を一文字ずつ書いていくわけでしょ、写経って。若冲はそれを絵で、要するにマス目を一つずつ埋めていくという作業を自分に課したんじゃないかと思うんですね。だから、ある種の修行のような意識があったんじゃないかと思うんですよ。」
「確かに本当に一つ一つこう、まっさらな気持ちになるような作業でしょうね。」
「そうですね、無我の境地と言いますか。そして、偶然にしても、絶望の中で誰もやっていないことをやってやろうというエネルギーってすごいですよね。それを同じように再現しようというエネルギーを持って、時を超えてチームが、若冲の熱意がこのチームにも伝わって、何百年か後にこういうプロジェクトが完成するというのは嬉しいことですね。」
「素晴らしいものを今日は見せていただきました。ありがとうございました。」
伊藤若冲、寛政十二年、千八百年、八十四歳です。