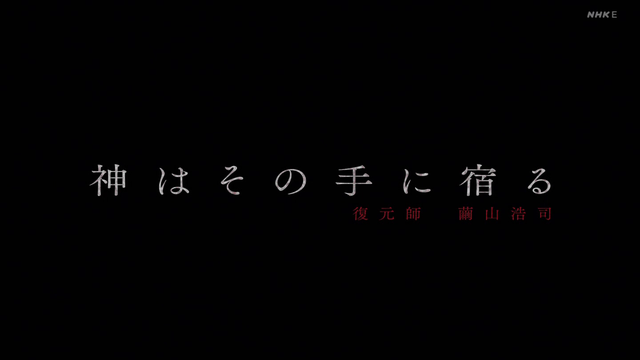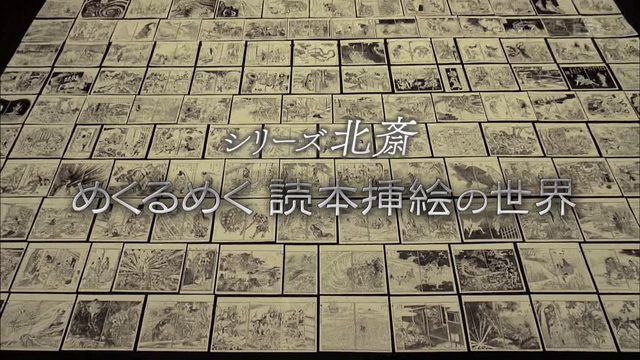“ゴッドハンド”の異名をとる男がいる。やきものの修復師・繭山浩司。その技を育てたのは戦後の口外できぬ仕事の数々。極秘に古美術商から預かった破損品を、どんなに目を凝らしても傷跡がわからないまでに修復してしまう。今回託されたのは、“無傷なら国宝級”とされる青磁の花入、そして割れてしまった脚本家・向田邦子愛用の蕎麦猪口など。モザイク必須の工房で、人類の宝を後世につなごうと 復元師 のゴッドハンドが躍動する!
【出演】繭山浩司 繭山悠 藤田清 千宗屋 太田光
初回放送日: 2022年4月3日
日曜美術館「 神はその手に宿る 復元師 繭山浩司」

神の手を持つと言われる男がいる。
ばらばらに割れた器がはいこの通り。
焼き物修復の中で不可能はない。
彼の仕事は完全に焼き物の世界のトップですから。
修復界の中にゴッドハンド
技は人目をしのび磨かれてきた。
埴輪の破片を粉にしたものなんですけど。
埴輪が来た時にはこれを材料として使う。
ミイラはお断りしました。
依頼人も様々。
その始まりは闇の仕事だった。
かなり影の部分が多くて。直したことを言わないで売り買いされてた時代なので。
復元師。その知られざる世界。
依頼人の藤田清。
国宝9点など日本有数の古美術コレクションで知られる藤田美術館の館長だ。
そしてご意見番の武者小路千家千宗屋。
依頼品は長年美術館の蔵に眠っていたものだった。
素晴らしいですね
八百年ほど前に中国で作られた青磁の花入れ。
痛々しい補修の跡が残る。
「箱書きに京都毘沙門堂什器、同品なりなりと書いてあるんですけど、毘沙門什器っていうのは今国宝になっている青磁の花入れで王様と言われる万声という名の花入れがあって、一応それと同手だということがここには書いてあるので、連れが国宝っていうことですよね」
「傷がないような状態に直せると、作品としてはベストなのかな」
傷がなければ国宝級。
「箱に鳳凰耳となってますけど、耳の形がちょっと変わってますよね」
「鳳凰じゃないですね」
「あんまり他に見たことない」
確かにこの花入れには鳳凰の顔が付いていない。
一体どういうことなのか。
改めて依頼品と向き合う。
割れ目には漆で次ぎ金を施す金継ぎ。
直して大切に受け継がれてきた証だ。
耳の部分にも補修の跡がある。
まさに傷だらけ。
金継ぎの金をはがす。
「様子が分かったので残りのちょっと部分は悠の方にとってもらえばと思うんで」
「全部とっちゃう」
息子の悠はこの道に入って十年。
取れたのは漆と石の粉を混ぜたもの。
欠けた部分を埋めていた。
「取っていくとやっぱりこう下で隠れてる肌とか出てくるんでそういうのを見てる間に終わってますね」
金が全て取り除かれた。
ちょっと破ってあげるから
花入れは漆を溶かすために薬剤に漬けられていた。
「どっちがどっちか分かんない」
「明らかはもう色は違う」
「粘土のね生地の幅がもう全く違うこっちはもう円だし。これは薄いしね。明らかに予備継ぎ」
過去の補修では別の青磁から取られた部品が付けられていた。
元々の形が失われている。
それで鳳凰の顔がついていなかったのだ。
「この割れ口には漆の細かい付着物が残っちゃってるから」
断面には無数の黒い斑点が。
接着に使われた漆が解けずにこびりついていた。
漆は一粒ひと粒掻きだすしかない。
「焼き物の修復っていうのは透明度の表現との戦いみたいなところがあって、焼き物ってもう本当に透明度が高いもので、透かすと本当に光が透けてくるものがほとんどなので、それをどうやって再現していくかっていう。自然に見せるかっていうのが本当に大事だなっていうのが」
二週間の作業の後、汚れは全て取り除かれた。
汚れなき断面。
白い生地の上にかかる青い上薬。
その透明感が青磁のこの上ない美しさを生み出す。
貴重な青磁をどう直すのか。
依頼主と話し合うことに。
「耳のところが予備継ぎ」
「バランス的にはこの万声をある程度イメージしながら作らせていただく」
鳳凰の耳は国宝の万声を元に復元することになった。
「ヒビが来てるんですよ。これを先に消しとかないと、くっつけた後だと消えなくなっちゃう」
入と呼ばれる小さなヒビ。
これを消すという。
使うのは時間がたつと固まる透明な樹脂。
「ミスると終わりなんで」
器を火で炙り始めた。
本当に消えた。
「入の場合は隙間がほとんどないので、必ず少し加熱してやらないと吸い込まない」
隙間に入り込んだ透明な樹脂が光の反射をなくす。
それで傷が消えたように見えるのだという。
「これは僕らでもあとどこ消したか分かんなくなっちゃうんで」
繭山が名乗る復元師という仕事。
礎を築いたのは大正生まれの父、萬次。
漆職人から身を起こし独自の技術を編み出した。
「金継ぎなんかはね漆でしたりするんで、そういうのを見てて、父はこれがもし分かんなく直ればいいなという風に思ったみたいですね。仕事は業界の方からも名人って言われてましたから、自分でその材料も含めて開拓してきた」
そのずば抜けた技故に萬次の存在は久しく表に出ることはなかった。
「あまり存在を知られてはいけないというか。完全にというと変なんですけれども、かなり影の部分が多くて、直したのをあんまり言わないで売り買いされてたものっていうのもあったりした時代なので、だから僕が仕事始めたぐらいから少しそのま世の中に知っていただけるような形になり始めたかな」
禁断とも言える技を受け継いだ繭山。
その仕事は今父を超える。
ばらばらに割れた香炉。
修復のあとはどんなに目を凝らしても分からない。
その実力は他の追随を許さない。
神の手を必要としている器がここにも。
三角の部分が失われていた茶碗。
天然の岩絵の具を使って色を入れていく。
必ず青を使う?
「この色は結構焼きものには若干この色の傾向が混じっている場合が多いです。七八色ぐらいかな」
見た色をいとも簡単に再現。
失敗はない。
「色味はまあまああ近いですね」
次はろくろで挽いた時にできる指の跡。
今度は筆。
「これでやるとつかなかった場所とかつく場所とか出てくるんでね、偶然性が多少出るんですね」
針の先でごく小さな点を打っていく。
失われた三角が蘇ってゆく。
また依頼があった。
爆笑問題太田光。
「実はあの妹の和子さん。向田さんの和子さんと話してた時に、向田の遺品がいっぱい
家にあるのよって言われて、一つくださいよって言ったら本当にくれて、使ってたんですけど、お手伝いさんが布団と一緒に乾燥機にかけて訳分かんないって言ってそれはもう大笑いだったんだけど」
「本当にちょうど真っ二つに割れて」
「向田さんも多分どっかの骨董市とかで本当にあそんなに高価なもんじゃないって思うんですけどね、そういうのが好きだったみたいな」
昭和の名脚本家向田邦子。
何気ない日常を丁寧に見つめそこに潜むドラマを鮮やかに描き出した。
趣味の骨董にも同じまなざしが注がれた。
ただ自分が好きかどうか
それが身の回りにあることで毎日が楽しいかどうか
本当はそれでいいのだなと思えてくる
三度の食事と仕事の間に楽しむ煎茶、番茶
うんあまり知り過ぎず高望みせず
この時をいい気分にさせてくれればそれでいい
そこには茶渋のような使い込んだ味わいが。
向田はそれを洗い落とさずに楽しんでいたようだ。
「恐らく金継ぎされた時に少し両サイドきれいに取られてしまったのかもしれないね。この感じに戻した方がいいのか・・・できるだけこの味も損なわないような形でのお直しということですね」
「はい僕も向田さんが結構好きなんですが、エッセイとかにもね出てくるよね。書かれてて何か感慨深いですね。ご本人が使われてたっていう」
青磁の花入れ方耳の復元が始まった。
「ここがないと人間で言ってたのは顔がないとかそういう意味での話になっちゃうんで」
石膏で鳳凰耳の下地を作る。
「これ一回り以上外側落とさないと駄目だと思うけど。二ミリぐらいは少なくても。もっとだな」
「こっちの方が入ってるじゃない。これこれよりこっちが出てるじゃない」
「どこまでやれ見てる見てる見てろって言ったらこれ見てるへーよく一言でストップっていえうん。もっともうまた折れるよ」
鳳凰耳の下地ができた。
太田光に頼まれた向田邦子のそば猪口に取り掛かる。
「これ擦ってる」
擦ってるって何ですか?
「普通こう合わせると、線は見えるけどあんまり引っかからないんだけど、これ谷になってしまっている。この部分はもう完全に斜めに釉薬を削ってるっていうことですね。これはもう恐らく一番やっちゃいけないこと。最もやってはいけない」
一度削ってしまえば元の素材は二度と戻らない。
「もうしょうがないから茶渋はずしたら」
「でも底に当たるの嫌なのよ。すぐ取れちゃいそうで。タイミングわかんないじゃない」
「イライラしてる時やったってまろくなことなんかやめとけよ」
薬剤に付け込むと底の味わいも取れてしまう。
やむなく筆で塗ることに。
「向田さんがボロ市とかで買ってきたものなんだとしたら、まある程度残してあげないと
かわいそうだなっていうのもあるんですけど。人が持ってたっていう履歴みたいなもんなので」
断面には漆だけでなく接着に使われた合成樹脂がこびりついていた。
「本来だったらこんなことやりたくないですけど、うんでもそうなっちゃうとこういうことぐらいしかできないから」
「大事にしてきたものをこういうことするっていうのは理解不能。うちの直しっては父親もよく言ってるんですけど、何十年後か何百年後か分からないですけど、そこにそのその時に家より全然直しがうまい人がもし出てきた時に、その元通りの状態に戻してそのうちが傷を増やさない、割れたら割れたときのままの状態で渡せるようにしたい。だからできないことはしないのと余計なことはしないっていうのをうちは気にしてやってますけど」
再び接着し直す。
「これ以上は入らない」
「粉だけ入れればいい。それで拭く」
父親はここぞという時に頼りになる。
「とりあえずそれで固めて」
「ああしょうがないんだから」
「でもそのところに取れてるよ。やっぱり休み取れてるよ。頑張ったんだ」
「仕事うまいですよね。圧倒的に。いまだに弟子なんで。ずっと。まあと十年たっても弟子だとは思うんですけど。別になんかその父自体がそんなに仕事注がせたいみたいな感じの人じゃなかったんで。でもいずれ父もその年齢的に仕事できなくなったりとかする時は必ず来るんで、その時に少なくとも今の父のレベルまで行ってないと」
青磁の花入れは大詰め。
一番の難関。
鳳凰の顔作りが始まった。
描くのは二センチ四方に満たない狭い範囲。
鳳凰の顔がみるみる出来上がってゆく。
青磁の上薬に模したものを作る。
「ここだけはちょっと失敗できないですね」
色はぴったり。
でもまだ終わりではない。
「これがね、中に空気が入ってる粒子なので、粉みたいに見えると思うんですけど」
中に気泡が入った粉末は断熱材にも使われる特殊な素材。
これで釉薬の中にできた気泡を再現するのだという。
「下から透けてくる感じが大事」
完成した器が依頼主のもとに到着した。
千家の若宗匠も駆けつけた。
対面の時。
「いやびっくり。できた当時はこうだったんですよね。すごいなあ」
はいはいありがとうございます
復元された青磁の花入れ。
光を通し、きらめく様は青磁そのもの。
完成を祝い、茶をたてる。
「最高です」
太田光に託された向田邦子のあのそばチョコも仕上げの段階だ。
使われるのは七十年以上前の抹茶の粉。
三代に渡り使い続けている。
太田が譲り受けた時には付いていた底の茶渋。
向田が愛したその味わいを復活させる。
「そう言ってもらえる以上はそれに答えられる仕事をしなきゃいけないっていうのは常に思ってますけども、結局すごくうまく治ると、それが次の基準になっちゃう部分がある
じゃないですか。だからうまく直せば直すほど次のハードルがどんどんどんどん高くなって
いっちゃうっていうことだから、本当に自分で自分のハードルを上げてちゃってる」
「これじゃまだ驚かないでしょうね。本当に分からなくなりましたねって言っていただければと思うんだけどそこまで何とかいけるように」
「どうも今日ところありがとうございます。お預かりしてさせていただいた。全く分かんないですよもうどこが悪いんじゃないか凄いあ」
底の茶渋もすっかり馴染んでいた。
「本当にもらった当初の感じ。これはちょっともうたまにしか使わなようにしよう。だからまさかねそんな子供の頃に向田作品と出会って、大人ってこういう仕事して、ましてやそういうこういう形見のもらえるとかも思ってなかったので、より貴重なものになった気がします」
「お渡しできてほっとしました」
「めちゃめちゃ喜んでもらえたから良かった」
「僕ら預かるものっていうのは非常にやっぱり貴重なものだったり歴史があるものだったりするのでそれはあくまでもそのたまたま今僕らが今手にしてるけどもそれは僕らの時代で
もちろん終わらせてしまってはいけないもので必ずその後世に伝えていかなきゃいけない」
明日と来週
— 繭山悠 (@yumayuyama) April 2, 2022
4/3(日) 9:00〜9:45・20:00〜20:45
4/10(日)20:00〜20:45
NHK Eテレ「日曜美術館 神はその手に宿る 復元師 繭山浩司」https://t.co/g4k68DbdzR
番組で収蔵品を2点修復させていただきました藤田美術館様もリニューアルオープンをお迎えになりました。
そちらにも是非お運びください。 pic.twitter.com/2S2NTSzL9p
陶磁器を鑑賞し使用する文化は古くから大切にされてきたが、破損などにより鑑賞や使用に堪え難くなってしまった貴重な陶磁器も多く存在する。修復により本来の魅力を復元し、後世に伝えてゆくことができればと修復の仕事に携わっている。修復された陶磁器は日本各地の美術館に展示、また国内外のコレクターに所蔵され、現在までに5000点を超える修復を完了している。2015年には佐賀県立九州陶磁文化館所蔵の鍋島色絵芙蓉文大皿の修復を完成させ、2016年の特別企画展「日本磁器誕生」で修復に関する特別記念講演を行った。
繭山 浩司|公益財団法人 日本文化藝術財団
大阪市都島区網島町にある、東洋古美術を中心とした大阪府の登録博物館。