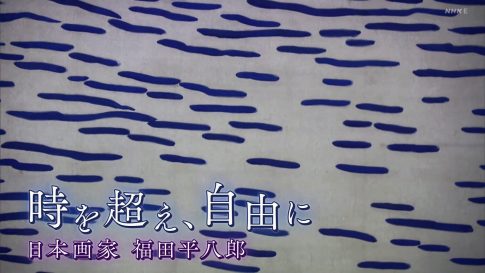卓越した技と美。日本工芸の粋が一堂に会する日本伝統工芸展が始まっています。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の工芸分野7部門で選ばれた539点の入選作が、全国12か所を巡ります。磨き抜かれた伝統の技を、新しい感覚とオリジナリティで新たな作品への昇華させた匠たち。アトリエ訪問も交えながら、受賞作16点のすべてを紹介します。とどまることなく進化し続ける日本の伝統工芸の「今」をご堪能ください!
初回放送日:2024年9月15日
日曜美術館
卓越した技と美。日本工芸の粋が一堂に会する日本伝統工芸展が始まっています。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の工芸分野7部門で選ばれた539点の入選作が、全国12か所を巡ります。磨き抜かれた伝統の技を、新しい感覚とオリジナリティで新たな作品への昇華させた匠たち。アトリエ訪問も交えながら、受賞作16点のすべてを紹介します。とどまることなく進化し続ける日本の伝統工芸の「今」をご堪能ください!
初回放送日:2024年9月15日
日曜美術館 「伝統に新しい風 〜第71回日本伝統工芸展〜」
技を極めた匠たちが生み出す美の世界、珠玉の作品が一堂に会する日本伝統工芸展が始まりました。今年は、染色や均衡など七部門から千八十五の応募の中から十六の作品が受賞しました。今、伝統工芸の担い手たちは大きな変化の時を迎えようとしています。
「今は特定制度がほとんどなくなりまして、ほとんどが大学、あるいは専門学校、さらには独自に制作に入った、そういう環境がものすごく増えてきました。バリエーションが増えてきたそうすると、やっぱり思考も違うし、視野も違うし、表現も違うので、すごくそういう意味では展覧会そのものの作品が面白くなってきていますね。」
伝統の世界に吹く新しい風、伝統工芸の今を見つめます。
「伝統に新しい風 〜第71回日本伝統工芸展〜」

虹色に輝くのは、切り出した夜光貝の大きさを変え、丹念に散りばめた螺旋です。まるで天秤の絵画のようです。螺旋で描いたのは、沖縄の風景。川の紀水域に生育するマングローブの森です。強い日差しが生み出す陰影やきらめく光、沖縄の風景は、箱の裏側にも見たこともないラデンの絵画として表現されています。どんな作家が作ったのでしょうか。

でも、こう、丘を抜ける風が気持ちいいですね松崎さんですかよろしくお願いしますnhk の森本ですよろしくお願いしまして、初めまして、沖縄県立芸術大学で講師をしている松崎盛平さんです普段は研究室で制作していますおお ですたくさんこれ大きいですねかのかいこれが夜光貝という沖縄でたくさん撮れる貝になるんですけども、この夜光貝をたくさん使って作品を作っています松崎さんは東京出身東京芸術大学で出現を学びました四年前にラデン技法の研究のため、大好きな沖縄に移住今回描いたマングローブの森は、妻と一緒に参加したカヌーツアーで目にした景色です僕の中ですごく憧れてたんですそのところに すごく独特の食生で木々が生えていて、水辺から入ってるんですよねすごいな、 この風景はあってなんかアーティスト光ってて、なんかバーッと景色が広がってて、なんか自分の中で色が見えてきたイメージみたいなのって、すごく頭の中に残ってるんですけども、そういったのが作品にふわっと広がってくれればいいなと思って、ラデンレイ学会が作業を見せていただきました並べるの好きなんでしょうね色や形の違う貝の欠片を一つ一つ漆の上に置いていきます例えば、波の色味が移り変わって、一色ではなくて水の表現をしたい時に、緑色に着色した屋根街のすり替えを貼っています合わせて黄色の黄色というか、金箔を張った夜光貝のすり替えのものも併用して、ちょっと黄緑色っぽくというか、少し明るい緑っぽい雰囲気にしたいなぁ ここはと思ったので、それを貼っていますこれが薄く酢って言って、薄く加工された貝これはもう購入したものですけども、この貝の裏側に金箔が貼ってるのわかります金額ですか これそういった形でひっくり返すと金色が透けて見えるように、例えばこれなんかは緑色に見えると思うんですけれども、これは緑色の漆で接着をこの金箔を押してあげることによって、ちょっと同じ金箔を貼ってるんですけども、色々しの見え方で色が違うよという螺旋の裏側に色をつけ、多彩な輝きと色合いを作る伏せ剤式松崎さんが得意とする技法です使う場所によって色や形を変えて、およそ三十種類の螺旋を揃えました今回使う螺旋の中に苦いという琉球王朝時代から伝わる沖縄ならではの技法があります松崎さんは先輩の研究者からその技を学んでいますまず、夜光貝を海水と同じ塩分濃度の水で半日間煮込み、木槌でたたきますこれを二週間続けます表面の切開室などが剥がれ、真珠層が出てきたら、ペインティングナイフで層を一枚一枚丁寧に剥がしていきます夜光貝を煮ることで取り出した淡く輝く真珠層、その厚みはゼロ一ミリ以下ですこれですね触るのが怖いくらい、すごく繊細な、もうあるかないかわかんないからよ苦いには伏せ剤式とは違った落ち着いた輝きがあるといいます僕の作品で言うと、空間の中で手前ではなくて水面の奥の方、この木々の森の部分に最終的に遠くの方になっていく部分だったりとか、距離感を作るために少し弱く見えたいところっていうのにこの苦いを使うことですごく作品の幅が広がったんではないかなっていうふうに自分の中で思っています箱を開けてみると砂浜を歩く塩まねき通勤と呼ばれる技法で作られています実はこれも沖縄伝統の失礼の技培ってきた自分の技術と、沖縄で学んだ伝統の技が息づいていますこっちに来て見た景色であったりとか、沖縄の自然の自分が育ってきたところとやっぱり風土が違う印象だったりとか、 その発見ですよね鮮やかさだったりとか新鮮さそういったものは今自分が感じていることもすごく感動している部分として表現したいなというふうにそこはすごく強く思っています

人形部門で受賞したのは、ゆったりと舞う琉球の踊り子です。光沢のある打ちかけにあしらわれるのは赤花と呼ばれるハイビスカスの花。あえて赤みを抑えることで、衣装の赤い色を引き立たせました。

銀泥を施した磁器には、枯れたほおずきの色絵。白と黒、二分された背景によって頬づきの表情が違って見えます。器の中に目をやると、視線を誘う優しい銀のライン。高い技術が生み出した幽玄な美の世界です。

照りつける日差しの中、涼しげにたたずむスイレンを描いた蒔絵の箱。リズムよく置かれた朱色の花。ほんのわずかな金粉で葉脈を浮き立たせ、みずみずしい葉が表現されています。

石川県和島で製作を続ける作家が一年以上をかけて完成させました。

青森で出会ったヒバの森をモチーフにした型絵染めの着物。使う色は青、緑、灰色のわずか三色。あえて色数を絞りました。リズミカルに連なるヒバや鳥の姿、木立をそぞろ歩くような気分にさせてくれます。

全国から集まった千点を超える応募作。その頂点に輝いたのは金工の作品です。黒い鉄字を覆う白銀の線。線に沿って規則的に連続する点灯面。一部の隙もない卓越した技が高く評価されました。金工作家の原智さんです。作家活動だけでなく、大学で近郊の指導を行っています。

鉄を金槌で何万回とたたいて作り出したふくよかな造形。そこに描かれた無限に広がる幾何学模様。その整然とした広がりは意外なものがモチーフでした。
「蝶の鱗粉をモチーフにしているんですけども、鱗粉とは言っても、鱗粉をさらに拡大した時にどう見えるかというのを色々調べていたら、電子顕微鏡で見たような画像だったんです。横線だけになっているんですよね。僕の場合はそれを斜めの線で構成して、あと点と円を少し入れて幾何形態に落とし込んで表現したと思います。」
幾何学模様は、象嵌という彫金の技法を組み合わせています。まずは、線象嵌。ガイドラインが見やすいよう、青く塗装された鉄の板に溝を掘ります。先端の幅が0.3ミリの鋼を当て、金槌で何度も叩き掘り進めていきます。目指す深さは0.4メートル。一本の線を四回に分けて掘り、徐々に深くしていきます。
「宝の癖があって、むしろ右側に行こうとしたりとか左側に行こうとしたりする時があるので、手はこまめに動かしながら、このラインからずれないようにというのは注意していますね。」
一見まっすぐに掘り出したように見える線ですが、実は匠ならではの計算があります。
「実は僕が打った時のほんの少しのムラみたいなのがとても重要かなと思っていて、機械で打てば割と均一にきちんと同じラインが引けると思いますし、すごい精度が出ると思うんですけども、ほんの少しの千分の一とか百分の一のズレが、作品が出来上がった時の石の柔らかさであったりとか、表情とかに影響を与えているのかなと思うので、ほんのわずかな揺らぎみたいなものも大事にしたいなと思っています。」
溝に銀の線を埋めていきます。銀線だけを正確に叩いて打ち込んでいきます。砥石で研ぎ出すと、鉄字と一体化した白銀の線が現れました。
続いて線の上に天造岩を施します。電動ドリルを使って直径0.6ミリから1.5ミリまで五つのサイズで穴を開けていきます。鉄字の厚さはわずか2ミリ。誤って貫通させないよう、手に伝わる感触や音の変化に気を配りながらの作業です。そして少しだけ頭を残して上から器全体に施した天造岩の数はおよそ2800個。
「好きな言葉で『神は細部に宿る』という言葉があって、やはり細部がしっかりしているからこそ全体が成り立っていくというような、そういう考え方や意識は大事だなと思っています。自分が作品を作る上でも全体が綺麗だったらいいかなって思えなくて、細かい部分の積み重ねによって全体が成り立っているということをいつも意識しています。」
原さんの強い信念は仕上げにも現れます。一つ一つを鋼でへこませていきます。
くぼみに光が反射して模様に立体感が生まれました。聖地な技を積み重ね、器全体に沿岸を施すのに一年もの歳月を費やしました。自然界に存在する美しい調和を作品で表現したい。その想いが日々の創作の原動力になっています。
この国の流れで基地の中で培われてきた美意識や自然の影響も大きいのですが、その美しさを感じて、それを自分でどうやったら表現できるかというふうに技術的なことを考えています。新しい心を巡らせたりとか、自分が表現したいものによって技術も変化してくるというのが僕のスタイルです。いろんなことを試して実験し、自分の表現したいことに結びつけるというような努力を日々しています。
今年、同じ近郊の部門で新人賞に輝いた作家がいます。二十七歳の若き近郊作家、藤川香生さんです。この春、金沢から京都へ移住し、自宅の工房で創作をしています。

受賞作「布目象嵌 五角鉢 涛」のモチーフは、金沢の海で見た豪華客船が雨の中、波を乗り越え前進する様を沿岸の技法で表現しています。船に見立てた五角形の八のイメージを形にするため、藤川さんは何度も試作を繰り返しました。
「こっちが船の前になって少し上げて、後ろはわかりやすいように、後ろはちょっとこうくぼませることで、船の進む方向をイメージしています。ただ、あんまり船ってわかると、それはちょっと面白くないかなと思っていて、やっぱりこの沿岸を見せたいので、できる限り単純な形状で、でも何かがわかるぐらいの、このギリギリのところを狙ってデザインしています。」
高校生の時、ふるさと熊本で伝統工芸の後継者育成教室に参加した藤川さんは、そこで布目沿岸という彫金の技に出会います。固い金属に模様を自由に描き出す技法に、藤川さんは目を見張りました。
「鉄の表面を刻んで、違う金属を入れて模様を作るというそのプロセスがもう意味が分からなくて、それがすごく面白くて、やっているうちにどんどんハマっていったって感じです。」
豪華客船の装飾に用いたのももちろん布目沿岸です。まず、幅九メートルの鋼を使って、鉄地の表面に縦横斜めに小さな溝を掘っていきます。一ミリの間に七本ほどの溝を彫り込み、細かい剣山のような下地を作ります。
続いて手にしたのが、鹿の角で作った鋼です。大波の形をした銀の薄板を小刻みに叩いて埋め込みます。弾力のある鹿の角を用いることで薄板が溝に入り込み、模様を定着させることができるのです。
「この布目というキャンパスを切ってしまえば、この範囲には何でも入れられるので、この板の表現であったり、線の表現であったり、粉であったり、こういったいろんなことができるので、イメージに一番近づけられる技法なんじゃないかなと思っています。布目沿岸をやっていて、そこから形、もっと造形だったり、そういう表現の選択肢を増やしたいと思って出てきたので、また戻って、僕があの頃始めた頃に作りたかった形を作れたんじゃないかなと思います。」
まだ見ぬ近郊の世界を求めて、藤川さんの旅は始まったばかりです。
独自のモチーフが光る作品は他にもあります。磁器の大鉢に映すのは、水面に漂う月の光。独特な幾何学模様は、配列や重ね方を変えたわずか五つのパターンで構成されています。五種類の金の上積みで消えゆく光をダイナミックなグラデーションで表現しました。

目を見張る不思議な模様は、赤土と池垣で囲まれた巨大な迷路がモチーフです。通常、色を隔てる銀線をギザギザに加工して模様に使いました。独自の技法を追求し、生み出した七宝焼きの新境地です。

緩やかな流線をたたえるのは、一木をくり抜いて作るくりものの作品です。モチーフは夕暮れの海を回遊するクジラで、形を引き立てるシンプルな木目を落ち着いた肌合いに仕上げました。一番の見どころは、上蓋とボディの合い口。湾曲しながらも寸分の狂いもなく重なる高い技術力は見事です。
次の受賞者に出会うため、金沢へ街中にある工房を坂本さんが訪ねました。「この辺のはずなんですが、こちらかな」と、意外な場所にたどり着きます。「ごめんください」「こんにちは、はじめまして。坂本と申します」と声をかけると、迎えてくれたのは木工作家の角間八海さんでした。
「こちらのクリーニング屋さんです」「そうですね、こちらですね。僕で三代目になります」「そうですか、じゃあ日中はお店に立たれているんですね」「お店に立って、それで仕事が終わって、夜作業をしていますね。」

受賞作は、褐色の色合いと緻密な木目が美しい十二角の木箱。幾年もの間、地中に埋もれていた貴重な古木神代杉を贅沢に使って切り出しています。目を引くのは、側面にはめ込まれた装飾透かし彫りと、奥に見える神代杉の繊細な木目が優美な調和を見せています。
角間さんが店を引き継いで十年、仕事柄大切にしてきた思いが創作にも影響していると言います。「仕事が中途半端だったら嫌なので、仕上げ方でもシワが残っていたら絶対にやっていますね。そこはきっちり仕上げる作品でもそういうところはあると思いますね。やっぱりちゃんとした作品を作りたいという、そういうのがつながってきていると思います。」
店の二階には、仕事が終われば毎日のようにこもる工房があります。「わ、ここが秘密の場所ですね。すごい木材がたくさんありますね。」琢磨さんは根源の専門学校で木工の基礎を学びました。卒業後、地元の木工職人に弟子入りし、技術を磨いてきました。
「木工っていう分野の中にも三つに分かれてまして、ろくろとくりもの、刺し物に分かれているんですけど、僕はその刺し物の技法で作品を作ったりしていますね。指物でまず大切なのは美しい箱を作ることだといいます。古くから釘など金物は一切使わずに板を組む多様な技が用いられてきました。」
「取れる取れるんですね」「ここはいいですか」「そうですね、ここが骨次っていう部分になりますね。この微妙な角度で接合部が斜めになる十二角の箱。受賞作の側面は雇いざね継ぎという技でつないでいます。およそ五ミリの厚みに対して幅十二ミリの溝を施します。溝を刻むのは、箱の内側より高い精度が求められます。」
水をぴったりに切り出した欅がつなぎを担います。「ここをはめつつ、それでここをこう折りつつ、ぎゅっきゅう」「そうですか、入った気持ちいいですね。」
自分で削ったかのような箱としての精度を極めた上で、いかに作品に個性を持たせるか。それが極端をくり抜いた透かし彫りによる装飾です。琢磨さんは過去にも二回、透かし彫りを施した作品を出品しています。
「すごい。しかし、受賞には至らず。この作品に関してはどのような評価を受けましたか?」「ちょっと機械的な感じがすると言われましたね。機械でやったんではないかって。そう言われるとそういう感じにも見えるかなと思うんですね。だから今回はメントリーとかして、機械的にならないように見せようかなと思って。」
三度目の挑戦となった今回、透かし彫りに改良を加えました。くり抜いたすべての縁に面取りを施したのです。削り出す面の幅にも変化をつけ、柔らかな表情を作り出しました。「こうやって面取りしたことで、やっぱり手でやった感が生まれてくると思います。」
確かにそうですね。この有機的な光の加減だったりとか、この工程を今日見せていただいて、ここまで本当に隅々まで血の通ったものなんだなぁと改めて実感しました。
木工の道で目指すところというのはどんなところなんでしょうか。「デザイン性がある箱を作ってはすごいと言われるよりも、その品がある、品格がある箱だなと思って見る人が思ってくれれば、僕はすごいいいなと思いますね。」
箱の魅力を引き立てるために自分の表現を添え、挑み続けることで見出した一つの到達点です。

緻密な技が光る受賞作が他にも。髪の毛ほどに細い金銭で描くのは、夜空に咲き誇る大輪の花火。線の太さや間隔を微妙に変えていくことで、花火の音やリズムまでもが表現されています。装飾を円形にそろえることで、四角い飾り箱に球体の花火を浮かび上がらせました。

重量感のある花入れに描かれた表情豊かな幾何学模様。重ね塗りした白と黒の化粧土を削ることで独特な風合いの染料を生み出しました。幾何学模様の重なりが色合いを変化させ、作品に奥行きを持たせています。

清涼感あふれる深いブルーの友禅、作者尾崎久野が自宅から見た多摩川の風景です。川を登る海水と下る淡水がぶつかり合う奇粋域。入り乱れる水の流れを、点で置いた糸目のりだけで表現したチャレンジ精神あふれる作品です。

漆黒のふたに表描いたのは、太陽が月に覆われた日食の瞬間。城花蒔絵を継承する家元、十六代目小原自己衛門の作品です。一子草原の白蒔絵法と色ぼかしを駆使して、太陽を縁取る炎の揺らぎを表現しました。

最後に紹介するのは、直径四十センチメートルを超えるふくよかな鼻かごです。蕾の中にニュッと詰まった花弁の重なりが、しなやかな竹ひごで表現されています。そこには、地区工芸の世界で造形美を模索する新たな試みがありました。
大木さん、よろしくお願いします。
「すいません、やってきたのは埼玉市の住宅街。日曜美術館の森本と申します。よろしくお願いします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。」
出迎えてくれたのは、地区工芸作家の大木敏恵さんです。
「ご自宅のこのダイニングで仕事をさせていただいて、生活スペースの奥にアトリエがあるんですね。」
大木さんは大学卒業後に故郷群馬の工房に入門し、地区工芸の人間国宝として活躍した飯塚小関西さんに指導を受けました。
「飯塚さんの言葉で印象に残っていることは、作品は創作をしなくちゃいけない人の真似じゃなくて、自分の表現をしなさいというふうに言われたことですね。」
その言葉を胸に近年取り組んでいるのが、竹ひごを組んで作る組物です。
「形が比較的自由にできるのが私は気に入って、よく組みの技法で作っています。側面は別に作って合体しています。」
大木さんはこれまで側面と底を別々に作ってきましたが、受賞作では一本の竹ひごでつながるように作ったといいます。
「一体感というんでしょうかね。そこから縁までつなぎ目のない、そういうまとまり感を出したかったので、長い紐を使って試してみました。」
「こんなに長いんですか?」
「そうですね、これを切らずに、この長さのままでいったんです。」
用意する竹ひごの長さはおよそ一五メートル。細い大きさのおからでは想像できないパワフルな作業です。
「これは本当に一本一本、手で作業していくんですよね。」
「全部竹のようにまっすぐと言いますけど、赤い部分が曲がっているんですね。」
「そうですね、まっすぐだけじゃなくて、節のところにうねりがあるんです。」
竹の持つ自然なゆがみも作品に活かします。厚みは一一ミリに揃え、百本もの竹ひごを作りました。
「ちょっといいですか?ちょっと怖いんですけど…あ、すごい、こんなに曲がるんですね。またすぐサッと戻る。このハリっていうんですかね、弾力がこの竹の一番の魅力かなと思います。」
いよいよ竹ひごに熱を加え、曲げていきます。大きく湾曲させながら、さらにひねりも加えます。
「すごいですね、こんなに曲がるんだ。」
今回初めて挑んだ長井武彦は、竹本来の力強さやしなやかさを改めて気づかせてくれたといいます。
「竹の特性をふんだんに生かすことで、これまでにない造形にたどり着きました。やっぱり竹を使う意味は、竹の美しさを生かさなければ、いくらその表現を頑張っても竹でやる意味がなくなってしまうと思うんですね。なので、自分の表現したいことと、竹の美しさを生かすことのバランスを取らないと、いい作品にならないかなと思います。」
技を極め、素材の限りない可能性を探求する作家たち。伝統工芸の舞台に新たな風をもたらすその挑戦は続きます。