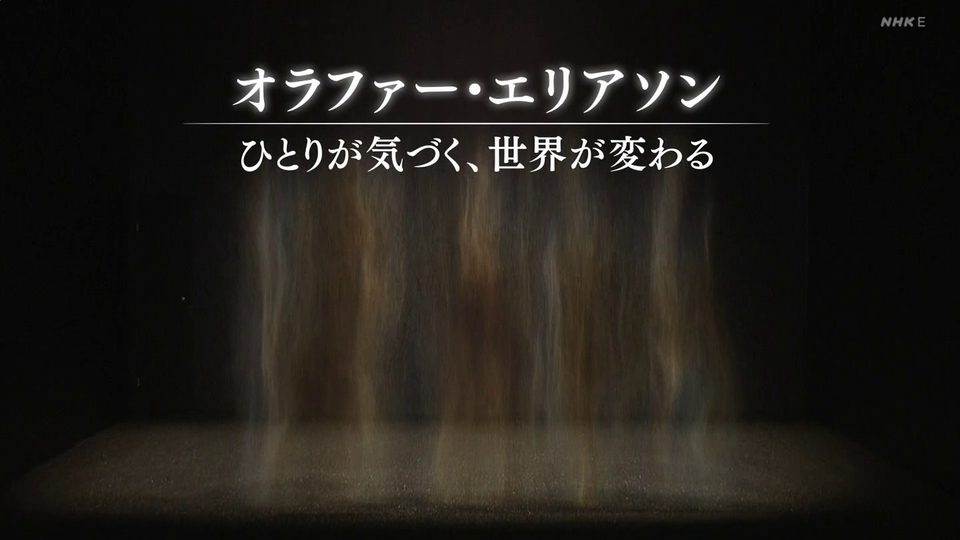知られざる花鳥画の天才・ 渡辺省亭 がついに登場!西洋的な写実と江戸の粋が融合した唯一無二の世界を展開した省亭。明治に初めてパリに渡った日本画家で、ドガら印象派の画家たちを魅了した。国内でも高い評価を得たが、画壇に属さず、弟子もとらず、市井の画家として孤高の生涯をつらぬいたため、いつしか忘れ去られた。生命感に満ちた傑作の数々を紹介しながら、渡辺省亭の高い観察眼と高度な技法の秘密、孤高の生き方に迫る。
放送:2021年5月9日
日曜美術館 「孤高の花鳥画家 渡辺省亭」
幾重にも花びらを重ねながら咲き誇る牡丹。
うっとりするほどに美しい色の移ろい。
そして確かな存在感。
鋭い眼光を放つ雉。
部分部分の羽の質感の違いまで伝わってくる脅威の描写力。
花や鳥を主題に描く花鳥画で数々の傑作を残した画家がいました。
渡辺省亭。
明治大正と活躍した日本画家で近年大きな注目を集めています。
省亭は日本画家として初めてパリに渡った人物。
この作品はある印象派の画家が省亭から送られ大切にしていたもの。
「全くヨーロッパの絵の描き方と違うわけでしょ。それでみんなすごく驚いたんだと思いますよ。もう拍手みたいな感じだったんじゃないかな」
さらに先生が描く鳥の正確さは鳥類学者も舌を巻くほど。
「省亭は鳥の体の構造をよく分かってたと思うんですね。ではその色とか形の正確性もそうなのでかなり観察してたと思うんですよ」
省亭の花や鳥は迎賓館・赤坂璃宮を飾る七宝にも息づいています。
しかし後年、省亭は画壇に属さず、弟子も取らず、市井の画家としての生き方を貫いたため次第に忘れ去られてしまいます。
孤高の天才画家・渡辺省亭の実像に迫ります。
日曜美術館です。
今日は明治から大正にかけて活躍した日本画家の渡辺省亭を取り上げます。
今ちょうど初めての回顧展が開かれています。
本当に花鳥の描写に驚きました。
あのすごいあの花が傷んだそれを今まで知らなかったらもう何で知らないことばっかりなんですね
今日はまずその省亭の花鳥画どんな世界なのかそこから見ていきます。
十分な余白を活かした画面。
その下半分にひときわ鮮やかな大輪の花。
淡いピンクの牡丹。
白い牡丹。
そこに蜜を吸いに来たクロアゲハ。
その鮮やかなコントラスト。
花弁には西洋の水彩画を思わせる絶妙なグラデーションが施され、花を立体的に浮かび上がらせます。
画面左には枯れた牡丹も描かれています。
抜け落ちたおしべはスローモーションのように落下していきます。
少し右に流れていくのは風に吹かれているからです。
洗練された画面と卓越した描写力。
従来の花鳥画にはない、省亭ならではの世界です。
長年省亭を研究してきた美術史家の山下裕二さんです。
「江戸時代以来の日本の絵画の描法ってのしっかり身につけた上で最初にヨーロッパに渡った人ですから、そこに迷うが的な表現も加味した自分の画風を作り上げた人なんですよね。もうこの時代の最高レベルの画業を持ってると思いますよ。僕は」
ではもう一枚。
春の野辺を描いた作品です。
少し散り始めた桜の下。
三羽の鳩が集まっています。
つくしにわらび。
そしてたんぽぽなどの草花が春の暖かさを感じさせます。
鳩は羽の色や体の向きを変えて、描き分けられています。
細かな筆を重ねて柔らかな羽毛や鳩の表情を繊細に表します。
輝く一瞬の命。
これぞ省亭の写実です。
渡辺省亭はこれほどの腕をどうやって身につけたのでしょうか。
省亭は幕末。
江戸の神田佐久間町の生まれ。
生粋の江戸っ子でした。
省亭が誕生した頃の江戸切絵図です。
この吉原というのが省亭の実家。
家業は札差で今で言う金融業でした。
すぐ近くに大きな飼鳥屋敷。
ここでは将軍の鷹のエサとなるスズメや鳩を飼っていました。
省亭は幼い頃から鳥たちを身近に感じて育ったと考えられます。
5~6歳の頃には絵を描くのが何よりの快楽だったと言います。
奉公先で給金が出るとすぐ絵草紙屋に走り、北斎や広重の浮世絵を買っては物置で模写していました。
そして16歳の時
日本画家の菊池容斎に入門します。
菊池容斎は歴史人物画で名をなした画家でした。
省亭は要塞の下でどのような教えを受けたのでしょうか。
「最初の三年間ぐらいは習字ばっかりやらされたってんですね。でもねそれが結果としてやっぱりすごく良かったんだと思う。書の素養がものすごく生きてますよ。それによって筆を完璧にコントロールできる技術を身に着けてるわけですね。徹底的に観察しろっていうことも教え込まれたみたいですね」
自然をよく観察し記憶し写生せよとの師の教えが省亭の写生の精神を育みました。
自らの修行時代を振り返った言葉が残されています。
画学に勉励すること昼夜寝食を忘れるくらい枕辺に紙筆を携えたままいつも寝るを知らず。
こうして省亭は腕を磨き、30代で自らの画風を確立。
そのスタイルは終生変わることはありませんでした。
花鳥画の集大成《十二ヶ月花鳥図》
四季折々の花と鳥を組み合わせ月ごとに表しています。
3月。
散りゆく桜が様々な技法を駆使して叙情的に描かれています。
悠然と歩む雉。
その緻密な描写からは体温まで伝わってきそうです。
6月。
刷毛で薄く描かれた雨は、湿った空気まで表し、紫陽花の青もわずかにくすんだように見えます。
身を縮め、雨に耐えるツバメの可憐な姿。
12月。
枯れつきた蓮。残った葉もすでに朽ちています。
その間泳ぐのは越冬する三羽の鴨です。
入念に仕上げたこうした作品を、省亭は月ごとに22枚描き分けたのです。
鳥類学者で鳥を書いた数多くの作品を見てきた高橋政雄さんは省亭の観察眼に驚かされるといいます。
「省亭を見てて思ってたのは、非常に鳥が好きなのはその通りだと思うんですけどその中でも熱狂的にこの人は好きなんだろうなと思うんですよ。これは当館の所蔵しているトラフズクの剥製ですけど、フクロウ類はネズミとか小動物を夜見つけて捕まえるので目が正面についていて立体視できるようになってます。耳というのはこの目の脇にあるんですけど、顔が丸くなっていてこれがパラボラアンテナの役割をして音を集約して、かすかな音も大きく聞こえるようにしてるんですね。そういう構造してるということは正面顔というのは平面的で書きやすいんですけど、
横から見るとお皿を横から描くようなもので画面をくちばしも全く見えなくなってしまって描きづらい絵になるんです。普通、画家の人はフクロウ類は真っ正面から描きますね。じゃあ俺は横から描くと、このトラフズクを横から描くんですよね」
これが省亭の描いた横向きのみみずく。
十二ヶ月花鳥図の一枚です。
「目とかくちばしが本当にちらっと見える。特徴的なこのパラボラアンテナのとこ持ってく質感が違うんですけど、今ちょっと目元が盛り上がってるような表現になってるんですけど、その辺をやっぱり本物を見て、ちゃんと構造を理解してしっかりと描いてるんでしょうね。ほかの画家を相当意識してたんじゃないかなと思うんですよね。描かなかったもの、描けなかったものを俺は描けるぞって結構挑戦状みたいに作品を残して言ったんじゃないかなあと、私はこの花鳥画を見ていて感じています」
ゲストのご紹介です。
省亭の展覧会を企画した古田亮さんです。よろしくお願いいたします。
今回の展覧会、どのくらいの準備に時間をかけられたんですか。
「三年ほど前から本格的に動き始めました。三年前にさかのぼるとまだ作品が揃うかどうかっていうぐらいに知られている作品は少なかったです。百とか150とかだったんですけれども、そこからいろんな人に教えてもらったり、個人人コレクターの存在を知ったりってどんどんどんどん重なって今では500を超えています」
「(リアルな描写は他の画家にない)「確かにその通りで、ちょっと触って質感。もふもふしたところ。そこがポイントです。その他の画家にはそういうことが江戸の流派の中にはなかった」
もふもふはそれまでない表現。
「浮世絵の中から出てきたような、わりと単純な形をしているわけなんですけれども、省亭が描くと、平面から平面ではなくて、最初からもう最初から3Dで観察している。さらに言うと表面はどういう質感で中はどういう構造になってるのかというところまで観察して写生する。というところがあって単純化されると今まさにそこにいるようなものになる」
そこにいて今にも身じろぎしそうな感じが本当にします。
「記憶だと思うんですよね。どうしても写真を撮る、カメラで一瞬をとらえるっていう事が思い浮かんでしまうけれども、そうではないんです。盛んに動いてるものを無理やり一瞬、シャッタースピード1/1000ぐらいで捉えようとしてるのではなくて、全部動きの中で観察した、それを絵にはどうしようかなっていう時に、横からでも描けるし、背中からでも僕には描けるよっていう」
1878年パリ。
この年、パリ万国博覧会が開催され日本も参加していました。
ある日、パリの日本美術愛好家が集まった席でのことでした。
一人の日本人画家が即興で絵を披露しその場に居合わせた参加者たちを驚かせたのです。
大体の輪郭線もないデッサンにも関わらず、明暗で光が描かれ、見事というしかない。毛先が潰れたカサカサの筆で本当にふわっとした羽毛の質感を表す。驚嘆するほどの技法を持つ。
その人物こそ渡辺省亭。
当時28歳。
日本画家として初めてヨーロッパへ渡ったのは省亭なのです。
この時に描いた作品が残されています。
素早い筆さばきで描かれた二羽の小鳥。
この絵はあるフランス人画家に贈ったものでした。
その人物とはドガース。
ドガースとは踊り子を書いた作品で知られる印象派の画家エドガー・ドガのこと。
省亭の筆を借りて自ら墨絵を描いたとも言われるドガは、終生この絵を手元に置きました。
省亭はパリ万博に作品を出品し銅杯を受賞しました。
それがこの作品。
《群鳩浴水盤ノ図》
浅草浅草寺境内の水盤に集まる鳩を描いたもの。
パリに渡る前の年。
27歳の作品です。
驚くべきは鳩の描写。
折り重なるように群れる鳩を輪郭線を用いることなく繊細な筆さばきで描き分けています。
印象派の父マネの弟子であるジュゼッペ・デミッティスが、この絵の筆法を研究するために購入。
しかしその技術の高さにも模写を諦めたという逸話が残されています。
その後アメリカのフリーア美術館に収蔵され、今では門外不出となっています。
また帰国後もロンドンで2度個展が開かれるなど省亭は海外で高く評価されました。
世界を魅了した省亭の花鳥画。
作品を模写することでその秘密を探ります。
「これがすべてを表していると思うのです」
日本画家で伝統絵画の技法の研究も行う向井大祐さんです。
二人の足が止まったのはこの作品。
ここで省亭が様々な線を用いていることに向井さんは注目しました。
「描いてる線の非常に有機的な線。くくってるわけじゃないことがよくわかりますよ。だからどうしてもその可能性もあるでしょ。下図を描いたらその下図の通りの輪郭線を用意するじゃないですか。それがラフと言うか、あったりなかったりとか全部の線が違うんだよね」
向井さんはこの横向きのみみずくの作品を模写することにしました。
枝をつかむがっしりとした脚。
柔らかな膨らみまで感じられる羽毛。
そして生き生きとした表情。
どのように描かれたのでしょうか。
作品は絹地に描かれたもの。
最初に下図と呼ばれる設計図を描き、絹に写し取って行きます。
ミミズクの部分。
まず白の胡粉で身体全体を塗って行きます。
「塗るんじゃなくて、割とこの羽毛の感じを意識しながら塗ってます」
次に胡粉の上に黄土色を塗り重ねます。
「本当に薄いですし、薄い絵の具の積み重ねですね」
乾かないうちに別の色を塗ることで色同士がにじみ、独特の風合いを帯びてくるといいます。
「陰影じゃなくて質感表現なんですね。今の段階でも影を描いてる訳じゃなくて、その中質感のものを絵具で描いている感じはするかなと思って」
省亭は西洋絵画のような陰影を使って立体的に描くのではなく色彩の塗り重ねによって質感をあらわしているというのです。
「筆の後でできる毛みたいなものと。最終的に自分でピッと入れる線みたいなものが、最初に混在するんで、そういう意味で線の質の幅が広い。といいますか、全部描いているんじゃなくて、途中途中できる痕跡をうまく残しているとこありますよね」
次に薄墨を加えさらに微妙な色の階調を作り出します。
そして細い筆で墨の線を入れる詰めの作業です。
「こういうとことか、ここしか入れないですね。この先は入れてないんですね。だからこの立体を陰影で表現するというよりは、線の最終的なしめの強弱で表現する。筆跡が筆跡じゃなくなるこの瞬間を楽しむというか。実際のみみずくの毛になる」
最後に目にハイライトを入れます。
「実際に描いてみてわかるのは、明暗ではないんてすね。陰影とか立体を表現してはいないんです。どっちかって言うとその質感を表現する中で身に迫ると言いますか、最初っからこのふわっとした毛の質感を付けつつ、その疎密のおかげでなんとなく立体も感じるっていう」
自在な筆さばきが生むリアルな質感表現で、世界を驚かせたのはこの省亭独自の技でした。
省亭独自の技ということで線ですか。
「線とともに省亭は筆を使ってるけれども何層か順番を非常に薄いんですよ。一つ一つの層が。油絵をちょっと想像するとどんどん塗り重ねていくとどんどん厚くなる。一見そういう風に見えるんですけどところがあの本当に薄い」
当時のパリの印象派の人達が活躍している時代ですよね。で日本の画家の作品だって見たことがなかったわけじゃないですよね。そしてそんなにびっくりしたんですか。
「一番驚いたのは、筆を実際に使っているところを見ることができたからです。浮世絵は版画ではたくさん見ているとは思いますが、構図なりは敏感に理解りしてみようと思うけれども、筆使いっていうのは全くその西洋の人たちの感覚とは違うものだった」
省亭はどのくらいパリに滞在したんですか
「はっきりしたことがわからないのですけれど、少なくとも一年はいたと思います」
何してたんですか。
「今美術館には行ったでしょうけども、誰かに学ぶとかそういった形跡はないんですね」
フランスに行って一年ぐらいいて、そのこと自体が彼の絵の質を変えたか。
「証拠になるものがなくて、絵だけを比べてみると、パリに行く前にこれだけのテクニックを持っていますので、更に何かをひっくり返すようなことではなかった」
パリに行けたのだから勉強に励んだというような痕跡はないんですか。
「まだ二十代後半ですから、認めてもらおうとか何かを持って帰ろうとかそういう若さだったと思うんですが、実際にはどうもそれがはっきりしません。だから省亭の言葉を拾ってみても海外にも欧米に人気がでるように描いたわけではなさそう。一貫して自分のこれが最高だと思うような描き方を追求していた。それが結果として印象派の画家たちも驚かせたし、それだけではなくて海外の多くの数の美術館が所蔵するというところまでは認められていたってことですね」
人生の大半をここ浅草や隅田川近辺で過ごした省亭。
これほどの画かが後に忘れられることになるのはその生き方と関係がありました。
明治31年。
日本美術院が創設された際、48歳の省亭は参加を要請されますが断っています。
この頃から省亭は美術団体に属さず、展覧会や博覧会にもほとんど出品しなくなりました。
画壇を遠ざけ、自分の作品を心から求める周囲の人たちのためにだけ描いたのです。
屏風などこれみよがしな大型作品は避け、掛け軸を中心に引きも切らない注文に応じました。
「自分の実力にはもう絶対の自信があって、求められれば注文に応じて描いてお金をもらう。それで生活できてるから別に自分が権威になりたいなんていう気持ちはなかったんだと思いますよ」
東京元赤坂にある迎賓館。
赤坂離宮2009年に法に指定されています。
明治42年東宮御所として誕生した日本で唯一のネオバロック様式の西洋宮殿。
ここで省亭の花鳥を見ることができます。
晩餐会などが催される花鳥の間。
内装は木曽の木材で板張りされ深い森のようです。
壁を飾るのは30枚の七宝。
四季の草花の中で戯れる鳥たちの姿が描かれています。
省亭の原画を濤川惣助が卓越した技術で七宝にしたものです
墨をぼかしたかのような檜。
アカゲラの羽毛は筆で描いたかのよう。
柳の枝に止まるのがヤマセミ。
細い枝に捕まるのがカワセミです。
飛ぶ宝石とも称される翡翠のような翡翠の青の羽が繊細なグラデーションで表されています。
これらを七宝で表すのは非常に困難なことです。
実は省亭と濤川は日本画の世界を七宝に移す試みを続けてきました。
その関係はこの時までに四半世紀に及んでいます。
一般的な七宝焼きでは銅の下地に下絵を描き、
銀などの薄い金属の線を張って仕切りを作ります。
その中にガラス質の釉薬で色を施し、焼き上げます。
金属の線を使うことから有線七宝と呼ばれます。
これに対して省亭と濤川が開発したのは無線七宝。
有線七宝とは違い釉薬をさした後、金属線を外し釉薬を混ぜ合わせて調整します。
焼き上がりを想定して釉薬を扱う高度な技法です。
省亭の原画が残されています。
いつにも増して密度の濃い描写をする省亭。
入念な原画を用意しました。
濤河も省亭の心意気に見事に応じてみせたことがわかります。
省亭の原画から濤河の七宝へ。
一分の隙もない30作が完成しました。
消して退色することのない七宝にうつされての花鳥です。
「これが国家的プロジェクトだからものすごい意気込んでとかそういう感じじゃないんだな。この人は。江戸っ子たるものそんなお上の仕事でね、へーこらなんかしないようん女将の仕事もね下町の旦那衆の仕事6年生にとってはね意識としては一緒ですよ。ただ画料の高いか安いかによって多少力込めたり手を抜いたりはした人だと思うけどね」
省亭は終生写生をし、作品を作り続けました。
大正七年。
68歳でその生涯を閉じます。
その後少なからの省亭作品が関東大震災や戦争で失われました。
省亭の絶筆です。
たんぽぽ家蓮華桜が咲く春の野辺
その上を飛び交う二匹の蝶。
この蝶だけが未完成のまま残されていました。
「お上だけが対象じゃなくて、誰に対しても、周りの画家たちに対しても、賞をもらって喜んでるというようなそういう制度的な話ですよね。近代が作っていった、そうすれば認められた人だとか。そうじゃないと。知られたいとか賞取りたいとかとそういうこととは違う作品の、一点一点のクオリティで物を追求した人」
名声には興味がなさそうですね。
「弟子もいないんですね。弟子を取って大家と言われるというような人も多かったわけなんですけれども、それに対して省亭の場合は一人で、弟子はおろかアシスタントもいない。結果としてはそのことによって伝えていく事が無くなってしまいましたよね。描き方もそうだし、活躍の実態というのもどんどん記憶が薄れていってしまう」
省亭の絵がほしいって人達は引きも切らず。
「浅草というローカルなその地を離れなかった。なのパリには行きましたけれども国内旅行は一切しなかった。注文に応じてひたすら絵を描いた。後半生は徹していたわけなんですけれども、ある意味では東京ではあるけれども、地方画家なのかもしれない。ところがそれがなぜか同時に欧米で認められるというグローバルな一面も一方で持っているというのが非常に不思議でもありますよね。一見平凡とは言わないけども当たり前の世界を描き続けた人かもしれませんよね。若冲なり江戸の奇想派という人たちと比べれば、同じ描き方でもこうすごく変わったいたんと言われたりエキセントリックだと言われるようなところを見せようとしてるわけですけども、一方で省亭の場合は特別なものというよりも当たり前のもの、日常的なものをそれをこういかに自然に描くかっていうところですので、もしかしたらつまらなく見えるんじゃないかなっていう不安もあったわけですけども、ところがむしろ当たり前の事っていうのがとても大事な時代。省亭の仕事のいいところを展覧会で見えてくるのであれば良かったなと思ってます」
今日はどうもありがとうございました。