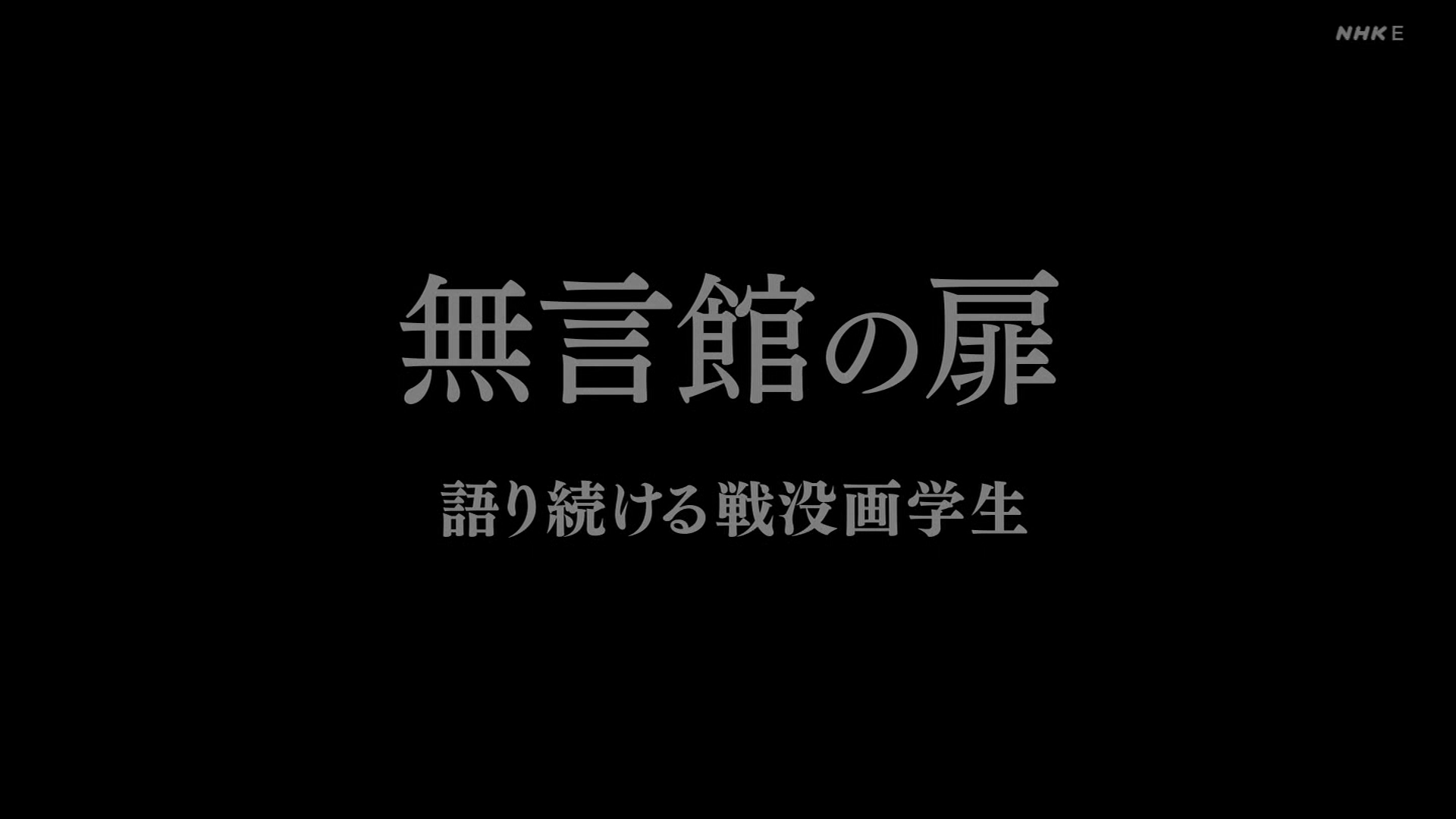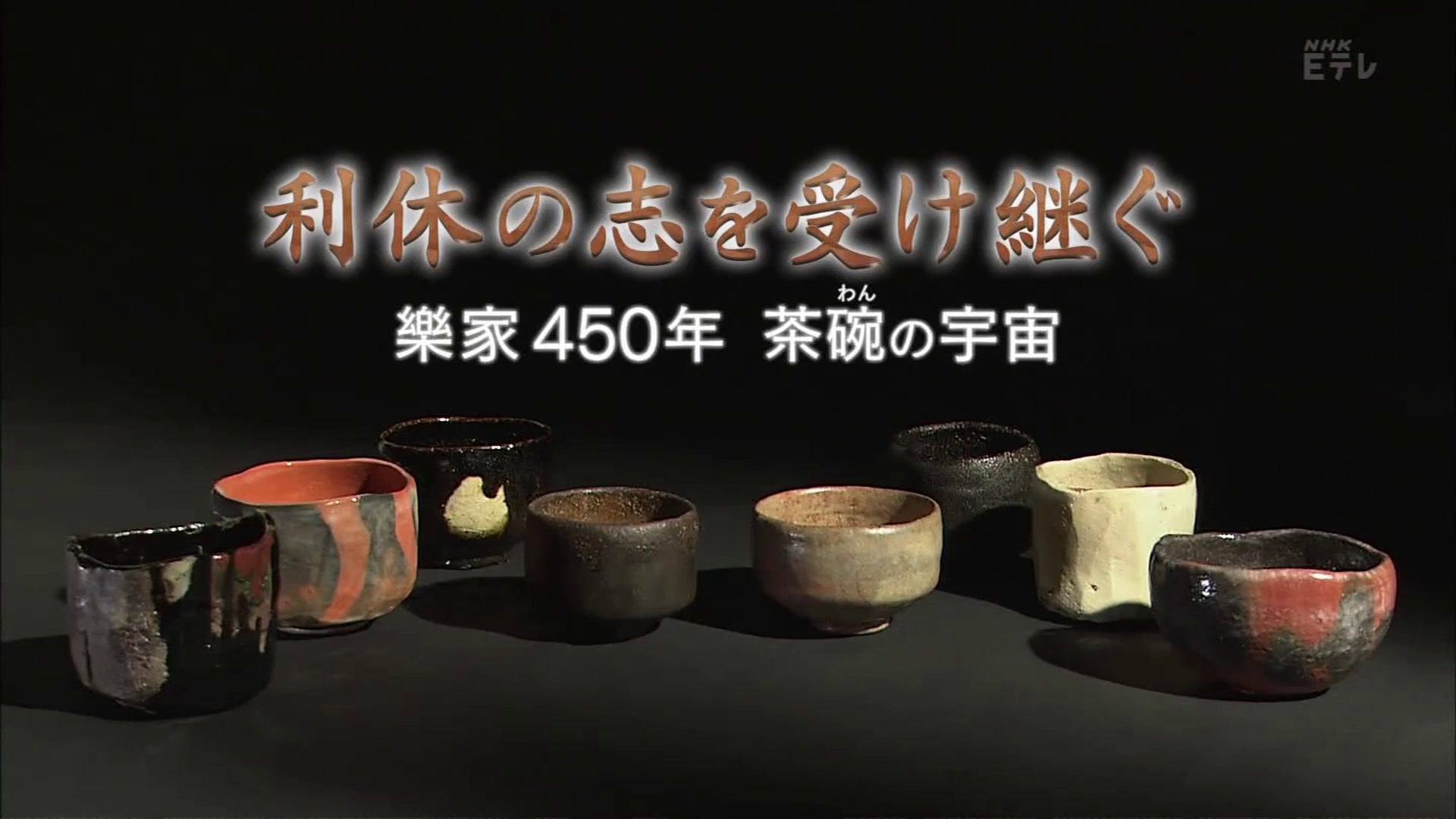700点を超える戦没画学生の遺作を所蔵する『無言館』。館長窪島誠一郎(78)が収集をはじめたのは、戦争の記憶の風化が叫ばれた戦後50年1995年のことだった。半世紀の時を越え、若き画家たちの作品と出会った瞬間の衝撃。そこには50年の歳月の重みがあった。絵の中に込められた“熱き思い”と半世紀という時間の中で確実に劣化していく絵の運命。そのリアルを伝えるか。修復家山領まりと窪島誠一郎の戦いを見つめる。
【司会】小野正嗣,柴田祐規子
放送:2020年8月9日
日曜美術館 「無言館の扉 語り続ける戦没画学生」

長野県上田市。
坂道を上ると小さな美術館があります。
戦後75年の夏、初めて訪ねます。
無言館の扉を開けると不思議な空気に包まれました。
無言館には戦没画学生の絵とともに、出征の時の写真や資料も展示されています。
「22歳ですよ。皆若くして亡くなられて。辛い」
1938年に東京美術学校に入学した学生たち。
彼らの多くは戦場に駆り出され戦死しています。
野見山暁治も満州に出征しましたが、病気となり療養のため帰国。
死を免れました。
戦後は画家として一線で活躍し文化勲章も受章しています。
無言館の歴史は野見山暁治と窪島誠一郎の出会いから始まりました。
野見山は戦後の人生の中で大きな忘れ物をしたと語っています。
当時、窪島は若くして亡くなった夭折画家の絵を集めたデッサン館を開いていました。
「今から43年前ですかね。まだ僕は引き算すると33歳、34歳ですかね。信濃デッサン館という美術館をこの土地に作ったんですよ。その時野見山先生が窪ちゃん。早死にした絵描きが好きなんだろう。僕の仲間にもね戦争から帰ってきたらさぞ才能を発揮したろうなっていう仲間がたくさん死んだ。戦後50年に近づいてきたらお父さんお母さんはなかろう。あるいはご親族の方もだんだん少なくなってくる。あいつらの絵がどうなってるかと思うとね。この世から消えていってしまうかと思うと残念なんだよとおっしゃった。それが発火点。絵描きは絵さえ残ればまだ死んでない。この世から彼らの絵がなくなったときはじめて彼は生きていた存在そのものがなくなる。間に合うんだったら今から集めたいと思った」
戦争は遠い過去となっても、遺族は画学生たちの遺作を大切に守っていました。
何かに駆り立てられるような旅が続きます。
屋根裏や押入れからひび割れ傷ついた作品が現れると、止まっていた時間が眠りから覚め動き出すようでした。
声も出せずに凝視する瞬間。
「大げさな言い方すると、自分がその絵を発見したっていうのは、その天井裏にあった絵に僕が発見されたようなもの。彼らの絵は、そう生きてきたお前はどういう生き方をしてきたんだっていう、なんか根源的な問いかけを持った気がします」
無言館の絵には戦争そのものは描かれていません。
画学生は死を覚悟し、自分が一番大切なものを描きました。
「きっとご自身のおばあ様ですね。これから戦争に行かなくてはいけない人が、何を絵に描くかっていう時に、自分のおばあちゃんの絵を描いた。蜂谷清さんにとっておばあちゃんはとても大切な人だったんだろうなと」
絵には祖母が幼い清をおんぶする時、羽織っていた袢纏が描かれています。
「おばあちゃんは少し遠いまなざしですが、蜂谷清さんを見てる。あの優しい眼差しなんだと思います」
1943年。蜂谷清は召集令状受け取り祖母のなつを描きました。
出世して2年。フィリピンレイテ島で戦死。22歳でした。
かわいがっていた四つ違いの妹。
「清楚な感じ。美しいまなざし。悲しい感じがします」
太田章は友禅職人の家に生まれ、父の期待を一身に受けて育ちました。
東京美術学校の日本画家で学んでいました。
章は満州で戦死。
23歳でした。
「優しい絵ですね。ご家族の団らん。
多分ご本人でしょうね。絵を描くと普通、描いてる人と家族と一緒の空間にはいないわけですけど、描いてる自分もその中に描くことによってご自身の大切な家族の中に居たかったということでしょうかね」
伊澤洋は美術学校在学中に召集令状を受けます。
満州、ニューギニアと転戦し26歳で戦死しました。
貧しい農家に生まれた洋は入隊する前日、家族への贈り物としてこの絵を描きました。
両親は大切にしていた庭のケヤキを切り学費に宛ててくれました。
綺麗な着物を着た両親。
果物と紅茶カップが並ぶ食卓。
この絵に描かれた暮らしぶりは現実ではなく、博の理想が描かれたものでした。
「佐久間修さん。愛する妻、奥様の絵を描かれたのですね」
佐久間修は周囲の反対の中で静子と結婚しました。
1939年に東京美術学校を卒業。
勤労動員先で空襲に遭い亡くなりました。
妻を描いたデッサン。
若き特攻兵を描いた飛行兵立像。
大貝彌太郎は卒業後鹿児島で教師をしながら出撃前の学徒兵を描きました。
「すごく損傷している絵ですね」
死を覚悟した若者。
戦後の歳月の中で無惨に傷ついた絵そのものが戦争の残酷さを訴えかけているようです。
戦争が終わって75年。
時代は足早で立ち去り、止まることがありません。
今も無言館の坂を登り、画学生の遺作を運び込む家族がいます。
一人娘だった原昌子さんが夫と共に兵庫県宝塚市から信州にやってきました。
「この画学生さんとの縁は」「彼女の父親です」
「この三点だけを遺しておこうと思って置いていたんですけれど、80近くなって先が心細くなってくるとお仲間の中にに置いていただく方が幸せかなって、主人と話し合って・・」
絵とともに父の遺書も持ってきました。
お父様は天皇陛下のために死ぬのですから
これが描いてあるのが私にはずいぶん引っかかりました。
悲しんではいけません。
これがずいぶん引っかかりました。
昌子ちゃんへ。お父様は天皇陛下のために死ぬのですから少しも悲しんではいけません。昌子が大人になって立派になるのをいつもお父様は見ていてあげますよ。お父様が昌子のそばにいなくても、お母様の言いつけをよく聞いて良い子でいるのですよ。
お父様は昌子が大好き。
「ちょっと普段ねあのご案内はあまりしてないんですけど、たまにご遺族を見せに行くのです。収蔵庫。飾り切れない絵が収蔵されている”時の蔵”といいます。
専門の方に作って頂いて貧乏美術館の割には設備をしっかりしてある。
絵を大事にしてある。普段は飾れない絵いはねここに。修復の待合室みたいにこれから修復していただこうかという絵もある」
全体で何点ぐらいあるんですか。
「600点ありますね。資料を全部含めてですね。
この絵は特攻隊で16で亡くなった画家学生。石井正夫っていう。修復したいんですけどね。軍艦を作ってんですよ。翌年彼は亡くなるんですけど」
この少年とそんな変わらないですよね。10いくつに見えますよ。
「早く修復して、なんとかスペース探して飾りたいなと思ってるんですけどね」
ご家族がずっと大切に持っていた。
「僕は駅伝で言えばね第二走者です。戦後50年。ご遺族が守ってきたのが50年という第一走者。そして今戦後75年ですか。残りの今25年を僕が走っている。実はねもう一つ見てもらいたいものがあったのはちょっと不思議な感じの絵なんですが、
この絵は大江正美と言う独学で絵を勉強した男の《白い家》という非常に暗い絵。あの絵の下にもう一つ絵がしまい込まれてたのがこの絵なんですね。その1枚目の下にこの絵があった。2枚。
それは非常に対照的な絵でね。
非常に暗い鬱の絵がこんなシュールな絵を描いていたって言うことがわからなくてね。修復の先生の所を預けしたら2枚絵はあるわよって言う連絡あって、不思議な出会いでしたね」
日本の絵画修復の先駆者山嶺まりさんが主催するアトリエ山領。
時の蔵に保管されている傷んだ絵はここで修復されています。
絵も一つの物ですから、時間とともに劣化していきます。
遺族から手渡された絵の具は剥落や亀裂が目立ち傷ついていました。
その損傷の修復するのか試行錯誤が続きました。
「こういう亀裂が結構。あんまり目立ってはないんですけど亀裂があって隙間が空いてたので、そういうところには膠をさしてこれ以上浮き上がってきたりめくれ上がってこないように接着の強化をまず最初に行いました。
黒っぽいとこについた白い汚れが染み付いちゃって
白っぽい中雨だれのように縦に垂れたような汚れが全体的に。汚れた水とかっていうものじゃなく、ふんっていう感じがものすごくリアルにそういうのが厭な感じがしたのでそれは丁寧に水で取っていきました」
山領まりさんは無言館の絵を守ってきた中心人物です。
損傷をどう扱うべきか。
一般の絵画とは違う独自の方法を模索しました。
最初に手がけた絵の調査票です。
患者のカルテのように絵の状態を記し、写真を撮り、記録を残します。
戦争から半世紀。
既に遺作は無残に傷ついていました。
修復を終え現在無言館で展示されている《編み物する婦人》
「それまではその絵が描かれた当初の状態に近く戻しえないけれども、近づける努力をするのが修復だって考えていたので、なだらかにしたほうがいいんじゃないかなと言って、非常に似た色を作って、少しずつ周りを埋めたんですね。そして見たところ、ものすごくわざとらしくて、作品を見やすくするどころか、邪魔なものを入れることになるんじゃないかって相談して、みんなとまたもう一度そこの絵の具をとって、残っている非常に鋭角的な欠損のままにしたんです。だから絵が傷んでくるっていう自然の法則みたいな、色々な力が働いてる。その姿なので、中途半端に手を入れて介入するっていうことは本当にその絵にとって命を奪うような感じを受けたので、その時に分かりましたね」
入り口に飾られ、無言館を象徴する《飛行兵立像》の調査票です。
特別に損傷が激しい作品でした。
遺族は絵を木枠から外して丸めて保管していました。
「病院で重症患者を受付た時と同じなんじゃないかしら。とにかく必要なことをやるしかない。だから落ちそうな所から落ちないように止めて接着した。損傷したものをそのままの形で止めるなら、そこには損傷そのものも尊重しなきゃいけないってことが本当によくわかる。あの絵に限ってもしかしたら描かれた当初よりも今の方が力があるのかもしれない」
損傷も絵が得てきた時間として尊重する。
剥落は埋めず、亀裂や折れはこれ以上悪くならないよう補修する。
遺族から手渡されたその時の感動を止めて未来へ手渡す。
修復が終わった一枚の裸婦像。
「よく直せましたね。この変形さまで」
「ここからだとわかりにくいですけど、この真ん中の部分は糸を後ろから足して、補強を行った。折れが強い部分ですね。
この部分がその強い亀裂のある所。糸が弱って裂けになる可能性がありましたので一本ずつ交互に長さの違う糸を接着してます」
修復を終え展示されている《霜子》。
この絵には切ない別れの物語が潜んでいます。
中村萬平は1941年の春、東京美術学校を首席で卒業しました。
自由闊達で明るい性格の萬平は学生の間でもリーダー的な存在で学生生活をエンジョイしました。
萬平はモデルだった霜子と恋におち、時代の重圧をはねのけるように結婚します。
召集令状を受け死を覚悟して一筆ごとに愛を込め描きました。
萬平の出征写真。
霜子には新しい命が宿っていました
夫を満州に見送り出産しますが、産後の肥立ちが悪く帰らぬ人となりました。
萬平は大陸の前線で長男の誕生と霜子の死を知らされます。
月となった霜子が会いに来たと両親への手紙に書きました。
そして1年後、萬平も26歳で戦死。
入口を入って左と右。
霜子と向き合うようなもう一枚の裸婦像。
モデルの横顔は真剣そのもので、描き手もモデルも緊張で固くなっているようです。
描いたのは万平より1年下で学んだ日高安典。
鹿児島県種子島の出身。
家族の期待を背負い上野の学校に通っていました。
卒業の翌年に召集令状が届き、満州へ出征しました。
上官に認められ軍務傍ら特別に絵を描くことを許されていました。
内モンゴルの大草原を描いた風景画です。
この絵も無言館に掲げられています。
1945年4月。安典は27歳で戦死しました。
無言館が開館して2年後の夏。
無言館には来館者が自由に感想を記すノートが置かれています。
その中に安典の裸婦像をめぐる思わぬ言葉が書かれていました。
「感想文ノートっていうノートがある。そこに安典さん。あなたとあなたの絵に会いにきましたという文章が載っていたのです。モデルを務めたこの女性のテンションをいくらか手を入れてご本人に迷惑がかからない程度に文章にいたしました。
安売りさんへ。安宅さん。日高安典さん。私来ました。とうとうここへ来ました。とうとう今日。あなたの絵に会いにこの美術館にやってきたんです。私もうこんなおばあちゃんになってしまったんですよ。だってもう50年も昔のことなんですもの。安典さんに得を描いてもらったのはあれはまだ戦争が激しくなっていなかった頃でした。安典さんは東京美術学校の詰め襟の服を着て、私の代沢のアパートによく訪ねてきてくれましたね。私は洋裁学校の事務をしていましたが、知人に紹介されて美術学校のモデルのアルバイトに行っていたのでした。あの頃はまだ遠い外国で日本の兵隊さんがたくさん戦死しているだなんていう意識がまるでなくて、毎日毎日私たちは楽しい青春の中におりました。安典さん。あの小雨の降る下北沢の駅で、勤めから帰る私を、傘を持って迎えに来てくれたあなたの姿を今でも忘れていませんよ。やすのりさん私覚えているんです。これを描いてくださった日のことを。初めて裸のモデルを務めた私が、緊張にブルブルと震えて、とうとうしゃがみこんでしまうと、僕が一人前に絵描きになるためには一人前のモデルがいないとダメなんだと。私の肩の絵の具だらけの手で抱いてくれましたね。なんだか私涙が出て、涙が出。けれど安典さんの真剣な目を見てまた気を取り直してポーズを取りました。あの頃すでに安典さんはどこかで自分の運命を感じているようでした。今しか自分には時間が与えられていない。今しかあなたを描く時間が与えられていないと、それはそれは真剣な目で絵筆を動かしていましたもの。
それがそれがこの二十歳の私を書いた安典さんの絵でした。そして安典さんは昭和19年夏、出陣学徒としない満州に出征して行きました。できることなら。できることなら、生きて帰って君を描きたいと言いながら。それから50年。それはそれは本当にあっという間の歳月でした。世の中もすっかり変わっちゃって。戦争もずいぶん昔のことになりました。安典さん。私こんなおばあちゃんになるまでとうとう結婚もしなかったんですよ。一生懸命生きてきたんですよ。安典さん。日高安森さん。あなたが私を描いてくれたあの夏。あの夏は私の心の中で、今もあの夏のままなんです」
「戦争ということを伝える同時にあの戦争というあの時代の中でもね、今の彼らと全く変わらない青春があったわけですね。じゃあこの画学生たちは本来。単に、ただ単に戦争犠牲者という館に押し込めておいて、この絵描きたちそのものがやっぱり果たしてちゃんと遇されていると言えるんだろうかっていう疑問があったね。彼らは一番喜ぶのは、やっぱり自分が何を描こうとしてたか。そして究極の、後一週間しか生きてられない。戦争に行かなきゃいけないって言った時に、絵を描くということを持っている幸福。これを伝えるとしたら、戦争を伝えることにあまりこだわっちゃいけない。今生きてるサッカーやったり野球行ったりして燃えてる彼、彼女たちにこそ見てもらうべきじゃないか。簡単に言えば君の命は何のためにあるの。だって、明日生きたい。絵を描きたいと言っていながら生きられなかった人の分を君は俺も生きてるんだ。その時間をどう使えばいいか。そこがすべてじゃないかな」
この人達はやっぱり戦争の中に生きてたけど描くことに喜びを感じたわけですよね。
「ましてやあの時代。絵を描くということ自体が非国民扱いされてた時代ですから、もう飛び抜けたイケメンであり飛びぬけたセンスの持ち主の若者たちなんですよ。決してめそめそして涙流しながら絵なんか描いちゃいないんです。大好きな女性の裸を直視して、一日10時間を費やして戦地に行った。あの濃密な時間っていうのを僕は芸術の根源であると同時に人間が生きていくことに一番尊い時間だった」
アトリエ山領へ毎年10点を超える傷ついた絵が運ばれてきます。
時間とともに進む損傷との戦いは終わることはありません。
戦争で画学生の命は断ち切られました。
しかし作品だけは保存し、未来へ伝えたい。
「これはあかん手強いよ」
忍耐強く、誠実な仕事が続きます。
「どういう形で後輩たちに仕事で渡して行くかっていうのは私は半ばに見えてきて希望を持っています」