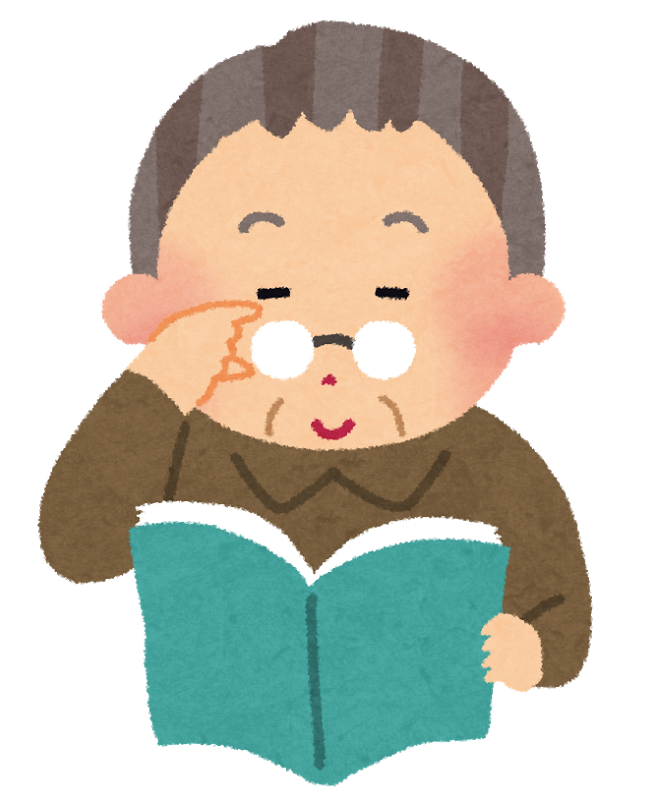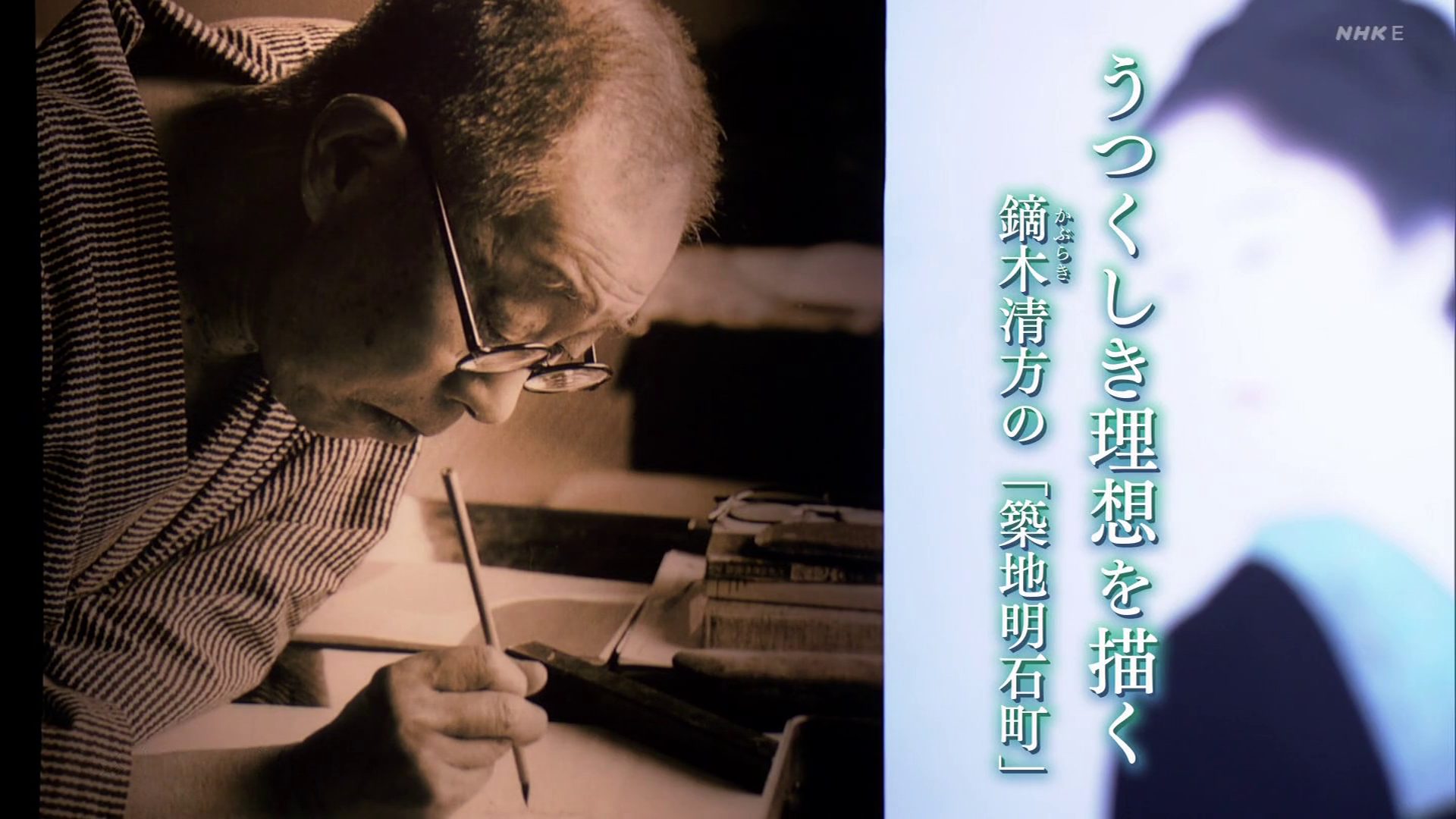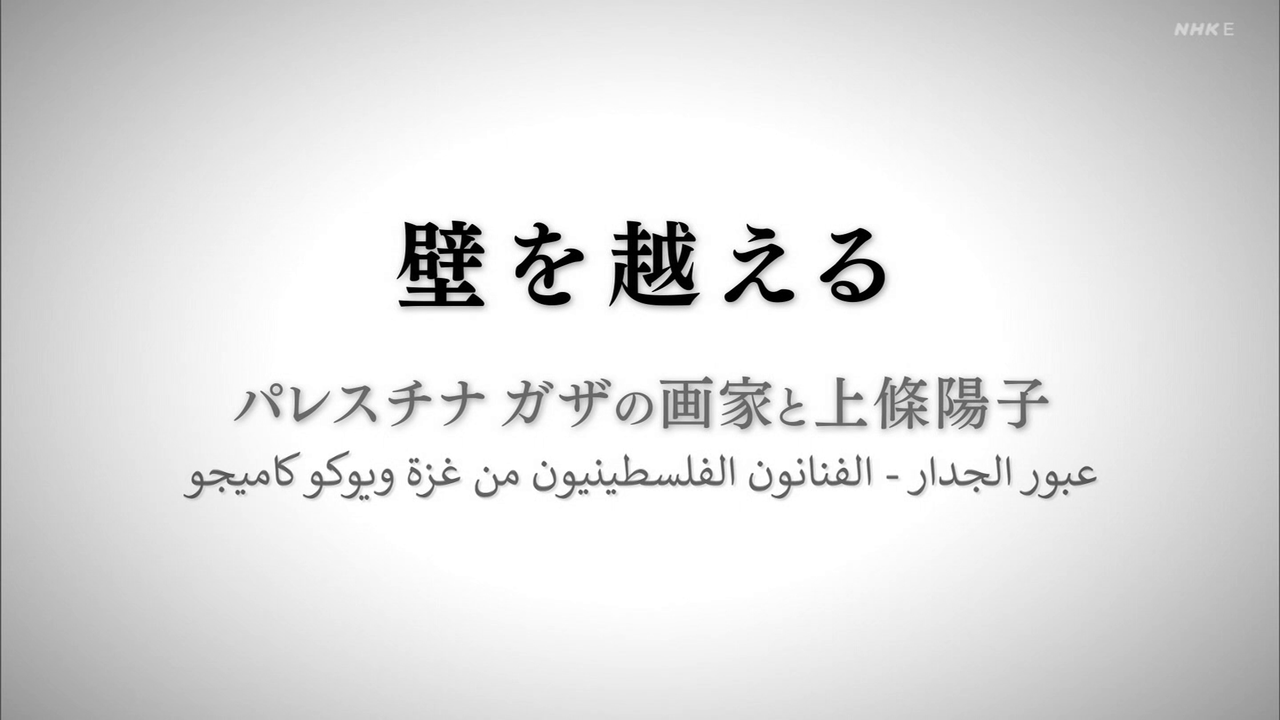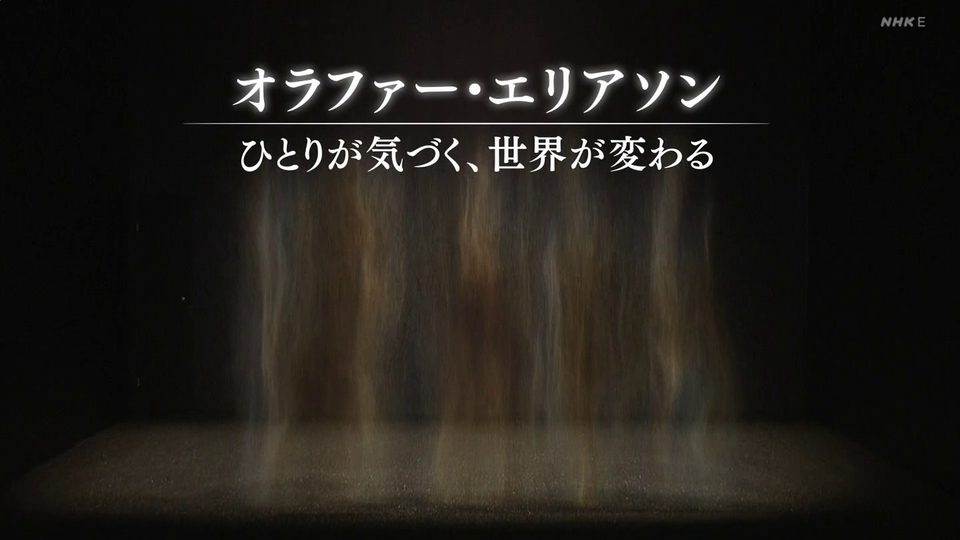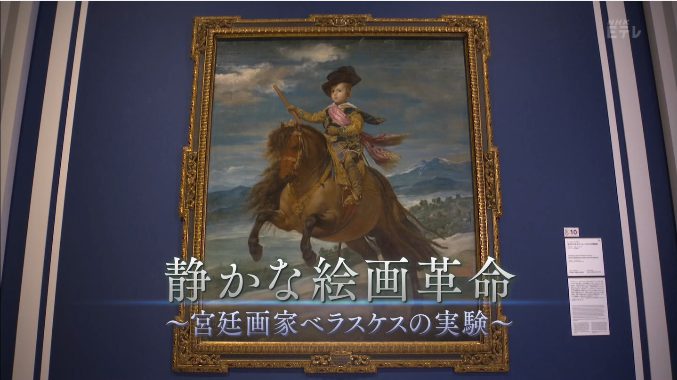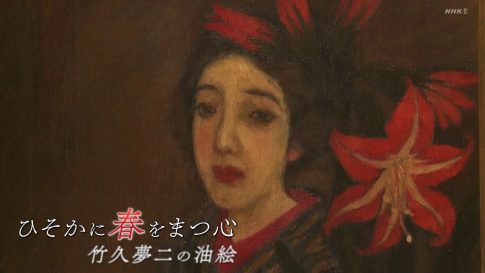885。現在、 国宝 に指定される美術工芸品の件数。そのうち、200件を越える国宝が集結するぜいたく極まる展覧会。縄文から近世まで日本の悠久の歴史がそこにある!
日本最古の国宝「火炎型土器」、「天橋立図」「秋冬山水図」など雪舟の水墨画6点、そして中世に生きた人々の抱いた恐怖を形にした「地獄草子」、さらには京都・龍光院所蔵の茶碗(わん)「曜変天目」。そのほか合わせて200件以上の国宝が集結する。舞台は京都国立博物館。一番新しく国宝に指定された「大日如来座像」「不動明王座像」から番組はスタート。日本の至高の美の歴史を味わい尽くす、45分。
放送日 2017年10月22日
日曜美術館「国宝を楽しむ」
新たに国宝になったのが大阪府河内長野市にある真言宗のお寺、
金剛寺の大日如来坐像です。
金剛寺のお堂は平安時代の終わりころ、1178年に建てられたという記録があります。
この像は堂と同じ時期に造られたと考えられます。
定朝の弟子たちが3つの工房に分かれました。運慶、快慶が属する慶派もそのひとつです。ほかに院派、円派があります。
この大日如来坐像は貴族の注文で造られたので、この3つの工房のどれかが造ったことは間違(まちが)いありません。
像の背後に立っているものを光背と呼びます。
像が発する光を表現したものです。
良く見ると小さな仏像が30体以上も付いています。
この小像は鎌倉時代に造られたものです。
こちらも新たに国宝になった不動明王座像です。
背後にある炎の一つ一つが不死鳥のような炎のように見えます。
平安のものに比べると顔の表情に人間らしい感情が現れています。
国宝とはどのような条件で認定されるのでしょうか。
「美しさや歴史的な意味合いというものは指定の重要なところとなっていますが、それに加えて、唯一無二の造形と卓越した技術というものも加えられて指定に至っているというものであります」
考古
縄文の美を代表する4点。縄文時代の国宝が4つ揃うのは今回が初めてです。
日本最古の国宝がこちら。深鉢形土器。火焔型土器とも呼ばれています。
その装飾の豊かさから祭りなどの時使われたと考えられています。
「鶏の頭に近いと言われていますが、何をかたどったのかということは未だに分かっていません」
考古の国宝を楽しむためのキーワードとは
「謎の部分との対話があるのではないかと思います。われわれがこうではないかと思ったことをぶつけることで自然と答えを戻してくれる。土の中で語らなかったことを雄弁に語ってくれるのではないかと思います」
国宝「土偶」(縄文のビーナス)尖石縄文考古館
長野県にある棚畑遺跡は、米沢(よねざわ)埴原田(はいばらだ)の工業団地の造成に伴い、昭和61年に発掘された、市内でも最大規模の遺跡です。この土偶もその広場の中の土坑と呼ばれる小さな穴の中に横たわるように埋められていました。
全体像は下方に重心がある安定した立像形で、全長は27センチメートル、重量は2.14キログラムあります。
頭は頂部が平らに作られ、円形の渦巻き文が見られることから、帽子を被っている姿とも髪型であるとも言われています。文様はこの頭部以外には見られません。
顔はハート形のお面を被ったような形をしています。切れ長のつり上がった目や、尖った鼻に針で刺したような小さな穴、小さなおちょぼ口などは、八ヶ岳山麓の縄文時代中期の土偶に特有の顔をもっています。また,耳にはイヤリングをつけたかと思われる小さな穴があけられています。
腕は左右に広げられて手などは省略されています。また、胸は小さくつまみ出されたようにつけられているだけですが、その下に続くお腹とお尻は大きく張り出しており、妊娠した女性の様子をよく表しています。
この土偶は、八ヶ岳山麓の土偶の特徴と造形美を合わせ持つことや、当時の精神文化を考えるためにも貴重な学術資料であることから、平成7年(1995年)6月15日に縄文時代の遺跡から見つかったもののなかではじめて国宝に指定されました。
国宝「土偶」(仮面の女神)尖石縄文考古館
「仮面の女神」の愛称をもつこの土偶は、茅野市湖東(こひがし)の中ッ原遺跡から出土した、全身がほぼ完存する大形土偶です。全長は34センチメートル、重量は2.7キログラムあります。顔に仮面をつけた姿を思わせる形であることから、一般に仮面土偶と呼ばれるタイプの土偶です。
「仮面の女神」の顔面は逆三角形の仮面がつけられた表現になっています。細い粘土紐でV字形に描かれているのは、眉毛を表現しているのでしょうか。その下には鼻の穴や口が小さな穴で表現されています。体には渦巻きや同心円、たすきを掛けたような文様が描かれています。足には文様はなく、よく磨かれています。この土偶は、土器と同じように粘土紐を積み上げて作っているため、中が空洞になっています。こうした土偶は中空土偶と呼ばれ、大形の土偶によく見られる形態です。
「縄文の女神」(西ノ前遺跡出土土偶)
縄文の女神は、高さ45cmと見つかっている完形土偶の中で最も大きい土偶です。重さは3.155kgとちょうど新生児の重さと同程度です。
頭部は半円形に丸くなり、複数の孔(あな)が開けられています。眼・鼻・口の表現がないのが特徴です。W字のシャープな胸、尖ったような腹、どの部分も洗練された形をしています。また、お尻は後ろに突き出ており、その形から「出尻形土偶(でっちりがたどぐう)」と呼ばれています。すそ広がりの脚の底面は少しえぐって、焼むらを抑えようとしています。
国宝「縄文の女神」 – 山形県立博物館
こうした妊婦をイメージさせる土偶は北条や子孫繁栄を祈るために用いられたと考えられています。
仏教絵画